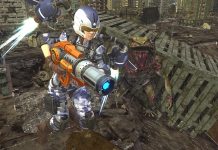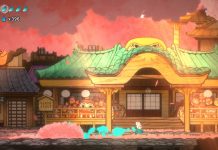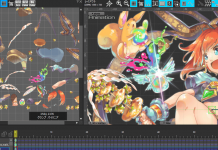ゲームづくりも多様化しており、数百人が携わる大作もあれば、少人数で作る小規模作品もある。昨今ではインディーゲームという言葉が、ユーザーにも浸透してきた。おそらく弊誌を読むユーザーとしては、インディーゲームについてのトピックに関心のある人も多いだろう。そうした需要に応えたいものの、なにをもってインディーゲームとするか定義が難しい。そこで、ざっくりとでも開発チームの規模がわかる作品を対象として、2021年に発売された小規模開発ベストゲームを弊誌ライターに語ってもらった。
『Death’s Door』
――今こそ大空へ羽ばたく時
開発:Acid Nerve
販売:Devolver Digital
対応機種:PC/PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/Nintendo Switch

小規模開発という条件付きで、本年度における高いクオリティを誇る作品を挙げるとするならば、『Death’s Door』の存在は欠かすことができない。ゲームデザインこそ「ダンジョンに潜って謎を解き、ボスを倒す」。『ゼルダの伝説』に代表される、俯瞰式の王道3Dアクション・アドベンチャーであるが、本作の優れた点は、それをひたすらに洗練させているという点である。
スリリングながら軽快なプレイフィールをもたらす戦闘アクションと十分なバラエティを誇るエネミー群。あえて強化要素を「戦闘の報酬」にしないことにより、プレイヤーに探索を促す、広々としたダンジョン。ただひらけているだけでなく、死角が数多く用意されており、そこに強化アイテムが待っているという構造が楽しい。膨大なセンテンスで構成された古典の中から消費者が求める部分を的確に引用し、すべての要素をあまねく楽しめるものとして実現することに全力を注いでいる。
ビジュアルも美しく、クレイアニメのような質感に豊かな色彩表現と自然光を当てたような柔らかなライティングが組み合わさることで、ミニチュアのような可愛らしいおもちゃの印象と、世界に対するリアルな実在感を同居させている。本作の物語は生と死の循環をテーマとしたダークコメディではあるが、このビジュアルのおかげで、重苦しいテーマも、スッと心の内へ飲み込むことができるようになっているといっていい。
総じて『Death’s Door』は、ひとつひとつの要素を吟味し、丁寧に調理したのちに美しくパッケージングした、高品質と呼ぶにふさわしい作品である。これを8人チームで作り上げたのだから驚異的である。ただボスを倒すことにのみに注力した旧作『Titan Souls』から、幅広いメカニクスを内包した『Death’s Door』へ。大きく広げたその翼は、Acid Nerveをさらなる高みへ連れて行くことだろう。
by. Takayuki Sawahata
『Webbed』
―― こだわり詰め込まれた蜘蛛らしさ
開発:Sbug Games
販売:Sbug Games
対応機種:PC

『Webbed』は、小さな蜘蛛が主人公の2Dアクションゲームだ。ボーイフレンドの蜘蛛が大きな鳥にさらわれてしまい、救出に向かうという物語。鳥の巣は非常に高い場所にあり、蜘蛛の力では到達できない。そこで、森に暮らすほかの虫たちの手助けをして、彼らの力を借りることとなる。本作では、蜘蛛のほかにハチやアリなど複数の虫が登場。キャラクターはどちらかというとデフォルメは控えめで、動きも実物をよく観察して制作されたことがうかがえる。それでも、みな可愛く見えてくるのが不思議。「蜘蛛なんてムリ!」という人向けには、すべての蜘蛛をまん丸スライムに置き換える設定も用意されているので安心してほしい。
本作の大きな特徴は、蜘蛛の糸を使ったアクションだ。スパイダーマンのウェブスイングのように、森の中を縦横無尽に飛び回れる。調子に乗っていると、トゲのトラップに飛び込んでしまうこともままあるが、慣れてくると爽快である。さらに、任意の2点間に糸を張ることも可能。糸の上は歩けるため橋として利用したり、オブジェクトを固定したり、あるいは蜘蛛の巣を作って宙を飛び回る虫を捕らえたりと、さまざま活用できる。もちろんクエスト攻略にも使う。ここまで蜘蛛らしさを追求した作品は珍しいが、蜘蛛の糸を表現する確かな技術とともに、上手くゲームに落とし込むことに成功している。
本作の開発は、楽曲制作などを除けば、開発元Sbug Gamesの設立者ふたりがほぼすべての作業を担当したという。地元のゲーム開発者コミュニティにプロトタイプを持ち込んだことをきっかけにし、テストプレイに仲間の協力も得ながら完成させたそうだ。本作は、チームの規模なりのコンパクトな内容ではあるが、ユニークな蜘蛛アクションを存分に活かせるレベル・クエストデザインとなっており、高い満足感を得られる作品であった。
by. Taijiro Yamanaka
『アイケンフェル』
――ひとりひとりのプレイヤーに向けられる、開発者からの愛
開発:Happy Ray Games
販売:Humble Games
対応機種:PC/PlayStation 4/Xbox One/Nintendo Switch

『アイケンフェル』は、魔法世界を舞台とするRPG。突然魔法が使えるようになった主人公マリットとして、行方不明の姉を追って魔法学院アイケンフェルへ向かう。個性豊かな登場人物が活躍するストーリーや、戦略性とアクション性を併せ持つ戦闘が魅力的なゲームだ。
本作を手がけたHappy Ray Gamesは、開発者シェビー・レイ氏の個人スタジオ。レイ氏が、ゲームデザイン、ストーリー、グラフィック、プログラミングなど、主たる部分を担当。外部開発者として、レイ氏と同じく性的マイノリティであるライターたち、バトルアニメ制作者、アニメ「スティーブン・ユニバース」の音楽を手がけたaivi & surasshuなどが参加した。
本作を選んだ理由は、これまでにゲームを遊んでいて感じたことのない「あたたかさ」を感じたためだ。ストーリー、キャラクターの作り込み、ゲームプレイに関する設定項目など、細部まで丁寧に作られており、なるべく多くの人が楽しめるような工夫が見られる。あらゆる属性を持つ人に向けて、優しく手を伸ばしているように感じられるのだ。
「あたたかさ」をもっとも感じたのは、エンディングだ。ネタバレは避けるが、登場人物たちが物語の中で学んだことを活かし、自分らしさを最大限に発揮して輝く姿が描かれる。ゲームを通して見守ってきたキャラクターが迎えるエンディングとして、これほど納得できたのは初めてだった。
主に英語圏で「他人に呼ばれたい代名詞」を示す考え方がある。本作では、ノンバイナリー(性自認が男性/女性の枠組みでは表せない人)が複数登場し、それぞれ好む代名詞も異なる。そのこだわりは日本語版でもしっかり受け継がれ、「ze/zir」という代名詞に「彼人(かのと)」というピッタリな訳が当てられていたのには舌を巻いた。ローカライズも愛に溢れている。
『アイケンフェル』は、自分らしさを肯定してくれる、あたたかくて優しい作品だ。
by. Maho Ikemi
『Muck』
――YouTube発の、異色の個人開発サバイバルクラフト
開発:Dani
販売:Dani
対応機種:PC

今年ゲーム業界を騒がせた個人開発のゲームといえばやはりこの『Muck』だろう。YouTubeのコメントに「マルチプレイサバイバルクラフトゲームを作ってみろ、できるものならな」と煽られたことから開発がスタートしたという本作は、本人の予想を大きく超える反響を獲得。Steamレビューは10万件越えで「非常に好評」というスマッシュヒット作品になった。なお開発のDani氏は自身のYouTubeチャンネルで本作を開発するに至った経緯と開発中の様子を動画にして公開している。
『Muck』大ヒットの背景にはDani氏のもともとの知名度や、本作が無料であったことなどがあるのは間違いないが、それ以上にゲームプレイが優れたものであったのが大きいだろう。前述の動画でDani氏本人が認めている通り本作は『Risk of Rain 2』に大きく影響を受けており、定番のサバイバルクラフト要素に加えて宝箱からのランダムアップグレードと、一度死んだらまっさらの状態で初日からやり直しというローグライク要素が組み込まれている。これがやたらにシビアな難易度設定と組み合わさって謎の中毒性を生み出しているのだ。
開発経緯からして仕方ないものの『Muck』のグラフィックやUI/UXはお世辞にも良いものとはいえない。そしてマルチプレイサバイバルクラフトは飽和気味のジャンルである。にも関わらずここまで新しいゲーム体験を提供できているのはひとえにDani氏のセンスが優れているからに他ならないだろう。そして『Muck』のゲームバランスが偶然出来上がった奇跡の産物ではないことを証明している。というのも、Dani氏は今年もうひとつ、Netflixにて大好評配信中の韓国のサバイバルドラマシリーズ『イカゲーム』とはまったく無関係の『Crab Game』というタイトルを発表しており、こちらも大ヒットしている。Dani氏は個人開発者としては間違いなく今年頭角を現した人物であり、今後の活動にも注目が集まるだろう。
by. Mizuki Kashiwagi
『A YEAR OF SPRINGS』
――あなたは「壊れた人間」である
開発:npckc
販売:npckc
対応機種:PC/Mac/Linux/PS5/PS4/Xbox One/Nintendo Switch

たとえば、好きなラブソングを聞いて共感することがあるだろう。月9ドラマを観てときめいたり、あるいは保険のCMが流れて将来の家族を思い描いたりもする。そして、温泉の広告を見て、ちょっといいなと考えてみるかもしれない。しかし、あるとき世界はあなたにいうのだ。「これはすべてお前のためのものではない」と。
短編ADV集『A YEAR OF SPRINGS』の主人公の一人、ハルのことが、私はあまり好きではなかった。彼女は生まれつき体が男性、心が女性のトランスジェンダーだ。それはいい。苦労もあったろう。しかしこのハルは、異様に自己肯定感が低い。友人がちょっと気を利かせて彼女のために何かするたび、「迷惑をかけた」と自己嫌悪に陥る。その繰り返しだ。いくら何でもうじうじしすぎではないか。ある場面までそう思っていた。
「こんな壊れた人間」と、ハルは自分を表現した。壊れた人間。あるべき姿でない自分。誰でも、周囲から求められる人物像と、本当の自分のギャップに苦しんだことがあるだろう。「どうして自分はちゃんとした人間ではなかったのか」と、不良品の自分を責めたくなることもある。誰にでも起こる一方、誰だって乗り越えてきた壁だ。それはハルも同じである。ただ彼女が違うのは、“お墨付き”だったということだ。法と、制度と、社会が、誰も彼女が「壊れた人間」であることを否定してこなかった。それだけの違いだ。
本作は大部分を開発者npckc氏が制作し、音楽を作曲家sdhizumi氏が手がけた、ミニマルな開発体制。自分が自分であることを否定されたことがある、そんな傷を抱えた人に遊んでほしい作品だ。
by. Yuki Kurosawa
『Road 96』
――大義によって駆動するロードトリップ
開発:DigixArt
販売:DigixArt/Ravenscourt (Koch Media)
対応機種:PC/Nintendo Switch

独裁主義国家と化した国からの逃亡を図る、ロードトリップアドベンチャーゲーム。国境越えに成功または失敗すると、また別の逃走者として最初からスタートを切る構造となっている。ただし、前に操作した逃走者による言動の影響がリセットされるわけではない。道中で出会うキャラクターたちの物語は継続する。逃走劇を繰り返し、出会いと別れを重ねるうちに、彼らの人生を左右していくことになるのだ。
自らの言動によって、選挙での変革を促すか、実力行使の革命を煽るか、あるいは諦念するか。ひとりの逃走者による草の根的な活動だけでは、周囲の人間の考え方や、国家の行く末を変えることはできない。だが、二人、三人と行為を積み重ねていけば、いずれ何かが変わるかもしれない。そのような可能性を、反復するゲーム構造を用いたナラティブによって提示している。ロードトリップという、個の旅路を描く物語として出発しつつも、社会を俯瞰して眺める視点へとたどり着けるように。
逃走者ならびに国民たちが置かれた状況を理解するにつれ、そして、プレイを重ね国境越えという個人目標の達成による喜びが薄れるにつれ、プレイを続ける動機付けにおいて「大義達成」が占める割合が大きくなっていく。ときには大義のために個人の夢(国境越え)を諦めるよう迫る選択肢が提示されることも。一見すると葛藤を生む選択に見えるが、プレイヤーからすると操作している逃走者は使い捨ての駒でしかなく、ほとんど葛藤する余地がない。自然と、個を犠牲にし、大局的に考えるように思考が流れていく。そこが逆に少し怖く、危うさを抱えているという点にも、興味をそそられた。
コアメンバー15人のスタジオが作り出した、局所・俯瞰のレイヤーになった反復構造と物語のメッセージ性は、実にインディーゲームらしい熱を帯びている。
by. Ryuki Ishii
『ElecHead』
――アイデアと知恵の挑戦状
開発:NamaTakahashi
販売:NamaTakahashi
対応機種:PC

電流を使った、2Dアクションパズルゲーム。テーマだけ聞くと、昨今Steamなどで見かける、ゲームのひとつに思えるだろう。しかし、本作には信じられないほど豊富なアイデアが詰め込まれている。そしてこうしたゲームの骨組みは、生高橋氏という、ひとりの人間によって作られたというのだ。
『ElecHead』の、ギミックそのものは単純。主人公のElecの隣接したオブジェクトに電気が流れる。それを利用するのだ。自身の頭を投げるなどもできるが、この「電流を流す」というのが本作の鍵を握る法則。仕組みもルールも、いたってシンプルである。
しかしながら、その引き出しの広さに舌を巻く。横の仕掛けに縦のギミック、人間の認知を利用したトリックなど、あの手のこの手でプレイヤーの頭脳を試すのだ。種明かしになってしまうので具体的な仕掛けの言及は避けるが、よくこれだけバリエーションを揃えられたものだと感心する。ルールはシンプルで、ゲーム側からもたらされる手札も限られている。正真正銘の頭脳勝負となる。単なる謎解きではなく、プレイヤーと開発者による頭脳での戦いなのである。このゲームをプレイした後は、いつも脳みそがほとばしるほど熱くなっている。頭がオーバーヒートする。もはや人類への挑戦状といっても過言ではない。
本作はそんな優れた作品を、たまたま1人の人間が作っていただけにすぎない。しかし逆説的にいえば、優れた作品は1人でも作れるということを改めて証明している。無論、生高橋氏はテストプレイなどで数多くの開発者に支えられてきたことにたびたび言及しており、決して助けなしの1人で生みあげたものではないだろう。それでも主要開発者は1人。ボリュームも膨大ではなく、ビジュアルも凝っているがシンプル。しかし、圧倒的なアイデアで、ユーザーに唯一無二の体験を届けることに成功している。アイデアさえあれば、一人で素晴らしい作品は作り得る。ゲームとしての完成度だけでなく、ゲームづくりの可能性を示す意味でも、『ElecHead』を、2021年を代表するインディーゲームのひとつに選びたい。
by. Ayuo Kawase
その他のAUTOMATON年末企画はこちら。
12月27日〜12月31日にかけて1本ずつ掲載予定。