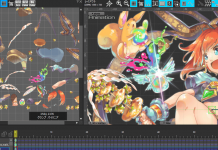Onion Games代表、木村祥朗氏にお話をうかがいました。木村氏はかつてPS『moon』やPS2『チュウリップ』を手がけた人物。現在はBitSummitにも出展された『Million Onion Hotel』の開発にたずさわっています。
――本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。
今日はちゃんと『Million Onion Hotel』(以下『MOH』)のTシャツを着てきたんですよ。
――見た瞬間に気づきました。
試作品[強調]。これはまだ僕と倉島くん(注: 倉島一幸氏。デザイナー。スクウェア出身で、現在はフリー)のぶんしかないのよ。
――ハンドメイドですか?
うん、ハンドメイド。……ハンドメイドっていうか、発注ハンドメイド。これをいっぱい作って、みんなの前で着てみて喜ばれるかな、って実験。
――オニオンじゃなくてアスパラなんですね。もしかしてメインキャラクターはアスパラ?
(笑) おそろしいことに、Onion Gamesのオニオンよりも、『MOH』に出てくる「アスパラさん」の方を開発者もファンも気に入っちゃって。
――ビジュアルがヤバかったからかもしれません。これが回転しながらせり上がってくる様子は相当なインパクトでした。
そう、だからなんか知らんけどこっちばっかりや(笑)
――顔が「チンクル」っぽいというのもあるかもしれません。ラブデリックの系譜をそこはかとなく感じるデザインでもあります。
あ、たしかに。あー……こいつ、チンクルに似てるのかー……。反省(笑) ……ラブデリック知ってるんや! ラブデリックくらいまでさかのぼれば普通に「ラブデリックだ」と言うしかないので、なんでも語れますよ。
木村祥朗のはじまり
――ではそろそろ始めさせていただきます。まずざっくりとしたところからおうかがいします。木村さんはゲーム業界に長くかかわっていらっしゃいます。そんな木村さんの Wikipedia の項目をひらくと、関連作品で最上部に来るのは『ロマンシング・サ・ガ2』のマップ制作、そして『ロマンシング・サ・ガ3』のコンバット・エリアマップデザイン(注: 正確には戦闘シュミレーション、マスコンバットのパート)です。
古いね……[感慨深く]。20年も前だ。
――当時、スクウェアに入社されたきっかけは? どういうものを創りたくて入られたのですか?
スクウェアはそれまで中途採用ばっかりだったんです。僕らが「新卒採用」第一世代で。その中にいたんだよ。僕とか、倉島くんとかが同じ世代です。光田くん(注: 光田康典氏。『クロノトリガー』のサウンドなど)なんかもだね。彼らが同級生だ(笑)
――どういう肩書で入社されましたか?
プランナー……?
――バトルやマップ、いわばゲームのコアともいえる部分にたずさわられたということになります。当時の手応えはいかがでしたか?
まあ、新人なんで。雑用全般をやってました。プランナーの定番ですよ。あとは、マップを描いてた。四角いブロックをたくさん置くようなやつね。だから、『ロマンシング・サ・ガ2』のプランナー班にはいたけど、べつに僕が『ロマンシング・サ・ガ』を創ったわけじゃない。言われると恐縮しちゃうよ。なんか……すいません(笑)
――(笑)
海外の方は「ああ! ロマサガ2にいたんだ!」って喜んでくれるけど、僕以外にちゃんとバトルやイベントを仕切っているリーダーがいましたから。あくまで、そこで修行をしていた感じです。
――ということは、ゲームをメインで創りはじめられたのは『moon』から?
そうだね。
プレミアもついたカルト作品『moon』
――『moon』はもはや伝説的なタイトルになっています。
『moon』が初めて自分で、自力を発揮して物語を書いたことになるかな。『moon』ではストーリーと、それをゲーム内に反映する作業をしてた。あとは、重要なキャラクターを僕が担当しました。「ヨシダ」とか「カクンテ人」とか。……「カクンテ人」が重要だと思ってたのは僕だけかも。ストーリー上からませようとずっと考えてたんだけど。最後のほうに「奇盤ってそんな意味があったんだ!」って織り込みましたよ。まあでも、鳥やね、関西弁をしゃべる鳥、「ヨシダ」。あれは僕の発明だった。
あとはね、粘土人形をみんなで作ってた。グラフィックの人だけが作るんじゃなくてね。僕はいっぱい作ったよ。粘土大好きなんで。モンスター用のやつね。人形作って、8方向から撮影して、パターンを倉島くんが創って。
もともとの素材が粘土なんで、リアルなわけ。それを半透明にして、モンスターの幽霊みたいにして、マップにまき散らした。あれは面白かったねえ。たとえばスライムが死んでて、そこにスライムの幽霊が浮遊してる。そいつをつかまえると魂が死体に戻って昇天していくってゲームだった。
実験で創ってるときもすごく面白かったよ。粘土をゲーム画面に置いた瞬間に、「死体っぽいわー!」「死体、出たね!」ってね。それを機に、みんなで手分けして粘土人形作って。マップ中のいたるところにモンスターの死体をばらまいたわけだ。それは面白い作業だったよ(笑)
――おっしゃっているような、かなりピーキーというか、独特な……なんと申し上げればよいのか、風刺や毒がきいた世界観創りがなされたゲームというのは現状あまり多くはありません。スクウェアを辞められて、今でいうところのJRPGを皮肉るようなプロットを創りあげられた動機は何だったのでしょうか?
んー……。スクウェアにいたのがRPG製作経験者だったから。で、僕らの先輩たちが『ドラゴンクエスト』やら『ファイナルファンタジー』やらを創ってるわけじゃん。同じもんを創ってもあかんよね、じゃあ違うもんを創ろう、ってなったのよ。でもファンタジーは好きだしRPGも好きだし勇者も好きだ、そんな矛盾した気持ちから生まれてる、ってとこかな。
僕がジョインしたときには、「勇者のゲームの世界」っていう概念自体はすでにあったのよ。それを使って僕が最後まで物語を書いた。物語を書いた時は……[熟考]……ゲームを遊んでいる人に向かって「ゲームなんか遊ぶのやめて外に出ろ」って説教臭いことを言う! って途中で決めたのがわりとデカい。そのあと、物語のいろんなディテールも説教臭くすることにしたのよ。ヨシダは説教臭いよ。全体的に説教臭いけど、関西弁で鳥だからまあ、許されるかなと。
――説教臭いプロットは開発中盤で決まったということでしょうか?
そうよ。僕、最初のほう3か月かはいなかったから。旅に出てたからね。僕が来てから決まったことってのもあるね。
当時ペルーに行きたくて、行ってたのよ。そんときはもうゲーム創るのやめようかなと思ってたんだけどね、ペルーの山奥で子どもがゲーム遊んでるのを見て、「やっぱゲーム創ったほうがええな」と思って帰ってきたらなんかつかまって(笑)ラブデリックに戻って。
そっから始まったのよ。本気スイッチが入って。「このシステムこうしたほうんがいいんじゃない?」「ストーリー書きなおしていいですか?」とかね(笑) ……書きなおして、ってのはひどいけどね、世界観が今まさにできようとしていたところだったので。『moon』ワールドの常識や、「じつは世界はプログラムされている」みたいな、裏の裏を匂わせるよう書いていこうって、製作したよ。
――冒頭から文章を紐解けば、「2回目見たらわかる」系のメッセージが随所に仕込まれています。
それは何回も何回も話し合った。「終わりのメッセージにたいして入り口のメッセージを掛けよう」ってね。書きなおしたりもした。でもみんなワイルドだったからね。同時にイベント作ってたし、他の人がやってることに文句も言わずにただ見てることもあったし。よく僕のことを放置してくれたと思うよ。最初に決まっていたプロットと違うことをやっていても「いいんじゃない?」みたいな。楽しかったよ。
――今でいうところのインディーっぽい雰囲気の開発だった、というところでしょうか?
「っぽい」っていうかね、そうよ。大きな会社を辞めて自分たちで集まってやるって、それはもはやインディーゲーム。今でこそそういうふうにはいわれないけど、あのころあった小さいところは全部インディーだったよ。
――たしかに、当時にも現在のような「インディーらしさ」のあるゲームはいくつかありました。
プレステのときに一度華やいだよね。
――出資者が登場していたという点も大きなところです。
おカネを入れるって行為ってのは、どこでもだれでもやってることだけどね。
――最近だと「プレイステーション・キャンプ!」あたりも、インディーシーンを盛り上げるに一役買っているような印象があります。
PSのときから「ゲームやろうぜ!」もあったね。……青田買われたいけどね、青くないからダメって言われそうだ(笑)
――完成されてるじゃないですか。
完成されてないですよ。僕のゲームの創り方じゃ全然ダメなんで。もっと精度を上げたい。
クリエイターの”精度”
――“精度“ですか? “精度”とは?
僕、木村風のキャラクター。ようは、ほかの人みたいにクオリティを高めたいとはいわないけど、僕には僕の世界があるわけじゃん。で、同じように”自分の世界”を高めてすごくなってる人はたくさんいるわけだ。僕にも”自分の世界”はあるけど、まだ積み重ねている途中。まだすごくはなってないです。いつかそうなるまで努力したい。
おじさんだし、昔創ったものが有名になってメディアに載ってるから、みんな「ゲームの世界で長くやってますね」って言ってくれるけど……なんか、僕より『TOKYO JUNGLE』の人(注: クリスピーズの片岡陽平氏)のが面白そうやな、とか思うね。
――(笑)
天谷くん(注: 開発室Pixelの天谷大輔氏)なんかもね。『洞窟物語』一本で、次『KERO BLASTER』出してて。この人の方が僕よりすごそうやな、と。基本的に世の中は僕よりすごそうな人だらけやな、と。
『メタルギア』と比べようとは思わないけど、独自の世界観を持ってる人のなかでも、「僕はもっと精進しなきゃならん」と思うわけです。僧侶みたいに。
――そこで“精度“ですか。
その”精度”とは何なのか? って自分で自分に質問したいですよ。アホさとか? よくわからへんけど。美しくて馬鹿馬鹿しい、そういうギャップを維持することとか? 両方維持するのが大好きなんで。
――美しくて馬鹿馬鹿しい。
馬鹿馬鹿しくて美しい。『moon』もそうなんですよ。美しいって感覚を残しながらアホな状態にしないとね。ただアホな状態のものを創っても面白くないですからね。
いわくつきの『RULE of ROSE』
――美しくて、というので思い出すのが『RULE of ROSE』なのですが……あれは――
『RULE of ROSE』の話できるってすごいね(笑)
――最低限はプレイしました。あれは、どちらかというと異色作です。これは木村さんにとっての異色であり、PS2というフィールドにとっての異色でもあります。あれに「企画原案、CGムービーディレクター、ストーリーボードデザイン」とかなりかかわられたようです。これも物語を書かれましたか?
そういやストーリーボードデザインもやったな……。コンテ描くときに僕が監修してたから。ただ、あれは僕がやってたといえばやってたんだけど、ゲーム全体を見ていたわけではないので。いろいろあってね。
ほかのゲームと比べたらちと耽美すぎたかな。薔薇とか出てくるし。
――メジャーどころでは『少女革命ウテナ』、ちょっとインコーナーなところだと映画『思春の森』や『エコール』あたりを連想するところがあります。いわば“幼女耽美“のようなところです。CEROの壁がありながらああいった試みに挑戦したというのは、じつに印象的です。
おかげでとんでもないことになってね。イギリスやイタリアとかで政府が発売を禁じるみたいな処置をくらったりしたよ。
でもね、真面目に愛の話をしようとしたのよ。愛って何? 子どもたちの間で現象として起こっている友情ごっこや愛情ごっこ、大人の愛情の縛り合い、そういうものは本来は同じものなんじゃないか、とか。それと、いじめや恐怖とも密接してもいる。少女が犬をかわいいと思って抱きしめすぎてしまう、みたいな。それは怖くないですか?ってことでホラーにしたんです。
最初は「飛行船で何かやってください」ってお題だけが来て。先にそういうプロジェクトが走ってて、困ってたのかな。それにたいして「ちょっとこういうの混ぜていいすか?」ってアプローチしたわけ。
――ずいぶんと混ざりましたね。
混ざったね(笑) 僕がたまたまイギリスが好きというかね、知り合いもいてね。旅人なもんでいろんなところにいくんだけれど、イギリスはちょっとした英語の特訓をやった場所でもあって。そこの記憶があってね。R101っていう飛行船がまさにそれだった。ヨーロッパでは過去の歴史としてメジャーなものでね、僕がヨーロッパ好きだったこともあってリンクしたのよ。そんで、孤児院の話と混ぜちゃった。混ぜるなよ、ってね(笑)
――孤児院はどこから出てきたのでしょうか?
どっから出てきたんだろう……。とにかく、子どもを取り扱いたかったのね。で、『RULE of ROSE』の最終形の一段階前の話も存在して。そっちのほうがもっとヤバい。
――インコーナーを攻めた?
インコーナーどころか、今ですら、PCゲームでもそれはどうなのか?って言われかねないようなネタです。それで一瞬考えたんだけど……。発売版には、少年とおっさんがいたじゃん。少年が命令して、おっさんが走ってくる。ようは、子どもがおっさんを操ってる感じ。アブないっしょ。で、ひとつ前の企画は、その、クレイジーなでっかいおっさんとピュアな少年がメインの物語だった。
――ちょーっと、マズいかもしれませんね。
僕としてはおっさんには最終的に勝つんでいいやろ!って思ったんやけど、あかんかったわ。まあ、昔そんな企画があったってことで。
――しかし皮肉なことです。イギリスがお好きだったのに、イギリスで『RULE of ROSE』が発禁めいた状態になってしまったというのは……。
発禁めいたっていうか、発禁ですよ(笑) フランスでは出てたから、フランスの人は知ってるんだよ。
――んー……。フランスはああいうのに寛容なのかもしれませんねえ……(注: この段階でインタビュアーの頭の中にあったのは性の解放等をテーマとしたフランス映画『エマニエル夫人』)
それはちょっと語弊があるんじゃない(笑) でもちゃんとやってみるとわかるっていうか、ストーリーパートを追うだけでも本当はわかるはずなんです。けど、表層だけ、オープニングの3分のデモだけ観たときに、それだけで「アブないからダメ」っていう人はいっぱいいたと思う。
――レーティングの審査も完全に正常には機能しているとは言いがたいと思えるのが現状ですから。
正常に機能してるんじゃないですか?(笑) レーティングの話をすると、それはまあいろいろだよね。日本、アメリカ、ヨーロッパ、全部違うんで。僕の感触だと、みんなそれぞれちゃんとしてる。ちゃんとしてるよ? ちゃんとしてないのは……。んん? ちゃんとしてないと感じるんだ? どういうところが?
――具体例はちょっと挙げづらいですが、ゴア表現でやりあうハメになったという話は風のうわさに聞きます。しかし、ではそのレベルのゴアが他の作品でないのか? となると普通にあるわけです。基準があいまいに感じられるんです。日本でとくに言われるのは部位欠損。レギュレーションはもちろん明文化されているのですが解釈があいまいで、国内ビッグタイトルだったら許されるようなことがマイナータイトルでは許されない、みたいなことがあるかなと。
コンシューマーゲームは基本的に全部ビッグタイトルだと思うよ、ある意味。インディーの僕から言わせるとね。
――現在の? いえ、最初からですね(注: メンタリティについて)。
最初から。そっかー、うん……。『NO MORE HEROES』をやり始めたときに、「木村さんだったらレーティングについて詳しいだろう」って感じで言われたんですよ。いやいやいや詳しかったら『RULE of ROSE』あんなことになってねえだろ!ってね(笑)
――(笑)
『RULE of ROSE』やったから詳しいだろ? ってわけわかんないこと言われて。いやそりゃ逆じゃないすか、って。あるプロデューサーからそんなこと言われたときはドキドキしましたよ。
……やった。この話、誰もDisらずにやれた(不穏な笑み)
――そんなにDisりたい人がいるんですか!(笑)
いや、いないいない(笑) やっぱり僕はもう、プロデューサーとかそういうお偉い感じの役割をもうやりたくないんよ。でも、お偉い人たちの頑張りもあるし、ちゃんとやってる人もいるじゃない。だから、リスペクトはしてる。自分ができないことだから。どちらかというと「僕を見出してください! もう一回ディレクターで!」みたいな気持ちなんで。なので、あんまり変に言いたくない。……どう? このオトナな感じ(笑)
中編へ続きます。



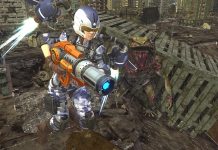


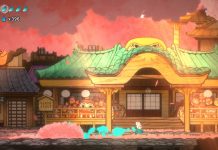






























![PLAYISM&AUTOMATON運営会社アクティブゲーミングメディア人事総務&経理財務スタッフ募集[大阪勤務]](https://automaton-media.com/wp-content/uploads/2023/04/20230410-243372-header-100x70.png)