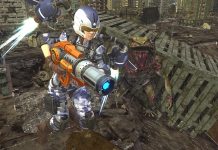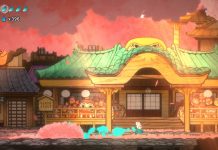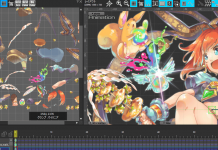2023年7月14日から16日にかけて、京都市勧業館 みやこめっせにて「BitSummit Let’ Go!!」が開催された。今年で8回目をむかえる同イベント、80作品以上が出展され、大いに盛り上がりを見せていた。
今回は出展作品の中から、カナダのモントリオールに拠点を置くインディースタジオ「Studio Cut to Bits」が手掛ける『Venture to the Vile』についてのインタビューお届けする。Studio Cut to Bitsは2019年に設立された新鋭の開発スタジオながら、在籍するメンバーには大手海外スタジオでの開発経験を持つベテランが多い。そんなスタジオが、アニプレックスとタッグを組むということで、見どころも多い。
同スタジオにとって第1作目となる『Venture to the Vile』は、これまでにない2.5DのメトロイドヴァニアとしてPC(Steam)・他プラットフォーム向けに開発が進められているという。いったいどのようなゲームなのか、プロデューサーを務める小林 正男氏にインタビューを行った。
──自己紹介をお願いします。
小林 正男(以下、小林)氏:
小林正男と申します。日本人ですが、北米に移住してもう27年くらいになります。元々はUbisoftで14年ほど働いていました。Ubisoftではローカライズ、ソーシャルメディアマネージャー、プロダクションコーディネーター、プロダクションマネージャーなどさまざまな仕事をしておりました。4年前に5人の仲間と一緒にStudio Cut to Bitsを創業しまして、2019年から『Venture to the Vile』を制作しています。

──ありがとうございます。『Venture to the Vile』がどのようなゲームかご紹介をお願いします。
小林氏:
『Venture to the Vile』は“2.5Dメトロイドヴァニア”と説明させていただいております。2.5Dというのは、2Dと3D両方の要素をあわせ持っていることを指しています。具体的には、3Dのゲームプレイをマルチレイヤーレベルデザインという構造で作っておりまして、2Dのゲームプレイスペースがいくつも繋がった状態のレベルを作っています。さらにゲームアセットも3Dと2Dを合わせて使っているので、たとえばライティングが3Dだったり、背景の一部が2Dだったりします。チーム は20年近くゲームを作っているメンバー がほとんどなので、これまでのキャリアで培ってきたこと をふんだんに使ったゲームになっています。
──2.5Dのメトロイドヴァニアというのはなかなかないコンセプト だと思うのですが、なぜこのようなシステムを採用しようと考えられたのでしょう。
小林氏:
もともとCut to Bitsというスタジオ自体 、クリエイティブディレクターのPaul Greenが『Venture to the Vile』の企画を考えて、今のチームに「こういうゲームを作りたいんだけど、どう思う?」と誘ったところから始まりました 。なので、開発チームのメンバーは すごくメトロイドヴァニアが好きなんです 。 しかし、メトロイドヴァニアのシステムデザインは、20年ほど大きく動いてないという意見が、企画初期からありました。
インスピレーションを受けているメトロイドヴァニアはたくさんあり、『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』がそのひとつ。でも、同作からジャンルとしてはあまり進んでいないなと。たくさんメトロイドヴァニアがある中で、どうやったら差別化できるか、そして、 このチームでしか出来ない物は何かと考えたときに、じゃあちょっと違ったものを作ろうというところから企画が始まっています。

具体的な 違いは 、2つの要素に分かれると思います。ひとつは先ほども説明した2.5D、奥行きがあるということで、2Dのゲームプレイに3Dのゲームプレイ要素が生まれます。ボタンを押して違うレーンのドアを開けたり、橋がかかったり、そういう3D的なパズルプラットフォーム要素があります。また、奥行きを使うことによってプレイヤーに「あそこに行ってみたい」という意欲をわかせる効果もあります。
基本的にこのゲームでは、背景が背景のままではないんです。何かが見えたらそこに行けるという方針でゲームを作っているので、プレイヤーさんが見て「何かありそう」「行ってみたい」というフィーリングを感じていただくという意味もあります。ここがまずシステム上の差別です。
もう一つはオープンワールド的なゲームデザインです。Cut to Bitsのメンバーには、AAAタイトルのオープンワールドゲームを作っていたベテランが多数在籍しています。たとえば僕は、『アサシン クリード』『ファークライ』『ウォッチドッグス』シリーズに携わりました。先ほど話に出たPaulは元々Rockstar Gamesで働いていて、『グランド・セフト・オート・バイスシティ』から『グランド・セフト・オートIV』までGTAシリーズに携わったほか、その後入社したUbisoftでも『アサシン クリード』『Far Cry』『スプリンターセルコンビクション』などにも関わっています。さらにIrrational Gamesでも『BioShock Infinite』に携わっています。彼の当時の 役職がミッションデザイナーなので、オープンワールドのミッションの作り方が『Venture to the Vile』でも活かされています。

手前味噌ですが、メンバーは皆、世界的なオープンワールドゲームを作ってきた ので、その経験をどのように面白くメトロイドヴァニアに落とし込むか、ということを考えて作っています。先に挙げた2つの要素以外にも、世界観をダイナミックにするために、昼夜サイクルや気候などの要素を加えています。これにより同じレベルでも、昼と夜で敵の配置、敵のタイプが違ったり、NPCが違う行動を起こしたり、特定の状況時のみ発生するクエストや、特定条件下でのみ見つけられるアイテムがあったりと、生命感のある世界を体験してもらえるゲームになっています。
──ゲームデザイン的にも立体的であると言いますか、単純な探索型のメトロイドヴァニアではないということですね。
小林氏:
そうです。いろんな意味で深さを追求したかったんです。
──ではこのゲームは一言であらわすなら、何系のメトロイドヴァニアと言えるのでしょうか。ゲームを知らない人に対して一言で伝えるキャッチコピー的なものがあれば教えてください。
小林氏:
あんまり何系という考え方はしていません。 今までメトロイドヴァニアになかった要素を盛り込んでいこうという考えなので。なんか名前をつければ いいんですけど、その辺下手なんですよね(笑)我々は開発の人間で、マーケティングの人間じゃないので。しかも基本的に 職人気質のメンバー なんで、名前をつけるのが恥ずかしいんですよ(笑) どうせなら作って見せようタイプなんで、社内ではそういうキャッチコピー的なものは考えてないですね。あえていうならやっぱり“2.5Dメトロイドヴァニア”だと思います。で、さらにそれにオープンワールドのストーリー性を落とし込んだゲームだと考えていただければ。
──ありがとうございます。ストーリー性のお話が出ましたが、本作は結構ストーリードリブンですよね。
小林氏:
はい。ストーリーもかなり真剣に盛り込んで作っています。現時点で公開している範囲で説明させていただくと、本作は主人公がルエラという親友を探すゲームです。物語の最初に、一緒にいたルエラがいなくなっちゃって、そしたらモンスターが出てくるようになって、こんな怖い世界になっちゃったんだけど、でも親友を探さなければいけない、ザックリいうとそういう話です。
──試遊した感じでは、かなり暗そうなストーリーだなと思いました。
小林氏:
本作はヴィクトリア朝をインスピレーションしているので、必然的にちょっと暗くはなります。ヴィクトリア朝時代 は変革の時代でした。産業革命があって、医学の進歩があって、科学の進歩もすごかったんですけど、その背景で人的被害、環境被害、いろいろなところでかなりネガティブなこともあった。そういうところに目をつぶらないというようなストーリーを作っていますので、メインストーリーには暗い部分もあります。
ですが、サイドクエストもいっぱいあって、サイドクエストは結構いろんなタッチのものを作っています。NPCによってコメディータッチのものもあれば、恋愛の話があったり、ホラーっぽいのがあったり。なので、全体で見るといろんなテーマのいろんなタッチのストーリーが楽しめるゲームになっていると思います。

──たしかTwitterで本作を元としたコミックのKickstarterをアナウンスされていましたよね。あれはどのようなものなのでしょうか。
小林氏:
実は我々、Lethal Comicsというコミック会社とスタジオをシェアするような形で仕事しているんです。スタジオのこっち側はゲーム、あっち側はコミッククリエイターのワーキングスペース、という感じで。4年くらい一緒に働いていて、一緒に仕事することもあったので、じゃあゲームの発表をしたし、コミックを出したら面白いんじゃないかという話になりまして。今は5人ぐらいのアーティストが、それぞれ違ったNPCの話を掘り下げてるコミックを作っています。これが今年の10月あたりに発送を予定していますが、読んでいただければゲームへの理解も深まると思います。
──今も支援者は受け付けていますか。
小林氏:
8月 5日(土)8:00a.m.(JST )までバッカーを受け付け中です。現時点では英語版だけですが、日本のユーザーさんに反響があるようでしたら翻訳も考えますので、ぜひ応援していただければ嬉しいです。
https://www.kickstarter.com/projects/cutobits/venture-to-the-vile-comic-project
Kickstarterのページはこちら
“新しいことへのチャレンジ”で結びついたStudio Cut to BitsとANIPLEX
──本作はアニプレックスさんをパブリッシャーとしてリリースが予定されていますが、カナダの開発スタジオであるCut to Bitsさんとアニプレックスさんはどのようにして出会ってタッグを組むに至ったのでしょう。
小林氏:
Ubisoftの頃お世話になった人伝手にソニーさんを紹介頂きまして、 アニプレックスさんの方でお話を聞いていただけることになりました。我々のようなインディースタジオとしては、話を聞いていただけるんだったら誰にでもお話しますというのが基本的なスタンスなので、内心「本作のゲームのような作品を出してらっしゃらないのでちょっと厳しいかもな」と思いながらもプレゼンしたら「面白そうです。やりましょう」とお返事いただいて、結構びっくりしました。
──アニプレックスさんもゲーム事業は展開されていますが、これまでの傾向としては国内デベロッパーと組んで日本向けにリリースすることが多かったので、Cut to Bitsさんと組むのはたしかに意外といえば意外ですね。
小林氏:
アニプレックスさんとしても新しい試みだと思います。海外のインディーデベロッパーで、完全に全世界向けに展開してくことは、まだやってらっしゃらないので。そういう意味ではやっぱり面白かったなと思います。我々としても、ゲーム自体を作るのは初めてじゃないですけど、新しい会社を立ち上げて新しいゲームを作るというのは、もちろん初めての試みですし、他のジャンルですごく実績のある方々が新しいことをやってみようという意味では、なにか親近感のようなものは湧きましたね。もちろんアニプレックスさんのほうが、我々より実績もありますし大きい会社ですけど。
──そういう意味では日本語でコミュニケーションできるという点で、コミュニケーション面での小林さんの存在は大きかったんじゃないでしょうか。
小林氏:
たしかに。アニプレックスさんはバリバリ日本の会社で、基本的に日本語で受け答えしますので、そういう意味では他の海外インディースタジオが売り込むのは難しかったのかなとは思います。

これまでになかったメトロイドヴァニアを目指して
──開発として想定するターゲット層というか、どういうユーザーに遊んでほしいというイメージはありますか。
小林氏:
やはりアクションゲーム、メトロイドヴァニアの好きなプレイヤーさんにはもちろんプレイしていただきたいですが、ストーリー性の強い世界観の立ったゲームが好きなプレイヤーさんにも、ぜひ遊んでもらえるとうれしいです。
──今開発はどれくらい進んでますか。
小林氏:
結構できてるよ、ぐらいに考えてもらえれば。
──わかりました。今頑張って開発してるよ、ということで。最後に読者に向けてメッセージをお願いします。
小林氏:
皆さんいろんなゲームをプレイされていると思いますが、我々の知る限り『Venture to the Vile』のようなメトロイドヴァニアは市場にないと思っています。新しい体験ができるように精進して作っているので、ぜひ触っていただければと思います。
──お話を聞いてすごく楽しみになりました。ありがとうございました。

『Venture to the Vile』は、PC(Steam)・他プラットフォーム向けに開発中。
©Studio Cut to bits / Aniplex
[執筆・編集: Junichi Matsui]
[聞き手・編集: Ayuo Kawase]