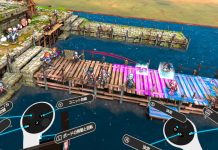国内インディーゲーム開発者の間で、作品の「開発期間見積もり」についての話題が盛り上がったようだ。複数の開発者が、自身の経験を踏まえて語っている。
リズム&アドベンチャーゲーム『ジラフとアンニカ』を開発した紙パレット(斉藤敦士)氏は、2015年同作開発当初のブログを振り返っている。企画段階における同作は、総プレイ時間30分程度を想定し、1年間での開発を予定していたという。しかし、実際の完成までには4年が経過。完成した作品は、クリアまで5~6時間と大幅にボリュームアップした。斉藤氏はゲーム会社勤務経験もあったものの、正確に自作品のスケジュールを見通すのは難しかったと語る。
現実的なスケジュールを立てることができたのは、デジゲー博2016にてデモ版を出したころだったという。とはいえ、その後もデバッグ進行などでなかなか予定通りにはいかなかったとの談。斉藤氏の場合は開発2年目に勤務先を退職し、フルタイムでゲーム制作をおこなっていたものの、「ゲーム開発はほんと時間かかる」と述懐している。
先日パズルアクション『ElecHead』をリリースしたばかりのデベロッパー生高橋氏も、同作の開発歴を振り返っている。もともと『ElecHead』は、生高橋氏が専門学校在学2年目に制作したプロトタイプが原型。卒業時に就職の道を選ばず、フリーランスとして独立するための試金石として、3か月で作品を完成させる予定だったそうだ。しかし結果的には2021年になりリリースを迎えている。途中で行き詰ったり、ほかの仕事に就いたりと紆余曲折の開発を経て時間を要したようだ。
とはいえスケジュールがまったく無意味というわけではなく、「期限とかマイルストーンは大事」と生高橋氏は語る。ある程度の締め切りがないと開発に終わりが見えず、またゲームジャムなどでも期限があることで完成できる例があることから、同氏は開発期間を見通すことに一定の価値を見出しているようだ。
甲殻対戦アクション『カニノケンカ』を開発したぬっそ氏も、開発期間の見通しの難しさを語っている。同作は、開発開始から早期アクセス配信に至るまで2年を要したとのこと。その時点でコンテンツはほとんど揃っていたものの、そこから最適化や追加要素の制作を経て、Nintendo Switch版をリリースするまでにもう1年を要した。さらに、機能追加や調整、バグ修正、移植などを続けており、結果的に『カニノケンカ』の開発には4年以上携わっているとのことだ。
ぬっそ氏はゲーム開発におけるスケジュール見通しの難しさについて、ほかメディアと比較して考察。漫画などではある程度の書き間違いがあっても全体のバランスを崩さず掲載可能であるのに対し、ゲームは一つのバグが全体を台無しにする命取りとなりうる。また終盤の調整でクオリティが一気に上がるケースもあるため、開発がリニアになりにくいとの見解を述べている。
また、東方二次創作ゲーム『幻想郷ディフェンダーズ』などを手がけたサークルNeetpia所属の少佐氏もコメント。開発開始からコミケットでの頒布までに2年、Nintendo Switch移植に9か月、Steam対応までに半年という長いスパンでの制作を振り返り、スケジュール維持の難しさを振り返っている。一方、「ある程度規模の大きい作品を出せる機会は限られている」と前提したうえで、「スケジュールを守るために後悔する品質でリリースしてはいけない」との意見も発信。さまざまなライフステージを経るなかでゲーム開発を続ける難しさに触れながら、スケジュール維持と品質担保の天秤について見解を述べた。
国内クリエイターチームのブイブイラボ代表ますだたろう氏も、開発中の『シューフォーズ』について言及。「300円くらいで遊べる超小粒ゲーム」を目指して3か月をめどに開発を開始したものの、要素が肥大化し、開発3年目に突入していたという。2021年秋頃のリリースが予定されている『シューフォーズ』は、現在インゲームのブラッシュアップ中。「何がどう製品版に実装されるのかは…まだ誰もわからない」として、苦心しつつもぎりぎりまでコンテンツを盛りこむ姿勢を示した。
ほか、Google Indie Games Festival2021にてトップ10入賞を果たしたモバイルゲームデベロッパーじぃーま(飯島勇介)氏も自身の開発についてコメント。3ヶ月で作るつもりの作品も半年~9か月程度を要するとしており、予定スケジュールはおおむね3倍に伸びる傾向があるとの見立てを語っている。また同氏は先日、開発中のモチベーション維持についてもツイートし、反響を得た。「ゲームを早く完成させなきゃ」という姿勢で開発すると、完成しない焦燥感からかえって意欲を損なってしまうという同氏の見解。一方、逆に一つ一つの作業を丁寧におこなうと、今度はゲーム完成が遠のくというジレンマがあるという。スケジュール管理とモチベーション維持は、二律背反の命題であるようだ。
こうして国内インディーゲーム開発者の間で開発期間の見積もりが話題となった理由としては、デベロッパー同士のフォローによるつながりがあるだろう。同時に別の要因としては、「講談社ゲームクリエイターズラボ」による告知があったようだ。同プロジェクトは、講談社が主催するゲーム開発者支援プログラムである。インディーゲーム開発者から、開発中のゲーム、開発したいゲーム企画を募集。選抜したメンバーに「担当編集者」をつけてサポートとケアをおこなうほか、最大で2000万円を支給するという大規模なプロジェクトだ。
しかし、ただ支援を受けられるわけではない。支給金の振り込みについては、「半年ごとに500万円」としている。つまり、2年間で2000万円を受け取れるわけだが、裏を返せばそれは「2年以内にゲームを完成させなくてはならない」という条件でもある。約束の期限内に完成させられなかった場合でもクリエイターに罰則はないとしつつ、「担当編集者がめっちゃ困ります」と釘刺し。この期限設定は2020年に募集された第1期のころから変わりないものの、今回改めて講談社のツイートが注目を集め、国内開発者に大きなインパクトを与えたようだ。
各開発者の経験を見ると、いずれのケースも制作当初は大規模な作品を意図せず、ミニマムに完成させようとしている傾向が見られる。しかし創作者の性として、どうしても作っているうちに作品が肥大化するケースが多いようだ。企業でのゲーム開発と異なり、インディーゲームは自分の納得がいくまで開発を続けられるのが魅力の一つ。しかしそれは、終わりの見えない追求を続ける開発者の苦労と表裏一体なのだろう。クリエイターたちが背負う理想と困難が垣間見えた一幕であった。
※ The English version of this article is available here