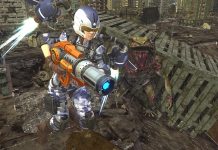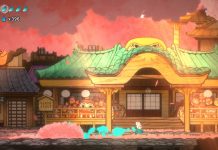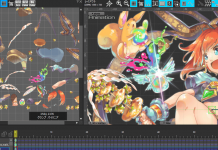しばしばその悪影響について語られがちなゲームだが、うつ症状に繋がるメンタルヘルスへの影響については無関係なのかもしれない。米国医師会が発行している医学雑誌JAMA Pediatricsは7月15日、10代の若者におけるデジタルメディアとメンタルヘルスの影響についての調査研究結果を公表した。それによると、ゲームのプレイ時間とうつ症状の徴候との間に相関関係はみられなかったが、SNSの利用とテレビの視聴については相関関係があることがわかった。
【UPDATE 2019/7/24 0:40】
記事初版にてAssociationを「相関関係」と表現し、その後「関連/関連性」へと訂正しましたが、日本語の「相関関係」は意味合いが広く、correlation(線形的な相関関係)とassociation(曲線的なものも含む相関関係)を包含するため、記事初版のとおりassociationを相関関係と表現する記述に再度訂正いたします。重ねての訂正をお詫び申し上げます。
カナダの学校生徒を対象に4年間の質問調査
JAMA Pediatrics(JAMAはThe Journal of the American Medical Associationの略。Pediatricsは小児科)は7月15日、カナダで行った調査研究の結果について公表した。調査内容は10代の若者におけるデジタルメディア利用とメンタルヘルスへの影響について。調査の詳細については以下のとおりだ。
・3826名の学校生徒を対象に、それぞれ四年間かけて調査を行った。
・カナダ・モントリオールにある学校の生徒が対象。
・7学年(年齢的に日本の中学1年に相当)の生徒を対象に調査を開始する。
・被験者に対し、デジタルメディアの利用時間が一日どれくらいであるか尋ねる。
・同時に、うつ症状の徴候に繋がるようなさまざまな経験がなかったかについても尋ねる。(例えば、孤独に感じることはなかったか、悲しくはなかったか、希望を持てないと思ったことはなかったかなど)
・デジタルメディアの利用については四種類を設定。SNSの利用(FacebookやTwitterなど)、ビデオゲーム、テレビ視聴、その他のPCの利用。
・調査期間は2012年~2018年。
調査の結果、SNSの利用とテレビ視聴の時間が増加すると、うつ症状の徴候を示す生徒の割合も増加することがわかった。特にSNSの利用については、一年のうちに一日当たりの利用時間が1時間増加するだけでも同じ年のうつ症状の徴候の増加が確認できるほど顕著な相関関係が確認することができた。
一方ビデオゲームについては、一日のうちのプレイ時間が延びてもうつ症状の徴候の増加との相関関係はみられなかった。ちなみにその他のPCの利用については、四年間を通して常に一日の利用時間が長い場合はうつ症状の徴候の増加との相関はみられたが、単年のみの利用時間の増加では相関が確認できないなど相関関係は軽微なものだったようだ。
この結果を受けてJAMA Pediatricsは、10代の若者においてSNSの利用とテレビ視聴はうつ症状の徴候と相関関係があると結論付けている。そして、SNSの利用とテレビ視聴がうつ症状の徴候を助長している可能性があり、必要な対応策をとるべきだ、としている。
「この発見には驚き」
この調査研究の結果について、複数の海外メディアがこれを報じている。カナダのニュースメディアであるThe Globe and Mailは、この調査研究チームの一員であるPatricia Conrod博士のコメントを次のように紹介している。「すべての種類のデジタルメディアの利用がうつ症状と関係があるわけではありませんでした。関係があったのはテレビとソーシャルメディアだけです」Conrod博士はモントリオール大学の精神医学の教授であり、またセントジャスティン大学医療センターで第一カナダ研究委員長も務める人物だ。
The Globe and Mailは、Conrod博士ら研究員達が立てていた三つの仮説についても紹介している。一つ目は「置換え仮説」というもの。デジタルメディアを利用する時間によって他の活動、例えば運動をするなどの精神的によい影響を与える活動をする時間と置き換わってしまうというものだ。しかし今回の調査結果からはこの仮説を裏付ける証拠は得られなかった。もしこの仮説が正しいなら、ビデオゲームのプレイ時間の増加においてもメンタルヘルスへの悪影響が確認できるはずだからだ。
二つ目は「上位社会との比較仮説」。理想化された肖像が若者の心に有害となるといったものだ。現実的な失敗に晒される10代の若者にとって、SNSの中でみんなが自分よりもうまくやり楽しそうにしている様子はそれを見ている若者の自尊心を傷つける可能性がある。この仮説はこの調査結果に対する一つの説明になり得るのではないかとConrod博士は見ている。
そして三つ目は「強化スパイラル仮説」。人々は自分の精神状態にあった内容を選択しそれを消費する傾向がある。うつ症状を促進させるようなデジタルな活動に没頭している若者は、よりうつ症状を促進するような内容のものに引き込まれていく、といったものだ。
「この発見には驚かされましたね」カナダの公共放送局であるCBCにそうコメントしたのはこの調査研究チームの別の研究員であるElroy Boers博士だ。「ビデオゲームは少し幸せにしてくれるようです。これはいい気晴らしですね」
ゲーマーにとっては福音。しかしSNSは悪者なのか?
今回のこの調査研究結果は、とかく容疑者扱いされがちなゲームについてその冤罪を晴らしてくれた形になるので、一人のゲーマーとしては喜ぶべきことなのかもしれない。しかし筆者はこの調査結果について、一部やや懐疑的に思えてしまう部分がある。この調査結果からSNSとうつ症状との間に相関関係があるとは言えても、因果関係があるとまでは言い切れないのではないかと思うからだ。
統計学において使われる表現で「相関関係は因果関係を含意しない」という言葉がある。相関関係があるからといって因果関係があるとは決め付けられない、という意味だ。とある事象において、Aという原因によってBとB´という現象が起きていたとする。しかし調査ではBとB´のみしか対象としていなかった。すると調査の結果、Bが多いとB´も多いということがわかった。このことからBがB´の原因であると結論付けてしまう。B´の本当の原因はAであるにもかかわらずこういった誤った結論に達してしまう。これを「虚偽の原因の誤謬」という。たとえば今回のケースで言えば、人間関係を気にする性格というものがもしあったとして、そういう性格の人はデジタルメディアの利用においてSNSにより時間を割きやすい。それと同時に、そういう性格の人はSNSをやっていようがいまいが精神を病みやすい傾向にある。そういった可能性もあるのではないかと、この調査研究結果の考察に対して少しだけ疑義を感じてしまった部分があった。

かつては…
現在中年である筆者がまだ若かりし頃、世間では「ベル友」という言葉が流行っていた。ポケベルにメッセージを送れる機能が追加され、それを利用してコミュニケーションをとることが当時の若者の間で流行していたのだ。ポケベルを介した友達なので「ベル友」というわけだ。中にはこの「ベル友」とのやり取りが高じて、数十分おきにメッセージを送らなければ気がすまない、という人もいた。近くの公衆電話に駆け込んで数字のボタンをガシャガシャと連打しはじめる。休み時間になると、学校の公衆電話には女子生徒の行列ができている。そんな有様だった。そして少し時代が進むと、「メル友」という言葉が生まれ使われるようになった。その頃普及し始めたガラケーにはEメールの送信機能があり、これを利用したコミュニケーションが流行したからだ。「メル友」にはまった人間は、いつでもどこでも携帯を手放さず、中には会ったこともない人も含まれる相手にEメールを送り続けていた。授業中でもガラケーのボタンをポチポチポチポチ。家族との食事中にもポチポチポチポチ。テレビや新聞では、そういった当時の若者達の様子を一種の社会的病理かのように扱い報じていた。ポケベルや携帯が若者の精神を蝕んでいる、との批判もあった。まるでどこかで目にしたような内容だ。
さらに昔の話では、筆者よりも年配の方が中高生だった時代、混線遊びというものが流行していたようだ。深夜0時頃などに時間を決めて、固定電話から117の時報に一斉に電話をかけると、電話回線が混線して知らない誰かと話すことができる、というものだ。深夜になると居間や廊下でコソコソと知らない誰かと話している若者の姿は、当時の大人達からさぞ白眼視されたことだろう。いつの時代も、若者の一定層はその時代のコミュニケーションツールにどハマりしてしまうものなのかもしれない。
人との繋がりに飢えた10代の若者が手にするものが、固定電話の受話器からポケベル、ガラケー、そしてSNSを覗けるスマホに移り変わっていったからといって、なにかが変わったのだろうか? あくまで個人的な経験に基づく主観に過ぎないが、そんなに変わっていないのではないかというのが筆者の印象だ。時代によって槍玉に挙げられるものが移り変わっているだけのように思える。
日の下に新しきものなし、とは聖書にある言葉だが、科学や技術が進歩しても人間自体はそんなに変わらないのかもしれない。
ゲームに罪はない
ともあれ、今回の調査研究結果は、ゲームに罪はない、ということを示してくれた。一方で、WHO(世界保健機構)は中毒性を理由にゲーム依存を精神疾患と位置づけるなど、ゲームは悪影響であるとの見方も根強い。はたしてゲームは人間にとって悪影響なのか否か。今後、更なる多角的な研究が行われることに期待したいところだ。