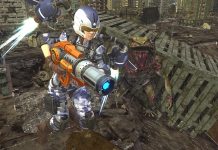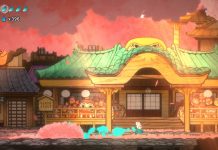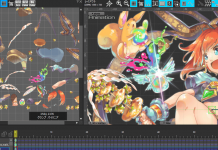『The Last Guardian』という名称のゲームタイトルがSCE(現在のSIE)から発表されたのは2009年6月、E3でのことだった。数日後、『人喰いの大鷲トリコ』という邦題が国内向けに発表された。国内外で高い評価を受けた『ICO』『ワンダと巨像』のゲームデザイン担当・上田文人氏が手がける新作ゲームということで、ゲームプレーヤー達の期待は急速に高まり、2010年には発売時期が2011年冬と発表された。
その『人喰いの大鷲トリコ(The Last Guardian)』が2016年12月6日に発売される。プラットフォームが当初予定のPlayStation 3からPlayStation 4に変わったこと、発表から約7年半と開発期間が大幅に延びたこと、その間に上田氏がSCEを退社したこと、SCE自体の社名がSIEに変わったこと、すべてはもう過去のことである。大切なのはこれから確実に『人喰いの大鷲トリコ』が発売されるという“事実”だけだ。その一点の“事実”の前に、今までの経緯に対する不満も憶測もほとんどがすべて浄化され、発売を楽しみに待つ。ゲームプレイヤーとはそういう生き物だ。
だが、『ICO』がPlayStation2で発売されたのは2001年だ。同じ年に生まれた赤ん坊は、今年もう高校受験生になろうとしている。さんざん待たされた気持ちの問題はどうとでもなる一方で、実際流れた時間もまた、厳然たる“事実”であることも否定はできない。
また、『ICO』『ワンダと巨像』『人喰いの大鷲トリコ』はナンバリングをつけられた続編ではなく、『ICO』と『ワンダと巨像』にはゲームデザイン上ほとんと類似点は見られない。しかし、舞台になる世界、根底に流れているテーマの連続性は確実に見られる。プレイヤーにとっては間違いなく、そしておそらく製作者の気持ちの中でも、『人喰いの大鷲トリコ』は『ICO』『ワンダと巨像』に連なる「続編」なのだ。
あらゆる意味で『人喰いの大鷲トリコ』は世界中のゲームプレイヤー、ゲームメディア、あるいはゲームクリエイター達に注目されている大作タイトルだ。その発売直前になった今、過去作である『ICO』『ワンダと巨像』とあらためて真剣に向き合い、その何が評価されたのか、その存在が何だったのかを問い直すことには、事前準備として多少なりとも意義があるように思える。
※本記事には『ICO』『ワンダと巨像』のネタバレが含まれます。
母性からの分離、あるいは外の世界への接続『ICO』
「この人の手を離さない。僕の魂ごと、離してしまう気がするから」。このキャッチコピーが暖かみのある世界観と牧歌的な優しさを連想させるアクションアドベンチャーゲーム『ICO』。ゲームプレイ画面上では独特な光の表現処理がほどこされ、一見すると雰囲気を楽しむ作品のように思えるが、実際のゲーム内容はそれほど優しいものでも、易しいものでもない。
主人公は角の生えた少年「イコ」。彼の生まれた村では、角がある子供は誰もいない城に連れて行かれ生贄にされることになっていた。13歳の誕生日、イコは3人の神官に連れられて、お城にある何かのカプセルに入れられる。時間が経ち、突然城が揺れた瞬間にカプセルが落ち、その拍子にイコは外に投げ出される。城をさまよい歩くうちに、イコは檻に閉じ込められた少女に出会う。イコは彼女を助け、共に城を脱出しようと奮闘するのであった。
これが『ICO』の物語のあらすじであり、しかも最後までこれ以上に大筋が変わることはない。プレイヤーがゲーム内ですることは、少女ヨルダを連れて城を探索しながら次に進む方法を見つけて実行するだけ。しかし、ストーリーラインは単純かつ明快でありながら、『ICO』は非常に作家性の強い作品でもある。明確かつ普遍的なメッセージと独自のゲームシステムが、『ICO』では奇跡的に融合している。
『ICO』にはビデオゲームならほぼ必ず存在する「数値」「ゲージ」の類の表示がない。そして主人公のイコはまるで不死身のヒーローだ。角の生えた少年の持つ身体は頑丈で、ある程度の高さから落ちても平気だし、敵として出てくる影に攻撃されたとしても、しばらく動けなくなるだけですぐに元に戻る。一方で謎の少女ヨルダは弱々しく、高い所に登ることを拒否する上、影人間の標的になりすぐ捕まって連れ去られる。プレイヤーは序盤、このゲームを「非力なヨルダを助けて進めていくゲーム」だと考えるだろうし、それは間違った感想ではない。高所に登る際には上から手を差し伸ばし、崩れた橋を渡る時も身体を支え、影の攻撃から守り、黒い空間に引きずり込まれそうになっているところをを引っ張りあげる。彼女が影に連れ去られてしまったら、その場でゲームオーバーだ。序盤、プレイヤーはヨルダをお荷物だと感じることもあるだろう。自分一人ならもっと楽に探索できるのに、一人なら楽に脱出できるのにと。やがてそれを繰り返していく内に、プレイヤーはヨルダに対する親近感や保護欲が沸いてくる。そしてこう思うのだ。「この手を決して離さない」と。
それがまさしくこのゲームが持っている、プレイヤーを(いい意味で)引っ掛けるトリックだ。
前述したように、イコは敵に負けない。頑強で勇敢な少年だ。一方、ヨルダは未成熟で弱い少女。そしてこのゲームのルールは「ヨルダが連れ去られたらゲームオーバー」である。ほかのゲームならば、敵の攻撃を受けライフゲージがなくなった状態と同じ。つまり、『ICO』というゲームの世界において、ヨルダは少女の形をした「ライフゲージ」そのものだ。少女の形をし勝手に動き回るAIをライフゲージとして持つ少年。そこに思い至った時、初めてイコの持つ圧倒的な弱さと、何故プレイヤーが必死にヨルダを守ってしまうのかがゲームのメカニカルな意味合いで理解できる。ヨルダが消えれば自分も死ぬ。イコとヨルダは同一のキャラクターなのだ。
一方で、ストーリーラインからも「なぜヨルダを守るのか」は読み取ることができる。『ワンダと巨像』もそうだが、『ICO』は「父性」の物語の側面を持つ。冒頭、少年が少女と出会い、彼女を守ると決意する。そこには少年が少女と出会いさまざまな経験を積むことによって大人になっていくという、ジュブナイル的な成長譚はない。突然、雷にでも打たれたのかのように少年は決意する。「この娘を守らなければならない」と。それは恋愛感情と呼ぶにはあまりにも大げさで、むしろ使命感に溢れた感情といえる。
守るべき人間ができた時、少年期は終わる。つまりイコは大人の男性としての精神的な強さはもともと兼ね備えた少年だったのだ(角は男性のメタファーと考えるべきだろう)。ヨルダの出現は、すでに精神的な強さを宿していたイコが、次の段階へとステップを進めるための「触媒」に過ぎない。守るべき少女が現れた瞬間から、イコは名実ともに「大人」である。ヨルダという未成熟な存在を母性の権化としての「城」から切り離すため、自身の存在を「父性原理」へと昇華させる。出会いの瞬間からイコにとってヨルダは文字通り「自分の命よりも大切な」存在になったのだ。ここにストーリーとシステムの幸せな旅路が始まる。イコにとっては「ヨルダが連れ去られる=自分自身の喪失」なのだ。システム上においても、ストーリーにおいても。
物語が中盤に差し掛かる頃、このゲームのもう一人の登場人物である「女王」が登場し、このゲームでは数少ない言語による意思疎通のシーンを挟む(ヨルダはイコと別の言語を話し、意思疎通ができない)。ここで初めてイコは傍らの少女の名前が「ヨルダ」であることを教えられ、ヨルダが女王の娘であることと、この城を継ぐ存在であることを知る。普通の神経ならイコはここで迷う筈だ。なぜならヨルダという名の少女は、この「城」と「女王」に帰属している存在であり、意思疎通のできないヨルダが本当にこの城から出ることを望んでいるかどうか確かめようがないからだ。だがイコはその言葉にまったく動じたりしない。女王の力で閉じられた門を開ける道をふたたびび探し始める。もちろんヨルダに対する態度も変わらない。
余談ではあるが、『ICO』の考察に「城」を「子宮」になぞらえるものがいくつかあった。これは公式の設定ではないため断言はできないが、個人的には納得のいく解釈だった。「女王」は未成熟な娘であるヨルダを「子宮」内に包み込んで離さない。イコにとってヨルダが「自分の存在意義」なら、女王にとっては「自分のすべて」なのだ。イコと女王。「父性」と「母性」の相克。そこに『ICO』というゲームを通じて一貫している普遍的なテーマはある。母親の強烈な「支配欲」と母と娘の「共依存」が生暖かく延々と続く呪いのような状態、それを「切り離し」外の世界に「接続」する存在、それこそがイコであり、彼は決して成長途上の少年ではない。むしろこの旅を通じて成長していくのはヨルダであり、話が進むにつれ彼女は初めて目にするイコ=父性の持つ強さ、意志の力に影響されて「自立」を意識しはじめることになる。ラストシーンでヨルダが取った行動にこそ、それがすべて集約されている。『ICO』、それは「少年」の成長を描くのではなく、美しく無垢で弱い「少女」の成長譚なのだ。
多少辛口な言い方をすれば、『ICO』は難易度が高めではあるものの、パズル性の強いアクションアドベンチャーゲームとしては及第点である。それでもこのゲームが高く評価されるのは、決してその雰囲気、音楽、グラフィックのためだけではない。作家性をシステムが、システムが作家性を相互補完する調和が本作にはあり、その調和が創り出す美しくも酷薄で力強い物語こそが、本作を名作たらしめているのである。
次ページ: 「守れなかった男」の悲壮な決意『ワンダと巨像』