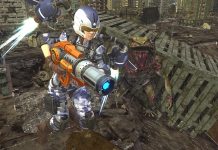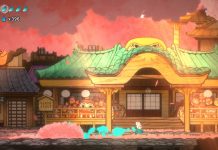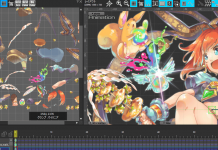『ファイナルファンタジーXIV』(以下、FF14)の拡張パッケージ漆黒のヴィランズ(パッチ5.0)」。その物語は先日配信されたメジャーアップデート「クリスタルの残光(パッチ5.3)」をもって見事完結へと至った。そして筆者が冒険者としてエオルゼアの地に立ってからまもなく1年が経とうとしている。思い返せばいろいろなことがあった。プレイヤー同士のアイテム売買や、ハウジングシステムを利用した店舗運営ロールプレイといった、大勢の人間がリアルタイムで各々の遊び方を実践していることに対する驚き。初めてパーティを組み、ダンジョンに潜ったときの緊張感。出会って数分、顔も知らぬ人達と高難度コンテンツをクリアした際に心へ去来する、得も知れぬ高揚は、私を戦いの虜にした。ディスコミュニケーションからくる「ギスギス」と呼ばれる状況に遭遇したこともある。どれもこれもが決して色あせぬ、自身のゲーム観に衝撃をもたらした唯一無二の思い出ばかりである。
とは言ったものの、私は本作を継続してプレイしているわけではない。多忙で手に付かないときもあれば、他作品への没頭を優先することもある、きりの良いところでプレイを中断しては出戻りを繰り返す。そういったスタンスで、『FF14』と一年を過ごしてきた。ではなぜ、私は繰り返し『FF14』の元へ里帰りをするのだろう。もちろん、超がつくほど充実した復帰者・新規者に対するサポート体制が整っていることが前提としてある。
だが、それだけではない。私にとって『FF14』最大の魅力とは、新生から7年の歳月を経て今もなお語ることを止めないメインストーリー。幻想とテクノロジーが交差する広大な世界の中で、旅と戦いを通じ、善悪の垣根を越えた内省的な題材を提示し続ける、実に『FF』らしい、長い長い物語にある。そして私が思うこの魅力は、単に個人的な感覚に留まることなく、たとえばレビュー集積サイトMetacriticにおいてメタスコア92点を叩き出した「漆黒のヴィランズ」のページでは、評価すべき点として、各メディアは必ずといってもいいほど、 メインストーリーの質の高さを挙げている。多くの長期運営型のゲームサービスにおいて、プレイヤーをエンドコンテンツへ導くための大義名分に過ぎないストーリーの部分が、なぜ沢山の人間の心を震わせ、賞賛の声を浴びるに至ったのだろうか。
本稿は「漆黒のヴィランズ」完結を記念し、「新生エオルゼア」から現在まで『FF14』のメインスト―リーが何を語り紡いできたのかを、ライトな光の戦士2年目の視点より振り返るものである。
※以下「新生エオルゼア」から「漆黒のヴィランズ」に至るまでのメインストーリー関するネタバレが多分に含まれます。
「新生エオルゼア」とはなんだったのか――
善と悪の台頭

すべてはここから生まれ変わった。第七霊災からの復興を遂げたエオルゼアの大地を舞台に描かれたのは、光と闇。善と悪。『ファイナルファンタジー』というゲームシリーズにおいて、あまりにも使い古された二項対立。世界を旅する一介の冒険者が救世の英雄へと至るまでの物語である。光・善の象徴たる星の意思ハイデリンに導かれ、暁の血盟と呼ばれる仲間達と共に、悪の象徴たるガレマール帝国、その背後に蠢く闇の使徒「アシエン」との戦いが語られる。
この「新生エオルゼア」時点におけるメインスト-リーを単体の作品として観た場合、内容としては「退屈」という印象強く抱くことになった。冒頭でも述べたが、私は本作を約1年しかプレイしていない。すなわち、「新生エオルゼア」が発売された当時の熱狂を「吉田の日々赤裸々。」をはじめとする文献を通じてしか知らない人間である。あくまで最近のプレイヤーによる視点であることに留意してほしい。
そのうえで、物語から提示されるのは、友情・努力・勝利。あまりに平々凡々なテーマと、没個性までとはいかないまでも、典型的なキャラクター像を持った仲間たち(軟派だがキレ者エージェントなサンクレッド。自らの才能に鼻を高くする天才少年アルフィノ、研究者気質な魔術師ヤ・シュトラなど)によって形作られたその姿は所々盛り上がりに欠ける。冒険者という何でも屋まがいの職業を演出するため大量に用意された本筋の進行とは関係ないお使いクエストと、旧版で行うことができなかった世界観説明の嵐が、単調であり冗長。悪い意味で相乗効果を及ぼしている。蛮族という意思疎通可能である獣人たちはアイデアこそユニークであるものの、新生時点では背景設定の説明係以上の役割をもたせることができていない。結果「珍味」や「もしミン」というその惨場を端的に表現するミームが生まれることとなった。これを自嘲してか後の物語では「英雄はお使い好き」とNPCから揶揄されることもある。まるで原野の開墾作業のように、地道な仕事が延々と続く。大地を耕し、種を蒔く。いつか芽吹き、花開くことを信じて。
「蒼天のイシュガルド」とはなんだったのか――
復讐と寛恕の物語

ファンタジーのテンプレートの上に成り立っていた『FF14』の物語は、聖教の都イシュガルドにて脆くも瓦解する。いや、真の姿を表すといった方が正しいか。同胞たるクリスタルブレイブの裏切りを契機として始動するメインストーリーは、竜と人が1000年を越えて争いを続ける竜詩戦争を軸に、善と悪という明確な二項対立から、両者が解け合う復讐と寛恕の物語へと深化を遂げる。過去に愛する妹を人間に謀殺され、ただひたすら怨嗟の吐息をこぼす黒き竜ニーズヘッグ。1000年後の謝罪が何になろう、とあくまで今を生きるものとして被害者然とした態度を取りつつ、人の世を切り拓かんとするトールダン7世。そんな両者に相対するは、竜に憎悪を抱く竜騎士エスティニアンと人間を忌み嫌う氷の巫女イゼルを仲間に組み入れた冒険者一行だ。すべての登場人物が、傷つけられた被害者であり、明確な加害者でもある。
果たすべき大義と切り離し難い個人の感情とが錯綜する「蒼天のイシュガルド」の物語は、利己と利他の狭間で揺れる心の在り様をまざまざと描き出すことに成功している。生きることとは、自らが善人あると同時に悪人であることを許容し、喜びも悲しみも背負い、次世代へ託していくことなのだということが、許すことも託すこともできずに押し潰されてしまった者との対比を通じて伝わってくる。こうした「在り方」にフォーカスする物語を描くことができたのは、「新生エオルゼア」時点において、おおまかな世界観に関する説明をやりきっていた部分が大きいだろう。事実「蒼天のイシュガルド」ではストーリーに直接関係の無いだらだらとした描写が挟まることがほとんどない。
また一歩前進を遂げたのは物語そのものだけではなく、典型的だと評した主要キャラクターたちにも当てはまっている。一度大きな挫折を味わい、個人の限界を痛感したアルフィノを筆頭に、暗黒騎士のジョブクエストや盟友オルシュファンの死を通じて、単なるプレイヤーの分身からおぼろげながらも独自のキャラクター像の輪郭が形成された主人公。自らの信条に従い、敵を救おうと奔走するという、「蒼天のイシュガルド」が持つテーマ通りの行動を見せるウリエンジェ。今思い返してみると、「新生エオルゼア」で登場した見慣れたキャラクター像は、後の物語において成長描写をより効果的に、明確なかたちで提示するための布石だったのかもしれない。汗を流し蒔いた種がようやく芽吹き始めたのだ。
画一的と見られた物語はシンプルな題材から一歩踏み込み、善と悪とが混沌とする人の在り方、そして生きるとは何かを示すに至った。しかしまだまだ語り足りない。ふとしたきっかけによって人が善人にも悪人にもなり得るのであれば、それを見定めるのは所属する文化圏から絶対的な尺度として提示される「正しさ」である。だがニーズヘッグにしろ、トールダン7世にしろ、主人公たちによって悪とみなされた者たちは自らの行いを正義だと断じていた。すなわち、コミュニティによって正しさの所在は異なるということだ。「蒼天のイシュガルド」がミクロな観点から二項対立を覆したのであれば、続く物語はマクロな観点から二項対立を覆していく。
「紅蓮のリベレーター」とはなんだったのか――
相対化する正義と相互理解

名実ともに英雄と呼ばれるに相応しい働きをした主人公が次に向かう先は、紅蓮の血風吹きすさぶ戦場。帝国からの解放を願うアラミゴとドマを救うため、東奔西走することになる。戦争という舞台こそ「蒼天のイシュガルド」と同じではあるが、「紅蓮のリベレーター」にて語られるのは個人が抱える多面性ではなく、それぞれの思惑が錯綜する世界の複雑さ。第三者ではなく当事者として、英雄という機能として戦争に参加し、自国の正義を背負わされることで見えてくる他国の正義である。
本拡張の興味深い点は、当事者としての戦争を帝国VSアラミゴだけで終わらせることなく、わざわざ東方という異文化圏を用意したことだろう。これによって、既に存在する起承転結の内にまた異なる起承転結がねじ込まれ、語りのテンポこそ損なわれてはしまってはいるが、世界に奥行きを持たせると同時に、テーマをよりわかりやすく明確な形で表現することに成功している。たとえば帝国の圧政に苦しむ住民ひとつとっても、アラミゴでは既に民間によるレジスタンス組織と支配に順応した派閥が戦いを繰り広げている一方、ドマは向かうべき方向性を失い、ただただ諦観に塞ぎ込んでいる。彼らが主人公たちの介入によって再起していく過程も、片や軍事協力、片やリーダーシップの提示と明確に異なる。
騎馬民族をモチーフとしたであろうアジムステップ地域では宗教に関する話題も登場し、相対化する正義というテーマをより現実とリンクさせる内容に仕上げている。最終的に物語はエオルゼアと東方地域の連携によって帝国を打倒していくという流れに向かっていく。だが、そこに立ちふさがる敵をシンプルな悪役ではなく、「ゼノス=常人では理解できない存在」「神竜=生まれながらにして世界の害でありエゴイズムの象徴」というキャラクターとしたのがまた面白い。しかも、前拡張で赦しの物語を語ったにも関わらず、だ。時に語り合い、時に殴り合うことでコミュニケーションを図り、互いの落とし所を見出してきた(たとえそれが平和的な解決に至らなくても)プレイヤーに対し、明確な「断絶」を示したことは、すべては相互理解可能という心地よい夢ではく、ドロリとした苦味を残し物語の内容を強く印象づける。この「断絶」は後編に至っても引き継がれ、今も昔もヨツユを迫害するドマの民と、一度殺されかけながらも彼女に理解を示すゴウセツという対比構造を用いて表現されている。
典型的な二項対立から始まった物語は5年の歳月をかけ、善悪を同時に内包する「個人の多面性」と「想いの継承を旨とする人の生き方」を描きつつ、「一枚岩とはなり得ない世界のあり方」と「相互理解の可能性」について丁寧に論じてきた。つまりは「新生エオルゼア」時点におけるテーマの再考、および否定であり、一見このことは「『ファイナルファンタジー』らしさ」と呼ばれる概念に対するアンチテーゼにも思える。だがそれは違う。「蒼天のイシュガルド」と「紅蓮のリベレーター」はあくまで向かうべき到達地点にたどり着くまでのプロセスに過ぎない。対立構造自体には『ファイナルファンタジー』を『ファイナルファンタジー』たらしめる要素がないことを証明したに過ぎないのだ。では『FF14』は物語でもって何を表現したかったのだろうか。ならばまだ問うていない領域がひとつだけ存在する。そもそも善とは何か。悪とは何か。なぜいつの世も英雄は支配者に立ち向かうのかという、『ファイナルファンタジー』シリーズにおける根源的命題である。
「漆黒のヴィランズ」とはなんだったのか――
『ファイナルファンタジー』 それは最後の夢の物語

蒼天はやがて紅蓮に染まり、遂に漆黒の帳に包まれる。“光を闇に、正義を悪に覆していく戦い”が、第一世界という、滅びゆく完全な異世界にて繰り広げられていく。「漆黒のヴィランズ」の特徴は今しがた述べたとおり、「蒼天のイシュガルド」と「紅蓮のリベレーター」を経てもたらされた二項対立の崩壊を踏まえ、それでも人はなぜ相争い、現状に抗うのかという題材が絶妙としか言いようのない演出のもと語られていくことにある。序盤から中盤にかけ、光の氾濫によって崩壊しつつも立ち上がろうとする第一世界を懇切丁寧に描写し、終盤一転して6年にわたり敵とされてきたアシエンたちが抱える悲惨さ、目的達成にかける熱意を真摯に描くことで、プレイヤーの中に「第一世界を守りたい」という決意と、彼らに対する敬意を、両立させることに成功している。通常、敵のバックボーンを解明したところでそれは安っぽい同情に留まることが多いが、そうならないのはやはり「新生エオルゼア」にはじまり、「蒼天のイシュガルド」と「紅蓮のリベレーター」を経たプレイヤーが積み重ねてきた経験によるものが大きいだろう。憎悪にまみれた竜と人の悲しみを受け止め、決して一つにならない世界の広さを知ったプレイヤーだからこそ、彼らを敵以上に一つの種として認識し、リスペクトするに至るのだ。
同時に善の象徴であったハイデリンの正体が強大な性能を持った1ソフトウェアであったことも明かされ、光の戦士と持てはやされたプレイヤーもまた、一人の冒険者としての立場に巻き戻る。「お前はもう戦えない。戦う目的がない」。そうした顛末を経て突入する2つの最終決戦は、英雄と支配者の立場を冒険者とアシエン、両者交互に入れ替えながら、善悪の源たる概念を闇夜の下にさらけ出す。仲間を助けたい。世界をもっと良くしたい。人が抱く素朴な願いであり、夢である。誰かの幸福を想う夢こそ、自らを英雄に変え、他者を支配者に見せる。物語を生み出す根本原理なのだ。『ファイナルファンタジー』。それは各々が最後に抱いた、叶えたい夢の物語。私達は彼らの夢を引き継いで、生きていく。
星と命を巡る旅の最終章へ向けて
7年。7年の歳月をかけて、『FF14』は自身が正真正銘『ファイナルファンタジー』のナンバリングタイトルであることを改めて宣言する。積み上げたテーマと1プレイヤーの思い出とが一点に収束し『FF』そのものを表現する心地よさ、美しさは長期運営型のゲームサービスでしか成し得なかった奇跡であるとしか言いようがない。ハイデリン世界で過ごした時間に、何一つとして無駄な瞬間などなかったのだ。一年選手である私がそう思うのだから、「新生エオルゼア」の実装当時から、いや旧版のサービス開始時から遊び続けていたプレイヤーは並々ならぬ想いを抱いたことだろう。
もちろん、緻密に作り込まれた世界観設計や、ストーリーを異なる側面から表現してくれる多種多彩な楽曲群といった、縁の下の力持ちの存在が居たからこそ辿り着くことができた場所であるということは忘れてはならない。そして次に冒険者が向かう先は、終末の獣が鎮座する玉座か。はたまた、獅子の座を冠する道化主演の劇場か。『ファイナルファンタジー』という題材を描ききった上で、それでもなお何を語るのか。来年の発表に対する期待は高まるばかりである。しかしまだ夜明けの時間にはほど遠い。星と命を巡る旅の最終章へ向けて、今はただ目の前にあるコンテンツを、つながりを楽しむことにするとしよう。