AUTOMATONライター陣が選ぶ「ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2024」
「ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2024」。本稿では、1年の総括として各ライターの個人的なゲーム・オブ・ザ・イヤーを紹介する。

今年2024年を振り返る、AUTOMATONの年末企画第4弾。年末最後の企画となる本稿では、1年の総括として各ライターの個人的なゲーム・オブ・ザ・イヤーを紹介する。2024年も多種多様な素晴らしいゲームたちが登場した。そのうち、ライターごとの個人的なベスト作について語ってもらった。
『Balatro』
──何も生み出さない時間の肯定
開発元:LocalThunk
販売元:Playstack
対応機種:PC/Nintendo Switch/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Android/iOS]

我々は日々、社会の一員として理性を持って生活している。誰かの良き隣人として、なるべく慎ましやかに、ひとさまの迷惑にならないように生きることを求められているのが、人間という社会的生物だ。そして、そういう日々に疲れたとき、だらだらと脳内麻薬に溺れたくなることがあるのも間違いない事実である。少なくとも、私はそうだ。
『Balatro』には感動的なストーリーも、心に残る名言もない。ただ落ち着いたビートを聞きながらスートを統一し、カードパックの中身に一喜一憂し、ひとときの射幸心に身を委ねるゲームである。重く響く効果音に脳幹をじんわり揺らされ、桁の増えていくスコアを涎を垂らして見つめ、倍率を上げに上げたストレートフラッシュで高得点を叩き出し、おおよそ最後には統一したスートをボスに全部縛られて、ろくでもないゲームだと怒鳴り散らして終わる。そんな、可処分時間をただただ溶かしていくようなゲームだ。
例に漏れず、今年も『Balatro』以外にも素晴らしいゲームタイトルが多数発売された。物語性やメッセージ性の強い、心に鮮烈な爪痕を残していくようなゲームもあった。しかし、心を感動で大きく揺さぶられるゲームは、とにかくこちらのエネルギーを食ってくる。感動で自分の情緒を揺さぶられることに、2024年の私は少しばかり疲れていたらしい。テキストを読むのが億劫になっていることに気が付いて、少しばかり休憩したくなった。そんなときに私を脳内麻薬漬けにして、癒やしてくれたのが『Balatro』だった。
「時間を溶かす」という表現は、ときに悪い意味にも使われる。『Balatro』を遊んだ時間がいったい自分の人生にとってどう有益だったのか、というレビューを見かけたこともある。限られた時間を「正しく」使わなければという強迫観念に、社会が取り憑かれているような気がする。いやいや、ただただ気持ちよくなるためにカードを引いて、求めるカードが揃わずに年甲斐もなく机を殴って、結果が悪かったら不貞寝をする。それでいいじゃないか。長い人生のなかに無駄があることの意味を肯定しよう。だからこそ私は、『Balatro』を2024年の個人GOTYに選出したい。
by. Aki Nogishi
『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』
──30年越しのリベンジ
開発元:スクウェア・エニックス、株式会社ジーン
販売元:スクウェア・エニックス
対応機種:PC/Nintendo Switch/PS5/PS4

「かつて、ロマサガ2を途中で諦めた あなたへ」とは、本作の発売前後に新宿駅に掲示された巨大広告に書かれたキャッチコピーだ。『ロマンシング サ・ガ2』は高い難易度も持ち味であり、SFCでオリジナル版が発売された当時クリアできなかったという人もいるだろう。このキャッチコピーはそんな人の興味を引くもので、筆者もオリジナル版『ロマサガ2』をクリアできず、このキャッチコピーに惹かれたひとりである。
『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』は、1993年にスクウェアから発売されたSFC向けRPG『ロマンシング サ・ガ2』のフルリメイク作品だ。オリジナル版の2Dグラフィックが3Dグラフィック化し、フィールドも刷新。そして、ゲームシステムも現代向けに再構築がおこなわれており、オリジナル版と比べて非常に遊びやすくリメイクされている。
『ロマサガ』を遊びやすくするということは、非常にバランスの難しい変更であると思う。程良い不親切さこそ『ロマサガ』らしさであると考えていたし、そう思っていた人も少なからずいるのではないだろうか。では、遊びやすい『ロマサガ』は、『ロマサガ』として楽しめるのか。オリジナル版の『ロマサガ2』らしさはあるのか。その答えは個人的にはYESだ。便利になった一方で、『ロマサガ』シリーズの特徴のひとつであるフリーシナリオシステム自体に大きな変更はない。そのため、オリジナル版で存在したカンバーランドの滅亡やコムルーン火山の噴火など、取り返しのつかない要素はそのままだ。自分だけの帝国の歴史を作るという、『ロマサガ2』ならではの楽しさは本作でも味わえる。『ロマサガ2』という、とっつきにくいながらも面白いシステムをもつゲームが、コアなプレイヤーからライトなプレイヤーまで楽しめるようになったことが本作の最大の功績だろう。
そして遊びやすくなったある部分が、オリジナル版をプレイする上で感じていた筆者のストレスを見事に解消してくれた。オリジナル版は、どの技を使えばどの技を閃くのか、どこに行けばイベントが起きるのかなどがゲーム内で実際に試さなければわからない作品だった。しかし、リメイク版ではそれらが可視化され、ほとんどが手探りだったパーティーの強化やゲームの進行が、ストレスなくプレイできるようになった。情報を見ずに自力でのクリアを目指し、挫折した筆者にとっては、この変更があったからこそリメイクでクリアに漕ぎつけたといっても過言ではない。
筆者は、リメイク版で培った知識でどこまでできるかと、今度はリマスター版をプレイしているところだ。このことには、かつて『ロマサガ2』を諦め、ずっとリベンジする気も起こらなかった筆者自身が一番驚いている。筆者の闘志を再び燃やしてくれた『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』に、個人GOTYを贈りたい。
by. Koutaro Sato
『Little Kitty, Big City』
──猫のカワイイが詰まっている
開発元:Double Dagger Studio
販売元:Double Dagger Studio
対応機種:PC/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One

本作は、子猫を主人公とするアドベンチャーゲームだ。子猫は、マンションの高層階で暮らす飼い猫であるが、ある日寝ぼけて地上へと落下してしまい、家に帰るための冒険をする。舞台となるのは日本風の街で、オープンな環境となっており自由に探索可能。好物の魚を見つけて食べると、建物などの壁にあるツタをよじ登れるようになり、食べるたびに探索できる範囲が縦方向に広がっていき、やがて家にたどり着けるという流れだ。また、街に暮らすさまざまな動物と交流しサブクエストをこなしたり、アイテムを収集して子猫のカスタマイズアイテムをアンロックしたりといった要素もある。
本作の最大の魅力は、主人公の子猫自身だといえる。ゲームプレイ的には目新しい要素はほぼないものの、街を探索するなかで、いかにも猫らしい仕草が随所に見られてたまらないのだ。たとえば前脚でヒョイッと物を払ったり、箱に飛び込んだり、あるいはヘソ天で寝たり、状況にあわせたちょっとした耳の動きであったりなどなど。ただ歩いている際のアニメーションにしても、実際の猫をよく観察して制作されたことがうかがえる。
猫が主人公のゲームというと近年では『Stray』が挙げられ、リアルなビジュアルでのこだわりの猫表現が注目された。一方本作『Little Kitty, Big City』では、アニメ的なビジュアルであることを活かしてか、リアルという以上の多少誇張された“カワイイ”が容赦なく襲ってくる。また、『Stray』とは異なり平和な世界観であるため、ただただ子猫のかわいさに浸って幸せな時間を過ごすことができるのだ。
筆者は、猫に接する機会が多い幼少期を過ごしたこともあって、猫は大好き。ただ当時は、猫のかわいさやそもそもの接し方についてちゃんと理解していなかったように思う。気軽に猫を飼えなくなったいま思い返すと、ちょっとした後悔もある。一方で、筆者の猫愛は近年なぜだか深まるばかり。本作の子猫は、ある意味では都合よくキャラクター化されたものともいえるが、得も言われぬ癒しを与えてくれた。そして自身の思い出を振り返るという、個人的にゲームでは滅多にない経験に結びついたこともあり、本作はとても印象深い作品となったのである。
by. Taijiro Yamanaka
『Until Then』
──喪失のなかで、運命の輝きを見つけた
開発元:Polychroma Games
販売元:Maximum Entertainment
対応機種:PC/PS5
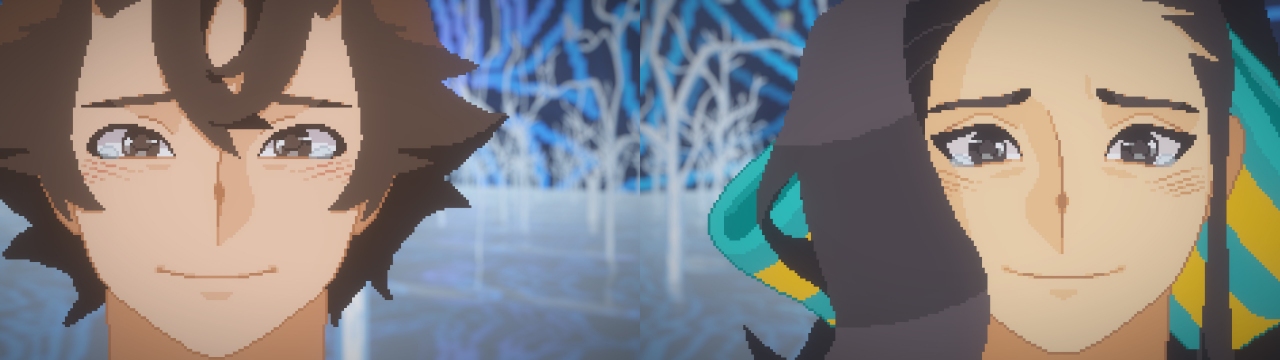
『Until Then』は愛と友情、喪失をテーマにしたSF物語だ。本作は震災や事故によってもたらされる無情な悲劇と哀しみから、人々がどう立ち直っていくかを主題としている。ドット絵にて、キャラの表情から心境の変化を感じることができるほど繊細で緻密なアニメーションが描かれている。
本作の物語は、大切な人を“忘れないため”にピアノを始めたマークと“忘れるため”にピアノを止めたニコールという男女の関係が描かれていく。二人は対極の動機を持ちつつ、喪失感という同一の心で惹かれ合っていく。そんな本作では二人の関係性を演出する要素の一つとして、ピアノ連弾曲が使用される。オリジナル曲の「Memories(想い出)」や「時が二人を引き裂いていく」などが、亡き人を偲ぶシーンや二人の繋がりを強調するシーンで挿入されていく。
連弾曲は、その性質上「二人の人間」が協力し合うことで完成する。お互い別々の動機で連弾曲に触れたニコールとマークは、この協力関係のなかで、今まで内に潜めていた喪失感を共有しあうようになる。そのなかでは喪失感への向き合い方が人それぞれであり、喪失感を乗り越えるために心の殻を破る様子が表現される。
深い悲しみを経た人間の心は「悲しみの五段階」というプロセスを経て立ち直っていくという理論がある。一方で本作が映し出す心境変化は混沌としていて、本作の魅力はそこにあるのだと筆者は思う。登場するキャラクターたちは過去に思いを馳せて悲しんだかと思えば、大切な人を失ったまま訪れる未来に絶望を感じるシーンも描写される。悲しみへの向き合い方は各人で異なり、喪失感を剥き出しにしながら右往左往する心境変化が描かれていく。
そして本人たちにとっては時と世界が止まったように感じる出来事であっても、周りは無情にも時計の針を進めていく。そうして喪失に苛まれる二人の人物と「時を越えて人を想う心」が描かれる様は、筆者にとって非常に生々しく感じられた。
本作は、主人公たちの目線を通して描かれる物語はSF要素を含みながらも、誰にもいつかは訪れる“大切な人との別れ”を現実的に描写している。本作をプレイして筆者は堪らず、今はもう居なくなってしまった人々に想いを馳せ、キャラクターたちの心境に自身を投影し落涙してしまった。そのうえで本作を通して、今いる人との繋がりを大切に保つこと。そして分かち合いによって人々が根付いていくことを再確認する体験ができた。
何よりも、最後に登場するカフェが「Tadhana(運命)」という名前であったことに期待と救いを感じた。「時が二人を引き裂いていく」ことがあっても、運命のその日まで、想い出が2人を強くしてくれるはず。人との繋がりの豊かさを再確認させてくれた本作に、本年度のゲーム・オブ・ザ・イヤーを贈りたい。
by. Mayo Kawano
『Lorelei and the Laser Eyes』
──私はすべてをレーザーの目で見届ける
開発元:Simogo
販売元:Annapurna Interactive
対応機種:PC/PS5/PS4/Nintendo Switch

ゲームには、娯楽として大きく2つの側面が存在すると筆者は考えている。ひとつはプレイヤーの問題解決能力・処理能力を試し、時には競い合わせるための舞台としての側面。これはまさにスポーツ的であり、ゲームのこの側面を磨き上げたものこそがeスポーツであろう。そしてもうひとつが、ストーリーテリングのいち手法、創作者のクリエイティビティを披露するための舞台としての側面だ。『Lorelei and the Laser Eyes』はそんな、インタラクティブメディアとしてのゲームのひとつの到達点だ。
『Sayonara Wild Hearts』でよく知られるスウェーデンのスタジオ「Simogo」が今年リリースした『Lorelei and the Laser Eyes』は、ひとことで言えば脱出ゲームだ。謎のホテルに招かれた女、大量の鍵がかかったドア、意味深なメモやノート、数字に図形……。ゲームプレイ自体は(ポイント&クリックではないものの)ブラウザで遊べるような脱出ゲームとほとんど変わらないと言える。
脱出ゲームのキモとなる謎解きの内容は比較的簡単な部類で、必要な事前知識がある場合は作中で非常に丁寧に提示される。「あまり複雑に考えすぎない」というのがこのゲームの謎解きのコツであり、ゆえに人を選ばずに楽しめるゲームだと思っている。
本作ではどちらかというと大量に同時並行で提示されるヒントのどれがどの謎に該当するのかを考えるほうがメインと言っても過言ではない。最序盤から手に入る情報が最後の最後まで使われなかったりもするし、逆にパッと見で「これは対応するヒントを見つけないと解けなさそうだな」という謎が実はその場の情報だけで解けたりもするので、純粋なパズル力よりかはゲームを横断する思考力のほうが問われているゲームかもしれない。
もちろん謎解きと同時並行で「自分は何者なのか?」「ほかの登場人物たちは何者なのか?」「このホテルは何なのか?」と言った疑問も浮かび上がってくる。こちらは謎解きのヒントやメモに散りばめられたロアピース、そしてグラフィックのディテールや緻密な演出でじわじわと明かされる形となっていて、謎解きゲームというジャンルを存分に活かしたストーリーテリングとなっている。
娯楽の種類が飽和しつつある現代だからこそ、インディーでは特に「10~20時間でクリア出来る、小さく綺麗にまとまった作品」が非常に高い評価を受ける傾向が強まってきている。『Lorelei and the Laser Eyes』はまさにそういった作品のひとつであろう。「人を選ぶ作品だ」と評する人もいれど、筆者はむしろ本作はあらゆる人間が楽しめるゲームの形であると感じている。アートとスポーツの間を揺蕩うゲームというメディアは、時に挑戦であり時に体験でもある。本作は間違いなく2024年を代表する「体験」であり、万人が享受しやすい「アート」としてのゲームのひとつの完成形である。
by. Mizuki Kashiwagi
『Elin』
──混沌と未知に溢れた底なし沼
開発元・販売元: Lafrontier
対応機種:PC

今年はゲームが豊作だったように思う。期待のシリーズ作品や大型リメイクはもちろん、キラリと輝く新作もたくさんあった。個人や小規模開発による魂が込められた傑作も、どこかから彗星のように流れてきては話題にあがっていた。たくさんのゲームを夢中になってプレイしたが、まだまだ気になるタイトルはライブラリとウィッシュリストに積み上がっていて、まったく遊び尽くせたとは思えない。積みゲーが増えていくのはおおむね例年通りであるものの、今年はそれとは別に遊び尽くせていない感触があった。かつて多くのプレイヤーの時間を溶かした『Elona』が、新しく『Elin』としてやってきて、ベータ版と早期アクセスで2度生活になったからである。『Elona』もそれなりに遊んだが、『Elin』は生活感によりもっと深い沼となっていた。
改めて紹介すると『Elin』は、フリーゲーム『Elona』の開発者noa氏が手がける、同作の後継作だ。プレイヤーは何者かとなり、なにもない土地を与えられ、ローグライクをベースとしたファンタジー世界で生きることになる。生きる手段はなんでもいい。土地を耕して作物を育ててもいいし、ランダム生成されるダンジョン「ネフィア」へひたすら潜ってもいいし、街で依頼を受けて生計を立ててもいい。たとえ犯罪を犯しても、カルマが少し下がる程度だ。ただし税金の滞納だけは重罪である。そのほか本作では生活系も含めて多数のスキルが用意されていて、プレイヤーは農業をしているだけでも成長する。本作は冒険や生活によってキャラクターが成長する、ローグライク作品なのだ。
すでに200時間以上プレイしているが、本作ではまだまだわからないことが多く、予想外の事態にも遭遇する。直近では強いNPCを仲間にしたところ、彼女が仲間を巻き込んでエーテル魔法を連発するせいで、パーティー内でエーテル病が大流行してしまった。当人を除いて全員首が太いか、甲殻があるか、足が蹄になっている。
到底把握しきれないシステムも、理解してくると、本作ではルールが一貫しているので、謎の物体の作成も板についてくる。理屈はわかるけれどよくわからないものが、実は効率の良いアイテムであったりするため、進んで謎の品物を作るようになる。多数の要素と自由なプレイイングが、混沌とした状況を生み出してくれるのだ。謎の要素はアップデートと研究で増え続けているのでので、混沌に慣れきる日はきっと来ないだろう。
また本作では食事が重要な要素であるが、拠点関連の要素やより良いご飯と月々の納税に追われていると、異世界で本当に生活しているような感覚に陥る。予想外の出来事と混沌に彩られた日々には、辞め時のない小さなタスクも相まって、つい本当に住んでしまう魔力があった。綺羅星のようなゲームたちを押しのけ、時間を溶かし続けた本作こそ、今年の個人的なGOTYにふさわしいだろう。
by. Keiichi Yokoyama
『九日ナインソール』
──ホラーゲームの名手が見せた、ほとばしる情熱
開発元・販売元:RedCandleGames
対応機種:PC/Nintendo Switch/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One

RedCandleGamesが『SEKIRO』ライクの2Dアクションゲームを開発中と聞いたとき、筆者の心中は期待よりむしろ疑念の方が大きかった。当時の自分には正直なところ、『返校 -Detention-』や『還願 Devotion』といったホラーアドベンチャーゲームで知られる同スタジオが、アクションゲームを作るイメージがなかったのである。ストーリーなどは期待できる傍らで、アクション要素の出来については一抹の不安を抱いていた。
そうして配信された本作『九日ナインソール』は、結論から言えば極めて完成度の高い作品だったし、なにより作り手の並々ならぬ“情熱”を感じられる作品だった。道教とSFを融合させたという「タオパンク」の世界観はユニークで、メインストーリーに直接関わらないロア要素への力の入れ方などからは、自分たち独自の世界を作り出そうという意気込みが感じられる。背景のアートワークも美しく、キャラクターの造形やモーションからも鬼気迫る熱量を感じる。
そして筆者が本作でひときわ気に入ったのが、「弾き」を中心としたバトルシステムだった。本作はザコ敵すら攻撃力が高めで、まともに攻撃を食らっていたらあっという間に死んでしまう。どの敵を相手どるにせよ、弾きはほぼ必須のテクニック。そして本作はこの弾きがとにかく楽しいのだ。操作感は軽快で練習しがいがあり、成功させれば爽快な効果音が鳴り響く。判定に理不尽さを感じたこともなく、とても念入りに調整されていることがうかがえた。
RedCandleGamesの過去作からは想像もつかなかった繊細かつスピーディーな戦闘に、筆者は熱中した。どのボスとの戦いも手に汗握ったし、ラスボス戦は本当に苦労した。何度コンティニューしたか聞かれても答えられないほどである。それでも投げ出したくはならなかったのは、どの敵も戦っていて楽しかったからだ。発売前の筆者の勝手な思い込みに反して、本作は何よりも面白い「アクションゲーム」だった。
個人的に2024年のゲームを振り返ると、楽しいゲームはたくさんあった。難しいゲームもいくつかあったし、なかには『九日ナインソール』より長時間詰まっていた作品もあったかもしれない。ただ今になって印象に残っているのは、本作の“熱”だった。それは過去作とは違う新たなジャンルに果敢に挑み、見事な作品を生み出した開発元の情熱であり、本作で数々の強敵への挑戦を楽しんだ、プレイ中の自分が感じていた熱気でもある。今年の自分をもっとも熱くしてくれた本作に、個人的GOTYを捧げたい。
by. Akihiro Sakurai
『アストロボット』
──時代の寵児
開発元:Team ASOBI
販売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント
対応機種:PS5

“全てのゲームは、ここに集まる”。初代プレイステーションに関するキャッチコピーの1つだ。『アストロボット』というゲームの特徴は、プレイステーション30周年の節目に、このコピーを作品の全身で体現していることにある。
私はゲームプレイという行為を、開発陣とのコミュニケーションであると考えているが、それは言語の代わりにインターフェースへの入力を通じて行われる。プレイヤーは入力によって現れる画面への反応を確認することで、作者の意図を感じ、表現に対する解釈を行う。そして言語は「世界を表現するための道具」である。つまり、ゲームプレイにおいては入力方法の数だけ、世界の表現がある。たとえば、ゲームセンター専用ハードで楽しめるゲームや、VR機器を通じたゲームには、そこでしか体験できない世界が存在していると言える。
『アストロボット』は1つの入力行為に対し、数多くの操作感を成立させることにより、1つの作品に数多くの世界とそれに準ずる独立した体験を内包したゲームになっている。トリガーボタンを押すという1つの行為に対し、適度な重さと振動、適切な映像描写を組み合わせることで、殴る、噴射する、塗る、押す、引く、潰す、吸収する、収縮する、絞る、縮こまる、射つ、投げる、というように、多種多様な操作感を生み出すことに成功している。実際は全部同じ入力なのだが、すべて異なる入力に感じられるのだ。この仕様によって、難易度の維持を通じたプレイヤー層の幅広さを確保しつつ、さまざまなゲームの世界を旅する経験を成立させている。正直なところ本作は終始、敵を殴って壁を壊し、登ったり引っ張ったり、危ない足場をジャンプするゲームである。それでいて「まったくそうではない」と思わせるほどの体験バラエティを生み出し、1つ1つのステージが独立した内容として感じられるという凄まじさを誇っているのだ。この内容は長年さまざまな作品を送り出してきたPlayStationシリーズとソフトウェアの関係性を体現するものであり、ハードウェアの性能を120%活かしきる、開発陣のクリエイティビティの成せる業である。
また、本作の物語体験にも心動かされるものがあった。まさに時代の渦中にあるSIEが、ジャパンスタジオ出身のTeam ASOBIが、積み重ねた経験と企業を超えた繋がりによって現状を打破し、自身を修復する物語を消費者に向けて提供したことは、ある種の決意表明として私の目に映った。IPを大切にしていくと。ゲーム専用ハードを今後も開発していくのだと。ゲーム業界は今まさに転換期を迎えており、ゲームが誰のものになっていくかも分からない。PlayStationそのもの、そして背負われた業界の運命を体現する『アストロボット』は、単なるメモリアルタイトルにとどまらない、今年を代表するゲームと言えるだろう。
by. Takayuki Sawahata
『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』
──画面とボタンしかない集中世界
開発元:Ubisoft Montpellier
販売元:Ubisoft
対応機種:PC/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch

筆者は集中力のない人間だ。小学校の成績表には毎年「落ち着きがない」と必ず書かれていたし、映画ではソワソワして何度も姿勢を変えてしまう。大好きなバンドのライブでも楽しみながらふと違うことを何度も考えてしまう。今こうやって文章を書いている時だって、無意味に立ち上がったり、お手洗いに行ったりを繰り返してしまうのだ。そんな筆者の集中力のなさはゲームプレイにも影響しており、長い時間かけてじっくりとストーリーを楽しむゲームでは、頻繁に休憩を挟んでしまう。その結果、明確な区切りが多いゲームや、1プレイが短いゲームを好んで遊ぶようになった。
そんな筆者が個人的にゲーム・オブ・ザ・イヤーを贈りたいのが『プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠』だ。『プリンス オブ ペルシャ』シリーズの最新作であり、2Dのメトロイドヴァニアとなっている。しかし、時間をかけてマップの隅々まで探索し先に進むメトロイドヴァニアは、集中力のない筆者の弱点とも言えるジャンル。しかも筆者はシリーズを1作も遊んだことがない。口コミの良さとアクションシーンのかっこよさに惹かれ、衝動買いしただけの作品であった。
夜中、どんなもんかとプレイを始める……ふと窓を見たら外が明るかった。自分でも不思議なほどに本作に集中し、プレイが途切れることがなかったのだ。そこから筆者の夜の時間は本作に吸い込まれた。ほかのゲームであればふと画面外が気になっちゃう筆者が、本作を遊んでいるときはとにかく画面にかじりついた。ふとした時間で指遊びをする筆者が、本作を遊んでいる時はずっと指がボタンに張り付いていた。本作を遊んでいるときは、画面とボタンだけにスポットライトが当たっている感覚を覚えていた。
なぜここまで筆者は本作に集中できたのだろうか。それは本作が徹底して「ゲームプレイを途切れさせない」つくりになっているからだと考えている。リトライまでの時間が早いのはもちろんのこと、アスレチックでは、やられた瞬間に先に進むヒントが見え、きちんと正解のルートが見えるようなレベルデザインがなされている。戦闘ではパリィ、避け、あるいは能力、あらゆる手段で攻撃に転ずることができるうえ、一辺倒なだけでは勝てないようなバランスを作り上げている。巨大なマップの探索においては、今後行けそうなポイントを写真のように記憶できる「記憶のかけら」機能があり、それを見直すことで、攻略が進みそうな場所にダイレクトで行けるのだ。
今思い返せば、本作には短期的にも長期的にもゲームプレイを途切れさせないような工夫が細かく凝らしてあった。隙あらば別のことに気を取られる筆者を絶対に飽きさせない密度。筆者にとって稀有なゲーム体験をもたらしてくれた本作にGOTYの“王冠”を贈りたい。
by. Tamio Kimura
『ユニコーンオーバーロード』
──タクティクス、かくあれかし
開発元:ヴァニラウェア
販売元:アトラス
対応機種::Nintendo Switch/PS5/PS4/Xbox Series X|S

ゲームにおける選択は、すでにほかのプレイヤーによって答えが見つかっていることが多い。そしてそれは、特に現代において非常にアクセスの簡単な情報となっている。最強編成、最強スキル、おすすめ育成ルート……娯楽としてタイムパフォーマンスを求めるならば、失敗を避けるために、あるいは時短のためにそうした情報が利用されることも多いだろう。しかし『ユニコーンオーバーロード』は、試行錯誤の外側から遊ぶ機会も増えたゲームという娯楽において、試行錯誤の“内側”に強く引きこむ魔力を帯びた作品だ。
本作で亡国の王子アレインとしてフェブリス大陸を駆け、戦いに身を投じていく中では、数多の選択が提示される。それはSRPGにおけるタクティクスの領域に留まらない。たとえばゼノイラに支配された大陸のどこから解放していくのかといったストーリー上の選択がそうであるし、敵対していた勢力を自軍へと引き入れるかという葛藤なども存在する。仮に引き入れたのならば、どう編成に採用するかという悩みも生まれうる。本作ではゲームにおける選択肢以上に、プレイヤーの決意や悩みがゲーム内に如実に反映されるわけだ。
そして選択や葛藤の合間に展開される戦闘は「ボタンの掛け違い」ひとつで如何様にも表情を変えていく。隊の編成、装備品、クラス。アクティブスキルやパッシブスキルを実行する順番。スキルの発動条件。発動した際の、対象を取る優先順位。数多の選択にて構成されるタクティクスは、すべてが密接に勝利へ、あるいは敗北へ直結する。敵の編成や攻撃手法などにもバリエーションはあるのだから、想定外の結果、つまり敗北がもたらされることもある。もし負けたのであれば改善が必要だ。多くの変数を振り返り、変更し、再び戦いに挑む。己の描いた理想を、戦いの中で得た発見を、思う存分形にできる。試行は止められず、思考はついにゲーム外にも及び、理想の編成/スキルを考察しだすまでになる。
このPDCAのサイクルを回す行為は究極的には作業ともいえる。しかし“作業”は、膨大なバリエーションによって無数の自由度を誇る選択として提供されており、美しいグラフィックと王道を往く物語がそれを彩る。
本作は立案と実行、選択の極致であるところのSRPGとして、それらを正面から描き、パッケージングしきったのである。プレイヤー自身の葛藤と選択を受け止め、ゲームプレイとして表現させる。自身で戦術を発見する楽しみを間髪入れずにプレイヤーへと叩き込み続ける。そんな『ユニコーンオーバーロード』の魅力に当てられた身としては、本作にゲーム・オブ・ザ・イヤーを捧げる「選択」をせずにはいられないのだ。
by. Kosuke Takenaka
『SILENT HILL 2』
──訪れる者の内面を映す街
開発元:Bloober Team
販売元:KONAMI
対応機種:PC/PS5

『SILENT HILL 2』オリジナル版をプレイしたのは、約15年前のこと。高校生だった筆者は、肝試し気分でさまざまなホラーゲームをプレイしていた。当時の感性で魅力に気づける作品もあれば、逆も然り。本作は、魅力に気づけなかった方のゲームだった。なんとなく気に入って周回プレイもした傍らで、高い評価を受ける理由にはピンと来ないままであった。
そんな筆者がリメイク版をプレイして第一に感じたのは懐かしさでも新鮮さでもなく、「これが本当のサイレントヒルだったのか」という気づきであった。そう思わせた大きな要因は、筆者の変化だ。
ホラー作品における脅威には、何かしらの原因があるものだ。心霊、ウイルス、人の怨恨など、何が恐怖を引き起こしているのかが示される。ただ物が動くだけではなく、霊が動かしていると思わせるからこそ恐怖が掻き立てられる。そして『SILENT HILL 2』において恐怖を引き起こしているのは、ジェイムスの苦悩だ。妻を亡くし、罪悪感に苛まれるゆえに、彼の目には異形が映る。幻聴が聞こえる。
高校生の筆者には、愛する妻を亡くした男、ジェイムスの心中に理解がおよばなかった。それゆえに何度遊んでも、筆者はサイレントヒルに入り込むことができなかった。異形も異世界も、アートデザインに圧倒されながらも、その裏にある意味にまで考えは巡らなかった。たとえ他人の考察を読んでも、感心こそすれど、その胸に実感は湧かなかった。
しかしそこから十数年を経て、人生に思い悩むこともあったし、誰かを愛することも知った。今の筆者には彼の罪悪感が少しくらいは感じ取れる。女体を思わせる怪物のデザインや、意味深な文章の数々。純粋さを失ったゆえに、比喩が散りばめられたサイレントヒルを味わえる。今の筆者ならもしオリジナル版を遊んでも魅力を堪能できただろう。
対してリメイク版は、魅力を味わうといった生半可な遊び方を許してくれない。先を知った上での遊び直しとは異なる、余裕のない新しい体験をもたらしてくれた。そして何よりリメイク版では肩越し視点が採用され、ジェイムスの目線により近づいて、彼が見た霧の街や錆にまみれた裏世界をより近くで目の当たりにすることとなる。
筆者はリメイク版で、精神的にも物理的にもジェイムスに寄り添ってサイレントヒルを歩むことになった。彼の苦悩への共感と憐れみが原動力となり、目を背けたくなるような異形と異世界が実体感をもって胸を揺さぶる。そんな心をすり減らし続ける体験は、もはや“肝試し”とはかけ離れていた。筆者の変化と、ゲームの変化が組み合わさったからこそ生まれる特別な体験であった。あの頃逃してしまったサイレントヒルを味わう新たなチャンスをくれた『SILENT HILL 2』リメイク版に、個人的なGOTYを贈りたい。
by. Hideaki Fujiwara
『龍が如く8』
──価値は生命に従って付いている
開発元:龍が如くスタジオ
販売元:セガ
対応機種:PC/PS5/PS4/Xbox One/Xbox Series X|S

今年の初旬、私は人生でも有数の難局にあった。そのなかで遊んだ『龍が如く8』は、「男のゲーム」の枠から抜け出すことで、予想外に近く、暖かく私に寄り添ってくれた。
上述の難局について説明したい。私はトランスジェンダーである。昨年の中頃に「男のフリをしていた」ことに気づき、本当の性別である女性として生きられるよう移行を始めた。さまざまな差別に晒されつつ、新しい環境に適応しようともがくなかで心は疲弊し、一時は仕事さえままならなくなった。そうした中で、かつてからファンだった『龍が如く』シリーズへの見方も変わった。
というのも、『龍が如く』シリーズといえば「男のゲーム」だった。そもそも初作のコンセプトが「国内の成人男性に的を絞ったゲーム」であり、その方針は続くシリーズ作品にも色濃く受け継がれていた。物語としても基本は主人公・桐生らの「男らしさ」が軸にあり、“女子供”は守られ、悲劇に巻き込まれ、健気な存在として描写された。そして、私のようなセクシャルマイノリティは嘲笑の対象だった。『龍が如く7』では主人公が春日に交代され、コンプライアンス面もアップデートされて普遍的なヒューマンドラマが志向されていたものの、過去作の歴史もあり私と『龍が如く』の間には気まずさの壁が一枚できていた。
しかし、『龍が如く8』は、さらにもう一歩、私に歩み寄ってくれた。「男のゲーム」から「みんなのゲーム」へと本格的に変貌を遂げたと、私は感じたのだ。本作でも引き続き、多種多様な属性の人を扱う手つきには危うさもある。不器用さ、不用意さを感じる部分もあった。しかし、春日たちのさりげない会話などを通じて「あなたたちマイノリティを認識しているし、傷つけたくない」という各所への目配せは盛り込まれている。
私は、この「寄り添い」に心を打たれた。『龍が如く』を「特定の人だけではなく、みんなのゲームにする」という開発陣の真摯な姿勢を信じられたのだ。この姿勢は、本作の2人の主人公の有り様にも通底しているだろう。春日は「誰も置き去りにしない」という信念を、最後の最後まで貫き通した。桐生は、自分が大切に貫いてきた「男(極道)らしさ」という規範を見つめ直し、「人」として答えを出した。
本作のテーマ曲である、椎名林檎さんによる「ありあまる富」の歌詞を借りて、総括したい。価値は私達それぞれの命に従って付いている。あなたと、あなたが大切にしているものの価値は、春日が浴びたような「野次馬の無責任な言葉」や、桐生が縛られていたような「男(極道)としての規範」などに決められることはないのだ。そう思えば、私達の心の内は、見えない富で溢れているはずだ。
by. Sayoko Narita
『ファイナルファンタジーVII リバース』
──「物語」がもたらすパワー
開発元・販売元:スクウェア・エニックス
対応機種:PS5

ゲームは数多くの変遷を経て、過渡期に入ったように思える。ゲームのフォーマット化が進み、仕組みが研究され、フォーマットや仕組みが優れたものが再生産される時代になってきた。それゆえに、理論によって作られ成熟した、よりラッピングされたゲームが味わえるようになった。個人からもそうした優れた作品が届けられるようになった。素晴らしい時代である。一方で、全体的なゲーム体験が均質化されたようにも感じる。面白いけれど、なんとなく見たことがある。楽しいけれど、このゲームならではのものではない。それは良い悪いではなく、傾向として感じていたのである。そんな2024年において、僕はゲーム体験の唯一無二性をひとつ見つけた。それが物語である。
『ファイナルファンタジーVII リバース』は、物語体験の結晶である。美しいビジュアルや壮大な音楽や、モダンな探索&バトルメカニクス、ちょっと懐かしいアクティビティ。あるいはリッチで膨大な冗長とまで思える数のミニゲーム。それぞれ卓越しているが、唯一無二性はない。これらの要素は物語体験のためのパーツである。クラウドは悲劇に遭い、エアリスは悲運に遭う。原作の脚本に綴られた宿命を危惧しながら、不穏な旅路を辿る。その先に待つものは何か。『ファイナルファンタジーVII リバース』のすべては、その結末一点に収束する。「結末一点突破」である。ストリーマー全盛期のこの時期に、ゲームを見て楽しむこの時代に、ゲームの結末で勝負するなぞ正気ではない。リプレイ性が求められる、プレイヤーごとに異なる体験が求められるこの時代に。なんとも時代逆行的である。『ファイナルファンタジーVII リバース』は、歪さを含みながらも質の高いパーツを揃えて、物語とその結末にすべてを出力するという一手で、結末を見届けたプレイヤーである僕の心を静かに大きく揺さぶった。これこそが物語がもつ、ゲーム体験のパワーである。
物語は一度ネタバレされれば無意味と化し、プレイする意味がなくなる。それは少なくとも、マーケティングにおいてはそうかもしれない。しかし物語はゲーム体験の唯一無二性をもたらす大いなるパワーをもつのである。『未解決事件は終わらせないといけないから』『The Rise of the Golden Idol』……面白かったゲームをあげると暇がないが、記憶に残ったゲームをあげると物語ゲームばかりだ。物語ゲームがいかにパワーをもつか、そして人に影響をもたらすか。
『ファイナルファンタジーVII リバース』は、リメイクシリーズでありながら原作とは異なる運命を描く、極めて複雑で歪なタイトルだ。異形とまでいっていい。原作で人気のあるシーンや結末に手をいれるリスクは大きい。そんな状況で、プレイヤーの心に響く結末を用意したのだ。自分の余韻は、クリアから9か月経っても色褪せることはない。この衝撃、あるいは痛みこそが、ゲームがゲームでなければいけない存在証明である。あるいは、ゲームの物語の可能性を証明する試みでもある。自分にとって2024年はゲームの「物語」時代の復権を感じさせる年であった。物語には無限の可能性がある。巨大IPを背負いながらゲームの「物語」の可能性に挑戦し、そして成し遂げた『ファイナルファンタジーVII リバース』に、2024年を代表する物語ゲームに、僭越ながらもゲーム・オブ・ザ・イヤーを贈りたい。
by. Ayuo Kawase
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。



