AUTOMATONライター陣が選ぶ「ゲーム・オブ・ザ・イヤー 2025」
大晦日を飾る本稿では、1年の総括として各ライターの個人的なゲーム・オブ・ザ・イヤーを紹介する。

今年2025年を振り返る、AUTOMATONの年末企画第5弾。大晦日を飾る本稿では、1年の総括として各ライターの個人的なゲーム・オブ・ザ・イヤーを紹介する。2025年も素晴らしいゲームが多数リリースされる豊作の年であった。そのうち、ライターごとの個人的なベスト作について語ってもらった。
『Cast n Chill』
──大自然に身を任せてただ癒される
開発元・販売元:Wombat Brawler
対応機種:PC/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch

『Cast n Chill』は、小さなボートに乗って魚釣りをするゲームだ。川や湖などに複数の釣り場が収録され、それぞれに固有の魚が生息。ボートで任意のポイントまで移動し、釣り糸を垂らして、魚が食いついたら釣り糸を巻き上げて、釣り上げることを目指す。釣った魚は売却してお金に換えることができ、ショップにて釣具などの購入やアップグレードをおこなって徐々に装備を充実させながら、まだ見ぬ魚を狙ったり、新たな釣り場をアンロックしたりする流れとなる。
筆者は、実際の釣りは「やったことある」という程度で、特に造詣が深いわけではないし、釣りゲームのファンというわけでもなかった。ではなぜ本作を手に取ったかというと、ドット絵の美しいビジュアルに惹かれたのがまず第一。釣り場ごとに異なるのどかな大自然が精緻に描かれ、さらに時間経過による風景の移り変わりまで表現されており、つい見入ってしまう。また、ドット絵の2Dゲームであるがゆえに、釣りゲームとしてそれほど複雑なシステムではなく、気軽に始められるかもしれないと考えたのだ。
実際、本作の釣り操作はシンプルで、魚が食いついたら釣り糸を巻き上げ、魚が抵抗している間は釣り糸が切れないように緩める、ただそれだけだ。1ボタンで操作できる。それだけではあるが魚の挙動が絶妙で、特に大物相手だとファイトしている雰囲気を味わえて楽しい。一方で、狙う魚によって、ルアーおよび釣り竿の種類をうまく使い分けないと、突いてはきても全然食いついてくれない。ルアーの種類によっては釣り竿の細かな操作も大事になる模様。さらに、特定の時間帯にしか姿を見せない魚もおり、そんなちょっとした奥深さからも“釣りをやってる感”が演出され、いつしか夢中になっていた。
実は、本作は放置ゲームとしてもプレイでき、これが意外と筆者の心に刺さった要素だった。放置モードをONにすると、魚釣りから釣果の売却までをすべて自動でおこなってくれる。お手軽にお金を稼げることもありがたいが、それ以上に放置中に聞こえてくる水音などの環境音による癒し効果がたまらないのだ。振り返ると、2025年は癒されるゲームが数多く話題になった年だった気もする。本作は、釣りゲームの楽しさという新たな発見を筆者にもたらしてくれた上に、癒しまで与えてくれた作品であった。
by. Taijiro Yamanaka
『Europa Universalis V』
──愛すべき怪物
開発元:Paradox Tinto
販売元:Paradox Interactive
対応機種:PC

ゲームを遊んで、心の底から驚された経験はあるだろうか。ただ面白いとか感動したとかそういった次元を超えて、もはや「度肝を抜かれた」としか言いようがないような、強烈な衝撃を受ける体験である。
『Europa Universalis V』を遊んだとき、筆者が味わった感覚はそれだった。本作は異常なほど巨大だ。世界には総計2万8000を超えるロケーションが存在し、それぞれに地表環境・気候・植生・港湾適正・資源が設定されている。世界には無数の文化と宗教に分かれた人々がおり、彼らを支配する勢力がある。足利幕府のもとには146の大名が、神聖ローマ帝国には312の諸侯がいて、それぞれでプレイ可能である。全世界を舞台とした作品としては、ありえないほど緻密なスケールだ。
そしてゲーム内には大量のパラメーターが存在しており、互いに複雑に絡み合っている。どんなプレイヤーも圧倒してしまうほどだが、『EU5』は広範にわたる自動化機能を導入し、本作をゲームとして成立させている。特に数千のロケーションをもつ大勢力を操作する場合、一つ一つのロケーションを手動で日々管理するのは、現実的に不可能だ。本作の自動化はただのオプションではなく、プレイヤーの注意力というリソースを管理するための、ゲームの根幹的なシステムとして機能している。
その巨大さと複雑さは歴史サンドボックスの極致であり、戦略ゲームとして比較に値するタイトルは、ほかのParadox作品のなかにすら見当たらない。むしろ、圧倒的ボリュームに基づく極めて細密なディティールと、それによって醸し出される唯一無二の没入感という意味では、『The Elder Scrolls』シリーズや『Grand Theft Auto』シリーズといった超大作たちこそが、本作の比較対象にふさわしいようにすら思える。
戦略ゲームといえば、どのように現実を抽象化・単純化してゲームシステムに落とし込むか、ということに焦点が当てられがちである。しかし本作はむしろ、可能な限りデフォルメせずに、ありのままの現実を描こうとしていると感じられる。それは奇しくも本作の開始年代となるルネサンスの芸術を思わせる、写実的な表現技法だ。『EU5』はストラテジーゲームの雄、Paradoxによるルネサンスの試みであり、その結果生み出された巨大な怪物リヴァイアサンなのだ。
どうやったらこんなゲームを作れるのか想像もできないし、もっと言えば開発陣がこんなゲームを作ろうと考えたことすら信じられない。ただ感じられるのは、ゲームの中に近世の世界をまるごと作り出そうとした、開発陣の狂気じみた意気込みである。こんな作品が現実に生み出されたという事実を、筆者は未だに信じがたいような気持ちでいる。夢にすら見なかった愛すべき怪物に、筆者の個人的GOTYを捧げたい。
by. Akihiro Sakurai
『Tainted Grail: The Fall of Avalon』
──湯を沸かすほどの熱いRPG愛
開発元:Questline
販売元:Awaken Realms
対応機種:PC/PS5/Xbox Series X|S

『Fallout 3』をプレイしたときの衝撃を覚えている。PS3の本体の中に街が、世界が丸ごと入っていた。良い所は多々あれど、要は「未知の世界を自らの手で探索する」という一点にやられたのだ。偶然の出会いによる期待感と、そのハードルに応えるユニークな報酬。こと「探索」においては、筆者にとってベセスダ作品を超えるものは無い。
だからこそ、最新作『Starfield』の探索は残念だった。多彩なアクティビティは魅力的で当初は楽しめたが、探索のメインとなる惑星の地表はプロシージャル生成の繰り返しで、報酬もほとんどがランダム装備。1200時間以上遊ぶなかで徐々に心躍る瞬間は減っていき、最終的に残ったのは漆黒の宇宙空間と同じ空虚感だった。
最新作を心から楽しめず、自分もいわゆる“懐古ファン”に成り下がってしまったのだろうか……そんな疑念を払しょくしてくれたのが『Tainted Grail: The Fall of Avalon』だった。
今年5月に正式リリースされた本作は、アーサー王伝説をダークに再解釈し「オープンワールド一人称視点RPGへのラブレター」を掲げたRPGだ。『Skyrim』ライクなシステムをベースに、回避偏重のスピーディな戦闘といった独自要素を加えている。だが本作を特別たらしめているのは、間欠泉のように湧き出る「未知」との出会いだ。
大岩に磔にされた巨人が鎮座する村や、血の池の底に隠れた洞窟など、少し進むごとに異質な何かが表れる高密度のフィールド。そして膨大な種類のユニークアイテムがちりばめられた世界は、どこへ行っても「手ぶらで終わる」ことを許さない。ハイペースで見つかる装備や魔法はいずれもプレイスタイルを変えうる多様性があり、「試すのが追い付かない」という贅沢な悩みも生まれる。“敵をチーズに変える攻撃魔法”、“多眼爬虫類の赤ちゃん”など実用性のないものも大量に存在し、違う角度から好奇心を刺激してくる。
プレイ中どれだけ「なんだこれ」と思えたかを重要視する、そんな“未知との遭遇ジャンキー”である筆者の冒険心を、本作は満漢全席のように過剰な物量でもてなしてくれる。この探索への返報性の高さが、「ここにも何かあるだろう」という信頼関係や、アヴァロンの地を隅々まで歩きたくなる動機を生む。
ベセスダ的なRPGへの敬意と熱意が、プレイ中の手触りや、痒い所に手が届く最適化されたシステムを通して伝わってくる。気づけばコントローラーの存在を忘れ、モニターの中に頭を突っ込んでいるような没入感を覚えるほど熱中していた。『Fallout 3』と同じ、自分の足で歩む感覚だ。長らく忘れていた、筆者にとっての「探索」の原体験。昔と同じ熱中を感じさせてくれた本作に、愛を込めてGOTYを贈りたい。
by. Yusuke Sonta
『Fretless – The Wrath of Riffson』
──さぁ、いっちょかましてこい
開発元:Ritual Studios
販売元:Playdigious Originals
対応機種:PC

年末が差し迫ったある日、個人的ゲーム・オブ・ザ・イヤーを選ぶことになり、私は少し困ってしまった。ゲームの記事を書いていても実際に遊んでいるときも、開発者の工夫やこだわりを垣間見ると、どの作品も好きになってしまうからだ。候補は多くともひとつを選ぶというのは、それだけで骨の折れる仕事だった。
さて、私が選んだのは『Fretless – The Wrath of Riffson』である。一人のミュージシャンが悪のレーベルの陰謀に立ち向かうという、それほど長くないRPGだ。グラフィックはかわいいドット絵調で、どこもかしこも音楽にちなんだモチーフが散りばめられている。ミュージシャンがバトルするとあって、楽曲も素晴らしい出来だ。ただ、私はこのゲームを始めた最初の1時間ほど、それほどおもしろいとは感じなかった。どの要素も良い出来だが、肝心の戦闘はただのコマンドRPGのように思えたのだ。その評価はすぐに覆ることになる。
本作の戦闘ではQTEが求められる。タイミング良くボタンを押すと、敵に与えるダメージが大きくなったり、敵から受けるダメージを減らせたりするシステムだ。この仕組み自体はそう珍しくはない。ところが、ここでひとつの引っかかりが生ずる。入力受付時間がほかの作品と比べて妙にシビアなのだ。なかなかQTEを成功させられない。そのことも当初の「本当におもしろいのか?」という思いにつながっていたのだろう。なお一応QTEの判定を甘くする設定もあるが、このシビアさこそが本作の肝なのでオススメはしない。
なぜ判定がシビアなのか。答えは「音楽」だ。戦闘をうまくこなすには目押しに頼ることなく、しっかりとリズムに乗らなければならない。何度も戦闘で同じリフを使っていると、次第にそのリフのタイミングがわかり始める。まるで自分のものにしたような感覚になってくるのだ。つまり本作の戦闘は、新しい楽器を始めたときのような「思ってたより地味で楽しくない」が、習熟するにつれ「最高に楽しい」に変わっていく。ゲームそのものが音楽なのだ。いつしか身体は自然と揺れてリズムと同化し、自分がとてつもないミュージシャンになった錯覚さえおぼえた。
ところで私は幼少期からピアノを習っており、大学ではサークル活動でバンドもやっていた。基本的にはベースを弾いていたが、時にはキーボードを借りることもあった。オリジナル曲を作る楽しさや、本来ギター2本でやる見せ場パートの片方をキーボードで務め、速いフレーズまでバチッと合わせきったときの快感は今でも覚えている。日常的に演奏をしなくなってから久しいが、本作はかつて音楽に賭したあの頃の感覚を呼び覚ましてくれた。そしてゲームを終えてみると、控えめに感じられたボリュームすらも熱いライヴのように「もっと続いて欲しかった」という余韻を残している。今年プレイした数多くの作品の中で、燦然と輝く思い出となった1作であった。
by. Naoto Morooka
『Type Help』
──ミステリーゲームの新しい可能性
開発元・配信元:William Rous氏
対応機種:itch.io(ブラウザ/PC)
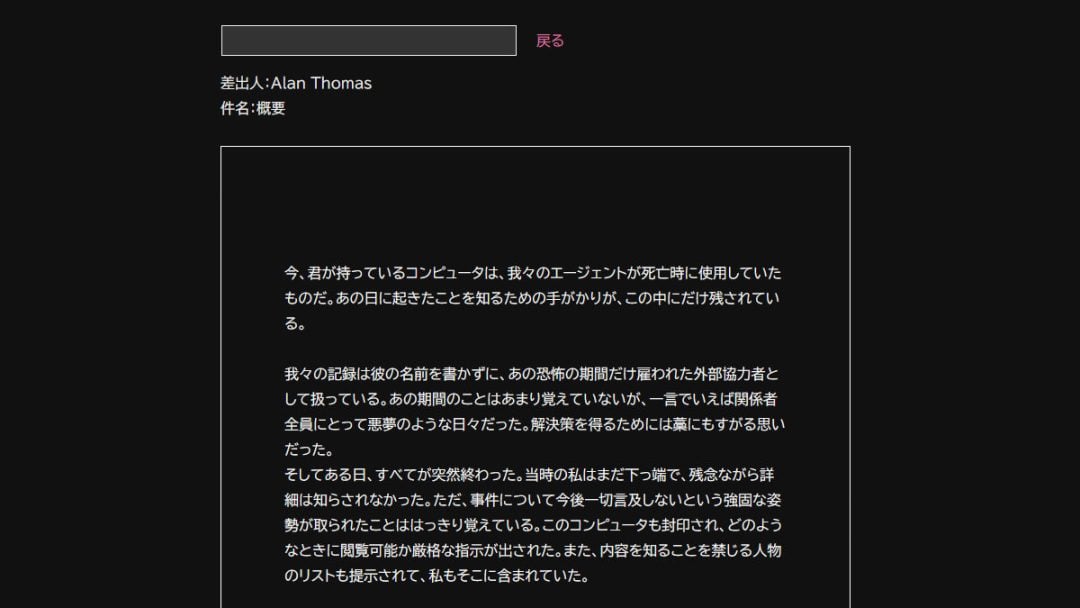
『Type Help(Type Help by William Rous)』は、古いコンピューターのファイルへアクセスして大量の遺体が発見された怪奇事件の真相を追っていく、ミステリーゲームである。本作の世界には1930年頃、Galley Houseなる何十年も空き家のままの屋敷が存在していたのだという。しかし1936年3月、地元の人達がなぜかそんな空き家へ向かうと、大量の遺体が存在していた。遺体はいずれも死亡したばかりで、ほとんどは死因も特定できず、身元が公になったのは1名だけだった。手がかりがなかったこともあってか、やがて事件は忘れられていったそうだ。
本作でプレイヤーは、あるエージェントが使用していたというコンピューターを入手し、怪奇事件を追っていく。なぜ、Galley Houseには大量の死体があったのか。どうして、彼らは死亡したのか。そもそも、彼らはどこの誰なのか。本作では謎だらけの怪奇事件を巡る、壮大なミステリーパズルが繰り広げられる。なお本稿では仕組みから探る作品の性質上、基本的に内容を開始5分程度で得る情報にとどめているが、あらすじで興味を持ったのなら、無料なので先を読む前にプレイしたほうがいいかもしれない。本作は、いずれも推理ゲームである『Return of the Obra Dinn』『Her Story』などからインスピレーションを得ており、これらの作品が好きだったのならきっと本作も好きになるだろう。リマスター版も登場予定となっている。
ミステリーゲームの面白さとは何だろうか。大きな謎の牽引する物語。仮説に仮説を重ねて真相を手繰り、謎を解いた時の快感。点が線となって描かれる、ありえないはずの真実。あるいはルールすら不確かな中、手探りで進めていくゲームプレイそのものだろうか。個人的に、本作にはそのすべてがあった。その上で、本作では謎を解いた時の手応えと、可能性を予感させる仕組みが備わっていた。本作ではファイル名を推測することで、隠された新しいファイルへアクセスしていく。過程では何らかの推理が必要になるが、推理があっていれば新しいファイルが手に入る。さらに物語の続きと新たな情報が手に入り、どんどん引き込まれていく。推理の順番は自由なので、何かに気づいてしまったのなら、早々に回答することも可能。違和感と仮説を抱えて、終盤まで待っている必要はないのだ。そうしたシンプルながら目新しい手応えのある仕組みが、謎解きの気持ちよさを支えていた。また本作は時にゴリ押しも有効であるものの、テキストを読み込んでいくとヒントが存在。メモ機能が用意されており、現代の作品として仕上げが行われている。すでにフォロワー作品が登場しているが、同じ仕組みの作品をもっと遊びたいと思わせられた、新しい可能性を見せてくれた本作に個人的なGOTYを贈りたい。
by. Keiichi Yokoyama
『ファイナルファンタジータクティクス – イヴァリースクロニクルズ』
──我が身の製造責任を問う
開発元・販売元:スクウェア・エニックス
対応機種:PC/PS5/PS4/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Xbox Series X|S

今年は『空の軌跡 the 1st』のリメイクなどもかなり感触が良かったが、とはいえ個人GOTYにリメイク/リマスター作品を選ぶのはやや「禁じ手」感があるだろう。そんな感性もあり、候補として『StarVaders』『White Knuckle』『The Roottrees are Dead』『Million Depth』あたりを吟味していたところ、突然気付きが降りてきてしまった。今年は『FFT』リメイクが出てプレイしたではないか。これは、この企画は、今年だけは、AUTOMATONの誌面を使って自分と『FFT』について語れる最初で最後の機会ではないのか?ふむ……よく考えてみるとリメイク作品がダメだなんてのは自分ルールも良いところである。今年のGOTYは『ファイナルファンタジータクティクス イヴァリースクロニクルズ』以外ありえないだろう。異論などあろうはずもない。
『FFT』は、自分の人生にもっとも大きな影響を与えたゲームと言っていい。特に自分でねだったわけでもないがなぜか自宅にあったPS1と『FFT』は、当時小学校低学年であった自分にとっては初めて本格的に自力で攻略に取り組んだゲームであった。『FFT』のシステムは難解で、あの悪名高い「黒本」も小学生には必須級。第二の説明書として穴が開くほど読み込んだ。しかし、『FFT』が自分にもたらした影響の源泉はゲームプレイ部分ではなく、そのシナリオにある。当時の読書習慣が辞典や図鑑などといったノンフィクションに酷く偏っていた自分にとって、『FFT』は生まれて初めて触れる「大人の物語」であった。その衝撃が自分にもたらした影響は計り知れないと、今になって思う。
『FFT』のシナリオの魅力は多くあるが、もっとも特徴的なのはなんといっても全体的な救いの無さとそのエンディングだろう。幼少期に『FFT』とそのエンディングという劇物を与えられた自分は、ごく素直に「物語の本質とは、辿り着いた結末ではなく、そこに至るまでの過程にある」「物語のキャラクターは、どれだけ不幸だっていい」という強烈な価値観の刷り込みを受けてしまい、それが今に至るまで尾を引いている。いまだに自分は『FFT』のエンディングはゲーム史に残るもっとも美しいエンディングだと思っているし、物語の結末でやや強引なハッピーエンドを見るたびに「なぜわざわざそんなことをするのだろう?」と思ってしまう。美しい物語であるために幸福な結末は必要ではなく、キャラクターはその歩む軌跡が、語る物語が魅力的であれば別にいくら不幸でも良いのだ。なんなら率直に言って、不幸な方が面白い。ハピエン厨の真逆を行くバケモノが誕生しているわけだが、露悪趣味のつもりは毛頭ない。『FFT』による情操教育の賜物である(『FFT』開発陣にとっては心外極まりない製造責任であろう)。そもそも成人してからプレイしなおせばそこまで極端に露悪的でもなんでもないのだが、とはいえ子供にはそれだけ衝撃的であったということだ。プレイしたほうがいいですよ……『FFT』は。人生を変える力がある作品とはまさにこのこと。
by. Mizuki Kashiwagi
『BALL x PIT』
──遊びの原点×革新×中毒
開発元:Kenny Sun and Friends
販売元:Devolver Digital
対応機種:PC/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|S

「ブロック崩し」が好きだった。バーを左右に動かしてボールを跳ね返すというシンプルなルール。隙間から裏側へとボールを送り込み、大量のブロックを壊せたときの快感。遊びの原点そのものだった。しかし、その快感は長くは続かない。さらに、終盤になるとわずかに残ったブロックを延々と狙う時間が続く。ブロックを崩すという楽しみを追い求めるほどに、数が減り快感も次第に失われていくという、やりがいのなさが大きな欠点となっていた。飽きたわけではなくこの欠点が嫌で、いつしかプレイしたいゲームではなくなっていた。『BALL x PIT』がリリースされるまでは。
『BALL x PIT』は、一見するとブロック崩し風のゲームだ。しかし本作は「ブロック崩し」の課題であった、快感が失われていくという構造を解消している。まず本作では敵が画面奥から絶え間なく押し寄せるため、ブロックを壊す快感が延々と続く。どれだけ崩しても、大量にブロックを崩す快感が継続するわけだ。またキャラクターを上下左右に操作し、狙った位置にボールを撃ち続け、跳ね返す必要はない。隙間にボールを送り込むことも、残った敵を処理することも容易に達成できる。さらにはミスという概念が体力に置き換えられることで、快感を途切れさせることなく異なる緊張感をもたらしている。
ここまでであれば、“欠点のないブロック崩し”どまりだ。しかし本作ではこの核となるゲームプレイに、ローグライト要素が組み込まれることで変化が生まれる。武器となるボールのランダム取得および合成により、毎回異なるビルドが構築され、従来のブロック崩しとは逆に時間の経過とともに快感は増していく。また、キャラクターごとにシステム自体が変化し、2人を組み合わせて挑めるため、立ち回りもその都度異なるものとなる。拠点建築による永続強化や敵が強くなるNG+も用意され、画面は派手になりつつも歯応えは失われない。これらすべてが遊べば遊ぶほど魅力が薄まるブロック崩しと対照的に、プレイを続けさせ、もう一度とプレイさせる強烈な中毒性へとつながっている。
既存ジャンルとローグライトを組み合わせた作品は毎年数多く登場するが、本作はブロック崩しというジャンルそのものを新たな次元へと切り開いた。近い将来、このシステムが一つのジャンルとして定着する可能性すら感じさせる。何よりも筆者にまた「ブロック崩しが好きだ」と言い切れる体験を与えてくれた。ブロック崩しの原点の楽しさを思い出させ、快感が増え続ける体験へと変えた『BALL x PIT』に個人GOTYを贈りたい。
by. Haruki Maeda
『Hollow Knight: Silksong』
──ゲームが人生でいちばん大切な人のためのゲーム
開発元・販売元:Team Cherry
対応機種:PC/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PS5/Xbox Series X|S

前作から約8年。待った甲斐はあったと断言できる。『Hollow Knight: Silksong』はいわゆる続編作品が持つ数ある形式の方向性、その究極の1つとして君臨したゲームだ。ゲームデザインに対して数々の「前提条件」を設けることで、「面白い時間しか存在しない」というゲームの理想に限りなく迫ったゲームである。
もとより本作は前作『Hollow Knight』のDLCをコンセプトとして開発されたゲームである。そして、『Hollow Knight』は『ロックマンシリーズ』のみならず、「メトロイドヴァニア」や、「ソウルシリーズ」から大きな影響を受けているゲームだ。つまり、本作は前作をクリアしているという前提をゲームデザインに組み込んでいる、また、前作をクリアしているということは、メトロイドヴァニアやソウルシリーズを攻略する上での文法に詳しい(たとえば壁を叩けば隠し道がある、詰まったら引き返して他の場所を探索するなど)はずである。
結果、チュートリアルのみならずゲームに対する段階的な慣らし、といった退屈さの発生源を極限まで削ぎ落とし、最初からフルスロットルな展開を用意することができている。これは決して暴走ではない。むしろフルスロットルのまま、最初から最後までゲームの面白さを維持できているのだから凄まじい。一見すると攻略困難に見えるエリアやボスでも、他のエリアに足を運べば攻略法が見つかるように設計されているばかりか、攻略方法も多彩だ。仕様に関して理解不能なプレイヤーなど存在しないという前提を置くことで、カットされた説明時間の分、間延びさせないまま体験の豊かさを提供する荒業である。難易度に関してもエリアのギミックとボスがセットで設計され、そのバランスは絶妙である。攻略が難しいギミックのあるエリアのボスの体力は低めに。その逆も然り。ずっと重い苦労が続くデザインになってはいない(とはいえ、前作をクリアできる実力、ストレス耐性を持った人間がプレイしているという前提だが)。細部に徹底的にこだわった背景美術も最高だ。世界の息遣いが聞こえてくるような演出を通じて、困難への挑戦がそのまま未知の冒険に昇華される。
そして何より興味深いのは、このゲームが大ヒットしたという事実だ。本作は上述のゲームデザインからゲーム内容の習熟に時間がかかる。最悪なプレイフィールを抱く危険性すらある。これは完全に筆者の直感ではあるが、高難易度化や複雑なメカニクスを搭載した、プレイヤーへの負担を重視しないゲームの盛り上がりも最近顕著であると思っている。平たく言えば、「ゲーム以上に大切なことがある人」向け作品のみならず、「ゲームが何より大切な人」のためにある作品もまた、改めて強く求められるようになったという印象だ。ゲームは限られた人間にしか楽しめない娯楽から、端末の普及を通じて万人が触れられる娯楽となった。そして今。さらに変化を見せつつある。『Hollow Knight: Silksong』はこの過渡期を象徴するゲームと言えるだろう。
by. Takayuki Sawahata
『スプリット・フィクション』
──見せてほしい景色、見せたい景色
開発元:Hazelight Studios
販売元:Electronic Arts
対応機種:PC/Nintendo Switch 2/PS5/Xbox Series X|S

今振り返れば、筆者のゲーマーとしての原体験には、遊びを通じて他者と感情を共有できるという胸の高鳴りがあったと思う。幼少期から筆者は弟と共にゲームを遊んできた。なにもマルチプレイ作品に限った話ではない。時にはシングルプレイ専用タイトルを一方がプレイし、もう一方が鑑賞。それぞれの“遊びざま”を語り合うことで、ゲームが生み出す感動や興奮を分け合うことも。一つのキーボードをシェアして、無理やり協力することすらあった。筆者にとってのゲームは昔から、その体験を誰かに伝えることまでを含む娯楽だった。
大人になってからもそれは変わらない。筆者は弟と『スプリット・フィクション』を手にとった。別々の姿に変身して異なる役割を発揮したり、互いの背中を追いかけるように共通のアクションを楽しんだり。黒い境界線で区切られた(もしくは一つに繋がった)ゲーム画面には、自らは見せたい景色、または相手に見せてほしい景色が入り混じりながら広がっていた。ちなみに大抵の場合そんな余裕はなかったが、隣の様子が気になってつい脇見をしてしまうこともあった。
協力プレイゲームは数あれど、昨今ではオンラインプレイが基準の作品が多く、お互いが“同じ画面”でゲームをプレイすることも減ってきた。本作ではオンラインプレイであってもお互いが同じゲーム画面を見てプレイするため、非対称的な相手のギミックに目移りするのもさることながら、物語の中で相手が抱く感情が知りたくなった。
そんな本作は、他者と力を合わせて協力し合うにとどまらず、得た体験を「共有」し合うことをプレイヤーに迫るゲームだ。お互いの異なるメカニクスを組み合わせてステージを突破するために、プレイヤー間でのコミュニケーションを要する場面も用意されている。この構図は、初めは必要に駆られて協力していたはずが、気づけば互いの心の支えになっていくミオとゾーイに重なり合う。彼女らの機微を、同じ冒険の中で繰り広げられるシーンの一つひとつを通して分かち合えることに大きな喜びを感じた。そして本作が他の協力ゲームの追従を許さないのは、この特別な共有体験を、映画さながらのプロットと映像美の上に築き上げたからだろう。クリア後もなお、共に歩んだ物語の思い出や感想を共有できるところにも本作の魅力はある。
さまざまなジャンルが飛び交うゲームプレイ、そして同じ画面を共有するゲーム体験からは、並んで同じキーボードを叩いた古い記憶も呼び覚まされた。お互い社会人になり、住んでいる場所も離れ、昔ほどは時間を共にできなくなった弟との、まさに集大成のようなゲームであった。これを読むあなたが、もっとも想いを共有し合いたい人は誰だろうか。そんな相手と一緒に遊んでほしい一作である。2025年の個人的ゲーム・オブ・ザ・イヤーは『スプリット・フィクション』に贈りたい。
by. Shion Kaneko
『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』
──まさに“too 狂”。
開発元:トゥーキョーゲームス、メディア・ビジョン
販売元:アニプレックス
対応機種:PC/Nintendo Switch

優れたゲームの条件とは何だろうか。アイデア、奇抜さ、かわいい/かっこいいキャラクター、中毒性……。『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』が出した答えは単純だ。誰もが“思いついたこと”くらいはあるだろう、シンプルな答え。そう、「100通りの全く異なるエンディングを用意すること」である。
ひとえに物量のすさまじさが、本作を個人GOTYに推す理由である。もちろん物量を抜きにしても、あっと驚く物語展開やキャッチーなキャラクター性など、光るものがたくさんある作品なのは間違いない。しかし、狂気的な領域に到達するためには、ちょっと面白いだけではだめなのだろう。本作は圧倒的な物量を持って、クリエイターの狂気を表現してみせた。
『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』は、最終防衛学園に集められた15人の少年少女が100日間の防衛戦を繰り広げる、アドベンチャーSRPGだ。ごく普通の高校生である澄野拓海は、家族や幼馴染のカルアと共に、平凡な日常を過ごしていた。しかしある時、日常を過ごしていた「東京団地」が襲撃を受ける。気がつけば「最終防衛学園」にいた彼は、特別防衛隊に任命された15人の学生がとともに、正体不明の敵「侵校生(しんこうせい)」から学園を100日間守り抜くことを命じられる。
――冒頭のあらすじだけ見れば、比較的ありそうなジュブナイルものである。本作の怖いところは、物語がここからびっくりするほど分岐する点だ。1つのエンドにたどり着くまでにも30時間くらいかかるし、私は未だに全部のエンドを見ることができていない。ちょっとした差分が100種類あるのではなく、きっちりとした展開の分岐が100種類あるのだ。ある程度プレイした友達とも、別エンドのネタバレを話してしまう可能性があるので全く感想を言い合えない。なんだこのゲーム……。
「全区間実況OK」というのも狂っている。それならば、と挑んだ配信者が敗北していくのをたくさん見た。「アドベンチャーゲームはネタバレに弱いけど、ネタバレしきれないくらいの物量のルートを作れば解決だよね」という発想らしい。ストロングすぎる。
タイムパフォーマンスやゲーマーの可処分時間について話題になることも多い2025年に、物量で押し切るスーパーパワータイプの化け物ADVが出てきたことにも驚かされた。その在り方はまさに「too 狂」。正面から圧倒的な膂力をもって消費スピードの時代を殴りかかった『HUNDRED LINE -最終防衛学園-』に、個人GOTYを送りたい。
by. Aki Nogishi
『真・三國無双 ORIGINS』
──貴公こそ、真の三國無双よ!
開発元/販売元:コーエーテクモゲームス
対応機種:PC/PS5/Xbox Series X|S(Nintendo Switch 2版が2026年1月22日発売予定)

『真・三國無双』シリーズといえば長い歴史をもつIP群だ。筆者の個人的な体験で言えば、特に幼少の頃に触れた『2』の衝撃は大きかった。「三国志演義」の物語の壮大さ。魅力的な武将のひとりとなり、雑兵たち、そして時には敵将すらもなぎ倒していく爽快感。戦場で起こる出来事に次々対応する戦略性。もとより戦記や群像劇が好きであった筆者はすぐさま虜になった。
シリーズが複数作にわたって展開されるにあたっては多くの武将を登場させ、さまざまな戦いを落とし込む必要があっただろう。「三国志演義」のゲームを拡張するにあたって自然な流れでもあったが、シリーズを重ねるごとにある種“キャラゲー”のようになり、物語性よりキャラ性が目立っていた。さらに歴史の連続性や広大さの表現としてオープンワールドが取り入れられた『8』では、時に緊迫感すらもたらすアクション性さえ却って鳴りを潜めてしまったと感じた。
そんな中で登場した『真・三國無双 ORIGINS』。晋建国まで描いていた近年作とは違い、赤壁の戦いにまで描写を絞り、オリジナル主人公が登場。いわゆる“無双武将”は大きく数を減らし、武将ごとに展開されていたエピソードは、主人公、つまり「自分」の視点で紡がれていく一筋の物語に変貌した。これまで拡張を続けてきたキャラやエピソード数がごっそりと削られたわけだ。
しかしその分ストーリーは丁寧に描かれ、戦記物としての厚みが加わった。ミッションをなぞるだけでない、己の“選択”によって変わる運命は劇的だ。さらにはこれまである種、色物や絶対悪として扱われてきた張角、董卓なども、それぞれの信念と重みを感じる、より魅力的なキャラへと相成った。
そしてゲームプレイでは、大軍団と戦法によって演出される「群衆感」はシリーズ史上最高といえる。今まで戦場における舞台装置でもあった、ほかでもない兵卒たちとともに敵陣を駆けあがり、攻勢をかける瞬間の解放感は、初めて『三國無双』に触れた時の高揚を呼び覚ましてくれる。一転して復活したシステムでもある一騎討ちは、一騎当千以前に戦いが命のやり取りであることを思い出させる。
本作における体験は、物語面でも、ゲームプレイ面でも、ナンバリングを取り払い、再出発を名乗るにふさわしい魅力を持ったタイトルに仕上がっている。筆者がかつて『真・三國無双』に触れた時の高揚感を改めて呼び起こしてくれた、夢のようなタイトルであった。とはいえ、『ORIGINS』は名の通り始まりに過ぎない。赤壁の戦いは「三国志演義」において、序中盤の転換点にあたるような戦いだ。三国鼎立もなされておらず、真の意味の「三國」にはまだ遠い。
しかしそれは、筆者にとってはある意味で希望でもある。本作で抱いたこの高揚を、当時のような衝撃を、再びもたらしてくれるとの期待をせずにはいられないのだ。“Origins”として鮮烈な再出発を果たし、心震わす「無双」を届けてくれた本作。そんな本作の門出を祝し、前途を祈る意味でも、『真・三國無双 ORIGINS』に筆者個人のゲーム・オブ・ザ・イヤーを贈りたい。
by. Kosuke Takenaka
『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』
──歩くことに意味がある
開発元:KOJIMA PRODUCTIONS
販売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント
対応機種:PS5

筆者は、『DEATH STRANDING』が好きではなかった。配達ゲームという目新しさはあれど、配達要素だけでは単調で、アクセントとなっている戦闘もステルスもホラーも物足りない。特に終盤では大型の敵との戦闘が繰り返されるが、これも大味なバランスだった。ストーリーについても世界観設定を説明しきるためか終盤には長尺の説明が続き、少し冷めた気持ちでエンディングを迎えた。
『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』でもゲームシステムはあまり変わっておらず、前作から地続きのストーリーが展開される。物語の振り返りも用意されているものの、完全に楽しむためには前作をプレイする必要があるだろう。それでも筆者は迷わずに本作を個人的なGOTYとして推したい。前作を楽しめなかったゆえに、だ。
『DEATH STRANDING 2』では前作から戦闘が増え、配達と並び立つほどの比重を占めている。このことでより際立ったのが、本作が「移動」を体験の本質に据えたゲームという点だ。配達においてはルート選択から始まり、移動手段を選び、戦闘あるいはステルスなどに対処できるように荷造りをするマクロな観点での移動計画が求められる。そして実際の道では転ばないように足場に気を付けたり、敵に見つからないように移動したりといったミクロな観点での移動が必要になる。
ただしこれらは前作からほとんど変わらない流れであり、そもそも前作時点から移動を軸にしたゲームであることは評価されてきた。しかし筆者個人は、プレイを通してそのことに気づけなかった。配達という目的の方に目が行くばかりで移動そのものを体験の核として捉えられていなかった。
一方で『DEATH STRANDING 2』では配達と戦闘が並び立つ要素となったことで、それらを特徴的な移動システムで繋ぎあげていることが手触りとして分かりやすい。また本作の終盤には「移動」がキーワードとしても示されることになる。筆者は否が応でも『DEATH STRANDING』を移動するゲームとして受け止め直すことになった。
そのうえで作中で何度も見続けてきた「山あり谷あり」の風景を最後にもう一度見せられたときに、そして守り抜いてきた存在の尊さを見たときに、筆者の中で不思議なまでに前作と本作の体験が“繋がった”。前作と本作で積み重ねてきた行為が、別の意味を帯びた瞬間だった。
『DEATH STRANDING』の配達は、移動する目的でしかなかった。そして移動とは山を越え谷を越え、何が起こるか分からない先行きの見えない道をひたむきに進み続けること。その中では人と出会い、助け合うこともあれば、恐怖に晒され、別れに涙することもある。
『DEATH STRANDING』と『DEATH STRANDING 2』で体験してきたことは、そんな人生の縮図だ。移動という本質を理解したことで、前作で渋々続けていた配達が、後から意味をもった。2作品分のゲームプレイと物語が渾然一体となって力強いメタファーとして迫ってきた。歩いてきて、よかった。前作と、そして生きることと繋がる体験をゲームとしてもたらしてくれた本作に、個人的なGOTYを捧げたい。
by. Hideaki Fujiwara
『Cronos: The New Dawn』
──その「ホラー」は、なんのために
開発元:Bloober Team
販売元:Bloober Team SA/セガ(国内)
対応機種:PC/Nintendo Switch 2/PS5/Xbox Series X|S

筆者は、ホラーゲーム好きだ。幼少期に『サイレントヒル』といった傑作の洗礼を受けて以来、ホラーゲームに魅了され、手当たり次第に遊び続けている。インディーホラーゲームの流行もあり、近年リリース本数も急速に増えて嬉しいことである。しかしながら、筆者の心には物足りなさも募ることになる。その原因は「好むタイプのホラーゲームが少ない」ことだ。物語ではなく恐怖演出で楽しませてくれるのもいい。アイデアを活かした短編作品も好きだ。しかし、筆者が心の底から渇望しているのは、「ホラーそのものではなく、ホラーを通じて何かを描く長編作品」なのだと思う。
ずっと探索していたいような、なのに一刻も早くその場から離れたいような世界観。開発者の情念が滲むようなデザインとディティール。そして、それらを下地に表現される物語や体験を、筆者は求めていたのである。しかも筆者は我儘にも、できるだけ大きいスケール・ボリュームで、そうした世界に放り込まれたかった。そこに登場したのが『Cronos: The New Dawn』だ。
本作では、「人が融合する」病がパンデミックを起こし、人類はすでに終焉を迎えている。主人公は、その現在を変えるため過去へと乗り込んで、鍵となる人間の意識(エッセンス)を刈り取っていく「トラベラー」だ。プレイヤーはトラベラーとなり、肉の怪物となった人間たちを排除し、やめろと叫ぶ者の意識を抽出し、人の尊厳など顧みない人類救済を遂行していくことになる。
その中で筆者は死と肉が支配する世界を歩き、トラベラーのアーマーをはじめ、奇妙で不安を煽るデザインの数々に目を見張った。そして「自分は正しいのか」「これで本当に世界は救われるのか」と疑念ばかり膨らむ、重い罪悪感を背負わされる物語に囚われた。苦しい道のりを乗り越えたその結末では、さらなる選択がもたらす、罪悪感と絶望が待ち構える。
本作は「選択と絶望の繰り返し」の物語だ。意識をもった者は、意識がある限り、選択を繰り返し罪を犯す。際限なく罪悪感を重ねながら、それでも選んで進んでいく。しかしその無限地獄を進み続けるなら、微かな希望が見えることもあるだろう。本作がホラーゲームとして作り上げた世界観、下地があってこそ、この容赦ない物語は心に食い込むのだと思う。
『Cronos: The New Dawn』は荒削りさもあり、完全無欠の傑作ではない。しかし、本作をクリアした後、筆者は癒しがたいホラーへの渇きが癒やされた気持ちになった。その今年一番の満足感をもって、本作を筆者のGOTYとしたい。
by. Sayoko Narita
『エルデンリング ナイトレイン』
──そんなことも、できるんですね
開発元・販売元:フロム・ソフトウェア
対応機種:PC/ PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One

『エルデンリング ナイトレイン』の初見印象は、率直にいって悪かった。The Game Awards 2024での初報トレイラーを見た時は、ナンバリング新作かと思い胸躍らせたのち、マルチプレイ要素の強さやグラフィックの変化のなさを感じ、期待していた新作ではないことを感じとった。それからも期待値は下がっていった。過去作要素を盛っていたり、出てくるビジュアルアセットに不安をもったり。端的にいえば、フロム・ソフトウェアも“そういう会社になったのだな”と認識した。会社を存続させるため、ヒットした『エルデンリング』IPを使って、他社に外注させて雑にスピンオフゲームを割り切って出していくルートだと、勝手に想像していた。何せDLCも出たばかりであったし、フロムがPvEマルチプレイ中規模ゲームを仕上げられるとは思っていなかったから。
しかしゲームが出てみると、前述の懸念はただの愚かな戯言であることに気づかされた。既存のPvEのゲームを研究しつつもフロムらしさを残したコアゲームプレイ。潤沢な過去作素材によって深化されたゲームプレイ体験。難しいが難しすぎない絶妙な難易度。それぞれのジョブどれも強いと思える巧みなバランス調整。プレイヤーを飽きさせない緻密なアップデートスケジュール。そのアップデートもちゃんとニーズに的確につかんでいる。
自分の中で、“勝手に”物語を作っていた。フロムはマルチも対応できるが、あくまでAAA級シングルプレイメインのアクションゲームを作っていくのだろうと。宮崎英高氏含む少数の精鋭が天才的であるのだと。時代を無視して我流を貫くのだろうと。しかし実態は違っており、マルチプレイゲームを研究し、宮崎氏以外のディレクターが指揮をとり、中価格帯の面白いゲームを作り上げた。自分の中のストーリーは何ひとつ合っていなかったのだ。予想が打ち砕かれたのにもかかわらず、とても嬉しかった。
フロムは「職人」という印象が強い。職人は時代に取り残されるイメージもある。しかしフロムは職人でありつつ、今の時代と共に新しい挑戦をし、自分たちのあり方を開拓しているのだ。新しい挑戦に対して、自分を含む懐疑的な目をもつユーザーを、ゲームのクオリティで黙らせたのである。フロムほどの実力者が、それほどの挑戦をやるのである。そんなことも、できるのだなぁ。
ゲーム業界の荒波が激しくなっており、自分や会社の立ち位置も一寸先は闇。ゆるやかな衰退でもいいので、足を止めたい。動きが早すぎる。しかし挑戦なくして勝ち取れるものはないと、『エルデンリング ナイトレイン』は教えてくれた。自分らしさは、自分たちで変えていけるのだ。だからこそ、挑戦し続けなければない。僕自身を強く発奮させてくれたという意味でも、『エルデンリング ナイトレイン』に個人的なゲームオブザイヤーを贈りたい。ありがとう、フロム・ソフトウェア。
by. Ayuo Kawase
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。



