スクウェア・エニックス 齊藤陽介氏ロングインタビュー。『ドラゴンクエスト』から実写ゲームまで、王道と獣道を歩んだゲームプロデューサーの四半世紀
スクウェア・エニックス 齊藤陽介氏ロングインタビュー。エニックスに入社した93年から実写ゲーム時代、『ドラゴンクエスト』『ニーア』シリーズのプロデュース、アイドルグループの育成から趣味の人狼まで、王道と獣道の両方を歩んだゲームプロデューサーの四半世紀を振り返ってもらう。

「かわいい女の子と目線を合わせる」実写ゲーム
J:
そのあとで実写ゲームを作り始めましたよね。
齊藤:
『アストロノーカ』のデバッグをしながら、『ユーラシアエクスプレス殺人事件』(*)のために調布の日活スタジオに通っていた記憶があります。

*ユーラシアエクスプレス殺人事件:1998年に発売された実写の殺人ミステリーゲーム。齊藤氏がプロデュースした「シネマアクティブ」作品の第一弾。黎明女学園の修学旅行に同行した私立探偵の主人公が、ユーラシアエクスプレス号内で発生した殺人事件の解明を目指す。女子高生たちには好感度パラメーターがあり、キャストとして深田恭子や加藤あい、東山麻美といった新人アイドルを多く起用していた。
ーーでも冒頭の空港のシーンはスタジオ撮影ではありませんよね?
齊藤:
あれは府中の東京競馬場の通路です。それを朝5時集合で撮りました(笑)
J:
他のインタビューとかで実写は嫌だったと書いてあるけど、あの時そんな嫌々やってたっけ?
齊藤:
最初はめっちゃ嫌でした。
J:
確か『ナイトトラップ』(*)やってたよね。
*ナイトトラップ:1992年、メガドライブ向けに発売された実写アドベンチャーゲーム。アメリカ郊外で発生した失踪事件を調査する特殊捜査員として、住宅内の防犯カメラとトラップを使い、悪者から若者たちを救っていく。全く怖さを感じさせないB級映画テイストの作風や、当時米国で議論を呼んだ暴力・セクシャル表現などで知られている、FMVの歴史に名を残す作品。
齊藤:
やってました。とんでもなくつまらないなと思いながらやってました。
J:
結構おもしろそうに遊んでるなと思ってたんだけど、違ったのか。
ーー実写ゲームは、日本ではなかなか売れないジンクスがありますが、そのような実写ゲームをどのようにプロデュースしようと考えたんですか?
齊藤:
『ナイトトラップ』を遊んでいて、なんだこれ、こんなのやだなと。でも何が足りてないんだろうと考えてみたときに、かわいい女の子がいて、そのかわいい女の子と目線を合わせることができれば楽しめると思って。テレビドラマでもそういう演出はありますが、多用はできません。ゲームであればカメラ目線で話すことを必然化できる。それを多用できるんだったら面白くなるんじゃないかと。なので参考にしたのは他の実写ゲームではなくて、『同級生』や『ときめきメモリアル』です。
J:
それまでの齊藤さんの印象として、そういうのに興味があるとは全く思っていなくて、そっちも行けるんだとちょっとびっくりした記憶があります。
齊藤:
めっちゃ勉強しました。ただ、もともとおニャン子クラブとかはみんな好きな世代だったし、「ASAYAN」とかも見ていたから、遠くはないんですよ。世代的にも。当時は誰でも好きなアイドルがいるくらいの距離感だった気がするんですよね。今は趣味が分散してしまったので、「好きなアイドル誰?」とはあまり聞かないと思いますけど。
ーーそもそも会社から実写で作ってとオーダーされた理由は何ですか?
齊藤:
当時の社長の福嶋康博さんから、CGは高すぎると言われて。CGはいくらでも作り直せるけど、実写は一回撮ればそう簡単には撮り直せないので、値段が上がらないだろうという考えです。
ーーでも実写3作目の『ザ・フィアー』になってくると、CGの割合が上がってますよね。
齊藤:
『ザ・フィアー』はCGが多いですね。
ーー『ユーラシアエクスプレス殺人事件』では、小島秀夫さんや故・飯野賢治さん、前述の森川さんなど、多数の著名なクリエイターが出演されていますが、これはどういう経緯だったんですか。
齊藤:
多くは一緒にやっている高島健一さんというディレクターの方からお願いしたんです。話題作りとして。
ーーどうして探偵モノになったんですか?
齊藤:
映像として新しいことをやるんだったら、ゲームデザインはシンプルにしようということで探偵モノにしました。
ーー2時間以内に解くというコンセプトは『Dの食卓』を彷彿とさせます。
齊藤:
それはディスク容量の都合です。映像容量がCD4枚組くらいになり、これ以上増やせない状態になって。容量からシナリオボリュームが決まった感じです。
ーーたった2週間違いで、スクウェアから『アナザー・マインド』というアイドルの実写ゲームが発売されましたよね。当時、どのように受け止めたんでしょうか。
齊藤:
先に発売された『アナザー・マインド』が厳しかったんで、「やばいなこれ」と。
ーーあ、そんな受け止め方だったんですか(笑)
齊藤:
しかもキャストが全員ホリプロさんだったんですよ。キャスティングを同じ事務所にしたほうが楽なんですが、それだと事務所が売り出したい女の子が優先的になってしまうので。女の子全員を均等に可愛くキャスティングできない可能性があるじゃないですか。そういうのは『ユーラシアエクスプレス殺人事件』ではしたくなかったので、かなりがんばりました。
ーーなるほど、それが『ユーラシアエクスプレス殺人事件』のマルチヒロインシステムに繋がってくるわけですね。まさに『同級生』や『ときめきメモリアル』の流れですね。
齊藤:
そうそう、それはまさにそうしたかったです。
ーーちょっと面白い話として、堀井雄二さんは『白夜に消えた目撃者』という時間制限がある列車サスペンスを構想されたことがあるんですが、ご存知でしたか。
*AUTOMATONでは幻の作品『白夜に消えた目撃者』について堀井雄二氏から伺ったインタビューを掲載している(記事リンク)
齊藤:
みたいですねえ。当時はもちろん全然知らなかったです。
ーー『アストロノーカ』に続いて『ユーラシアエクスプレス殺人事件』もシステムサコムが開発していますね。
齊藤:
それは単純に、メインでコーディングするプログラマーが2人くらいで済む仕様だったので、新しい会社に依頼するよりも知っているプログラマーに頼もうと思ったからです。
【UPDATE 2019/11/18 16:45】上回答の誤字修正
ーーそもそも齊藤さんはゲーム業界に入る以前は、アドベンチャーゲームをプレイされていたんですか。
齊藤:
一番好きなのは『デゼニランド』か『サラダの国のトマト姫』です。『は~りぃふぉっくす』や『惑星メフィウス』もプレイしました。関係ないですけど、『ドラゴンナイト』もがっつりやっていたり。最初に買ったのはPC-6001mkⅡですけど。『ポートピア連続殺人事件』はファミコン版からなんですよね。
新人時代のアイドルを大量発掘

ーーそして実写ゲームは売れないというジンクスを破って、『ユーラシアエクスプレス殺人事件』はヒットしたと聞いています。
齊藤:
まあまあ売れましたね。深田恭子さんと加藤あいさんのおかげですよ。
J:
キャスティング当時は本当に新人だったはずですよね。
齊藤:
週刊少年マガジンで1回グラビアをやったかやっていないかくらいのときでしたね。
J:
発売のタイミングで東京ゲームショウをエニックスがやったじゃないですか。その時、ひどいことになったの覚えてます?
齊藤:
俺がステージにいて、隣の隣くらいのブースまで人が集まったのを覚えてます。
J:
イベントをやっている最中に、スタッフが隣の隣のブースまで謝りに行ってたもん。しかも日曜日だったよね。
齊藤:
前日に登壇したのは佐伯日菜子さんと東山麻美さん。
J:
確かその2人が仲良いから、深田恭子さんと加藤あいさんを一緒の日にしたんだよね。そしたらもう見物のお客さんの量がすごい。
齊藤:
事前にサインを書いてもらい、俺が急遽ジャンケン大会をしている間に後ろからはけてもらいました。パニックになりそうだったから。
J:
あのときに芸能人の凄さを覚えたよ。芸能人の瞬発力と、売れるときの勢い。『ユーラシアエクスプレス殺人事件』は齊藤さんにとって、ひとつのエポックメイキングだったよね。
齊藤:
新しいことはできたかなと思いました。ウォークスルーを同ポジでつなぐということと、待機アニメーションを止めにしないで3秒くらいの映像を再生と逆再生で作っていることは、『ユーラシアエクスプレス殺人事件』の挑戦ポイントだったと思います。
ーー静止画の実写ゲームではなく全編動画の実写ゲームというところが、当時、画期的でした。
齊藤:
そのあとの『øSTORY』(*)は、もっとやりたいことがあったんだけど、できなかったんです。PlayStation 2は「ポリゴンマシン」だとずっと言われていて。ソニーさんのミドルウェア開発もポリゴンに注力していて、動画再生のミドルウェアが最後の最後まで出てこなかった。だから素材はあるのにいつまでたってもPS2で開発できなくて、やりたいことを削ぎ落とした結果、今でいうQTEがメインになった感じです。
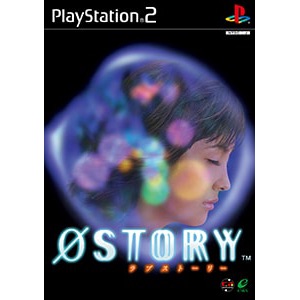
* øSTORY(ラブストーリー):2000年、PlayStation 2用に発売されたシネマアクティブ第2弾。交通事故で亡くなった青年が、霊体となって現世に戻り、若手アイドルのリナと6日間共に過ごす。主人公の言動によりリナの愛情値が上下。リナの心を読む「心の矢」システムを導入していた。リナ役は平山あや。そのほか眞鍋かをり、藤崎 奈々子、佐藤 江梨子などが出演。
ーーもっとやりたかったけどできなかったというのは、具体的にはどういった内容ですか。
齊藤:
例えば一人称視点で映像空間の中を自由に移動したり、幽霊になってもっと動けるようにしたかったんです。
ーーなるほど、そこは『ユーラシアエクスプレス殺人事件』が踏襲されている感じですね。製品版では弓矢を引いたら心の声が読めるというシステムが含まれていましたが、これは最初から構想としてあったんですか。
齊藤:
回数制限で使える弓矢のシステムは最初から考えていましたね。それは開発後期でギリギリ、かろうじて入ったアイデアです。
ーー取材の直前に『øSTORY』を改めてプレイしたのですが、エモーショナルで感動しました。女の子の心理状態がわからないけれど、弓矢を引いたら実はこんなことを思っているという、そこのギャップが泣けますね。
齊藤:
そうそう、俺はあの最後の展開も好き。プレイヤーの名前を呼ばせるっていうね(笑)
ーー探偵モノの前作から一転して芸能界モノになってますね。
齊藤:
芸能界モノというよりは、ファンタジーをやりたかったんです。自分が幽霊になって、普段見れない絵が見れるという。空撮とかも含めて。
ーー今作から主人公が喋るようになりますが、そこの変更について迷いはなかったんですか。
齊藤:
確かに迷いましたが、ドラマとして作る期間など、いろんなしがらみを考えたときに、喋った方が楽という判断になりました。
ーー実際、しゃべったほうが良かったと思います。映画のように観賞できる楽しさが増えたので。
齊藤:
自分もそう思いますね。
J:
『øSTORY』で覚えているのは、眞鍋かをりさん。デビューしたてだったよね。あと佐藤江梨子さん。佐藤江梨子さんも確か東京ゲームショウで大変だった。『øSTORY』の時は危ないから囲いのあるステージでやってたんだけど、ぎゅうぎゅうになって大変だった記憶がある。
齊藤:
『øSTORY』といえば平山あやさんも。最近、速水もこみちさんと結婚しましたね。
「俺が獣道を作ったら、他のみんながついてきた」
J:
その翌年にもう『ザ・フィアー』(*)を出していますよね。
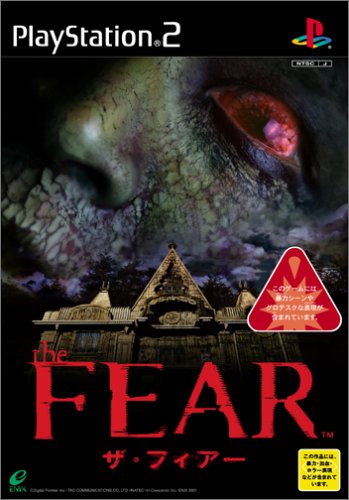
*ザ・フィアー(the FEAR):2001年、PlayStation 2用に発売されたシネマアクティブ第3弾。実写ムービーシーンが多く、ディスク4枚組での販売となった。心霊番組の撮影のため山奥の洋館に訪れた撮影班と売り出し中のタレントたちが不可思議な事件に巻き込まれていく。引き続き若手アイドルを起用しており、今作では芸名のまま登場。加藤夏希、金田 美香、福井裕佳梨などが出演。
齊藤:
めっちゃ仕事してました。今もしてるけど。『ザ・フィアー』は最後だからいいだろうと、お金を使いすぎました。
ーーあの作品の撮影は実際のペンションなどを借りて改造したのか、それともセットを組まれたんですか。
齊藤:
あれは東映大泉のスタジオです。2階建てに見えるけど、セットは実際にそのように組んだわけではないですよ。その階のひとつの通路を全部実際に作って、通路に見えてる扉の中身はない部屋も多いんです。各部屋は隣のスタジオにバラバラに作ってて、それを後で繋げています。
ーーあの背景の美術はどこまでがCGで、どこまでが実写なのか境界線がわからないです。
齊藤:
あれは全部実写ですよ。
ーーえ!?まさか……それはとんでもないですね。小物含めた美術がとにかく凝ってて、物凄くゴージャスでセンスがありますね。
齊藤:
『ユーラシアエクスプレス殺人事件』もそうだけど、映画のフルスタッフでした。
ーー『ザ・フィアー』では題材がホラーになって、後半になると女の子がえらいことになりますが、事務所からクレームがきてもおかしくない過激な表現ですね。
齊藤:
そこはホラー含めて監督の趣味ですね。監督が小田一生という漫画家の伊藤潤二さんの映像作品に多数関わっている人なので、ジャパニーズ・ホラーなんですよ。後半に関しては、ちゃんとそういう話ですという前提で皆さんに出演してもらってます。
ーー確かに怖いというより、伊藤潤二さんみたいに精神にくるような不気味な感じですね。あと、エンディングが大きく2つあって、しかも片方はクトゥルフ神話みたいな展開ですが。
齊藤:
それも監督の趣味ですね。私自身もクトゥルフ神話は大好きなんですが。『ユーラシアエクスプレス殺人事件』も『øSTORY』も、繰り返し遊びたくなるようにマルチエンドを入れました。絶対にマルチエンドじゃないといけないという訳ではなかったです。
ーー『ザ・フィアー』は、攻略サイトがなく、攻略本も発売されてないので聞きたいんですが、あの2つのエンディングの分岐条件は何なんですか。
齊藤:
途中の細かい分岐はプレイ時間とかをチェックしてて、クライマックスの大きな流れについては多分、監視カメラをメイクルームに置くか、寝室に置くかだったと思います。でも、正確な条件は忘れました(笑)。

ーーこれはかなり聞きたかったんですが、当時、『ザ・フィアー』の発表会では『レベルダイブ』という次回作を発表していますね。しかしこれは未発売のようですが。
J:
いや、『レベルダイヴ』は、『コンバットクイーン』(*)として発売されたんだよね。これは齊藤さんが最初だけ関わったんだっけ?
*コンバットクイーン:2002年、タイトーよりPlayStation 2用に発売された実写ありのガンシューティングゲーム。昆虫型ロボットに侵略された近未来の地球を舞台に、美少女アンドロイドたちが大活躍。若手時代の小池栄子、周防玲子、水川あさみなどが出演している。
齊藤:
いや、あれは渡部です。あの当時は、俺が獣道を作ったら、他のみんながついてきて似たようなものを作るという流れがあって。例えば俺が『クロスゲート』を作ったら安藤武博が『疾走、ヤンキー魂。』を作ったり、柴貴正が『ディプスファンタジア』を作ったり。俺が実写ゲームを作ったら安藤が『鈴木爆発』を作ってくれたし、渡部辰城は『コンバットクイーン』を作ってくれました。俺が歩んだジャンルを後輩たちが追いかけてくれているというイメージはありました。
ーー発表会では、シネマアクティブ第4弾と宣伝されていたようですね。
齊藤:
シネマアクティブは、本多圭司さんが「ジャンルを作らないといけない」と言ってつけた名前です。俺はピンとこなかったんだけど、まあいいやと。
*本多圭司:エニックス2代目社長。のちにスクウェア・エニックス・ホールディングス副社長・取締役を歴任。エニックス時代、齊藤氏がグッズ部門からデジタルゲームの企画部に異動するきっかけを作った人物でもある。古くから『ドラゴンクエスト』に続く主要タイトルを作り上げることを目標として掲げており、齊藤氏は今回のインタビューにて、そんな本多氏が退任する2018年までに『ニーア』IPを育てられたことを誇りに思っていると語っていた。
ーー『ザ ・フィアー』のクライマックスでもシューティングになるじゃないですか。それが『コンバットクイーン』に受け継がれたのかな?と思ったんですが。
齊藤:
ハハハ!全くないです。開発会社も違いますし。
オンライン運営の基礎を築いた『クロスゲート』
J:
『MaildeQuest(メールでクエスト)~虹色の夜~』(*)(のちに『みんなdeクエスト -那由多の道と異界の扉-(なゆたのみちといかいのとびら)』に改名)はいつ出したんだっけ?
*『MaildeQuest(メールでクエスト)~虹色の夜~:2001年にサービスが開始された多人数型ファンタジーRPG。ウェブブラウザでサーバーにアクセスしてキャラクターに指示を出すと、その結果がメールで返ってくる。30日300円の利用権で手軽に遊べるのが特徴であった。
齊藤:
『クロスゲート』発売直前です。当時PCショップまで行ってPCゲームを買ってもらうのはめちゃくちゃハードルが高かったので、まずはPCを持っている人ならば絶対に持っているウェブブラウザとメーラーで遊べるRPGを作っておきたいという意図があったんです。当時のソニー・コンピュータエンタテインメント(現ソニー・インタラクティブエンタテインメント)さんがやっていた「ゲームやろうぜ!」というゲーム開発者発掘企画で、ウェブゲームを作っていたリンドブルム(Lindwurm)という開発チームがあって、そこにダイレクトに連絡を取って作ったのが『MaildeQuest』です。
J:
『MaildeQuest』はめっちゃハマった。あれは面白かった。
齊藤:
当時はアイテム課金とかがなくて、月額300円だけでしたけど、もっと売上を出す方法があったかもしれないですね。
J:
メールで届いて結果がわかるという仕組みがよかった。
ーー今だと、なかなかピンとこないシステムだと思うんですが、実際、どういう仕組みだったんですか?
齊藤:
1日2回ウェブブラウザにアクセスして、自分の行動を入力すると、その行動の入力結果がメールで返ってくるという仕組みです。バトルで終わる日もあれば、冒険のフラグが立つと小説のような文章が返ってくる日もあります。
ーーヒットしたんですか?
齊藤:
ウェブブラウザでやっていた人はそんなに多くはなかったと思いますが、そのあと携帯電話向けに展開して結構な数の方に遊んで頂いたと思いますよ。
J:
『クロスゲート』(*)の方は台湾でヒットしたんだよね。齊藤さんが何度も台湾に行ってたのを覚えてる。
*クロスゲート:2001年にサービスが開始されたMMORPG。ほのぼのとした世界観の中、最大5人パーティーでのターン制バトルが楽しめた。国内サービスは2007年に終了したが、中国・台湾などではさらに長く愛されるタイトルとなった。
齊藤:
日本で稼げないと思って、自らカバンにノートPC入れて売りに行きました。小林と一緒に。韓国なんてW杯前だったので看板に英語とかが一切書いてなくて。ハングルだけ。なのに3日くらい経つと「カルビ」っていう字がなんとなく読めるようになる(笑)
J:
小林さんは今海外タイトルをみていますよね。彼は齊藤さんに連れられて回った経験があるから、そのあとスクウェア・エニックス中国に行って。そして海外タイトル専用レーベルの「エクストリームエッジ」に。だから小林さんの将来を決めたのは齊藤さんみたいなもんだよ。
齊藤:
ハハハ。
J:
あのころは本当に海外飛び回ってたよね。
齊藤:
そうですね。中国では2000万ダウンロード達成ということで、行った甲斐がありました。
J:
ゲームの発売後は海外に行って何をしていたんですか?
齊藤:
今でいうファンミーティングですね。ファンの人が継続的に遊んでくれているので、開発者が行って話してくださいという流れだったと思います。当時もうブロガーという言葉があったか定かではないですが、ゲームを広めてくれる人たちを食事に呼んで盛り上げましょうという会です。『クロスゲート』は今でもサービスしていますよ。スマートフォン向けにもリリースして、この間はそれの発表会に呼ばれて行きました。あと『クロスゲート』を学生時代に遊んでくれた人たちが、中国のゲーム会社の要職にいたりもします。
ーー韓国では『クロスゲート』が発売された当時からオンラインゲームの人気がありましたよね。
齊藤:
ありましたね。韓国でも発売したんだけど、すでに勝てる土壌ではなかったです。それでもある程度は売れましたが、台湾・中国の方が圧倒的に売れました。
ーーそもそも『クロスゲート』はどうやって企画が始まったんですか?
齊藤:
『ウルティマオンライン』とか『ディアブロ』をめっちゃ遊んでいて、新聞を読んでいたら日本でオンラインゲームを開発している会社があるという記事があって、「(北米が相当先行しているジャンルなのに)こんなバカなことを真剣にやっている会社がある、嬉しい」と思ってコンタクトを取りました。半年くらいかけて本多を口説いて、出張を許して貰って大阪に行って話をしたらめっちゃすごくて。当時からブラウザだけでMMOを作っているような京大生がいたんです。中嶋謙互(*)という天才プログラマーです。彼らは当時日本システムサプライという会社で『ストーンエイジ』というMMORPGを独自に作っていました。知る人ぞ知るゲームですよ。『ストーンエイジ』と、セガの子会社(ネクステック)が作った『ダークアイズ』は、日本の商業MMORPG黎明期において双璧を成す作品です。
*中嶋謙互:2010年までコミュニティーエンジンの代表取締役/CEO。現在はモノビット取締役CTO。
ーー『ウルティマオンライン』や『ディアブロ』はアシスタントプロデューサーの仕事をしながらやっていたんですか。
齊藤:
そうです。家に帰らず会社で『ディアブロ』『エイジ オブ エンパイア』『Doom』『Rainbow Six』らへんをやっていました。『エイジ オブ エンパイア』は負けた人が晩飯に牛丼を買ってくるみたいな謎なお約束がありました。
J:
夜にゲームで遊んで、そのあと飲みに行って、でも朝方ちゃんといるという、わけがわからない生活をしてましたよね。
齊藤:
夜中に仕事をしていると遠くから「ブォーンブォーン」という戦いが始まる音が聞こえてくるんですよ。当時はみんなMacで、社内LANで遊んでました。
ーーRTSやFPSをエニックスから出す動きはなかったんですか?
齊藤:
FPSではないんですが、対戦シューティングは地味に作っていました。『ポップンタンクス!』です。当時コンシューマーでは小さいキャラクターのゲームは売れないと言われていて、RTSが面白いことはわかっていたけれども作る人がいなかったんです。そもそも日本でRTSをちゃんと作れる会社はそうそうなかったですし。
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。



