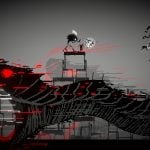アクション×ターン制ローグライク『Enter the Chronosphere』は「日本でなぜかめっちゃ人気」、心当たりないのに。その理由や日本ファンへの気持ちを開発者に訊いた
本作は発表以来日本からの注目度が高く、開発元も日本向けに専用トレイラーを制作するなど、力をいれているという。この度弊誌では、本作の開発を手がけるEffort Starにメールインタビューを実施。

パブリッシャーのJoystick Ventures/Gamera Gamesは、『Enter the Chronosphere(エンター・ザ・クロノスフィア)』を配信予定だ。対応プラットフォームはPC(Steam)で、ゲーム内は日本語表示に対応予定。
『Enter the Chronosphere』はSFローグライクゲームだ。舞台となるのは、クロノスフィアと呼ばれる次元のゆがんだ異空間。プレイヤーは個性豊かなヒーローを操作して押し寄せる敵と戦い、クロノスフィアの最奥を目指す。本作は1ターンが細分化されシームレスにつながっているシステムが特徴で、アクションゲームとターン制バトルが融合したようなプレイ感覚の作品になっている。
本作は発表以来日本からの注目度が高く、開発元も日本向けに専用トレイラーを制作するなど、力をいれているという。この度弊誌では、本作の開発を手がけるEffort Starにメールインタビューを実施。日本語のプレイ動画を観るのが好きだという開発スタッフより、日本ユーザーへの想いやゲームシステムにこめられた狙いなど、興味深い話を訊けた。以下にその内容を紹介する。
──自己紹介をお願いします。
Ned Kirner(以下、Ned)氏:
ゲームデザイナーのNedです。Effort Starはオーストラリア・メルボルンに拠点を置くインディースタジオで、メルボルン出身のスタッフ9人を中心に、ゲーム開発をおこなっています。現在は『Enter the Chronosphere』の開発に励んでいます。
──『Enter the Chronosphere』の開発はどのようにスタートしたのでしょうか。
Ned氏:
『Enter the Chronosphere』の開発は2021年に、ゲーム制作イベント「7 Day Roguelike Competition」に参加したことがきっかけで始まりました。同イベント向けに作成したプロトタイプ版が好評で、それ以来開発を進めています。イベント参加当時はもっとこじんまりとした開発チームでしたが、現在はアーティストやミュージシャン、プログラマーなど複数の才能あるスタッフがチームに加わっています。現在公開中のデモ版も世界中のプレイヤーに遊んでいただくなど、好評をいただいております。
──本作の特徴や魅力について教えてください。
Ned氏:
本作の特徴は、ターン制の戦術ゲームとリアルタイムのアクションゲームが組み合わさったゲームプレイです。基本はターン制なのですが独自システムが盛り込んであり、一般的なターン制ゲームではなかなか見ないような、バラエティに富んだスタイルで戦いが楽しめます。
また明るいコミック風で、サイケデリックなアートスタイルも本作の特徴です。いろいろな時空が融合した世界観の本作では、さまざまな世界よりユニークな武器やアイテム、アビリティなどが登場します。
さっそく人気のキャラクターもいます。たとえばUrtarは、デモ版のプレイヤーより人気のキャラクターです。彼はクマのバーサーカーで、アビリティを使うことで弾丸を弾いたり、ダメージを吸収したりすることができます。こうした個性ある見た目や性能のキャラクターたちも、本作の魅力といえるでしょう。

──日本からのSteamウィッシュリスト登録件数が好調だとおうかがいしました。何か件数が増えるきっかけのような出来事があったのでしょうか。日本から注目を集めている理由について、ご自身ではどのようにお考えですか。
Ned氏:
もともと我々の公式X(旧Twitter)アカウントは、日本人ユーザーのエンゲージメントが驚くほど高かったのです。開発初期にゲームプレイ動画をXに投稿して以来、日本の方からは定期的にコメントをいただけています。ただより多くの方に興味をもっていただけたきっかけは、よよよ氏による実況プレイ動画だと思っています。
私は日本語はわかりませんが、知らない言葉でのゲーム実況を視聴したり、自分が手がけたゲームデザインを通じて人々と意思疎通したりするのはとても楽しい経験でした。私は3歳のころから、日本のゲームが大好きでした。時がたって今自分がゲームデザイナーとなり、日本の皆さんが私のゲームを遊んでくださっているのを観ると、特別な想いがわいてきます。
とはいえ、本作がなぜ日本から注目を集めているのかは、自分でもわかりません。シューティングゲーム的なゲームプレイにターン制バトルのひねりを加えた本作のゲームシステムに可能性を感じていただいているのか、あるいは特徴的な敵のデザインが気に入っているのか。ぜひ、日本の皆さんから理由を教えていただきたいです!
──ウィッシュリスト件数の多さは日本向けのマーケティング展開に影響しましたか。
Ned氏:
そうですね。まだ英語でしか発信をおこなっていなかったころから、とても多くの日本のプレイヤーが本作に注目してくださっていました。そこで我々としても日本へより注力していくことになり、日本語で新トレイラー動画を制作するなど、力をいれました。INDIE Live Expoに参加したのも、日本向けへの注力の一環です。新たなトレイラーをお披露目するとてもよい機会でしたから。
──本作を作るうえで、影響を受けた作品などはありますか。
Ned氏:
当スタジオのリードプログラマーであるRhysは『NetHack』『Ancient Domains of Mystery』といった古典的ローグライクゲームの大ファンで、本作もそうした作品から影響を受けています。一方私は以前仕事として『ダンジョンズ&ドラゴンズ(D&D)』のゲームを数年間運営しており、そこではさまざまな種類のアクションを、ターン制バトルのシステムとして表現する楽しさを学びました。
また、予想外と思われるかもしれないような作品からも影響を受けています。たとえばオリジナル版の『DOOM』からは、シンプルな挙動の敵も適切に組み合わせることで、とても豊かな戦闘体験が生まれるということを学びました。本作にたくさんのショットガンが登場するのも、『DOOM』の影響です。ショットガンにアタッチメントとしてショットガンを付けることも可能なんですよ。本作に登場する武器やエネミーのデザインは、さまざまな作品からインスピレーションを得ています。
──本作のリアルタイムアクションとターン制戦術バトルが融合したシステムはとてもユニークだと感じています。このシステムはどのように考えつかれたのでしょうか。

Ned氏:
本作の基本的なゲームシステムは、伝統的なローグライク作品に由来しています。ターン制で、プレイヤーが一回行動するとすべての敵が同時に行動するなど、基本はそのままです。ただRhysは正方形のタイルに縛られない、「グリッドなしのローグライクゲーム」というゲームシステムの構想をもっており、それが本作の出発点となりました。
本作のコンセプトは古典的ローグライクからグリッドを取り除き、命中を乱数で決めるのではなく、実際に弾を避けられる戦闘を再現する、というところから始まっています。2D空間を自由に動き回ることができ、アクションゲームのように本当に弾に当たったかどうかで命中が判定されるターン制バトルを追求したいと思いました。
プロトタイプ版が完成すると、このバトルシステムは想像以上にエキサイティングでした。弾幕シューティングのように弾をすり抜けられるのですが、あくまでターン制ですので、プレイヤーは好きなだけ時間をかけて考えることができます。じっくり数手先を読んで、次の行動を決められるわけです。一方本作はターン制ですがあえて立ち止まらず、ノンストップで動き続けることもできます。その場合のプレイ感覚は、ほとんどリアルタイムのアクションゲームをプレイしているのに近くなります。
──本作を制作するうえで、こだわっているところはどこでしょうか。
Ned氏:
気をつけているのは、スピード感とわかりやすさのバランスをとることですね。ほぼリアルタイムのスピードでプレイしても、画面で何が起きているか明確であるというのはとても重要なことです。プレイヤーには「ゲームのペースを完全にコントロールできている」と感じてもらう必要があります。
またわかりやすさのために調整した点でいうと、たとえば開発初期には、強力な武器の発射など特定のアクションの実行に2ターンかかっていました。しかしこれはプレイヤーを混乱させることがわかったため、カットしました。現在はすべてのアクションが1ターンで終わるようになっています。わかりやすさはプレイヤーが計画を立て、次に何が起こるかを予測できるようにするために、非常に重要なことです。
──本作では自分の撃った弾によって死ぬこともしばしばあります。自爆が敵の攻撃と同じくらい危険なゲームだと思うのですが、なぜ自分の攻撃でダメージを受ける仕様にしたのでしょうか。
Ned氏:
主な理由は視認性と一貫性です。プレイヤーには画面を一目見て、いま何が危険なのか理解してもらう必要があります。本作の画面上では敵の弾と自分の弾が入り乱れますが、どれが危険でどれが安全な弾なのかプレイヤーに混乱してほしくなかったため、一貫して弾は危険なものとして取り扱っています。

また自傷ダメージがあることにより、武器の種類の幅も広がっています。強力だけれど自分に当たってしまう危険性も高い、ハイリスクハイリターンの武器などをデザインできますからね。あとは正直に申し上げますと、個人的にプレイヤーが自爆している様子を観るのが楽しいということもあります。
ただ、現状のゲームバランスはちょっと自爆が頻発しすぎているかも、とも感じています。自爆を完全になくすことはしませんが、リスクを避けられる方法は今後増やす予定です。ビルド次第で自爆の危険がない安全なキャラも作れるし、リスキーな高火力武器で遊ぶこともできる、というように調整していきたいと考えています。
──お気に入りの武器やビルドを教えてください。
Ned氏:
お気に入りの武器はたくさんありますが、ひとつあげるなら「Stinger」に「Autofrail」「Venom Glands」「Patent 66」を組み合わせたビルドですね。Stingerは敵に素早く接近できる近接武器ですが、このビルドだと弾丸を跳ね返しながら周囲の敵を叩きのめし、最終的に毒の爆発を起こすことができます。
本ビルドの肝となる「Stinger」という武器は実は『デビル メイ クライ』シリーズのパロディで、ダンテの技「スティンガー」が元ネタになっています。パロディ元と同様に、本作のStingerを使うと敵に急接近して突きを繰り出しますが、武器の見た目は文字通り大きな虫の毒針(stinger)です。本作にはこういったジョークや小ネタをたくさん仕込んであります。パロディはすべてのプレイヤーに通じるわけではないのですが、個人的に気に入っている要素です。

──現在本作はデモ版が配信されています。プレイヤーからの評価はいかがでしょうか。印象に残ったフィードバックなどはありますか。
Ned氏:
ありがたいことに、多くのユーザーが本作をプレイし、フィードバックを寄せてくれています。なかにはデモ版を50時間以上プレイするなど、こちらの想像を上回るほど熱心なプレイヤーの方もいらっしゃいますね。本作のように開発の初期段階から、ゲームの方向性について意見を聞けるというのはとても心強いことです。
印象に残ったフィードバックはいろいろありますが、ゲーム内に実装されているすべての装備の有用性を評価したレビューや、キャラクターの強化スピードについて深く掘り下げた批評などは特に印象に残っています。本作のゲームメカニクスをよく理解し意見を寄せていくれるユーザーの姿を見るのは素晴らしいことですし、そうしたファンを驚かせるために我々も開発に励んでいます。
本作は2025年中に、早期アクセス配信を開始する予定です。そのためにも現在やっているように、プレイヤーのフィードバックを聞いてゲームを改善していく経験を積むのは、とても重要だと感じています。早期アクセス期間ではさらにユーザーの意見を取り入れて、本作を皆さんが望むかたちの作品へと改善するのに集中していきたいと思っています。
──日本のプレイヤーに向けてメッセージをお願いします。
Ned氏:
日本の皆さんに本作を遊んでいただき、とても嬉しく思っています。本作はローンチ時より日本語に完全対応いたします。発売を見逃したくないという方は、ぜひ本作をウィッシュリストにご登録ください!個人的に、日本の皆さんのプレイ動画を拝見するのをとても楽しみにしています。温かい応援とご意見に心より感謝申し上げます!
また現在、Steamにてオープンベータテストを実施中です。発売まで待ちきれないという方は、ぜひそちらもチェックしてみてください!
──ありがとうございました。
『Enter the Chronosphere(エンター・ザ・クロノスフィア)』はPC(Steam)向けに配信予定だ。ゲーム内は日本語表示に対応する。
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。