ディレクターでもプロデューサーでもない「ゲーム編集者」とは一体何なのか。『Touhou Luna Nights』などの仕掛け人、斉藤大地氏インタビュー
庵野監督のカラーから出資を受けたことでも話題となった「ゲームマガジン」の運営会社のバカーの元社長にして『殺戮の天使』の仕掛け人、現在はWhy so serious?の代表であり、ゲーム編集者を自称する斉藤大地氏にお話を伺った。

弊社アクティブゲーミングのPLAYISMより、Steam向けにリリースされている『Touhou Luna Nights』と『幻想郷萃夜祭』。デジゲー博2019会場にも試遊展示されていた東方Projectの二次創作アクション2本には、実は共通した一人の人間が関わっている。
庵野監督のカラーから出資を受けたことでも話題となった「ゲームマガジン」の運営会社のバカーの元社長にして『殺戮の天使』の仕掛け人、現在はWhy so serious?の代表であり、ゲーム編集者を自称する斉藤大地氏にデジゲー博2019会場でお話を伺ってきた。斉藤氏はどのような人物なのだろうか。
―――まずは自己紹介をお願いします。
斉藤大地(以下、斉藤)氏:
Why so serious?代表の斉藤大地でございます。ここ6年ほどはずっとインディーゲームのしごとをしています。途中、「電ファミニコゲーマー」の副編集長も兼任でやっておりました。最初、ニコニコ動画のドワンゴで「自作ゲームフェス」というコンテストなどインディーゲームの担当をしていました。その後、『殺戮の天使』というオリジナルインディーゲームをプロデュースいたしました。非常にniconicoを始めとしたネット上で人気になり、メディアミックスでコミカライズなども好評を頂いた結果アニメ化も果たしました。その後「エヴァンゲリオン」の庵野秀明監督が代表を務める株式会社カラーと株式ドワンゴから出資を受けて株式会社バカーを設立、『Touhou Luna Nights』をプロデュースしました。そして、10月に設立したWhy so serious?でリリースした『幻想郷萃夜祭』はPLAYISM史上最速のペースで売れているそうです。
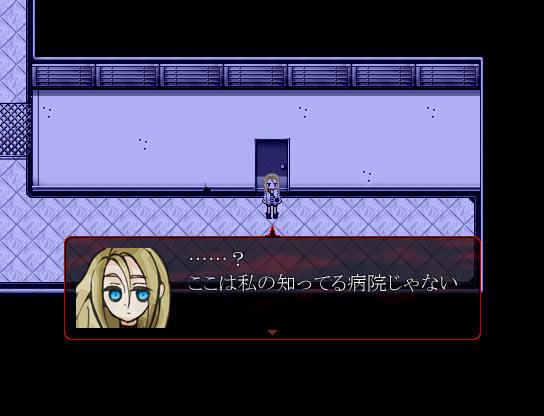
作品は作家のもの
―――ゲーム編集者を自称されていますが、ゲーム編集者という肩書にはどのような意味が込められ、どのようなことをされているのでしょうか。
斉藤氏:
ドワンゴ社員時代には、電ファミニコゲーマーの副編集長をしていたこともありまして、IGN Japanのインタビューではゲーム編集者と名乗らせていただきました。基本的には、漫画の編集者と同じようなことをゲームでやっていると思っています。時代が変わり、ゲームが個人でも作れるようになりました。けれど、それまでにもゲームを作ってきたような作家も含め、新しくゲームを作るようになった作家さんは、今まで作家として扱われてこなかったと思うんですね。
僕はゲームクリエイターも作家と呼ぶんですけども―――小説や漫画の作家と同じように、彼らにも独自のクリエイティビティがあります。それをどう活かしていくのか、その作家性とその作品全体を調和させていくのか、彼らにもいわば編集者の役割が必要だと思っております。これまでゲームというのは個人があまり作ってこなかったせいか、基本的にはディレクションやプロデュースと呼ばれてきたと思うんです。僕も外ではプロデュースと呼ぶことも多いです。それを僕は編集と呼び、出版の文化を参考にすることによって、作家と対話をしながら彼らのやりたいことや得意なことと作品の調和をとっていくことが必要なのかなと。
週1から長くて月1ぐらいで打ち合わせをして、ゲームの全体についてどういう風に考えて、どういうテーマでやっていますかと聞いて、例えばテーマがゲームデザインと調和を取れているかだったり、ストーリーについての案を出したりもします。ゲームデザインについて『Touhou Luna Nights』では「時を止める」のがキャラにおいてもゲームデザインにおいてもテーマだったで、「メトロイドヴァニア的なギミックは時を止める方に寄せたほうがいいんじゃないですか」「ナイフの上に立てたりしたほうがいいんじゃないですか」みたいな案出しもしたりしました。
ただ、忘れないようにしていることもあります。僕は編集なので作家の方が基本は上であって、命令していると取られないようにすることです。プロデュースやディレクションだと命令は発生することも多いと思いますが、それが一番違うのかな……と思います。作品はどこまでいっても手を動かす作家のものであるというスタンスを崩さないのが編集の心得なのかなと。これは先輩の編集者の方などから学ばせていただいたスタンスですね。

―――そうやって作品に関わりながら、作品はどこまで行っても作家のものだと断言されるのは立派な心がけだと思います。
斉藤氏:
状況によって「こうしないと絶対売れないからこうしないと出さないよ」みたいなことを言う編集者さんもいらっしゃるとは思うんですが、いまゲームでやるべきは少なくともそうではないだろうと。漫画よりもゲームのほうが一個一個に対して時間がかかりますから、自分のものだという感覚が強いはずで、そこをとにかく尊重しないといけないと思っています。
もちろん作家さんによって大事なことは違うので、ここはこの人にとっては譲りどころだなと思ったら「ここまでいけますよね?」ぐらいのことはいいます。ただ、どうしても譲れないところ、手が動かないところって作家さんによって出てきたりするので、その時はもうそれを前提とした上で他の部分で「こういうことにできませんか?」という風に提案するようにしています。基本的に作家さんのこだわり・やりたいこと・強みをベースに、僕の方でサポート出来ることを考えていく、ないしは作り方に対して提案するようにしています。
漫画文化へのリスペクト
―――影響を受けた編集さんなどは、いらっしゃるんでしょうか。
斉藤氏:
影響を受けたといえば、「ジャンプ」ですね。もちろん直接ではないですが、伝え聞いたり本を読んだりでジャンプ編集部から盗ませていただいたと思っています。電ファミニコゲーマー時代には、Dr.マシリトこと、鳥島和彦編集長に触れる機会があり、他にもジャンプに近い編集プロダクションの方と触れ合う機会が多かったりもして、ジャンプイズムについては影響を受けていると思います。
僕はやっぱり日本のクリエイティブを支えてきたという意味で、漫画は大きい存在だと思うんですね。その中でも編集者―――日本の編集文化は世界に冠たるプロデュース文化であると僕は思っていて、それをなんとかゲームに持ち込みたいというのがこの形で仕事を始めた動機ですね。あとはライトノベルの電撃文庫の三木一馬さんには担当作家さんのインタビューに同席いただいたり、本を読ませて頂いて影響を受けました。その編集論についてはとても参考にさせていただいているところがあります。
*鳥嶋和彦氏:「週刊少年ジャンプ」の元編集長。鳥山明氏の『Dr.スランプ』『ドラゴンボール』に編集として関わった人物。
*三木一馬氏:『ソードアート・オンライン』『とある魔術の禁書目録』などの編集者。
―――東方二次創作作品が続いていますが、今後はどのような作品に関わっていかれるんでしょうか。
斉藤氏:
元々ドワンゴで東方の原作者のZUNさんがビールをプロデュースする「ZUNビール」の企画担当をしておりまして、話をさせていただきやすかったこともあり、東方が2作品続いていました。今控えている中では、次は『ロードス島戦記』ですし、もう一個すごく古いアニメIPのタイトルを別のクリエイターと手掛けています。その次はまた別のIPもあったりとかで、基本的にはIPを預けていただいて、そのIPに適合した企画をクリエイターさんと作っていくことが多いです。かといって、オリジナルをやらないわけではないです。「ゲームに貴賎なし」と僕は思っていまして、あらゆるゲームに必要とされる限り、関わっていきたいです。とにかくクリエイターさんにとって良い形で、ゲームを編集して頂くことになるのかなと思います。

インディーゲームは、ゲーム史におけるミッシングリンク
―――編集者としてゲームと向き合うにあたって、ゲームに対する知識が必要だと思います。どのようなゲームをプレイしてきましたか。あるいはどんなゲームが好きですか。
斉藤氏:
僕自身は今32歳なので、FC・SFCと共に育ってきた世代ですね。SFC、GBAのゲームはかなりやったなと思っています。特に大学入ってからは中古でたくさん安く購入したりなど色んな手法で。男子寮にいたもので、100人の男がいるとゲームなんていくらでも出てくるものですから、4桁ぐらいのゲームを大学在学中にやったことが僕の原体験になっています。その後PS/PS2/PS3/PS4みたいな世代を追って行きましたけど、GBAとSFCのゲームは、今のインディーゲームに続くものがあると思っていてすごく好きです。
あと、中高生のときはお金がなかったので、PCフリーゲームばかりやっていました。それからKOEIが好きです。『太閤立志伝』とかを死ぬほどやり込んだことがあって、個人的にやるのはシミュレーションゲームがすごく多いです。最近では『ポケットモンスター ソード・シールド』とか『デス・ストランディング』はもちろんプレイもしました。おかげで仕事が滞っていて、大変申し訳無いと思いつつも、あれをやらないとゲームプレイヤーとして死ねない気持ちなのでプレイしましたね(笑)。インディーだと最近は『Ancestors: The Humankind Odyssey』『Noita』『スチームワールドクエスト』とかは結構楽しく遊んで、一人のゲーマーとしてはそこそこゲームをプレイしています。特にここ2か月は『ライザのアトリエ』も出たし、とにかくやらなきゃいけないゲームだらけですから睡眠時間を削るしかなくて、定常的に眠いですね(笑)。
※ インタビューが実施されたのは2019年11月17日
基本的には今のインディーゲームは個人制作であることもあって、やっぱり個人で制作しやすい2DゲームのデザインであるとかPS初期の作家性がすごく強く出たゲームたちの遺伝子を継いでいると感じます。よく言うのは「ゲームが工業製品になっていった歴史の中における、ミッシングリンク」だと思っているんです。あの頃のPS初期やSFCやGBAのゲームが、今の技術にあわせて進化していった可能性があるとすると、今のインディーゲームの形に近くなっていくのではないか。そんなことをよく思っています。
ゲーム史の中で技術の為によって発展しなかったゲームデザインの可能性だと思っていて、クリエイターたちがそれを今追求している。たとえば『Touhou Luna Nights』も当時のマシンスペックだと、時を止めるのも重い処理だったはずなんですよ。今のマシンスペックがあって、個人の手に追えるレベルの開発で作れるようになったというのが、マシンパワーとツールの発達によるものだと思っていて、そんな光景を楽しく見ています。
話がやや前後しますが、ドワンゴに入ってからインディーゲームの担当になって、ゲームのコンテスト「自作ゲームフェス」をやったんですね。担当が1人だったので、応募された約400作品の下読みを全部僕が全部でやるんです。勿論全てを最後までやることはできないんですけど、その時に膨大な数の中から一定の審査基準を見つけて、見抜いていくようなことが、今の原体験の一つかなと思っています。とにかく多く数のゲームをプレイしたことが大事だったのかなと思いますね。学生時代に死ぬほどゲームをやったことと、大人になって仕事でインディーゲームにたくさん触れたことが今に繋がっているのかなと思っています。なので、同世代の中では数をやっているほうかなと思っています。
―――400作品をそれだけの短期間でプレイしている方はそうそういないのでは。
斉藤氏:
その経験はすごく面白かったですね。それを2回やって、400と300だったかな。だからプレイしたゲーム本数でいうと、5桁はまだ届かないですけど、少なくとも4桁中盤ぐらいは―――3000とか4000ぐらいは触ったんだろうなと思っています。ちなみに、余談なのですが、その時にスパイク・チュンソフトの中村光一さんに審査員を務めていただき、バカーを建てたときは相談役にも入ってもらっています。その時ゲームデザインについてゲームを見ながら教えて頂いたことを、今も非常に役立っています。
―――1人の利用者として「自作ゲームフェス」を見ていましたが、運営側ではそんなことがあったんですね。
斉藤氏:
1回目から3回目ぐらいまでは別の担当者だったんですけど、大きく打ち出していこうというタイミングで僕に変わって、動画の撮影や記事なども出していったんですよね。なので、引き継いだという意識は強くて「自作ゲームフェス」の1回目を始めた僕の先輩は、日本のインディーゲームにとって偉大なことをしたと思っています。あの瞬間のニコニコってインディーゲームのプラットフォームだったと思っていて―――あの瞬間だけですけどね―――ゲーム実況と生放送と運営の試みと合わさった2年間ぐらい。あの瞬間だけは、ニコニコはインディーゲームのプラットフォームとしてすごいものになったと思っています。インディーゲームをやることというのを今の10代20代の女の子たちにまで広めた。
僕の知る限りニコニコ動画の動画投稿者や生主のおかげで日本におけるインディーゲームは、実はものすごく知名度がある。売上と比例する部分もあれば比例しない部分もありますが、インディーゲームという文化が、実はニコニコを通じて10代の女子にまで受け入れられたことはすごいことだなとは思いますね。僕はあの時の視聴者たちからクリエイターが出てくると信じていますし、そろそろだと思ってるんですね。あの時10代20代だった視聴者が、ちょうど大学生や社会人になって余裕がでてきて、ゲームを作り出すタイミングです。そこから偉大なゲーム作家が生まれると思っているので、とても楽しみにしています。
―――Why so serious?について聞かせていただけますか。
斉藤氏:
端的に言うと、バカーで斉藤がやっていたことをWhy so serious?でも変わらずやっていく形で、これまでお付き合いしてきた人はなにも変わらないかな…と思います。経緯が非常に長く、それを話し出すともう1回インタビューをすることになってしまいます(笑)。様々なひとたちとも関わることなので僕の一存でこの場で話すことはできないのですが、またどこかで話せたらなぁと思います。
名前については完全に僕の趣味で、「ダークナイト」のジョーカーが好きすぎるので、そこから取りました。ロゴについては、「アメコミ風のロゴでかつゲームっぽく」といったらああいうロゴがあがってきたので、大変に素晴らしいロゴだと思って満足しているところです。まだ名刺も出来上がっていないので、今は今後ともよろしくおねがいしますと挨拶回りをしているところです。

―――今後Why so serious?でやっていきたいことはありますか。
斉藤氏:
元々ドワンゴ時代は超会議とかでイベントも作っていて、ゲームのプロモーションを言い訳にして(笑)リアルな体験型イベントを作るのは僕の個人的な一つのテーマです。その瞬間は、僕もディレクターとして現場に携われるので、そういうことをしたい気持ちだったり、他にも個人企画としてやりたいことはあるので、企画会社的なものになってはいくと思います。もちろん、僕の個人的なスキルとしてのゲーム編集も変わらず追求して高めていきます。
※2019年12月、中国で東方Projectのブースを現地の協力者と一緒に作ったという写真
―――ありがとうございました。

コアなゲーマーだけでなく、徐々に世間からも認知されつつあり、変遷の途中にあるインディーゲーム。パブリッシャーではなく、編集者として作家との対話を試みる斉藤氏のようなあり方は、今後のインディーゲームシーンにおいて、重要な役割を果たしていくのかもしれない。





