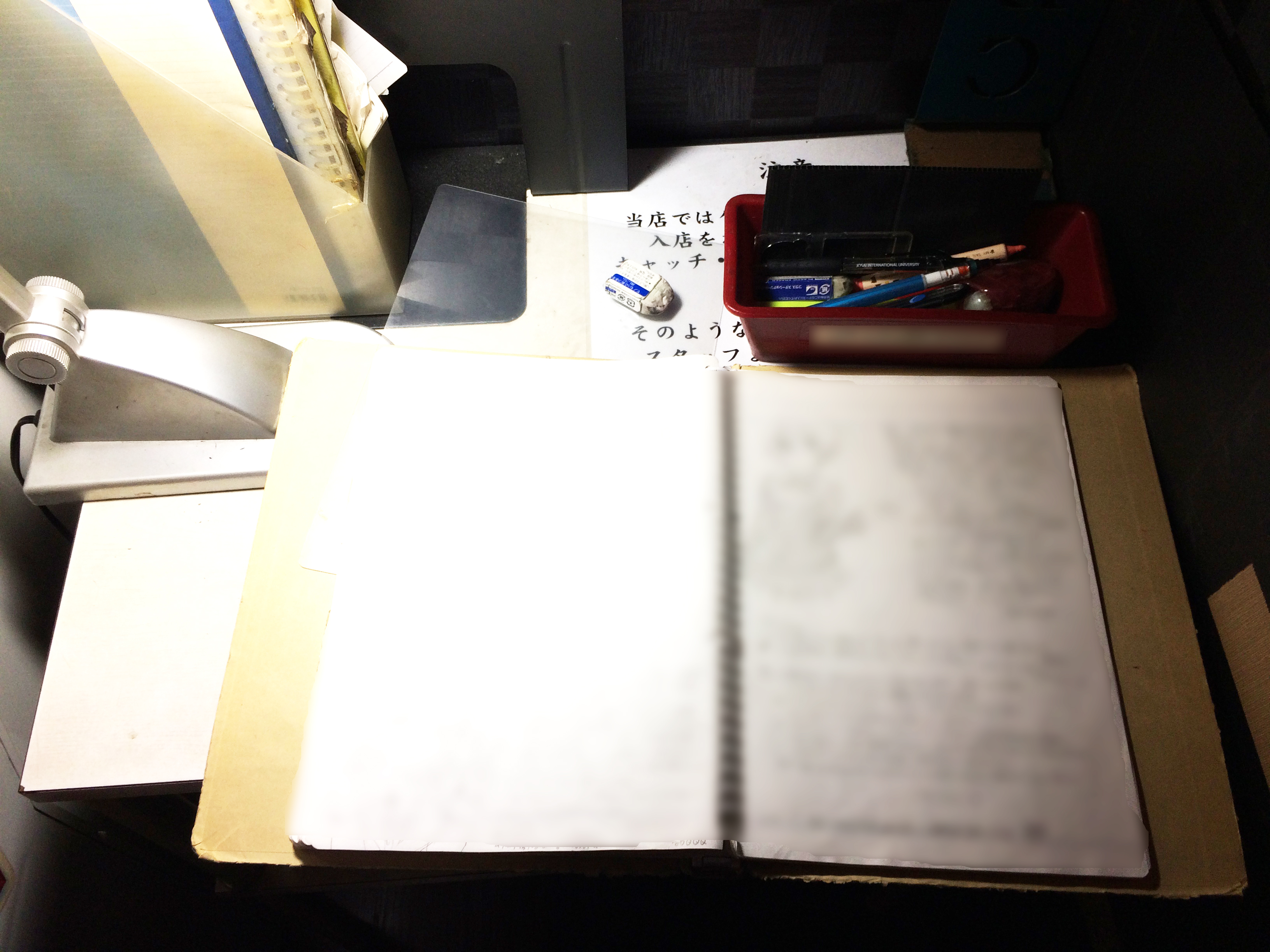『ゲームセンター文化論』著者・加藤裕康氏インタビュー メディアの進化に伴って変わるゲームの見方
かつて樹皮や石に彫り刻んだ「文字」は、書きやすく保存性にも優れた紙の誕生によって世界の歴史や文化を記録し、電子機器の発達によってデジタル化を遂げた現代でもコミュニケーションの疎通は変わることなく受け継がれている。

かつて樹皮や石に彫り刻んだ「文字」は、書きやすく保存性にも優れた紙の誕生によって世界の歴史や文化を記録し、電子機器の発達によってデジタル化を遂げた現代でもコミュニケーションの疎通は変わることなく受け継がれている。
1980年代。ゲームの攻略法をプレイヤー同士で共有しあう情報伝達手段だった「コミュニケーションノート」はゲームセンター独自のコミュニケーション文化であり、ゲームセンターがサービス業の側面を持つようになった1990年代以降はレバー・ボタンのメンテナンスや基板の入れ替えに関するリクエストなどを聞き入れる目安箱として店と客の架け橋の役割を持つようになった。
誰もが読み書きできることから、ゲームがクリアできないことへの憤りをぶつける者や、他ゲーム勢への愚痴を書く者、お気に入りのゲームに登場するキャラクターまたはオリジナルのイラストを描く者など、リアルでありながらネット上の匿名掲示板のようなコミュニケーションツールとして機能している。
そんなコミュニケーションノートに、少女が書き殴った一文があるという。
――「自分の存在を消したい」
『ゲームセンター文化論』を2011年に発表した加藤裕康氏は、この一文を見たことをきっかけに、ゲームそのものではなくコミュニケーションノートに焦点を当て、5年以上にも及ぶ取材を敢行したという。
今回は加藤氏に「コミュニケーションノートに目を向けたきっかけ」や「コミュニケーションノートの在り方」「取材を通じて感じたもの」などインタビューを行った。また、今年7月に中央大学で行なわれたシンポジウム「ゲームはスポーツなのか?」の補完として、教育的利用やデジタルスポーツとして推進されていくことによって「ゲームは悪」と見られる風潮が今後変わっていく可能性があるのかどうかを具体的にお聞きした。
1972年生まれ。東京経済大学大学院コミュニケーション学研究科コミュニケーション学専攻博士課程修了博士(コミュニケーション学)で現在は大学兼任勤講師。主な著作に「オンライン時代のゲームセンター ──ソーシャルメディアとゲームを媒介としたコミュニケーション」(『デジタルの際 情報と物質が交わる現在地点』聖学院大学出版会・2014年)、「娯楽と教養」(『レジャー・スタディーズ』世界思想社・2015年)、2017年9月には『現代メディア・イベント論』(勁草書房刊)に「ゲーム実況イベント ──ゲームセンターにおける実況の成立を手がかりに」という論文を寄稿している。
――現在、加藤さんは大学の講師を務められていますが、『ゲームセンター文化論』においてコミュニケーションノートを通じた取材を行われるまでのきっかけをお教えください。
加藤 私はもともと都内の出版社で機関紙・業界紙を作る記者だったんですよ。そこである日、ユニセフの「児童の商業的・性的搾取」をテーマにしたユニセフの国際シンポジウムを取材してコラムを書いたんです。1990年代の東南アジアでは貧困が原因で人身売買のように子供が性的産業で搾取されている問題は日本でも「援助交際」という形で各国から非難を受けていたので。そのコラムを書き終えたあと編集長から「自分で足を運んで実際の現場を見て取材してこい」と言われ、その日の晩に渋谷まで行ったんです。
――秋葉原や新宿、原宿ではなく渋谷を選ばれたのは特別な理由があったのでしょうか。
加藤 当時の渋谷はガールズ文化の発信地であり、援助交際の温床でもあると言われていましたし、あのころは『プリクラ』がヒットしていたのでゲームセンターにも休憩・交流用のテーブルやイスが設けられており、女の子たちがいるのを知っていたんですよ。と同時に彼女たちがゲームセンターを居場所にしていることに気づき、それからいろんなお店を見ていくうちに「コミュニケーションノート」を見つけ、その中に「自分の存在を消したい」という書き込みを見たことで声をかけ始めたのが決定的な理由ですね。
――ギャラリーを沸かすプレイヤーやゲームそのものではなくコミュニケーションノートに書き込んでいる子たちに取材を行うのは難儀されたのではないでしょうか。
加藤 ゲームセンター内での客の行動に関心がありましたので、巧みなプレイをする人だけでなく、決してうまいとは言えないプレイヤーにも取材していますが、あくまでもコミュニケーションノートを読み書きしている子たちが主だったので、『鉄拳』シリーズが人気のお店の場合「自分なんかよりあの人に話を聞いたほうがいいですよ、上手いんで」とはよく言われましたね(笑)。書き込みで交流を図る背景には、現実世界に居場所がない子たちが「ここにいる」と自己発信したものに対する反応を得ることでノート上だけでも自分の存在価値を見出しているケースが多いんですよね。
――著書の中では小さいころから複雑な家庭環境で育った占い師や恋愛の悩みなどを書いている子も多かったですが、発売から5年の歳月でゲームセンターを取り巻く環境は様変わりし、お客さんの流れやコミュニケーションノートの存在価値も変わったように思います。
加藤 取材をしていたころは駅前型のゲームセンターがいっぱいあったのでコミュニケーションノートを置いているところも多かったですね。よく「SNSの時代に変わったからコミュニケーションノートがなくなった」と考えられがちなんですが、駅前型のゲームセンターが減少しているからであって、いまでもノートを置いているところは盛り上がっているんですよ。「いろんな人と会う」「場所に行く」ということに価値が見出されているんですよね。たとえば『初音ミク Project DIVA Arcade』の聖地と呼ばれるゲームセンターに行ってコミュニケーションノートに何かを書くことがステータスだったり、いまだに『アイドルマスター』が稼動している店舗のコミュニケーションノートには各地のプロデューサーさんたちによる書き込みがあるんですよ。
――常連だけではなくさまざまな地方からやって来たプレイヤーが記念に書き込むことがある種のステータスになっているんですね。
加藤 ええ。なので新しいメディアが登場したことによってコミュニケーションノートが消えたのではなく、政治や経済、文化を複合的に見た中でコミュニケーションノートを見かけなくなったというのが正しいと思います。一般的にはメディアの進化しか見られていないのはちょっと違うと僕は思っていて、SNSが登場したことによってコミュニケーションノートに自分のアカウント名を書くようになり、そこでつながって仲間を増やしてTwitter上でやりとりするというケースも多いんです。
―――なるほど。ちなみに『ゲームセンター文化論』は著書ではなく研究論文として発表された経緯があるとのことですが。
加藤 プライベートで取材を続けたりビデオゲームやゲームセンターに関する資料に目を通してはいたのですが、企画が出版社になかなか受け入れられず、大学院で研究して形にしてみようと思ったんです。調査と取材を続けながら修士論文としてまとめ、博士課程に進学してから学会誌に投稿していたんですが、どんなに頑張っても1年に2本ぐらいしか書けず、各章にして博士論文にまとめたんです。それだけでも修士論文に2年、博士論文に3年で合わせて5年かかり、調査自体と合算すると10年ですね。研究分野にもよりますけれども、学術的なものって理論的に組み立てるものがオーソドックスで、『ゲームセンター文化論』のようなルポタッチのものってあんまりないんです。「エスノグラフィ(民族誌)」の研究手法はルポタッチに書くというスタイルがあるのですが、とりわけポピュラー・カルチャーを扱ったものは、学問の世界ではあまり認められないというか軽く見られがちなんですよ。
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。