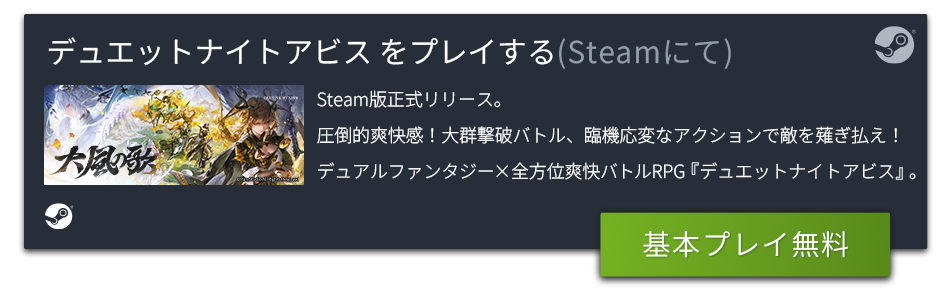『無双アビス』は、コーエーテクモのローグライトガチ勢が制作した「底なし沼」ゲーム。“武将を組み合わせてビルド構築” 開発者に訊いた、中毒性の高いゲームを作るための工夫
『無双アビス』は『無双』シリーズに登場するキャラクター(英傑)を操作して、全方位から押し寄せる大量の敵を蹴散らしていくローグライトアクションゲーム。開発者に話を訊いた。

コーエーテクモゲームスは2月13日、ローグライトアクションゲーム『無双アビス』を発表し、本日より配信開始している。『無双』シリーズ×ローグライトアクションという、ありそうでなかった試みを実現した『無双アビス』。このたび、本作のプロデューサーである平田幸太郎氏に対し、インタビューを敢行した。本稿ではその模様をお届けしよう。
『無双アビス』は『無双』シリーズに登場するキャラクター(英傑)を操作して、全方位から押し寄せる大量の敵を蹴散らしていくローグライトアクションゲーム。対応プラットフォームはPC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S。価格は2970円(税込)。
プレイヤーは英傑を操作するだけでなく、攻略の途中で盟約を交わすことで、さらに複数の英傑を召喚し、共に戦うことができる。英傑の組み合わせによって、さまざまな能力が向上し、攻撃がどんどん派手に、強力になっていく。このたび、電撃発表された『無双アビス』について、作品コンセプトやインディーズ意識など、根堀り葉掘り訊いてきた。
――まずは自己紹介をお願いします。
平田幸太郎(平田)氏:
コーエーテクモゲームス・ω-Force(オメガフォース)の平田です。ゲーム「進撃の巨人」シリーズのリードプランナーとディレクターを担当し、『WILD HEARTS』ではディレクターを務めました。『無双アビス』は私が初めてプロデューサーを担当する作品となります。

――『無双アビス』とはどういった作品なのでしょうか。
平田氏:
『無双アビス』は『無双』シリーズの戦闘アクション体験をベースに開発されたローグライトアクションゲームになります。地獄を舞台に、支配者「エンマ」に招聘された英傑たちを俯瞰視点から操作して戦い、深部に潜っていくゲームになっており、戦略性やリプレイ性を重視した作品になっているのが特徴です。
――コーエーテクモゲームスはこれまでに、さまざまな規模のゲームを制作してきましたが、価格帯をはじめ、本作のような規模感の作品はあまりなかったように思います。開発経緯を教えて下さい。
平田氏:
かねてより、ローグライトジャンルの開発に挑戦したいという想いがありました。また開発者として、これまでにはなかったタイトルを作りたいという気持ちも強くありまして……(笑)
『WILD HEARTS』の開発運営が一段落したあと、ローグライトをテーマにした、とある新規プロジェクトの企画書を作っていました。ただ、その企画だけを持ち込むのは、ローグライトタイトルを制作することを経営陣にアピールには十分ではないと感じて。そのために、いわゆる比較材料として作った企画が『無双アビス』の前身になります。だから最初は本命ではなかったんですよね。ただ、実際に企画として肉付けしていくと、格段にこちらの方が良くなった。そうするうちに、『無双』シリーズとローグライトジャンルの相性の良さを確信しました。最終的には『無双アビス』を本命にプレゼンをして、製品化までこぎつけました。


――ローグライトゲームであることが、『無双』シリーズよりも先立っていたゲームなんですね。
平田氏:
そうですね。私達の認識としてローグライトなアクションゲームは現在、世界的には大いに賑わっているジャンルだと思っています。一方、国内産のゲームにおいて、このジャンルに切り込んでいくタイトルは少ない。挑戦しがいのあるジャンルであると思います。
――最近の風潮として、大手開発会社の若手スタッフが小~中規模作品を作る社内インディーという開発形態があります。本作はどういった方々が開発に携わっていますか。
平田氏:
本作の開発は、ベテランから若手まで個性的なスタッフたちが携わっています。たとえば、本作の戦略的な部分を手がけたのは、過去に弊社の歴史SLG作品でディレクターを担当していたこともある方です。アートディレクターの方も、役職自体は初めてですが、他業界にて映像方面で活躍された若手のホープですね。本作は弊社の個性的なスタッフが集まって誕生したゲームになっています。弊社はこれまでにさまざまなジャンルを手がけてきました。『無双アビス』が成立したのは、その歩みがあったからこそであると思います。
――本作はどういったユーザーをターゲットにしていますか?
平田氏:
メインターゲットにしているのは、ローグライトアクションファンの方々になります。
――といいますと。
平田氏:
本作のアピールポイントとしては第一に「操作感」を挙げています。画面上に1000に近い敵の軍勢が登場し、簡単な操作で蹴散らしていく。この爽快感が、本作ならではの魅力のひとつです。プレイアブルキャラクターを100人用意しているのも特徴です。
また、個人的な感覚として、国内に置けるローグライトアクションのジャンルは、まだマイナーな立ち位置にあると考えています。よって、ジャンル名や作品概要を聞いただけではゲームの内容についてイメージすることが難しい方も多い。そこで、「簡単操作で爽快感あふれるクォータービューアクション」という特徴を設けることにより、ローグライトの沼にハマっていただきたいという意図を作品に込めています。
本作がきっかけで、ローグライトアクションジャンルがもっと国内で盛り上がるようになると嬉しいですね。

――平田さんが好きなローグライトゲームと、ローグライトジャンルを開発する上で重要だと思うエッセンスを教えて下さい。
平田氏:
ローグライトジャンルは今までにいろいろと楽しみましたが、いちばん私が好きなタイトルは『Slay the Spire』です。ダントツで好きですね。4ハードくらいで遊んでます。ぜんぶ含めて1000時間くらい遊んでるかもしれません(笑)。好きなクラスはアイアンクラッド。廃棄(※)を軸にした戦法が好きです。
※デメリット用のカードを手札に溜め込み、一気に廃棄することでアドバンテージを得る戦法。
そんな私がローグライトゲームを作る上で大切にしているのは、中毒性とも表現できるような高いリプレイ性です。それを実現するために、本作の開発にあたって、3つの軸を設けました。1つ目は「戦略性の高さ」。2つ目は「リトライを通じて高まる、クリアへの期待感」。3つ目は「定期的に爽快感や達成感を感じられること」です。私がこれまでプレイしてきたローグライトゲームは、複数の要素が絡み合うことで、リプレイ性を生んでいます。『無双アビス』では以上3つの要素のシナジーにより、高いリプレイ性を作り上げました。
たとえば本作における戦略性の高さとは、100人のキャラクターを組み合わせることで生まれる、戦術の変化になります。この戦術構築は複雑な仕組みになっているため、プレイヤーのみなさんが尻込みしないように、攻略の取っ掛かりとして、現在所持している英傑とシナジーのあるキャラクターのアイコンが黄色く光ったり、ガイドキャラクターのエンマがシナジーの生まれる組み合わせを構築してくれる仕組みを導入しています。しかし、ゲーム側が提供する組み合わせが必ずしも最強というわけではありません。プレイヤーが本作を攻略して、自分なりの戦術を発見することができた時には、いつの間にか、『無双アビス』の沼にハマっていることでしょう。
――ローグライトジャンルはインディーズゲームにもよく採用される都合上、個人開発者あるいは小さなチームによる小規模開発、低コストといったイメージが付く傾向があります。本作は大手開発会社、そしてベテランメンバーも参加した開発タイトルですが、それゆえに実現可能となっている体験はありますか。
平田氏:
代表的なもので言えば、「キャラクターの数」になります。しっかりモーションが作りこまれたプレイアブルキャラクターが100人いるというだけでなく、召喚システムを通じて、複数人のキャラクターが入り乱れて戦闘するという状況を作りあげることができました。この派手でハチャメチャで気持ちの良い状況を実現することができるスタッフが揃っていた、というのは、弊社がこれまでに積み重ねてきた資産があったからこそだと認識しています。
また、本作はローグライトアクションのファンのみならず、ローグライトアクションをプレイしたことのない方も意識して作られています。そのため先述したように、ジャンルに対する敷居を下げる仕組みを備えています。キャラクターのシナジーが生まれる組み合わせを提示する仕組みも、弊社の様々なタイトルに携わった経験豊富なスタッフだからこそできたものであると自負しています。

――プレイアブルキャラクターの選定基準や、それらのアクションについて、教えて下さい。
平田氏:
キャラクターの選定基準については、該当キャラクターがゲーム内に実装された際、戦術に相乗効果を与えることができるのか、キャラクターごとに面白い戦術が作れるのか、という点を最優先しています。たとえば、「織田家」のキャラクターを収集することで成立する、「織田家ビルド」という戦術を作るぞ、というアイディアに対し、織田家に関連したキャラクターを登場させています。一方、石川五右衛門というキャラクターは、所属としての相乗効果には乏しいですが、「特定の条件で敵を倒すとお金が大量に手に入る」という能力を持たせています。彼はビルドを長期的に成長させる上で、戦略的な要素の1つになるだろうという観点から登場させました。
また、プレイアブルキャラクターひとりひとりには「使いやすさ」というパラメーターが用意されています。高いほど強力かつ、初心者向けで使いやすいです。関羽が代表的ですね。しかし、だからといって関羽が最強と決まるわけではありません。戦術次第で、「使いやすさ」が低い英傑でも関羽を上回ることができます。例を挙げると、今川義元は操作こそクセがあるものの、彼自身が持つ特性に特化させた戦術を構築することで、非常に強力なキャラクターになります。このように、本作では(いろんなキャラクターを使ってもらえるように)強化の方向性を分かりやすくしています。
――好きなキャラクターをずっと使い続けるプレイスタイルはあまり推奨していない、ということでしょうか。
平田氏:
私としては、一人の好きなキャラクターをずっと使い続けてもらって構わないと考えています。本作には累計レベルというシステムが存在しています。特定のキャラクターを使えば使うほどレベルが高くなっていき、キャラクター間の基本的な性能差がなくなっていくというシステムです。また、プレイ中に獲得できるアイテムとしてキャラクターごとに対応するユニーク武器があります。これを獲得すると該当キャラの新たな能力がアンロックされるのですが、その内容に凄まじい強化が入っている人物が何人かいます。時間をかけてプレイすれば、好きなキャラクターが呂布に匹敵する性能を持つ、なんてこともあるかもしれません。100人のキャラクターの中から、敢えて1キャラを使い込むという贅沢を楽しんでほしいです。
とはいえ、攻略に詰まった時に、100人いる他の誰かにキャラクターを変えてみる、という感覚で遊んでみるのも良いと思います。本作が発売されたらやがて攻略動画が作られ、キャラクターのランク付けが出来るかもしれません。それに従うのも良いし、それに従わず自分のスタイルを貫くのも楽しいですよね。

――召喚システムに登場する英傑たちの特徴についても教えて下さい。
平田氏:
召喚によって登場する武将のアクションは、20種類以上存在しており、さまざまな範囲攻撃や、ステータスアップなどがあります。キャラクターごとの強弱ももちろんあります。
では弱い召喚技を持った英傑は使えないのか、というわけではありません。編成に組み込むだけで効果を発揮する「固有戦法」が強力だったりするなど、他の部分で差別化しています。たとえば「お市」の召喚技は防御力アップであり、殲滅力は持ちません。しかし、固有戦法は「倒されても一度蘇生できる」という強力な内容になっています。召喚システムに登場する英傑たちの特徴は、貴重な編成枠をどのように活かすのか、という点で戦術性を拡張するものになっています。また、ビルド構築の方向性を分かりやすく表現するうえで、同じ陣営(〇〇家や、魏呉蜀)で採用する英傑を揃えると、英傑同士のシナジーが生まれるようにもしています。一人召喚することで二人以上の英傑を同時に召喚できるキャラもいます。
ほかにも組み合わせによっては、「操作キャラだけですべてなぎ倒す」「無限に召喚できる」(召喚技のクールタイムが事実上消滅する)「同じ召喚技の英傑を採用し続け、強化することで無限範囲攻撃を行う」といったすさまじいシナジーもありますね。
――敵はどのような挙動をしますか。また難易度設定に関しても教えて下さい。
平田氏:
本作は爽快感を重視した設計になっているため、多くの敵は基本的にプレイヤーの攻撃で押し切れるように作られています。戦術の強化が仕上がる段階には、回避行動の一切が必要なくなるなんてこともあるでしょう。攻撃の予兆が発生している際に、チャージ攻撃を当てることで吹き飛ばせたり、弾幕攻撃はこちらのアクションで打ち消せるようにもしています。ただ、ボスに関してはゴリ押しが効きづらいように設計しています。体験が単調にならないようにするためです。
なお、継続的な製品のアップデートを予定しています。その都度、難易度の調整をしたり、キャラクターを追加するなど更新が入ると思っていただければ幸いです。

――ローグライトといえば周回プレイ要素が充実しているジャンルです。本作も周回プレイが前提になっている作りになっている、とのことですが、リプレイを促す工夫として、どのような仕組みが組み込まれていますか。
平田氏:
まず挙げられるのは、プログレッションの多さです。リソースを消費しての英傑のアンロックや、先ほど説明した、レベルが蓄積されていく要素やユニーク武器など、プレイを繰り返すほどに攻略に役立つ機能が解禁されていくようになっています。また、1プレイの終わりには最大ダメージ量や戦闘力がリザルトとして表示されます。いわゆるスコアアタックです。プレイの概要をシェアしやすいリザルト画面を作っていますので、ぜひカンストダメージを出して、SNSでシェアしてみてください。
――最後に、読者の皆さんに向けて、本作の発売に対しての意気込みをお願いします。
平田氏:
本作は「地獄に、沼れ。」をキャッチコピーに掲げています。改めて述べますが、『無双アビス』はリプレイ性をかなり重視して制作されています。はじめはライトな手触りから、次第に中毒性のある戦略面へ浸かっていただけると幸いです。
自分の考える最強の戦術で難関を突破したいと考える方や、長く気軽に遊べる、自分の生活に寄り添うゲーム体験をお求めの方、ぜひ本作をプレイしてみてはいかがでしょうか。
――ありがとうございました。
『無双アビス』は現在発売中。対応プラットフォームはPC(Steam)/PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S。価格は2,970円(税込)となっている。
[聞き手・執筆・編集:Takayuki Sawahata]
[聞き手・編集:Ayuo Kawase]
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。