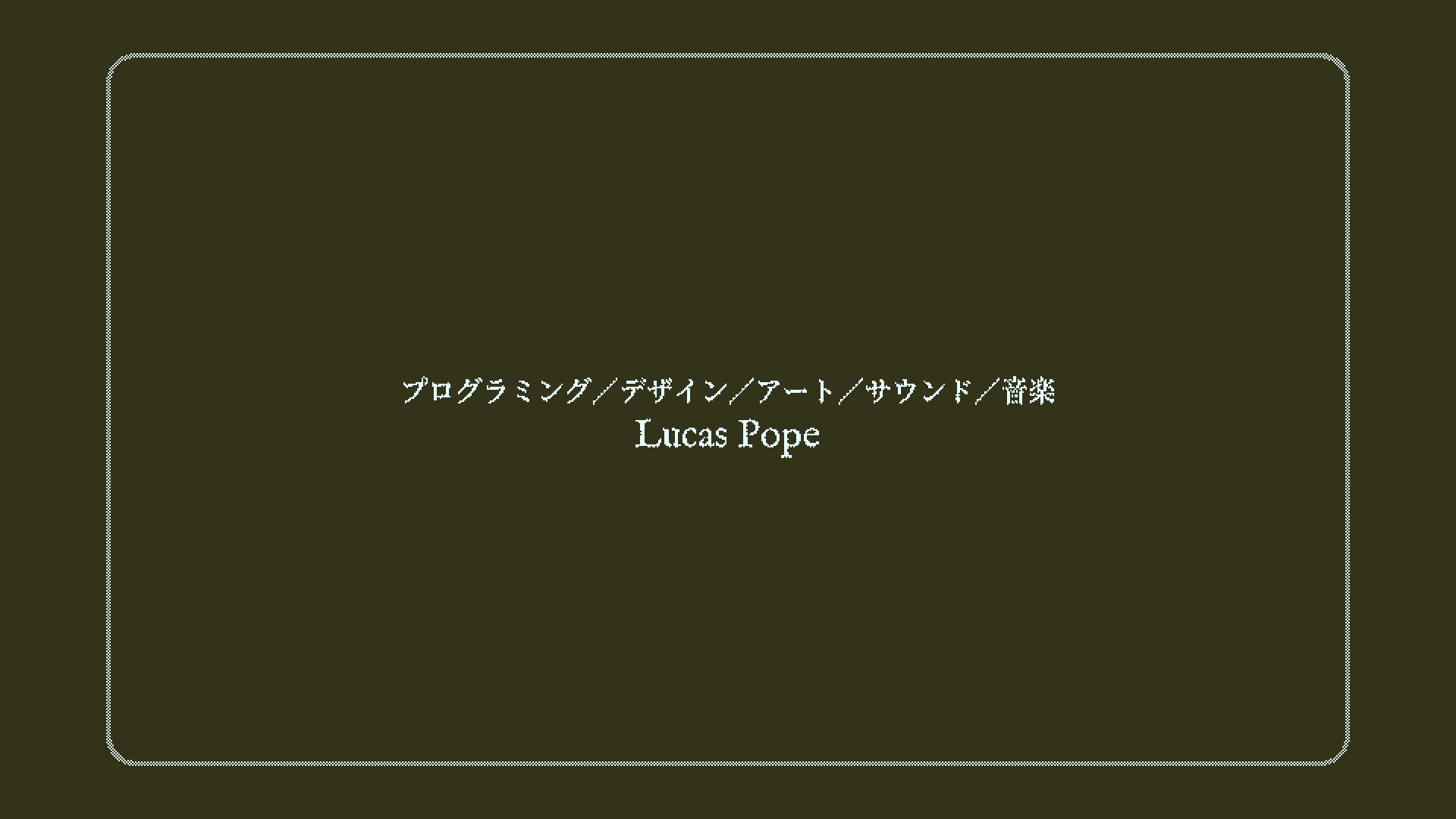奇才ゲームクリエイターLucas Pope氏インタビュー[人間編]。「ほかにはない」ゲームアイデアはどこから生まれてくるのか
ゲームクリエイターLucas Pope氏に話を聞くロングインタビュー後編。日本の埼玉県に住むPope氏の普段の暮らしや、“家から出ない”という生活スタイル、遊んでいるゲームなどパーソナルな部分についてお聞きする。

家族という協力者
───自分のアイデアを他の人に伝えるのが苦手で、個人開発を始めたとお聞きしました。『Obra Dinn』の開発にあたって外注した部分を教えてください。
Lucas Pope:
台湾人のキャラクターや台詞づくりにあたって台湾の方に協力してもらいました。友人であるネイティブの英国人にも助けてもらいました。キャラクターの発音が正しいか、会話文の意味が通じるか。ウェールズ人が言わないような台詞をウェールズ人のキャラクターに言わせたくないですし、声優の方々には正しい発音をしてほしくて。自分では判断できない部分なので他の方に協力してもらいました。
ローカライズにあたっては、ローカライズマネージャーのJosué Monchanと密接に連携しながら作業を進めました。ただ翻訳するだけでなく、複数の言語に対応した文章作成システムを構築する上でも協力してもらいました。どうすれば8か国語に対応しつつ文法的に正しい文章作成システムをつくれるのか。それは開発終盤における大きな課題のひとつでした。Josuéや、ほかの言語を話す方々と何度も話し合いながら決めていきました。
───ゲームデザイン/ゲーム設計は全部Popeさんひとりで完成させたのですね。
Lucas Pope:
はい、信じがたいことですよ。
───以前Lucasさんはご自身について「よいマネージャーではない」とおっしゃっていました(笑)。たびたびお話に出てくる奥様が、Popeさんのマネージャー役なのでしょうか。
Lucas Pope:
いえ、彼女は会計や財務の管理はしますが、ゲームデザインに関しては放任主義です。昔『Papers, Please』を彼女に見せて遊んでもらったときは「うん、わかった、変なゲームね。このゲームを完成させるまでは続けていいけど、終わったらちゃんとした仕事に就いてね」という反応が返ってきたのですが、『Papers, Please』が成功すると「あなたの好きなようにしなさい」という反応に変わりました。どんなに馬鹿げたアイデアを伝えても、「馬鹿げたアイデアね」という顔をしながら「好きなようにしなさい」と言ってくれるんです。
───ゲームづくりでは、誰にアドバイスを求めましたか。
Lucas Pope:
友人にゲームを見せてアドバイスをもらっていました。また無料のアルファ版を公開することで、フィードバックを得ていました。マーケティングというより、こうしたゲームに需要があるのか様子を見ていた感じですね。反応が良ければ、「よし、つくり続ける価値はあるぞ」と自信を持てるわけです。
───話を伺っていると、奥様や家族との関係性は、ユニークで素敵なもののように感じます。
Lucas Pope:
私はそれほどユニークな関係性だとは思っていません(笑)。IGFのステージでも話したのですが、好きな仕事ができている時というのは多くの場合、何かしらの犠牲がともないます。家から離れて長時間働かなくてはならなかったり。その点、私は仕事と家族に時間をフルに注げる、恵まれた環境にいると感じています。子供や妻には感謝しかありません。この生活が成り立っているのは妻の努力のおかげです。私が働いている間に子供たちの面倒を見てくれるだけでなく、私が家族と過ごせる時間をつくれるように調整してくれているのです。
───そうすると、奥様はプロデューサー的な立ち位置なのでしょうか。
Lucas Pope:
そうとも言えますね。ゲームを完成させるようプレッシャーをかけてくることはありませんが、「それはゲームを完成させる上で本当に必要なことなのか」「ゲームにとってどれくらい重要なのか」頻繁に確認してくれます。
───早くリリースしなさいと急かされたことはありますか。
Lucas Pope:
あまりないですね。急かしているのは多くの場合、私自身です。開発に疲れてヘトヘトで、さっさと終わらせたくなるんです。「もう問題が残っていても構わない、リリースしよう」みたいな。『Obra Dinn』では、3年連続でその心理状態に陥りました。
私のリリーススケジュールは、主にIGFのエントリー受付時期に合わせているんです。つまり10月です。毎年10月が近づくと「今年の10月までにゲームを終わらせられるだろうか」と考え始めるのですが、答えは大抵「ノー」でした。ゲームをリリースした去年ですら、完成させられるとは思っていませんでした。ですが「もう1年このゲームをつくり続けるのは厳しい、今年終わらせないといけない」と決心したんです。
───Popeさんは、過去に海外インタビューで、自身にパブリッシャーは必要ないといった趣旨の発言をしてきたかと存じます。その認識は合っていますか。
Lucas Pope:
パブリッシャーがいらないとは思っていませんよ。『Papers, Please』ではパブリッシャーがいなくてもなんとかなったので、その方程式を崩したくなかったのです。『Papers, Please』の成功に満足していたので、もう一度同じやり方でいこうと。パブリッシャーがいてマーケティングをしていれば、売上はもっと伸びるでしょう。ゲームに投資している人たちからフィードバックを得られるので、より良いゲームになるとも思っています。
パブリッシャーはユーザーが何を求めているのか理解しているので、参考になります。彼らにゲームを見せて、うまくいかないと判断されたのであれば、その意見に耳を傾けてみる価値はあると思います。一般的なユーザーが何を求めていて、何を求めていないのか。そのスナップショットだと言えます。
私の場合、主に自分自身のためにゲームをつくっていて、幸いなことにそれが他の人にとってもおもしろいゲームになっていました。『Papers, Please』がうまくいったからパブリッシャー抜きでもやっていけると考えるようになっただけで、先ほどお話したように、このやり方が次回作でも通用するとは限りません。
他の人を雇わないのは、他者の人生の責任を負いたくないからです。それは私にとって余分なプレッシャーとなります。パブリッシャーと手を組むと、彼らもあなたの成功に依存するようになります。あなたのゲームが売れないと、従業員に給料を払えなくなります。そうしたプレッシャーは私にとって、ゲームづくりに専念することを妨げる要因のひとつです。それらに縛られることなくゲームをつくれるのであれば、できる限りそうしたいのです。
アイデアはどこから生まれてくるのか
───『Papers, Please』『Obra Dinn』だけでなく、Lucasさんが昔つくったゲームにも、光るものがあると感じます。そうした無料ゲームのアイデアを発展させようと思ったことはありますか。
Lucas Pope:
少しだけ考えたことがあります。ですがゲームをつくっていると、どんどん次のアイデアが浮かんでくるので、過去の作品に戻って同じアイデアについて考え直すのは苦手なんです。『Papers, Please 2』をつくらなかった理由のひとつでもありますね。新しいアイデアについて考える方が、私にとっては簡単です。
───『Obra Dinn 2』をつくることもないと。
Lucas Pope:
最初にゲームのコンセプトが思い浮かんだときには、半年で完成させられるだろうと思っていました。そのあとで同じ技術やアイデアを使って、似たゲームをもう一作つくろうとしていたんです。ですが『Obra Dinn』の開発に4年半もかかったので計画が変わりました。
ビジュアルスタイルは相変わらず好きなので、シンプルな1-bitゲームをつくりたいという意欲はまだあります。ただ『Obra Dinn』や昔思いついたアイデアを再検討するかは分かりません。何も決めていないのですが、1-bitのビジュアルが好きだという点だけは確かです。今後も1-bitのゲームをつくる可能性は高いでしょう。
───ビジュアルスタイルとしては1-bitということですが、つくってみたいゲームジャンルはありますか。
Lucas Pope:
ないですね。ジャンルというと、他の人がすでにつくっていて、うまくやっているようなゲームが思い浮かびます。そうした分野に足を踏み入れても特出した結果を出すことは難しいです。それよりも、他の人がやっていないアイデアを拾ったり、まだ存在しないジャンルに挑戦して、新しい課題とその解決方法を自分で考えていくことの方が私には合っています。
───インディーゲームのトレンドは気にしていますか。最近だと『Slay the Spire』が出たあとに『Slay the Spire』ライクなゲームが続出しました。開発中のゲームが今のトレンドと合わないなと、気にしたりしますか。
Lucas Pope:
いえ、トレンドから外れている方が私にとっては好ましいです。個人開発者としては、チームでゲームをつくっているデベロッパーと同じようなゲームはつくれません。同じ土俵で競い合うことはできません。ほかに誰もつくっていないようなアイデアを常に探さないといけないのです。他のゲームと異なれば異なるほど、トレンドから離れているので、私にとっては良い傾向だと言えます。
───ずばり、ユニークなゲームをつくれる秘訣は何ですか。
Lucas Pope:
ひとりで開発していることが大きな理由だと思います。開発規模を考えると、他とは違ったことをしないとマーケットで目立つことはできません。『Obra Dinn』を始めたころには、誰も1-bitのゲームをつくっていませんでした。
ただ1-bitという技術的制約があるので、他の人と同じつくり方ではうまくいきません。色や透明度、視認性の良いパーティクル・システムなど無いものばかりなので、他の方法を思いつかねばなりませんでした。そのおかげで、他のゲームとは異なる独特のビジュアルや感触ができあがったのです。自由が制限されているからこそ実現できたわけです。プレイヤーにとっておもしろい解決手段を思いつかなくてはいけないような状況に追い込むための、意図的な制約です。
───とはいえ、他のゲームをプレイすると、どうしても何かしら影響を受けてしまうと思います。どうやって他のゲームに引っ張られないようにしたのでしょうか。
Lucas Pope:
アイデアの大半はゲーム以外のところで浮かんだものです。もちろん、ゲームを遊ぶという行為については、ゲームを参考にしていますよ。遊びやすさ、操作性のよさ、チュートリアルのわかりやすさ。そうした点はゲームから影響を受けています。
ですがゲームのアイデア自体は多くの場合、ゲームとは関係のないところから生まれています。『Papers, Please』の入国審査しかり。普通おもしろいとは思わない事柄や、ゲームにできるとは思えないことについて「もしもゲームにしたら、おもしろくできるだろうか」と考えていくことが好きなのです。
───どうやってアイデアを選んでいるんでしょうか。
Lucas Pope:
ゲームのアイデアは頭の中にたくさんあります。そのうち考えている時間が長いものや、ノンストップで考え続けているもの。それらが自然と、私にとって重要なアイデアになっていきます。私が次に着手するのは、一番長く思考を巡らせてきたアイデアになるでしょう。さまざまな思考過程を経ても淘汰されずに残ったアイデアです。
四六時中ゲームのアイデアについて考えているので、何からでも影響を受け得るんです。たとえばBitSummitのために京都に来て観光するだけでもアイデアが浮かんできます。
───ゲームづくりについて常に考える。それがLucasさんのオリジナリティあふれるアイデアの源泉なんですね。納得できました。本日は長い時間、ありがとうございました。

聞き手・写真 [Minoru Umise]
書き起こし・翻訳 [Ryuki Ishii]
編集 [Ryuki Ishii/Minoru Umise]
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。