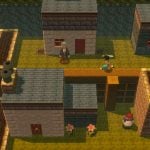奇才ゲームクリエイターLucas Pope氏インタビュー[開発編]。傑作『Return of the Obra Dinn』を生み出すため、いかに苦しみ抜いたのか
日本の埼玉でたったひとりでゲームを作り続けるLucas Pope氏は、インディーゲームシーンを語る上で欠かすことのできないクリエイターだ。そんな氏が手がけた唯一無二の魅力を持つ『Return of the Obra Dinn』を作る上では、どのような苦しみがあったのだろうか。
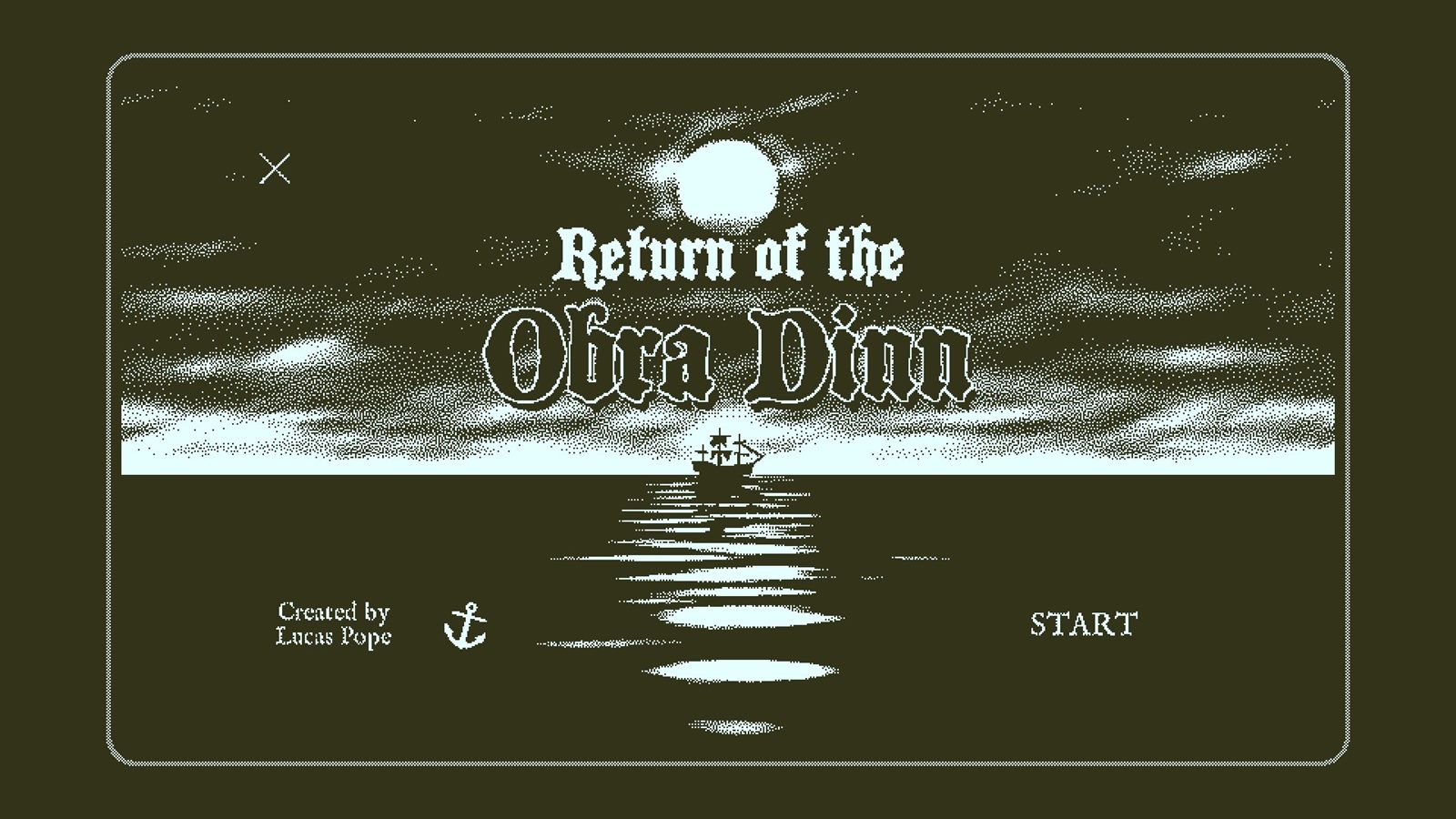
売れるかどうかは不安じゃなかった
───マーケティングに関して言うと、発売時にはプレスリリースやアナウンスメントが全くありませんでした。LucasさんがTwitterで“ふわっと”つぶやいただけですよね。ゲームが売れるか不安になりませんでしたか。
Lucas Pope:
そうでもありません。とても幸運なことに、前作『Papers, Please』は短期間で開発し、マーケティング無しでリリースしたにも関わらず、好セールスを記録しました。『Obra Dinn』がそれほど売れなくても何とかなるくらい、たくさん売れたのです。そんな経験をしたものですから、同じやり方を繰り返しても成功するだろうと思い描いていました。そして幸いなことに、上手くいきました。
いつまでも同じやり方が通用するとは思っていません。いつかはマーケティングにもっと力を入れないといけなくなるでしょう。ただ『Obra Dinn』に関して言えば、どれくらい売れるかはそれほど気にしていませんでした。売れなくても、まだなんとかなるからです。
それよりも気にしていたのは、『Papers, Please』に続く作品として、人々の期待に応えられるかどうかです。ゲームを好きになってもらえるかどうか。『Papers, Please』が好きだった人たちに『Obra Dinn』を楽しんでもらえるかどうか。そちらの方が心配でした。彼らを失望させたくなかったのです。完成までに時間がかかった理由のひとつでもあります。『Papers, Please』と同じくらい楽しんでもらえるような作品をつくること。売上ではなく、評判を気にしていました。
───もしも『Obra Dinn』の売上が芳しくなければ、『Papers, Please』のような短期開発かつ野心的な作品づくりに戻っていたと思いますか。
Lucas Pope:
はい、『Obra Dinn』も最初は短期プロジェクトにするつもりだったんですよ。でも私が予想した以上に、そして私が望んだ以上に、開発期間が長くなってしまいました。本当は短めのゲームをつくりたかったんです。でも『Papers, Please』に続く作品としての期待に応えようとしたことや、3Dのゲームづくりであったこと、ゲームの全体像が見えるまでに時間がかかったこと、新しいことをやろうとしたこと。さまざまな要因が積み重なって、開発が長引いていきました。
いわゆる2作目のジンクス/スランプが怖かったのです。あまりにも長く心配していたもので、心配することに疲れてしまったほどです。ただ、子供たちの成長を見守っていくうちに、ゲーム以外のことについても考えるようになっていきました。子供たちは私のゲームが面白いか面白くないかなんて気にしません。彼らのおかげで気持ちが楽になりました。私自身が十分な出来栄えだと思える段階で切り上げて、リリースすればよいのだと。
───現時点での売り上げは好調でしょうか。
Lucas Pope:
好調ですよ。『Papers, Please』ほど売れているわけではないですが、開発は私ひとりなので、出費は極めて少ないですし、爆発的なヒットにならなくてもよいのです。『Obra Dinn』の方が予算はかかっていますが、『Papers, Please』ほど幅広い層に訴えかけるような作品ではありませんし、おそらく今後も『Papers, Please』の売上に肩を並べることはないでしょう。それはそれでよいのです。私としては『Obra Dinn』の売れ行きに満足しています。
───4年半ひとりで開発を続けていて、不安や心配になることはありませんでしたか。
Lucas Pope:
もちろん不安ではありましたよ。さきほどお話したように、私は短期プロジェクトの方が好きなので。長引けば長引くほど、集中力を維持することが難しくなっていきます。『Obra Dinn』の開発にはいくつかの波がありましたね。やる気に満ち溢れているときと、疲れ果てているとき。そのふたつを行き来しました。できれば最初の波が去る前に終わらせたいですね。プロジェクトに興味津々で熱中していて、その熱が冷める前に完成させるみたいな。
───悪い時期をどうやって乗り越えたのですか。
Lucas Pope:
やめずに続けたいと思うだけの可能性を秘めていたからです。最初のデモ版をつくった段階で、良いゲームになる素質があると感じていました。誰かがこの原石を磨き上げれば、良質な作品が出来上がるという自信があったのです。完成品が何なのか、そして私自身に磨き上げる力があるのかは分からなかったのですが、誰かしらは良作に仕上げられる原石だと確信していました。そうした思いが支えとなって、最後まで走り抜けました。
もうひとつ、本作のビジュアルスタイルに関しては、開発の最初から最後までずっと好きだったという点もあげられます。1-bitでのビジュアル構築、キャラクターの作成、エンジニアリングの問題解決。その3つはずっと楽しみながら取り組めたので、開発を続けるモチベーションとなりました。
───ちなみに19.99ドルという『Obra Dinn』の価格はどのようにして決めたのでしょうか。
Lucas Pope:
最初は短いゲームにする予定だったので、10ドルで販売しようと考えていました。ですが開発を進めるうちに20ドルにした方がよいかもしれないと考え直しました。10ドルはよい価格帯ですし、『Papers, Please』で優れた結果も残せました。どんなゲームなのか分からなくても手を出せる手頃な価格だからです。それは『Papers, Please』のような変わったゲームの価格を決める上では、重要な観点だったと思っています。
『Obra Dinn』に関しては、パッと見ただけでも、もっと多くの価値があるゲームだと感じ取れるんじゃないかなと。20ドルに設定することで、よりコンテンツが多く、中身のあるゲームだと感じてもらえるのではないか、という狙いもあります。
───最近のSteamゲームは値段が安くなる一方ですよね。
Lucas Pope:
安くなるゲームがたくさんある一方で、高価格帯のインディーゲームは25~30ドルと高くなってきています。
───安いゲームは信用性に欠ける場合があります。高めのゲームは大抵の場合クオリティが伴っていて安心できます。
Lucas Pope:
ゲームにお金をかけるほど、より多くの時間を注ごうとするという考え方もあります。ゲームを楽しもうと、普段よりも辛抱強く遊んでくれるのです。『Obra Dinn』は序盤で諦められやすいゲームだと思っていて、楽しめるようになるまで少し辛抱してもらう必要があるかもしれないと感じていました。プレイヤーが少し高めにお金を払っていれば、そして少し高めに払うだけの価値があると考えていれば、通常よりも長めに様子を見てくれる。その結果、ゲームを楽しんでくれる人が増えるかもしれない。そう考えたのです。
[人間編]へとつづく
聞き手・写真 [Minoru Umise]
書き起こし・翻訳 [Ryuki Ishii]
編集 [Ryuki Ishii/Minoru Umise]
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。