Nintendo Switchで配信予定の“デンシ・グラフィックノベル”『ghostpia』には、どんなこだわりがこめられているか?暴力と美しさの歪みが生み出すハーモニクス
『ghostpia』は、デンシ・グラフィックノベルと銘打たれるアドベンチャーゲームだ。iOS向けにリリースされているほか、Nintendo Switch向けに配信予定の作品。パステル調のかわいらしいグラフィックが目を引くが、バイオレンスな表現も混濁している。どのような経緯で本作は作られたのだろうか。
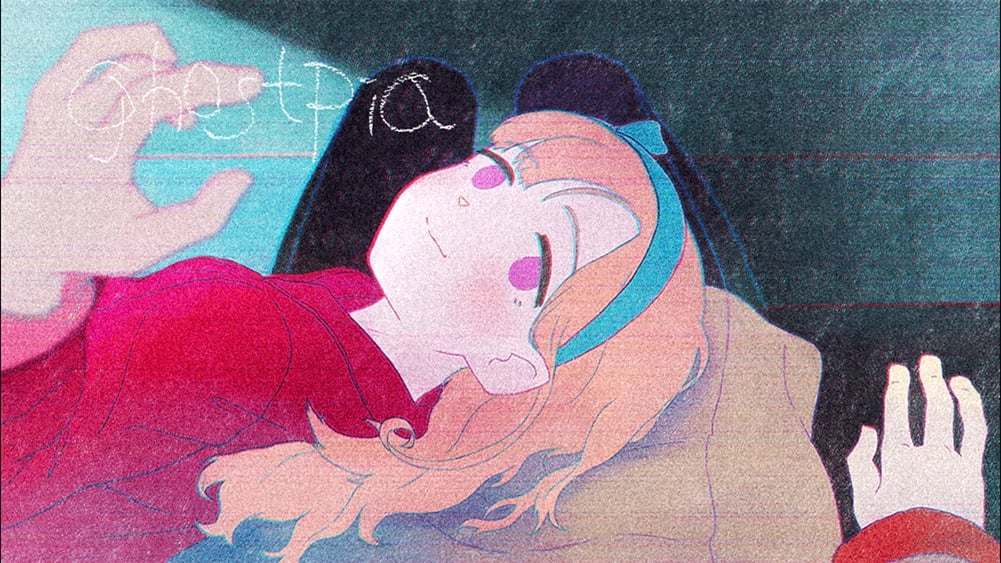
5月のBitSummit、8月のコミックマーケット、9月の東京ゲームショウ、いずれもブースを目にした瞬間に世界観に引き込まれるよう意匠が施され、ひときわ異彩を放っているブースがあった。サークル「超水道」が制作するデンシ・グラフィックノベル『ghostpia』である。iOSで無料でリリースされており、公式サイトからブラウザでもプレイが可能。Nintendo Switchで来年にリリースが予定されているタイトルだ。
『ghostpia』は、デンシ・グラフィックノベルと銘打たれてるように、次々とグラフィックがコマ割のように多彩に表示されながら、文章を読み進める作りになっている。舞台はロシアや北欧を思わせるような雪が積もった寒々とした町。だが、その町の外には出ることは叶わない。住民は日光を浴びると死んでしまい、リスポーンを繰り返して生き返る。そんな不思議な世界を舞台にしつつ住民から疎外されて暮らしている小夜子という女の子と、その仲間たちの絆を描く。
このような舞台設定と、イラストレーションから、本作をファンタジックでチャーミングな作風と思われるかもしれない。だが、それは半分は正解で、半分は間違いだ。実際は『ghostpia』は、チャーミングな日常のなかにヴァイオレンスが混濁し、ストーリーはある種の伝統的なアメリカ文学を思わせるようなハードな展開を見せ始める。
『ghostpia』を制作したサークル「超水道」は、20代中ごろを中心とした、ミタヒツヒト氏、斑氏、山本すずめ氏、蜂八憲氏の4人の若いメンバーで構成される。比較的、長い歴史を持つサークルで、10年前の学生時代から創作活動しているという。『ghostpia』は超水道のオリジナル作品としては7作目だ。
本作でシナリオを務めるミタ氏は早川書房から『イマジナリ・フレンド』を発刊した実績を持ち、文章力はすでに折り紙つき。そして、イラストを手掛ける山本すずめ氏はWacomのペンタブを愛用するイラストレーターにインタビューする特集「Drawing with Wacom」で取り上げられ、水面下で評価が高まりつつある。こんな個性的な2人がいるだけではなく、本作でディレクションを務める蜂八氏は本来はシナリオライターとしての顔を持つ人物で、効果音を手掛ける斑氏はグラフィッカーとしての役割も持っている、クリエイターの層の厚さが魅力のサークルなのである。なお、『ghostpia』の音楽は現代音楽家・高野大夢氏が手掛けており、Meno氏がチャーミングなヴォーカルを聴かせる。本作の世界観に合った荘厳な音楽はビジュアルと共に圧倒される特筆すべきものだ。
さて、ここ最近はさまざまな媒体で取り上げられ始めてきた超水道。このサークルに迫ったインタビューをお届けしよう。

――まずこのゲームを簡単に紹介していただけますか。
ミタ:
超水道というサークルは10年前から活動しているんですが、そのときから選択肢のない一本道のノベルゲームを作り続けてきました。『ghostpia』はその極致みたいなもので、イラストには史上最高に力を入れています。海外には漫画と小説の中間みたいなグラフィックノベルというのがありますが、それをノベルゲームでやってみるのがコンセプトのひとつです。
――このパステル調のビジュアルイメージが独自ですね。
山本:
「北欧のような寂れた町を舞台にした幽霊の話にする」というのは、ミタから企画があがったときにすでに出来上がっていました。ミタのイメージをもとに、他のメンバーが資料を探したり、僕がイラストを描き起こしたりして、もっとこういう感じがいいとか、ひたすらミタと擦り合わせて作り上げました。最終的にこういうパステルで描かれた絵本のようなアートワークにしようって決めたのは僕で、このイメージに決まるまで、今までで一番試行錯誤しましたね。難産でしたが、その甲斐はあったと思います。
ミタ:
各画面のビジュアル的な演出は、「僕はこういうのやりたい」と言うと、山本すずめのほうが絵の構成は詳しいので、「これは画面映えしない、これはこうしたほうがいい」とアドバイスをくれたりします。そうやって2人でペンを入れながら進めています。
――ここにある原画集でその2人の試行錯誤の歴史が垣間見えるわけですね。
ミタ:
そのとおりです。この原画集はグッズとして販売していて、数少ないマネタイズのモデルのひとつとしているものですね。面白かったという人がいたらグッズを買っていただけたらなと。広告を入れたらいいんじゃない?とよく言われるのですが、広告を入れたら興ざめなので、2014年のはじめころに、クラウドファンディングをやりました。目標を達成するまで、24時間もかかりませんでした。そうして支援していていただいたおかげもあり、『ghostpia』を作れるようになったんです。これまでiOSでリリースを続けてきましたが、それが今回はクラウドファンディングで、出資してくださったroom6さんにパブリッシャーになっていただいて、Nintendo Switch版としてグレードアップした有料版をリリースするという流れです。
――Nintendo Switch版の仕様については、最後にお聞きしたいと思います。インディーゲームで、これだけの大作なわけですが、完成させるための体制はどういう風にやられているんですか。インディーだとそこが如実な問題だと思うんですが。
ミタ:
今は『ghostpia』の1ラインですが、本来、超水道の体制は2ラインあって、山本と斑がイラスト担当、僕と蜂八憲がシナリオ担当なんですが、一人がシナリオをやっているとき、もう片方はディレクターをやっているんですね。『ghostpia』の場合は、僕がシナリオを書いているので、蜂八憲がディレクターをしています。
蜂八:
『ghostpia』のディレクションですが、役割としては「演出家」というより「制作進行」に関する部分が大きいですね。特に、自分の「本業」でもあるシナリオに関しては、各話ごとの文量調整や構成について重点的に助言しています。
ミタ:
シナリオに口を出せる人がいてこそ、ノベルゲームの品質はキープできると思うんですよ。僕らみたいな同人ノベルゲームだとシナリオライターが暴走しちゃう心配があると思うので、そこにもう一人が、「いや、ここはこうしたほうがいいんじゃない」とか、「このシーンは作り込んだほうがいいかな」って、アドバイスできる体制が超水道にはあるんですね。
蜂八:
ここ数年の超水道の課題として、大作化に伴って制作期間も長期化してきています。学生サークルとして出発した超水道も、今やメンバー全員が会社務めです。10年前のように「1週間徹夜で頑張ろう」というわけにもいかない。時間と体力の制約のなか、コンスタントにできるだけ早く『ghostpia』を皆さんにお届けすることが僕の役割だと思っています。
――同じシナリオの蜂八憲さんからみて、ミタさんのシナリオってどう思われますか。
蜂八:
とても好きです。流れるようなテンポの良さとか、ハッとさせられるような独特の言い回しとか。『ghostpia』ではアクションやバイオレンスの要素もあって、そのへんも見どころですね。色々と良いところは挙げられますが、なかでも一番推したいのは、彼は「さみしさ」を描く達人だということです。それは心の傷に沁みるけれど、同時に、確かな潤いをもたらしてもくれるんですね。
『ghostpia』のストーリーについて
――ここから『ghostpia』のストーリーについて具体的にお聞きします。ゲームでは、シナリオを進めることで町の全容が少しずつ明らかになる構造を採用していますよね。別に住民たちは町の秘密を隠そうとしているわけではなくて、単に主人公がそこに興味を持っていないからプレイヤーに伝わってこないだけ、というアプローチが面白いと思いました。
ミタ:
主人公の小夜子にはその発想がないんでしょうね。町の連中は知らないやつらで、そんなやつらはハナから信用できない。むしろ敵でしょ、みたいな警戒しかしていないのです(笑)。町をめぐって、クッキーでも差し入れしつつ「この町って、なんなんですか、どうなっているんですか」とインタビューして回れば、もしかしたら小夜子が納得できる答えがあるかもしれない。
――謎の真相や世界の核心を知っている素振りを見せる老人が出てきます。これも老人は秘密を隠そうとしているんじゃなくて、単にコミュニケーションが通じないから伝わってこないだけというか。
ミタ:
このゲームは世界観がわからないと思うんですが、老人がそれらしいことを言うことによって、「いやそれはないだろ」「これはどうなんだろう」と、想像の余地が生まれると思うんです。主人公の小夜子は戦闘能力でいえば誰にも負けないので、小夜子にとって怖い存在を作りたかったんです。
――教会にいる邪悪な神父というのは『Fate/stay night』を思い出さずにはいられないのですが、意識はされたんでしょうか?
ミタ:
いや、勉強不足なんですが、『Fate/stay night』はやってないんですよ。
――たとえば『ファイナルファンタジー』だと、お姫さまを助けるのがオープニングになっていますが、あれは『ドラゴンクエスト』の先を描くという意気込みがあったと思うんですね。そういう風に『ghostpia』の邪悪な神父が出てきたのは、『Fate/stay night』のその先を描こうという意気込みに見えたんですが、僕の勝手な妄想だったんですね。
ミタ:
えっ!……素敵なお話とは思うんですが、違うんですよね。神父のイメージは映画版『サイレント・ヒル』の敵教団のリーダーのおばちゃんのイメージ。閉鎖的な環境で嬉々として采配をふるう感じ。スティーブン・キングとかも好きなんですよ。最近『ミスト』の原作を読んで、やっぱりああいうのが良いなぁと(笑)。美少女ゲームに詳しいのは、僕じゃなくて斑のほうかな。
斑:
『Fate』を乗り越えるとか、恐れ多いですね。拳法を使いだしてたら、『Fate』になっちゃっているかもしれませんが(笑)。僕のなかで、そういう既存の美少女ゲームっぽくしたくないと思ってて、僕が知っている美少女ゲームに近づいたら「これは違う」って、ミタに言うつもりだったんで。ただそれに近づかないだろうなっていう安心のもと、今まで作ってきましたね。
ミタ:
美少女ゲームって話には聞くんですけど、僕はあんまりやっていないし、やったものは数少ないんですよ。まず『Fate』シリーズはひとつも触れていなくて。もっと触れた方がいいし、触れたいんですけど、僕はすぐ影響を受けるので『ghostpia』が終わるまでは、しばらくは作る方に専念ですかね。
――なるほど、つまり『ghostpia』はアドベンチャーゲーム、美少女ゲームの文脈で作られていないということですね。
ミタ:
美少女ゲームといえば、『沙耶の唄』と『アトラク=ナクア』と『WHITE ALBUM』をやって、これなら僕も作れそうだぞと思ったのがゲーム制作でノベルゲームを選択した大きなきっかけなんですよ。
――『Phantom -PHANTOM OF INFERNO-』は『ghostpia』に通じるものがあると思うんですけど、『沙耶の唄』のほうですか。
ミタ:
ええ。『沙耶の唄』は当時のノベルゲームとしてもリッチな表現ではないんだけど、いいシナリオさえ書いて、そこに合ってる絵さえ描ければ、いいものが絶対作れるんだと。『アトラク=ナクア』と『WHITE ALBUM』も、物語が良くて、しかるべきタイミングで音楽が流れ、絵にムードがあったら、こんなに面白いものが作れてしまうんだっていう衝撃を受けたんですよ。あと残酷描写やっていいんだっていう踏ん切りがつきました。でも美少女ゲームはそこで止まっちゃって。
――でもそうだとすると、『ghostpia』のバトル描写やバイオレンス描写の源流はどこにあるんですか。もちろんLeafなどの前例はあるんですが、ノベルゲームでバトル描写の潮流を作ったのはニトロプラスとTYPE-MOONだと思うんですよ。
ミタ:
多分、そこは幼少からカートゥーン・ネットワークを観て育ったので、影響を受けたのかもしれない。『パワーパフガールズ』で女の子が歯が抜けるまで、殴られるとか、髪の毛が切りそこなって坊主頭にされるとか。『アドベンチャータイム』で主人公が平然と宝を殴って奪う、ああいったモラルのなさ。『ghostpia』もそういう雰囲気なんですよ。可愛いキャラクターや女の子が暴力を働く、のっぴきならない雰囲気といいますか。
――『ghostpia』で、殴られるの人の顔の崩れ具合。あれは山本さんのセンスだと思っていたんですけど、ミタさんからの指定なんですね。
ミタ:
あれはいくらでも汚く殴られていいし、なんなら歯が飛んで、歯の神経がみえてくれてもいいぞと言って、そんなクソみたいな指示で、あの絵を起こしてくれてる山本すずめもまた、闇を抱えているのかもしれない。とはいえ、クラーラを酷い目にあわせている犯人は僕ですね。
――アメコミ、カートゥーン文脈の暴力性と、美少女ゲームの暴力性がミタさんのなかで出会ったから、『ghostpia』のオリジナリティ性が出ているんですね。
ミタ:
なるほど、そういう風に見えるんですね!逆に面白いと思いました。そういう化学反応が起こって、奇形なところがあるかもしれない。変なところといえば、意図的に変な日本語の文法を取り込んでいます。作品自体がどこか奇妙なので、このほうがしっくりくるかなと。たどたどしいしゃべりかたをする女の子の一人称なので、たどたどしい日本語なんですけど、ありがたいことに、これを気に入ってくださっている方がけっこういるんですよ。
銃器は詳しくなかったので、あとから勉強しました。銃を分解して組み立てる『World of Guns: Gun Disassembly』を遊んで勉強したり。実は山本すずめにはあんまり細かいところまでは指定していなくて。このキャラクターが「でかいリボルバー」を奪って、突きつけて撃つ、そこに意味があるというか。
――確かにニトロプラス的な銃器に対するフェティッシュさはそれほど感じないですね。あくまでキャラクターの行動原理から生み出されたアクションというか。
ミタ:
すぐ手がでる暴力が好きなんですよ。『Fallout』シリーズとか。昔から世紀末というか、終末の文明崩壊した世界の作品が好きで。すぐ手が出るというのは、すぐ暴力で解決するということで、「わかりあえた」解決じゃなくて。小夜子は対話より暴力に九千九百九十九万倍くらい長けているので解決はできるけど、そこには「わかりあえなかった」さびしさが残る。一方、ヨルは対話でわかりあうことに長けていますが、対話が無理な時は、小夜子が暴力で解決せざるを得なくなる。相手ももっと暴力的に出ないといけなくなる。その「結局、暴力に頼ってしまうせつなさ」みたいな色彩が作品に与えられていたならいいなと。
――小夜子って超然としていて、ヒーロー的な存在ではないですか。
ミタ:
内面は大概ですけどね。ヒーローといえばよく聞かれるんですけど、小夜子の身体能力の高さって、映画『レオン』とか、『ウォッチメン』のロールシャッハとか、あれくらいのヒーローの感じをイメージしています。
――小夜子のトレンチコートは、ロールシャッハのトレンチコートですか。
ミタ:
そうなんですよ、そこを初めて関連付けてくれる人が現れた!
――(笑)。でも僕は『血の収穫』の系譜である、『ミラーズ・クロッシング』に思いをはせていましたね。つまりギャングを同士討ちさせて壊滅させる点ではヒーローなんですが、その手法が非情すぎて、一番ヤバイのはギャングより主人公なのがわかってくる構造。ちょっと小夜子と通じる部分があるのかなと。
ミタ:
そこはあんまり考えてなかったけど、一理あるかもしれない。小夜子は強いけど、悲しい。強ければ強いほど悲しい。寂しくて強い怪物って感じですね。町の他の人から見たら怪物だと思います。町の人からしたら、アーニャとかパシフィカが小夜子と仲良くしているのは、ごまをすって自分が利権を得ようとしているじゃないかとか、そういう風にも見えるんでしょうし、ヨルは本当はもっと小夜子と同じくらい強いんじゃないかとか、あいつらが私たちの平穏な世界を壊すんじゃないかとか、そういう風に考えられているんじゃないかとか思います。
――物語が動き出すにつれ、それまで受身だった小夜子がかなりかき乱されて、能動的に動き出しましたね。
ミタ:
そのせいで町のパワーバランスががんがん変わっていくと思います。固定されていた人間関係が、最近では小夜子が動き始め、ヨルが働き始めたことで、ちょっとずつ変化していく。小夜子に友達ができたけど、逆に対立が深まる人もいる。
超水道の結成
――最後に超水道の結成のきっかけを教えていただけますか。
斑:
最初に僕とミタの2人で結成しまして、それが高校3年の終わりのころでした。『東方』の二次創作サークルから出発したんです。当時のグラフィッカーは僕だけだったんですよ。
ミタ:
僕はずっと演劇部に所属しておりまして、ものづくりが楽しかったんですね。その演劇部も高校3年のときに引退の時期になっちゃって、やることなくなったし、受験勉強が嫌過ぎて、別のことで忙しいふりしなきゃ!と斑に電話をかけたのがはじまりですね。山本すずめは中学校のころからの馴染みでしたが、高校のころに疎遠になっていたんですよ。高3の終わりのころに、もう一回連絡を取ろうと、そしたら山本すずめのほうも物を作りたいと。
山本:
実はこの3人で中学時代から創作の真似事みたいなことをしてけっこう遊んでいました。その時の「グループで物を作る」という楽しさはずっと覚えていたんですよね。疎遠になったあと、僕が美術大学の浪人をしていたときに、久々にミタから電話がかかってきて「受験の息抜きになるよ、辞めたくなったらいつでも辞められるよ」と……騙されて今に至ります(笑)。
斑:
彼はヤバイ奴で、中学生のときから絵を描くのがめちゃくちゃ得意で、音楽とか何でもできたんですよ。僕とミタは小学1年のころから馴染みでして、いつもつるんでいたんですが、中学生のときに「ヤバイ奴がいる」とミタくんとしゃべっていて、中学2年くらいのときにそのヤバイ奴と仲良くなりたいと思って近づいたほどなんです。
――蜂八憲さんはどのタイミングで加入したんですか。
蜂八:
最初に超水道と接点を持ったのは、自分が大学3年生の時でした。当時、超水道がTwitter上でシナリオライターの追加募集をしていたんです。それを目にした友人が、知らない間に僕のことを応募していました。「シナリオライターとして身を立てたいって言ってたから推薦しといたよ!」って(笑)。当時は「外部ライターとしてシナリオをひとつ書いてみないか」というお話でした。その作品が2013年の『佐倉ユウナの上京』というゲームです。その制作途中で、超水道メンバーとして参加しないかとお誘いいただきまして、今に至ります。
自分が超水道に加入したときに、「超水道らしさとは何か」という話をミタから伺ったんですけど、そのミタの答えが、「電車の忘れものらしきハンカチが床に落ちてる、と。それを見たときの切なさが超水道らしさです」というものでした。誰も拾わないハンカチ、誰が落としたのか、きっと捨てられちゃうんだろうな、という情感や物悲しさ。今でも印象に残っていますし、そうした「らしさ」はこれからも大事にしていきたいですね。
――時間がきたので、今後のことをうかがいたいと思います。Nintendo Switch版は有料の豪華版ということで、どのような仕様になるのでしょうか。また今年5月に4話がリリースされて、次の5話に期待がかかりますね。
ミタ:
感覚的な立ち位置としましては、iOS版がテレビアニメで、Nintendo Switch版は、そのテレビアニメが映像や音声がグレードアップして総集編として劇場版になる、あの感じに近いと考えております。もっとも、ストーリーは総集編とはなりませんが。iOS版はUIなど徹底したシンプルな作りでしたが、今回のNintendo Switch版はマシンスペックが良くなったので、全体的に豪華な作りとなって、世界観をより感じて頂けるかなと。効果音や劇伴楽曲など、音周りもより洗練されますし、HD振動だったり、ジャイロを使った視点移動の表現とか新しいことに挑戦しています。配信は、来年を予定しています。
Nintendo Switch版発表に合わせて、みなさんから喜びの声を頂いています。ただ一部のユーザーさんは、心のなかでiOS版はこれからどうなっちゃうのかな、と心配されてると思いますが、超水道はiOS版のことを忘れておりません。Nintendo Switch版が出るのもiOS版をみなさんが支えてくれたからです。そんなiOS版を捨てることはないです。5話も現在がんばって作っておりますし、4話ほどはお待たせしないかなと。『ghostpia』はファンの方ひとりひとりに育ててもらっている作品だと思うのでが、これからもみなさんと一緒に盛り上がっていけたら僕たちは幸せです。これからも『ghostpia』を、よろしくお願いします。
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。










