PS5『アストロボット』レビュー。PS5のポテンシャルと技術力を120%活かす、クリエイティビティの結晶
『アストロボット』は“全てのゲームは、ここに集まる”という初代PSキャッチコピーを、遊びとしても、物語としても、擬似的に再現したゲームである。

“全てのゲームは、ここに集まる”。初代プレイステーションに関するキャッチコピーの1つだ。『アストロボット』はこのキャッチコピーを、遊びとしても、物語としても、擬似的に再現したゲームであり、PlayStationシリーズそのものと言える。シリーズ30周年を象徴するにふさわしい作品である。
技術デモの先へ

インターフェースへの入力体験をゲームの要とする作品は世にごまんとある。家庭用ゲームであれば、任天堂が手がけるSports系ゲームが有名である。読者の中には、ゲームセンターに足を運びレーシングゲームや、音楽ゲームを楽しんでいる方もいるだろう。位置情報ゲームを楽しむために散歩をしたり、VR体験に勤しんでいる人もいるかもしれない。
インターフェースへの入力とは、表現物ならびに、その制作者に対するコミュニケーションの形であり、いわば言語のようなものだ。言語とはそれを操る本人の、世界の解釈を他人に示す道具である。わたしたちはインターフェースにコマンドを入力し、出力された映像=返答を確認することで、自らの解釈を覚え、作品と対話を図り、作者の意図を感じ、ときに楽しんだり、悲しんだりする。入力の仕方によっては同じゲームジャンルでも、同じ作品でも、体験が変わってくる。ホラーゲームのVR版が例としてわかりやすい。なかでも特定のインターフェースに依存する作品は、他には真似できない特殊な言語形態を用いたコミュニケーションの姿と言える。
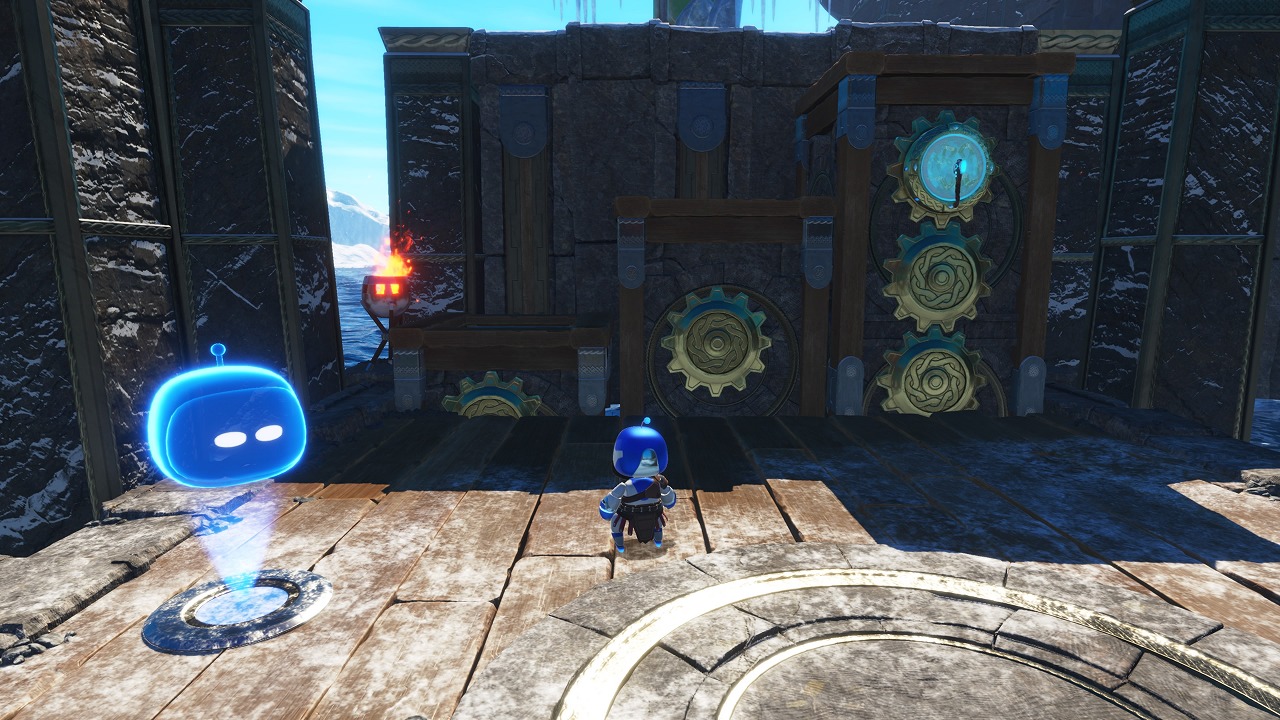
『アストロボット』もまた、インターフェースへの入力体験を面白さの要としている作品の1つだ。本作の面白さはDualSenseコントローラーへの入力体験と、それを寸分たがわず出力可能なPlayStation5の映像美があってこそ成立する。だが待ってほしい。この仕様は前作であり同じアクションゲームである『ASTRO’s PLAYROOM』にも同じことが言える。プリインストールの無料ゲームからフルプライス化にあたって、果たして何が変わったのだろうか。 端的に言えば、中身が「技術の展示会」から「3Dアクションゲーム」に最適化されたことである。ステージ中のギミックや映像に、連続性とダイナミズムを付与することによって、プレイヤーが立ち止まることを許さない。それはジャンプ台をはじめとする強制移動のギミックであったり、干渉することで「動く」「道が拓ける」ギミックがあったり。操作にあたって一度キャラクターを止める必要がある「タッチパッド」がギミックの解法として登場しないことが印象的である。触れると繊細かつダイナミックに動くオブジェクト群の存在や、探索可能な広さを誇るステージも効果てきめんだ。ボットやパズルのピースを探すという行為に関してはいわずもがなである。チュートリアルの自然さや、オートエイム、リトライのしやすさといったホスピタリティも備わっている。

「3Dアクションゲーム」への最適化を通じ、前作から変化を遂げた『アストロボット』ではあるが、当然としてギミックの攻略を通じた面白さもグレードアップしている。1つの入力方法に対し、凄まじい種類の映像出力と体験のバリエーションを用意しつつ、それでいてアクションゲームとしての統一感を持たせているのだ。
たとえば、トリガーボタンを押すという1つの行為に対し、適度な重さと振動、そして適切な映像描写を組み合わせることで、殴る、噴射する、塗る、押す、引く、潰す、吸収する、収縮する、絞る、縮こまる、射つ、投げる、というように、さまざまな操作感を生み出すことに成功している。実際は全部同じ入力なのだが、すべて異なる入力に感じられるのだ。
そしてこれらのアクションが攻略手段として心地よく活用できるために、作品の中で上手く使えず浮いているものが一切無い。私は記事冒頭にて「入力」とは「言語」のようなものだ、と述べたが、本作には単一の入力方式の中にさまざまな「言語」が備わっており、「言語」の数だけさまざまな世界の描写と体験がある。その姿は、1つのハードウェアごとに数多くの物語や世界を、ゲームを通して送り出してきた、PlayStationシリーズを体現している。
正直なところ本作は、ステージ進行に伴う難易度の発展は楽しいが、ステージギミックそのものに独自の面白さがあるとは言えない。敵を殴って壁を壊し、登ったり引っ張ったり、危ない足場をジャンプするゲームである。だが、そのシンプルな構造を補って余りある開発陣のクリエイティビティがプレイヤーを夢中にして離さない。たかがワンプッシュでこんなことができるのか。こんな表現があるなんて。最初から最後までプレイヤーを驚かせ、楽しませてくれる。これはDualSenseコントローラーの性能とPlayStation 5が生み出す映像美、そして、コレを120%活かす開発陣の発想と技術力があったからこそ実現したものだ。
未来を想う旅路

ハードウェアの性能と開発陣の力が化学反応を起こした攻略体験のみならず、本作がもつ物語体験……ボットの救出とPlayStation 5の修復劇に関しても言及しておきたい。この劇自体は非常に簡素なものであり、「PlayStation 5の中身を探検する」前作から、宇宙へ飛び出すという変化を通じて、フルプライス化に伴うゲームスケールの拡大をわかりやすく示している。ただ、筆者としては「PlayStation 5の修復」に過去作のキャラクターたちが協力するという形式に思うところがあった。ボットたちを助け、彼らの細やかなアニメーションを観察するたびに、あの作品の続編が登場したら……ありえたかも知れない未来を何度も思い浮かべた。
発売してからこの4年間、PlayStation 5というゲームハードにはさまざまな困難がついて回ったものである。品薄に見舞われたと思えば、スマートフォンの影響力やゲーミングPCの台頭によって、ゲーム専用ハード自体の意義を問われるようになった(これはPS5に限ったものではないが)。ジャパンスタジオは再編され、多くのタイトルの続編が制作困難になってしまった。
まさに時代の渦中にあるSony Interactive Entertainmentが、ジャパンスタジオ出身のTeam ASOBIが、積み重ねた経験と繋がりによって現状を打破し、自身を修復する物語を消費者に向けて提供したことは、強い「自己批判」であり、「今後もIPやファンを大切する」というメッセージなのではないかと私は感じた。

今回、改めて大々的に登場した主人公「アストロ」は、近未来的なマテリアルを感じさせながら、身にまとう意匠はシンプルで、まんまるとした姿をしている。寒冷地では小刻みに震え、暗がりでは怖がり、放っておくと遊び始める。愛されるべく生まれたThe マスコットと呼べるキャラクターだ。現状、残念ながら今のSIEには「マスコットキャラクター」を上手く運用できない、というイメージがある。彼にはこれを払拭し、PlayStation 5というゲームハードの「良き」象徴になってほしいと思う。今回は過去の名作にカメオ出演してもらったが、次は「アストロ」がDLCのアイテム等々で、未来の名作たちにカメオ出演していくことを期待したい。

“全てのゲームは、ここに集まる”初代プレイステーションのキャッチコピーを、物語としても、遊びとしても、擬似的に再現してみせた本作。開発陣の力を通じ、PlayStation 5の性能を活かしきったその内容は唯一無二と呼ぶにふさわしい仕上がりとなっている。一方で、その内容がPlayStationシリーズそのものであるがゆえに、今後続編が出ることに大きな意味を持つタイトルでもある。ぜひいつか、Team ASOBIには『アストロボット2』を制作していただきたい。そこで改めて、現行ハードの性能と合わせ、本作は評価され直すことになるだろう。
ゲーム専用ハードの未来は今まさに転換期にあり、先行きは極めて不透明。ゲームが誰のものになるのかも分からない。だが、『アストロボット』がPlayStationシリーズ30年の歴史の中で、燦然と輝き続けることだけは揺るぎようのない事実である。PlayStationはここにあり。
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。



