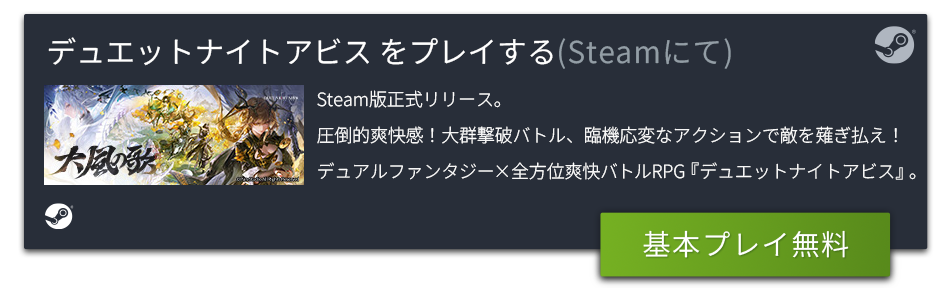『ゴースト・オブ・ヨウテイ』開発者は「ややこしすぎない操作」を徹底追求した。立ちはだかったのは“開発者はプレイヤーではない”問題
『ゴースト・オブ・ヨウテイ(Ghost of Yōtei)』について、海外インタビューにて開発元ディレクターがゲームデザインについて回答。操作体系が複雑になりつつも、それが“負荷”にならないように気を配っていたそうだ。

ソニー・インタラクティブエンタテインメントがPS5向けに10月2日に発売した『ゴースト・オブ・ヨウテイ(Ghost of Yōtei)』(以下、ヨウテイ)。本作の操作体系について、開発元Sucker Punch Productionsのクリエイティブディレクター、Jason Connell 氏が意識したポイントなどをGamesRadar+に明かしている。
本作は現在PS5向けに販売されている、『ゴースト・オブ・ツシマ』(以下、ツシマ)の流れを汲むオープンワールドアクションゲームだ。開発を担当するのはPlayStation StudiosのSucker Punch Productions。
『ツシマ』では13世紀後半の対馬が舞台になっていたのに対し、『ヨウテイ』の舞台は1603年、蝦夷地と呼ばれていたころの北海道だ。蝦夷富士とも称される羊蹄山を抱く地で、主人公・篤(あつ)の復讐譚が描かれる。

今回ゲームメディアGamesRadar+が『ヨウテイ』について、Sucker Punch ProductionsのクリエイティブディレクターであるJason Connell氏にインタビューを実施。本作の操作におけるこだわりを回答している。Connell氏によれば、ゲーム制作においては、操作が複雑になることによるプレイヤーの「認知負荷(cognitive overload)」が課題になるという。認知負荷とは、人間が脳で一度に処理できる情報量には限界があるという前提のもと、情報を処理したり理解したりする際に生じる精神的な負荷を指す。ゲームにおいては新たな操作を覚えつつ戦闘などをこなすとき、認知負荷が生じることになる。開発にあたってはこの負荷が重くなりすぎないような調整に苦心していたようだ。
というのもConnell氏によると、実際のプレイヤーに生じる認知負荷は、開発中のテストプレイだけでは測るのが難しいようだ。同氏によると、ゲームに何らかの新機能を盛り込む際、開発者は当然“開発自体”に取り組んでいるため、「長時間プレイした人」と同じような体験をしているわけではないという。つまり、長時間ゲームを遊んだプレイヤーが新機能として新たな操作体系に触れた時にどう感じるか、という視点が抜けがちだと説明している。
そして『ヨウテイ』では新たなメイン武器として、刀や二刀のほか、鎖鎌や大太刀などが登場する。それぞれ戦闘における強みは異なり、操作方法だけでなくその使いどころも変わり、シチュエーションごとの武器の切り替えも必要になる。『ツシマ』にはなかった複雑さであり、プレイヤーにかかる認知負荷も慎重に検討されたそうだ。

Connell氏は、実際のプレイヤーは、まず刀しか武器を持っていなかった序盤から武器を入手していく順番や間隔がまちまちだと述べる。新たな武器を手に入れるまでに長い時間が空き、じっくりと練習する機会のあるプレイヤーも多いそうだ。一方で開発中のテストプレイでは、武器がひとつだったところに一気に5種類の武器を試すといった状況も発生するとのこと。激しい戦闘において手が“こんがらがってしまう”ような状況で、実際のプレイヤーの認知負荷を検討する必要があるようだ。
Connell氏はこの課題へのシンプルな対策として、大量にプレイテストをおこなっていたことを伝えている。長年にわたって特定のチームが集中的に注意深く検討を続けて、認知負荷の調整がおこなわれていったそうだ。同氏はこのプロセスを「圧力鍋」に例えており、過度な認知負荷がかからないように“減圧”したり、あるいは新たな刺激として変化球的な要素を盛り込んだりといった検討を進めていったとのこと。たとえば『ヨウテイ』ではプレイヤー側も敵側も相手の得物を落とせるシステムがあるが、これも慎重な検討のもとで追加された変わり種要素だそうだ。
『ツシマ』ではメイン武器が太刀のみであったが、先述の通り『ヨウテイ』ではその種類がさまざま追加された。メイン武器については修得にまつわる印象深いイベントもそれぞれ用意されており(関連記事)、ストーリー面とゲームプレイの双方で深みが増したといえるだろう。一方で、複雑になったゲームプレイで発生する負荷をいかに軽減するかといったデザイン上の工夫も、徹底的に追求されていたようだ。
『ゴースト・オブ・ヨウテイ(Ghost of Yōtei)』はPS5向けに販売中だ。
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。