「手塚治虫」の「バトルカードゲーム」はなぜ生まれたのか? 手塚眞氏×イバイ・アメストイ氏インタビュー 後編
アクティブゲーミングメディアが正式発表した手塚治虫作品のカードバトルゲーム『アトム:時空の果て(Astroboy: Edge of Time)』。同作について語ってもらったインタビュー前編から、後編ではより幅広く。手塚眞氏とビデオゲームの関わりや、同氏のVRに関する考えなどを語ってもらう。
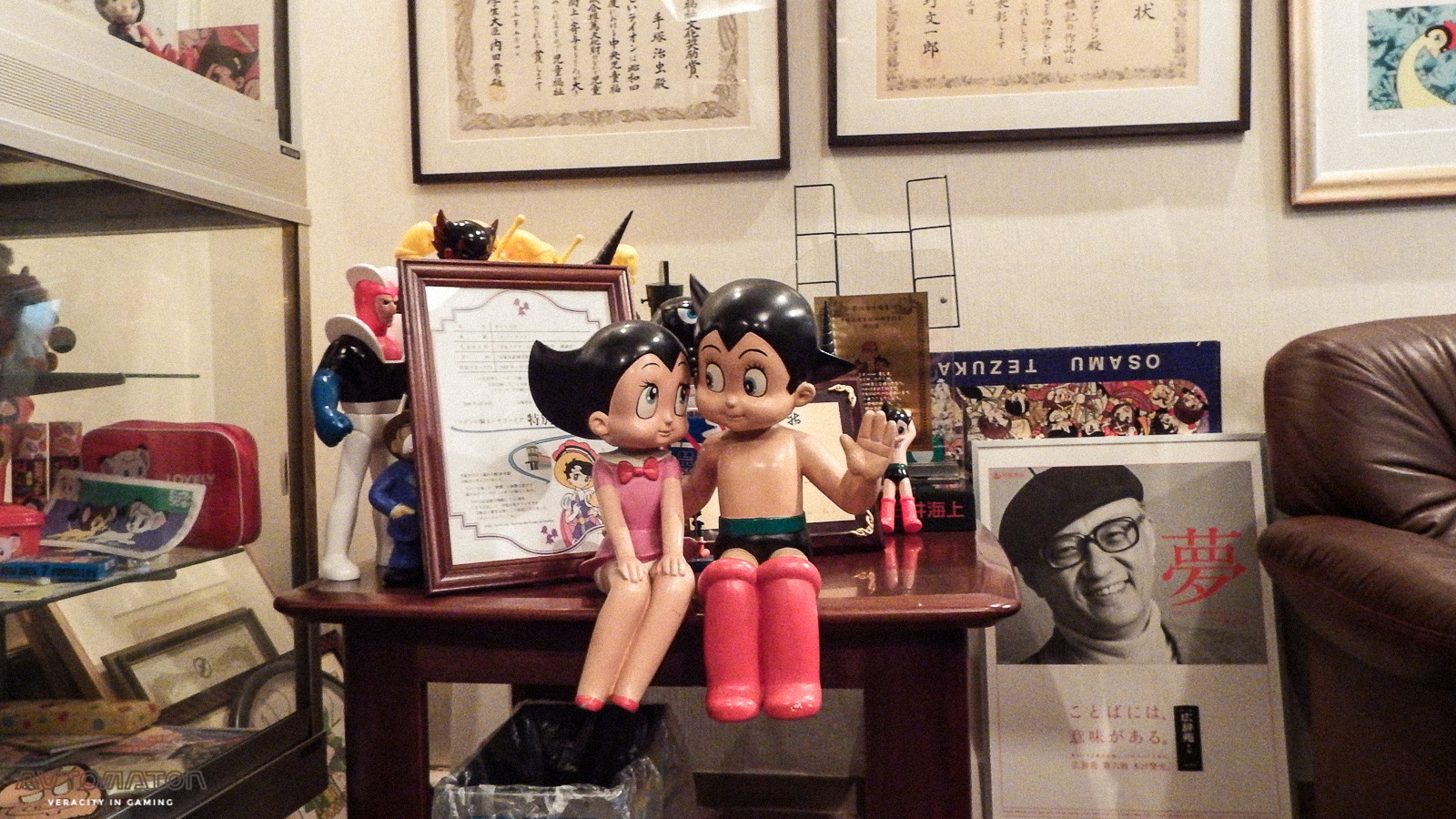
アクティブゲーミングメディアが正式発表した手塚治虫作品のカードバトルゲーム『アトム:時空の果て(Astroboy: Edge of Time)』。同作について語ってもらったインタビュー前編から、後編ではより幅広く。手塚眞氏とビデオゲームの関わりや、同氏のVRに関する考えなどを語ってもらう。
――任天堂の宮本茂さんは、「社長が訊く」やメディア「リッキー・レポート」の取材のなかで、手塚治虫先生からの影響を語ってらっしゃいます。さまざまな作品に同じキャラクターが登場する「マリオ」シリーズは、手塚作品の「スターシステム」などから影響を受けたのかもしれないと。
手塚氏:
宮本さんとずっと仕事していたけど、そんな話一度もしなかった。恥ずかしくてしなかったのかな(笑)
イバイ氏:
手塚先生は「スターシステム」をどのように始めたんですか?
手塚氏:
本人がアマチュアの時代、それこそ子供の頃に、自分の友だちとか兄弟で漫画の描きっこをしていたんですよ。その時、お互いのキャラクターを交換して描いたりとか、人が作ったキャラクターを自分の漫画に入れたりとか、あとは有名な作家の先生が描いたキャラクターをわざと自分の漫画に入れたりとか、そういうことをしていたんですね。そういうのが最初なんだと思います。
――ほかにも、手塚作品の手法がビデオゲームやマスメディア作品に与えた影響というと。
手塚氏:
アニメは全部そうですよね。7割、8割はそうだと思いますよ。アニメ自体の作り方から含めて。漫画もだいたいそうですね。見てると絵柄は違いますけど、表現のやり方っていうんですかね、ストーリーの運び方とか構成の仕方とかっていうのはだいたい同じですね。
手塚治虫以前の漫画っていうのは、コマってだいたい大きさが決まってたんですよ。そんなに特殊な形のコマとか使わないんですね。読み方も非常に単純に読んでいくだけの漫画が多かったんですよ。それを効果的なコマの形にデザインし直したのは、やっぱり手塚治虫からだと思うんですね。その流れで、今の漫画って出来てますから。基本的には、すべてが影響されてそうなってる感じです。
イバイ氏:
ストーリーはどのように構築されていたんでしょうか。最初の段階から、だいたい決めておられたんですか。
手塚氏:
初期はそうだったみたいですね。若い頃は緻密に脚本を書いて、それから文章を絵にしていくという感じでした。ただ忙しくなってくると、それをしている暇がなくなったんで、逆に頭の中で全部ストーリーを作って、いきなり漫画を描いていくという感じになったんですね。それがゆえに、最後に何作か絶筆になって、途中で連載が終わってしまった漫画の先がわからないんですよ。書き残されたメモがないので。
イバイ氏:
本人の頭の中にしかないですね。
手塚氏:
本人の頭にしかなかったですね。
イバイ氏:
そういえばほかにも、今回のプロジェクトのシナリオライターは、少ないコマ数で多くの情報を語る手塚先生の漫画はすごいとおっしゃってました。
手塚氏:
それはたぶん、日本人以外の方がご覧になると、すごくはっきりわかると思うんですよ。日本人ってそれに慣れてるから、そこに疑問を感じてないんですけど、実はそれはすごいことで。アメリカのコミックであるとか、ヨーロッパの漫画ってのは、コマごとに情報を積み重ねていって、やっとなんかものを伝えるっていう、具体的なディテールの積み重ねなんですね。だから足し算でコマが進んでいくようなとこがありますけど、手塚治虫の漫画って逆で、引き算といいますかデザインなんですよね。いかに情報を整理して、余計なものをそぎ落としていって、少ない形と線とコマだけで、的確に伝えられるかっていう、そういうデザインの感覚で作ってるものなんですよ。
これは特殊だと思うんですね。日本の漫画って感覚的に不思議だと思うんですけど、でもそれで日本の漫画は成り立ってるんで、日本人は絶対にそれがわからないんですよ。漫画ってこういうものだと思ってるから。ほかの国の漫画を読み慣れてる人は、やっぱりそれを見るとすごいと思うかもしれないですね。
イバイ氏:
確かに。
手塚氏:
シンプルにしか描けないんじゃなくて、なるべくシンプルになるように描いてます。ただまあ、いまの日本の漫画は長く時間をかけて人を楽しませようというのが多いんで、わざと話を引き伸ばしたりするんですけどね(笑)1ページで済む話を、だいたい20ページぐらいにしたりとかね。そういう漫画は多いですね。
イバイ氏:
キャラクターデザインの方向性はだいたい定まっているのですが、問題はシナリオですね。どうやって手塚先生のような、緻密なシナリオを完成させるのか。
――シナリオはどのように制作を進められる予定なんでしょうか?
イバイ氏:
基本的には1人のシナリオライターに任せていて、彼がストーリーの流れを決定をしています。プロットを確認したあとに、GOサインが出ればライティングを開始するんですね。
ただ、先ほども述べたように、手塚先生の作品はコマ数が少ないんですよね。例えが道徳的によくないかもしれないんですけど……「アラバスター」に「ロック」というキャラクターが存在します。「ロック」はずる賢いキャラクターで、いろんな手塚作品に出ているんですね。この「ロック」が、ある女の子を暴行しているシーンがあるんですが、女の子は透明人間のように表現されていて、読者はあまり変な気分にはならないんですね。非常にきつい暴行のシーンでも、本当にすっと読むことができて、なおかつ何が起きたのかは理解できます。なにも見えないし、暴行とかそういった単語も使われていないけど、なにが起きたのかはわかる。
これほどの表現がゲーム内でもできるんだったら、それはそれはすばらしいシナリオになるんですが。要するに、ストーリー自体はいいんですけど、実際にそれを少ないタッチで重みのあるものにできるのかは、今回の作品の成功するかしないかの1つのポイントになるのかなと思うんですね、個人的に。
――カードゲームというと、どうしても対人戦ありきなジャンルで、ロアなどの設定を除けば物語の進行には力を入れないという印象があります。
イバイ氏:
でも実は我々は、ストーリー上で登場したキャラクターのカードを使えるようになるというのが、一番自然の流れだと思っています。たとえば、「ブラックジャック」を探す物語があって、先生を見つけた時に初めて「ブラックジャック」のカードが手に入る。あるいは「三つ目がとおる」のカードがあるとしましょう。そのカードに、スキルで絆創膏をバーンと貼って、そのカードを弱体化させる。絆創膏はあくまで例であって使わないと思うんですけど、そういった原作にあるようなストーリー、世界観は守っていきたいと考えているんですね。
手塚氏:
一番最初にカードゲームって聞いていたのに、長いシナリオが出てきたから不思議だなあと思ってました。これどういうふうに使うんだろうって(笑)
イバイ氏:
ただ、暗くて重厚なストーリーにしただけでは、ユーザーはそれはそれで疲れてしまうと思いますから。軽さと重さのバランスは大事だと思っていて、眞さんの指導が今後も入ると思いますね。
――ちなみにストーリーの部分はどのような形で表現されるか、現時点でコンセプトは定まっていますか?アドベンチャーゲームみたいな感じなんでしょうか。
イバイ氏:
原作の世界観やストーリーを守るという意味でも、アドベンチャーゲームにはならないですね。基本的にはキャラクター絵とテキストで物語は進みますが、完全にリニアでストーリーのなかに選択肢があるわけではないです。ストーリー自体は漫画や本にしても楽しめるような内容にはなってますね。
――手塚さんはゲームをプレイすることには興味がなかったとのことですが、さまざまなプロジェクトの開発には携わってこられてますよね。
手塚氏:
自分から積極的に作り始めたのは、そんなにないんですよ。任天堂の宮本さんと作りかけてた奴ぐらいなんですけどもね。僕自身はゲームってシンプルなのが好きで、実はストーリー性のあるものって初めから興味が持てなかったんですよね。本当に単純なパズルみたいなものとか、本当にシンプルなアクションものとか、そういうのしか自分としてはやりたくないなと。
ただ、自分の趣味ということでなくてね。やっぱり広くゲームをやってる人たちがたくさんいて、それが年齢も性別も国籍も関係ないわけなんで、その人たちが楽しむっていうのはどういうことなんだっていう、そこには興味があるんですよね。どういうことに対して彼らが楽しむんだろうみたいな。
――過去には『TEO』という作品も……。
手塚氏:
ええ。ただ、あれはゲームじゃないんですよ(笑)あれはね、ゲームって言う人に対して、ものすごく抵抗して「これはゲームじゃない」ってね。あれは言ってみれば、バーチャルペットみたいな……ペットでもないんですけどね。バーチャルアニマルのソフトっていう、ある意味目的があるようでないソフトなんですね。
イバイ氏:
『TEO』は「たまごっち」よりも前にリリースされた作品ですかね?
手塚氏:
開発はだいぶ前ですね。プラットフォームはパソコン、完全にPCで、しかもWindowsでしか動かなかったんです。
イバイ氏:
いまだに海外では多くのコメントが寄せられていますよね。
手塚氏:
19か国でリリースされました。アメリカでもだいぶ売れましたね。あれはね、特殊なプログラムになっていて、OSごと入ってるんですよソフトに。だからOSを書き換えて『TEO』になって、また戻すみたいな。そういう非常に複雑で重いものになってるんです。
――当時としては、そこまで複雑にしないと動かないような?
手塚氏:
動かなかったみたいですね。技術的なところは僕がやってたわけじゃないので、当時の富士通の研究所の総力を結集してやってました。擬似AIなんですけど、擬似的なところでどこまで追求できるかという感じで。
――いまはAIの研究もゲーム分野では進んでいますが、あらためて『TEO』のような作品に挑戦するという考えは。
手塚氏:
興味は出てきてるんですね。というのは、今AIというものが具体的に流行ってきてて、IBMが作ったりしているじゃないですか。それをもっとカジュアルにできるんじゃないかっていうことが1つ。人間や生き物、コンピュータやスマホとかが、新しいテクノロジーを通じて、どうやって関係性を築けるかというのにも興味があるんですね。
つい最近、メールをもらったんですよ。昔の『TEO』のユーザーの人から。僕らはユーザーのことはユーザーと呼ばずに“コンタクティ”って言ってたんですけど、そのコンタクティからメールをもらって。自分が子どものころに『TEO』を楽しんでいて、今は親になってそのときの自分と同じくらいの子どもがいると。その子どもたちに、『TEO』の体験を味あわせたいんで、あれをまた出してもらえませんかというような。ちょうど一巡りしたんだと思います。タイミングとしては、今の時代があっているような気がしますよね。逆に『TEO』が出たのは早すぎたような気がします。
イバイ氏:
そうですね。
手塚氏:
当時、複雑なものは『TEO』しかなかったんです。あとはもう『たまごっち』とか、単純なものしかなかったし、ちょっとほかのソフトがついてこれないところまでいっちゃったんで。
――現在だと「バーチャル・リアリティ」分野の技術も進化しています。楽しめそうです。
手塚氏:
そうですね。そういう技術とあわせても面白いかもしれないし、いろんな可能性はあると思いますね。
――ちなみに「VRヘッドセット」はお試しになったことはありますか?
手塚氏:
もちろん、あります。使い方次第で面白くなるなと思いましたね。ただ、なんかその、ただこういう技術が面白いってだけだと、一瞬にしてそれは飽きられちゃいそうですよね。そこから発展して、これが何に使えるのかということを考えていけば面白くなると思います。
イバイ氏:
まあ時間かかりそうですけどね、人の生活に馴染むまでは。
手塚氏:
そうですね。
――サイズや重量、装着の手間など、まだまだ改善できる点は多いと思います。
手塚氏:
ちょっとそういう手間がかかりますよね。むかし、ティモシー・リアリーという学者と1回だけ話したことあるんです。わかります?
イバイ氏:
わかります。
手塚氏:
「バーチャル・リアリティ」なんかの理論を、本当に最初に考え始めた人。究極の「バーチャル・リアリティ」は、もうそういうハードウェアはいらないんだと言っていました。ちょっとあの人、飛んじゃってたから(笑)なにを言ってんだか半分わからないんだけど、「お前が考えたことが俺に自然に伝わるんだ」みたいな。それテレパシーですか?っていう感じだったんですけど、それが究極の「バーチャル・リアリティ」だって言ってましたけどね。ともかく、もっと自然に扱えるようになるといいなと思います。
イバイ氏:
ハードがいらない、まあそれは時間の問題でしょう。ただ私は、実際ああいう機械をかぶって、耳もふさいで家で長くやってると、すごく怖くなると思うんですよね。周りに何が起きてるのかわからないし、周りが見えない。ちょっとそこは難しいかなと思うところはあるんですね。
手塚氏:
やっぱり完全に仮想の中に入るというよりは、現実とどこかでリンクできている、リンクしているところを楽しめるような仕掛けができれば、エンターテインメントとかいろいろ応用がききそうな気はしますけどね。もちろん教育とか医療技術の分野で使われるってことはあると思うんですけど、やっぱり僕らはエンターテインメントだったり、アートっていうものにどのくらい使えるかっていうところに興味があるんで。ただそのなかの世界だけを探検するんだったら、面白くないと思うんですよ。ぜったい自分のいる場所とか、そこの現実とのリンクをどうさせるかというとこだと思うんですよ。
――現在、同プロジェクトのKickstarterおよびMakuakeキャンペーンが実施されています。
イバイ氏:
なぜクアラウドファンディングをやったのかというと、まず1つは、経験も技術もある漫画家の方々に手塚キャラクターのデザインをしてもらうためです。どうして「アトム」や「ブラックジャック」のデザインを社内でしないのかといえば、原作をしっかりわかっている人たちに携わって欲しいから。さらに有名なキャラクターをリデザインするには、我々の力ではちょっと足りないとも素直に思っていました。そうなると、必然的に何年も何十年も前から漫画家をやっているような先生方に頼んだ方がいいですよね。
もう1つは、単純にファンに参加していただきたいからですよね。これからこの作品を、1年間ではなく10年も20年も運営していきたいと考えていますからね。手塚を愛した人たちやファンにも、できれば参加してもらって一緒にやりたいから、Kickstarterを選んだんですね。
手塚氏:
おそらくこのプロジェクトが完成すると、衝撃を受ける人がいっぱいいると思うんですよ。もちろん絵だけじゃなくて、世界観というところでも。あまりにも自分たちの知ってる手塚治虫の世界とまた違うものなので。ただ、楽しんでもらえれば、絶対にこれは「手塚治虫の精神につながってるものだ」ってわかるはずなんですね。そういう意味では手塚治虫の世界が広がっていくような感じがすごくしますんで、期待してもらっていいんじゃないかと思います。
イバイ氏:
わたしとしてはただひとつ。いまから一緒にゲームを育て上げていって、楽しみながら手塚治虫のキャラクターに再会できるように、ぜひご協力ください。
――ありがとうございました。
[聞き手 Shuji Ishimoto]
[写真撮影 Mon Gonzalez]
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。







