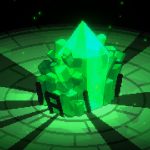大手スタジオからのレイオフ、そしてインディーへ。クビから始まった男の挑戦 『Dungeonmans』開発者インタビュー
ゲームタイトルの数だけドラマがある。それはインディータイトルでも変わらない。Jim Shepard氏は2014年12月に『Dungeonmans』をリリースした。『Dungeonmans』はアカデミーを拠点とし、ダンジョンに潜り続けるローグライクゲームだ。

ゲームタイトルの数だけドラマがある。それはインディータイトルでも変わらない。Jim Shepard氏は2014年12月に『Dungeonmans』をリリースした。『Dungeonmans』はアカデミーを拠点とし、ダンジョンに潜り続けるローグライクゲームだ。開発者によれば、『TOME』『DoomRL』『Elona』『Castle of the Winds』などから影響を受けて生まれたのだという。ゲーム中死ぬことは少なくないものの、さまざまな措置がなされており、小気味よく進行する。そんな派手さこそないがSteamで高い評価を受けている『Dungeonmans』の裏側には、どんなドラマがあったのだろうか。

――自己紹介をお願いします。
Jim Shepard(以下、Jim):
Jim Shepard、37歳、プログラマーだ。『Dungeonmans』の開発者でもある。最初にプログラミングに触れたのは7歳か8歳の時のApple IIeだね。でも2004年まではこの業界では仕事していなかったんだ。
――2004年までは何をされていたんですか。
Jim:
5年間映画館のチェーンで働いてたんだ。週末の夜に楽しそうに映画を見に来る人と会うのがとても好きだった。ポップコーンと爆発音も大好きさ。でもゲーム作りはずっと続けていた。『Shinobi』や『スペースハリアー』を真似たゲームのコーディングをしていたね。『スペースハリアー』は僕の大好きなゲームのひとつでさ。
――プログラミングは独学でしたか。
Jim:
全部が全部ではないけどね。大学ではVisual BasicとC/C++コースをとっていて、本当の科学とは何かを教えてもらったんだ。
――プログラマーとしての経歴をお聞きしてもよいですか。
Jim:
もちろん!僕はずっとAAAスタジオで仕事をしていた。Raven SoftwareからSurreal/Midway、次にGearbox、それにArmature、最後にBioWare Austin。2012年に独立して、2014年に『Dungeonmans』をリリースした。

画像出典: Wikipedia
――最初に関わったタイトルは何でしょうか。
Jim:
『Quake 4』だね。『Doom 3』にも関わったけど、コンソール機への移植を数週間手伝っただけだった。だから『Quake 4』が実質的に最初のプロジェクトだね。デザイナーたちと一緒にAIやゲームプレイの多くに関わったんだ。
――Raven Softwareは当時人気タイトルを複数抱えており、決して小さな会社ではありません。キャリアがない状態でどう入社したのですか。
Jim:
当時はアメリカ全体で若い人を雇う風潮があったんだ。それに大卒であることは重宝されたね。でも一番重要視されたのはゲーム作りを楽しめるかどうかと、プライベートでさまざまなことを楽しめるかどうかだった。まあそれに、経験のない開発者は安く雇えるからね(笑)Raven Softwareは、たまたま若い開発者を求めていたんだ。今でも学位は求められるけどね。それにしてもあれから12年かあ。僕も年をとったな(笑)学位のないデザイナーは2003年にこぞってValveに行ったなあ、そういえば。

画像出典: Wikipedia
――Valveに行くというのはその当時でも現在でも大きな野望ですよね。一緒に行かなかったんですか。
Jim:
行きたかったさ。2008年に面接を受けたんだけどね。採用してもらえなかった。でもあの時の面接は今でも心に残ってるよ。ゲームを作るというのはどういうことか、改めて勉強させてもらった。彼らは僕にゲームを作るプロセスを見せた。僕を雇う決断をしなかったにもかかわらず僕の新たな才能を教えてくれたんだ。そのほかにも、「ユーザーとの関係がいかに大切か」、「常に買うユーザーをイメージし好みを意識して作れ」など、たくさん教えてくれた。あの日は本当に素晴らしい日だったよ。

画像出典: Midway Games(Internet Archive)
――Midwayという響きは少し懐かしいですよね。あの破産の時期にいたのでしょうか。
Jim:
Raven時代の僕の初めの上司であるRick Johnsonはとてもいい人で、兄貴のように慕ってた。Midwayが危うくなった時に彼が僕をGearboxへ連れて来てくれたんだ。
――Gearboxは今では世界を代表するデベロッパーのひとつですよね。どのような雰囲気でしたか。
Jim:
エキサイティングな場所だったよ。良いゲームを作ることを常に考えていた。そして今も考え続けているよね。みんなが野心的で成功を望んでいた。例えば、インセンティブがそうだね。社内でもっとも良いとされたゲームのチームはたくさんの追加報酬をもらうシステムだった。だからこそ良いゲームを作れた。人格も素晴らしかったね。『Borderlands 2』をプレイした時は、あそこで働いている友人たちを思い出して懐かしい気持ちになったよ。彼らは働いている時もああいったジョークが好きでね。ゲーム開発はシリアスな雰囲気になりがちだけど、僕らの仕事は癌を治すことじゃない。ユーモラスに楽しまなきゃ。

画像出典: Battleborn
――あなたがこれまで働いていた他の会社はインセンティブシステムを採用していなかったんですか?
Jim:
いいや。Gearboxはそういった意味でかなりユニークだった。またGearboxはその人が“会社にいかに合っているか”でボーナスが出ていたんだと思う。どのゲームに関わっているかは関係なくね。上層部は『Borderlands』シリーズをスタッフの私欲の矛先にしないようにうまくコントロールしたがってたね。
――しかし、インセンティブシステムというのはプレッシャーやストレスとは切り離せませんよね。
Jim:
そのとおりだ。Gearboxは給料が平等に払われない問題に慎重に対処していた。でも、一番のプレッシャーは解雇されないようにうまくやらなければいけないことだ。ゲーム会社はいつだってレイオフをおこなう。それが僕が独立した理由のひとつでもある。でも僕はGearboxのみんなが大好きなんだ。その次の会社のArmatureも良い経験をさせてもらった、小さなチームで決断力があったね、関わってたタイトルは開発中止になってしまったけどね。
――それでも、大手のスタジオにいれば経済的には困らなかったのでは?インディーへ行くことに恐怖はなかったんでしょうか。
Jim:
もちろん、とても怖かったよ、正直に言うとね。でも、大手のスタジオにいるような収入がなくても、頑張ればある程度の収入は得られるだろうと思っていたんだ。

画像出典: Star Wars: The Old Republic – Flickr
――インディーへ行こうと決心した大きなきっかけは何ですか。
Jim:
2012年にBioWare Austinで仕事をしていて『Star Wars: The Old Republic』が終了後、大きなレイオフがあったんだ。僕もその中のひとりだった。いろいろ考えた結果、インディーに行こうと決めたんだよ。人生は冒険なんだ。恨みっこないよ。働く前から「EAはレイオフでおなじみの会社で、MMORPGは安定していない」ってわかっていたからね。
――さまざまなスタジオに行かれましたが、スタジオを離れる理由は似ていましたか。
Jim:
いいや、その時々で異なっていた。レイオフもあれば、倒産もあり、個人的な理由もある。他の開発者は僕のように頻繁に移籍はしないね。

画像出典: BioWare Austin
――レイオフというのは日本ではあまり馴染みのない言葉です。
Jim:
小さな会社であれば、レイオフの勧告は個人個人でやるみたいだね。オフィスで告げられて、みんな泣き出す。でもBioWare Austinの時は違ってた。セキュリティガードが無言でレイオフする人々のデスクの周りを取り囲むんだ。
――「恐怖」に近い方法ですね。それでもあなたようなキャリアのあるプログラマーなら業界にイスがあるのでは?
Jim:
少し怖かったね、正直言うと。プログラマーの人材難はどの産業でもあることさ。あることを長く続けていたら、いつか人は腰を落ち着かせたくなるんだよ。
――インディーを始める前から開発するゲームは決めていたのですか。
Jim:
ああ。『Dungeonmans』は仕事しながらもずっと続けてきたプロジェクトだ。2007年から、週末や祝日、年末を使って開発してきた。
――平日は会社でゲーム開発、休日は自宅でゲーム開発、とてもモチベーションが高いんですね。
Jim:
なんてったってゲームが大好きだからね。単純な話さ。スウィングダンスと並ぶ僕の2大趣味だよ(笑)でも特に好きなのはゲームを開発する方さ。
――『Dungeonmans』はひとりで開発されましたか。
Jim:
フルタイムで働いていたのは僕だけだった。契約を交わしたデザイナーやコンポーザーはいたけどね。僕は絵がヘタなんだよ(笑)Andrew Averseが音楽を担当してくれた。Jearmy Cookeはリードデザイナーさ。彼はGearbox時代からの友人で、僕と同じゲームを愛している。ほかにも10人ものデザイナーと契約したけど、Jearmyはすべての絵を高水準に調節してくれた。彼自身もたくさん絵を描いてくれたけどね。
――ひとりで開発する時間に、孤独を感じませんでしたか。
Jim:
感じたさ。一日中家にいて塞ぎこむのは簡単だ。でも、僕は友好的で社交的だから、無理矢理にでも外出して友人と楽しい時間を過ごした。仕事中でも他のインディー開発者とアイディア交換もしたね。良き友人とコミュニティと出会えたのが僕の幸運だった。
――最終的にインディーを始めてからリリースまでは実際にどのくらいかかりましたか。
Jim:
インディー自体は2012年に始めて、2013年にKickstarterを始めた。アーリーアクセスは2014年5月に始めて2014年12月に正式リリースしたね。
――Kickstarterを成功するまでに、他の業種につくなど生活に困りませんでしたか。
Jim:
貯金もしていたし、BioWare Austinからもらった手当があったからね。
――Kickstarterのキャンペーンを成功させるのも簡単ではないですよね。
Jim:
Kickstarterの面白いところは、名前と顔を知ってもらえるところだ。僕は”Madjack McMad”っていうハンドルネームを持ってるんだ。でも、人からお金をもらうためには顔と名前を知ってもらう必要がある。ファンはよく「よお、Jim」と言ってくれる。彼らや友人のサポートなしには成し得なかった。個人的な事情で、引っ越しを繰り返さなければならない時期があって苦しかったんだ。も、彼らをガッカリさせたくなかったし、誇りを持てるゲームが作りたかった。いろんなユーザーに助けられてここまで来れたんだ。
――Kickstarterはファンディングの成功後も資金の管理など、難しいことがたくさんあります。
Jim:
お金の管理は難しいさ!僕も十分にできたとは思ってないんだ。でも僕が言えるのは、良いお金の使い方をしたほうがいいということ。今ではUnityのアセットもとても安く手に入るし、インディーにとってめちゃくちゃ便利な時代なんだ。でもしっかり開発を手伝ってもらう人とは、その人がしっかり生活ができる契約をして、公平に接さなければいけないよ。タダ同然で開発者を募る人もいるけど、健全じゃないね。給料が安いとすぐに燃え尽きてしまうしやりがいも感じにくい。プロジェクトを成功させるには、妥当な額を払い、信頼関係を築かねばならないんだ。
――ボランティアの方はいなかったのですか。
Jim:
ボランティアの人がいた時期もあった。Jearmyはそれに近いような手伝い方をしてくれたからね。でもほとんどが金銭の発生する契約だった。お金を払わず人を雇えば、その人はいつだってやめることができる。リスクがあるんだよ。

Jim:
はは!あの演出は映画館にいた経験が生きたのかもしれないね。レベルアップした時にユーザーは幸せを感じる必要があるんだ。体力が回復し、窮地に追い込まれた時はピンチがチャンスになる。あと、みんな上に登る矢が好きじゃないか(笑)ユーザーにもイカしたレベルアップ演出だって褒めてもらえるのはとても嬉しいね。実はこのアイディアは『FINAL FANTASY XII』にヒントを得てるんだよ。多くのゲームは戦闘後にレベルアップが告知される。でも『FINAL FANTASY XII』は違うよね。戦闘中にレベルが上がるんだ。
――個人的に気に入っているクラスはありますか。
Jim:
ほとんどのクラスが大好きなんだ。Psychomanserは味わいのある職業だよね。開発の一番最後で作られたクラス。とてもユニークでやや複雑。特に好きなのはBannnermansかな。中距離戦闘を得意としていて、近接でもなく遠距離でもなく、絶妙なんだ。
――Rangermansはどうですか。
Jim:
Rangermansは初心者にはぴったりだね。ゲームのいろはをたくさん学べる。スタミナを切らす前に困難から逃れられるしね。モンスターとの位置関係のコツも学べる。それと初心者はアカデミーにすぐ帰ることを恥ずかしがらなくていい。このゲームはアイテムをアカデミーに還元できるからね。

Jim:
おそらく『Dungeonmans』はローグライクの中では最も簡単なゲームのひとつだろう。Diabloライクと呼ばれるのは素晴らしい賞賛だね。『Diablo』シリーズは『Dungeonmans』に大きな影響を与えてる。素早く移動できたり、敵を倒すことに気持ちさを感じてもらえるようにデザインしているのもそういう影響があるんだ。
――そんな『Dungeonmans』ですが、やはり言語の壁は大きいように感じます。現在英語しか提供されていませんが、ローカライズの予定はありませんか。
Jim:
それは考えてないんだ。開発当時、ローカライズをできるような仕様を作れなかった。次にゲームをリリースする時は正しくできれば良いと思う。日本のファンに謝りたいし、言語の壁を越えて遊んでくれている人には本当に感謝しかないよ。
――ローカライズしないではなく、できない、ということなんですね。
Jim:
そうだ。完全なミスだった。同じ過ちは犯さないよ。
――『Dungeonmans』は音楽も素晴らしいゲームですよね。正統派ファンタジーの音楽だと感じました。コンポーザーのAndrew Aversa氏にどのような注文をしましたか。
Jim:
そう思うだろう!?曲のイメージはふたりで自然と思いついた。初めて会った時から、PlayStationやセガサターンのようなmidiシンフォニーのような音楽が作りたいと思っていた。僕らは崎元仁の大ファンでそういった音楽を鳴らしたいと思っていた。Andrewの音楽からは何を伝えたいのか感じ取れるようだった。彼もそうだったようでとても楽しかったよ。Andrewはビジネスの面でも開発の大きな助けになった。開発を通じて本当の友人になれたんだよ。友人は『Dungeonmans』はAndrewの音楽のために生まれたんじゃないかって冗談言うんだよ!(笑)
――インディータイトルで耳に残るサウンドは8bitサウンド、いわゆるchip tuneが多い気がします。
Jim:
僕もそう思う。個人的にもchip tuneは大好きなんだ。でも『Dungeonmans』に合うとは思わなかった。このゲームには32bitが必要だと感じていた。
――Andrew氏はインディーゲームのサウンドを多く手がける売れっ子です。どのようにオファーをしましたか。
Jim:
友人が彼を紹介してくれたんだ。彼の音楽は聞いたことがあったんだけど、会うまでは正直少しナーバスでね。でもすぐにAndrewは『Dungeonmans』を気に入ってくれた。開発の初期段階だったけれど、このプロジェクトに真剣になってくれたんだ。数か月後に、ボルチモアに引っ越した、そこは彼の家から20分の場所で、それから個人的によく遊びに行くようになった。それから仕事の連携もかなりとりやすくなったんだ。今はシアトルに住んでるけど彼は定期的に遊びに来てくれるよ。
――信頼関係は仕事を円滑にする、と。
Jim:
もちろん。信頼関係は少なくとも欧米においてはゲーム開発において最も大きな部分だ。とても長い時間一緒にゲームを作るからね。それに、ゲームが発売されてみなよ。フォーラム、コメント、Reddit、みんなが「お前はダメだ」って言うじゃないか(笑)助け合える友人がいたほうがいいね。
――『Dungeonmans』は現在でもアップデートを続けています。DLCもなく1年半アップデートを続けるタイトルは決して多くはありません。
Jim:
ゲームに新しく要素を導入してユーザーに喜んでもらえるのは楽しいことさ。それに、アップデートをするとしばらくは、ちょっとだけ売上もあがるんだ。でも流石にもうお年寄りだし、『Dungeonmans』のアップデートはそろそろおしまいかな。
――ゲームで1年半はお年寄りですよね。ゲーム自体の売れ行きはどうでしたか。
Jim:
おかげさまで、Kickstarterの成功、アーリーアクセス、製品版の売上で1年は暮らせるぐらいは売れたよ。まだ何千ものプレイヤーがいるし、まだまだゲームの楽しさを知ってほしいね。
――良い報せですね。『Dungeonmans』はあまりセールされないことでも有名です。バンドルにも入っていません。
Jim:
まだバンドルに入れる気はないね。一度バンドルに入るとゲームの価値はほとんどなくなる。そういう状態はあまり望んでないんだ。
――さて、改めてお聞きします。インディーになってから、大手スタジオにいた頃と比べると生活は変わりましたか。
Jim:
僕にはこっちのが合ってると言えるね。でもそれがみんなに当てはまるとは限らない。すべての失敗は自分が引き受けなければいけないんだ。でも、リリース段階でバグがあっても何が悪いか自分ですぐにわかるし、すぐに直すことができる。大きなスタジオにいるときは、そういった決断をするとほかの人を巻き込んだ負の連鎖になる。何も干渉せずに座らなければいけない。それが自分のためにはよくなかった。それと、ユーザーと近い距離で会話できるのがいいね。アップデートする意欲も湧きやすい。これも大きなスタジオでは、ユーザーの声よりもマネタイズを意識しなければならないよね。
――これからインディーを目指そうとしている人々へメッセージをいただけますか。
Jim:
インディーゲームを作る際は、それがいかに小さなゲームだとしても、どのようなユーザーに伝えたいか考える事が大切だ。何を残し、何を削るのか、何を重要とするのか、どのような要素を特徴とするのかを常に意識すべきだね。今まで見たこともないゲームのアイディアが考えつくのは素晴らしい、でもそれがゲームとしていかに機能するかが大事なんだ。とにかく完成までたどり着くこと。開発中は「ああ、この要素はいまいちだ、ここを良くするためにコードをいじってしまおうか、エンジンを変えてしまおうか」と考えるかもしれない。最近のエンジンは魅力的だからね。でも、それはやめよう。まずは完成させるんだ。溢れ出るアイディアは次に取っておけばいいんだ。
――ありがとうございました。
Jim氏は4月6日に『Demon Truck』を発表している。トラックをかっ飛ばしながら、銃ですべてを吹き飛ばす、アーケードスタイルのアクションゲームとなっている。Jim氏は「何も考えずにこのゲームを遊んで爽快になってほしい」とメッセージを送っている。Steam Greenlightでも投票が始まっているのでチェックしてほしい。
[聞き手: Minoru Umise]
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。