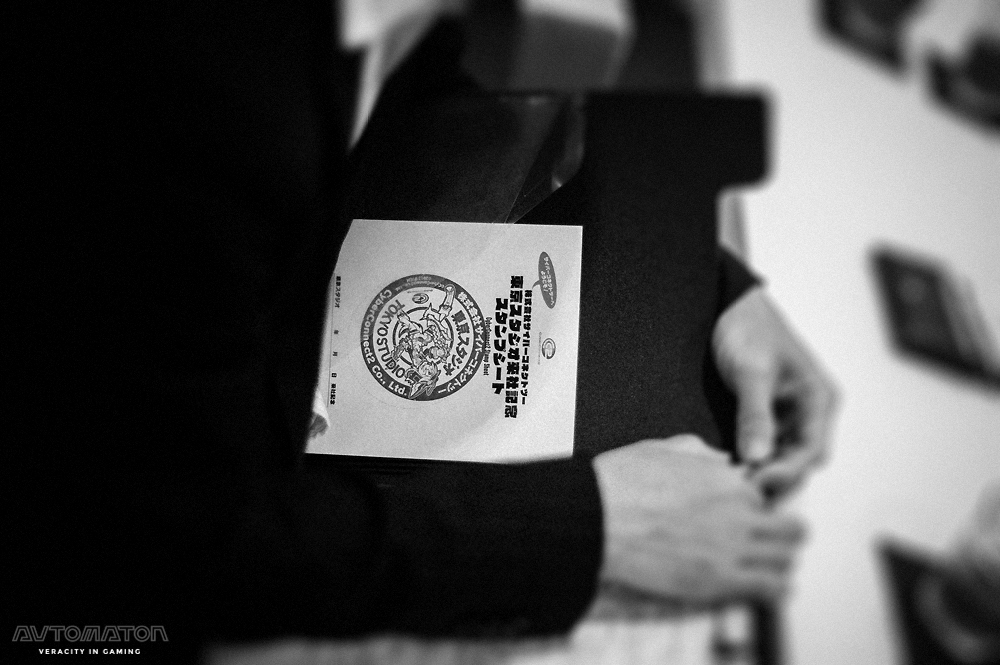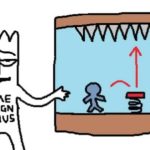AUTOMATON vs. 松山洋 サイバーコネクトツーのルーツと信念 (後編)
中編から引き続き、サイバーコネクトツー松山洋氏へのインタビューです。

中編から引き続き、サイバーコネクトツー松山洋氏へのインタビューです。
――なるほど。ところで、現在の製作ラインは、スマートフォンとコンシューマーという形で大体わかれているのですか?
そうですね。いま福岡本社が180人くらい。東京スタジオが40人くらい。合計220人くらい。その中には開発者以外に宣伝、人事、総務、経理、といった部署のスタッフが20人ぐらいもふくまれます。
そのなかで家庭用ゲームが5ライン。スマートフォンのタイトルが5ライン。合計10ライン。もちろん始まったばかりのものもあれば、完成間近のものもあります。すこしずつ毎月編成を変えていますから。そうやって10プロジェクトをまわしています。それとは別に未来に向けた3年後のタイトルを、だいたい5タイトルくらい企画を仕込んでいます。そうやって私は大体15本くらいみてます。実際に動かしている現場は10本ですね。
――では、具体的にゲームの現場について。サイバーコネクトツーのゲームはアクション要素をアニメや映画的演出に取り込むものが多いように感じますが、それはやはり自分たちがやりたいものとしてそのような趣向を打ちだしているのですか?
もちろん好きで得意だってことはあるんですが、商品とは面白そうで面白くて売れるもの、入り口は「面白そう」なんですね。ゲーム機ってハードルの高い娯楽です。そもそもゲーム機を買わないと遊べないですし、モニターに接続しないと遊べません。リビングのテレビモニターを家族を差し置いて独占しなきゃいけませんし、そういう意味で結構ハードルの高い娯楽なんです。
遊ぶ前にまず面白そうと思ってもらわなきゃならないです。いまも変わってないのは、日本の子どもたちに、“このゲームを購入する決め手になったきっかけはなんですか? ”というアンケートをとると、70パーセントの子どもがテレビCMって言うんですね。テレビCMって15秒じゃないですか。15秒でシステムの説明はできないですよね。なんとなく面白そうって思えるかどうかじゃないですか。それでやっぱり映像演出となります。
結局、面白そうと思ってもらうための演出をしないと、そういうタイトルにしておかないと、最初の話にあったように、「遊んだら面白いんですけどね」という負け惜しみを言わなきゃいけなくなってしまいます。なので弊社では面白そうに見える企画書を作りますし、プリプロダクションのときもただ動いていればいいではだめで、そこに一つ尖がっているユニークな部分が求められます。面白そうと思ってもらえるポイント、それはサムシングニューだと思っています。既存のタイトルと比べてなにがあたらしいか、いままで体験したことがないものかどうか、ということをつねに求めていますね。
――なるほど。弊誌のなかで『サイレントボマー』が好きだという者がおります。あのゲームはそれこそ、パッと見わかりづらいんですが、話を聞くと「遊んだら面白い」という評判ですよね。
見た目ではなかなか伝わらないでしょう。でも遊んだら面白いです。見た目でわからないというのは、このとき学んだことのひとつです。
本当に『テイルコンチェルト』と『サイレントボマー』が私の原体験ですね。あの結果は本当に……『魁!!男塾』の伊達臣人みたいに血が出るほどこぶしを握りしめるほど、悔しかったですね。
――つまりは、自分たちとしてはすごく面白いものを創ったけど、伝わらない。
あれでは伝わらないです。本当に反省ですね。
――いまのサイバーコネクトツーのイメージだと、『ナルティメット』シリーズや、最近だと『アスラズ ラース』などがかなりインパクトがありました。あの作品はサイバーコネクトツーを知っている人にとっては「おお、これこれ」という感じもあったのでしょうが、わからない人にとってはかなり驚きの内容であったと思います。映像が主体でQTEのアクションという内容は、確信犯的にやったものですか?
そうですね。カプコンさんは『バイオハザード』や『デビルメイクライ』などアクションが得意な会社です。なので触って面白いアクションゲームは売るほどあるので、やっぱり誰も見たことがない経験したことがないものを、と話し合いました。弊社とカプコンが組む以上、なんならこれは本当にゲームなのか?って賛否が出るくらいでちょうどいいんじゃないか。言葉なんか分からなくたって見てるだけで大笑いしたり、感動できるような、そういうぶっ飛んだ突き抜けたタイトルを創ろうぜ、って生み出されたのがあれです。
――それはほかのインタビューでも拝読したのですが、最初は意外とアクション寄りで、カプコンさんからもうちょっとサイバーコネクトツーらしさを出してほしいと言われたとか……
そうです。そういうアクション寄りのゲームはもうあるからいいです、と言われました。
――じゃあもう自由にやっていいんだ、と。
ええ、まあだいぶ語弊はありますが。サイバーコネクトツーの得意とするもの、表現したいものをもっと全面に出してほしいというオーダーですね。
――でもかなり私としては、こういう言い方をしていいか……悪ノリというか、サイバーコネクトツー色をガンガン出したという感じに見受けられます。
そうですね。企画書に大きく「破天荒」って書いてありました。
――お話をうかがってきたかぎりでは、松山さんにとってゲームの会社、デベロッパーというのは、ただ作品を創るだけじゃなくて、それを興味深いこととか、関心を引き立てるものとして見せる演出面、プロモーション面も非常に重要視していらっしゃるようです。 では、最終的にお客さんが満足するかどうかに関してはどのようにお考えですか? 面白そうだと思ったのに、そんなに面白くなかったという場合、それはなおさら残念な気持ちになるわけですが。
はい。なので、われわれの課題はそこだと思ってます。単純にわれわれの実力不足です。「面白そう」って100点満点に思ってもらうけど……よくお客様からも言われることですが、ゲームの中身はいつも60点。
――それはけっこう辛辣な意見ですね。
お客様の評価がそうなんだな、って思います。われわれはもちろん全力を出しきって100点満点のつもりで創っていても、結局のところお客様の評価がそうなんであれば、我々は60点の会社なんだなって。それがお客様の評価なんですから。
――それは認めるしかない部分があると。
65点、70点、そして100点に近づける努力をもっともっとやっていかなきゃいけないです。そこはもうただひたすら頑張ります。なので、賛否いただけるお客様からのメッセージは、どちらもありがたいですね。一番おそろしいのは、叩かれることも知られることすらなくスルーされることです。「知りません」て言われるのが一番怖いですね。それはゲームにかぎらずどのコンテンツもそうだと思います。漫画家さんでもそうだと思います。私も根っこのところでは漫画家さんと同じなんです。「なに描いてるんですか?」「知りません」と言われることが一番さびしいです。これ芸人さんとかもそうじゃないですか。「テレビとか出られてます?」ってね。一番それが辛いことだと思うんですね。
――いまなにをなさっているのかということと、今後の創りたいものなどのお話をしていただきたいと思います。今後も『.hack』のような一風変わったメディアミックスのものをまたやりたいとか、それとは別にいまとは異なる版権のキャラクターのゲームを創りたいなど、ございますか?
サイバーコネクトツーはキャラクターゲームの会社だと思われがちです。ですが、『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル』を創るまでは、キャラクターゲームは『ナルティメット』シリーズだけでした。それまでは『.hack』シリーズのような、他のメディアと新しいムーヴメントを作りたいという想いでオリジナルを創ってきました。
――つまり『.hack』がある程度終わった段階から、つぎのかたちの……?
それはずっと考えています。今の時代はゲームのプロジェクトだけで成功することも難しく、ほかのメディアもあわせてこそ盛り上がるものです。そういったタイミングはずっとはかっています。なので、もう『.hack』のようなタイトルはやらないんですか? とよく言われるんですが、もちろんやりたい気持ちもあるし、みなさんに求めていただいているのもわかっています。
立場的には、しかるべきときがくれば……みなさんの前でお伝えできる日がくると思いますよ、としか言えないのです。
――これはサイバーコネクトツーとは別に、松山さん個人がこういうゲームジャンルに興味があるとかこういうものを創ってみたいとかはおありですか?
私はジャンルに固執しているわけではないですね。やっぱり一番の得意技で勝負したいと思っています。そして絶対やらないことははっきりしてます。リアルな挙動の車のゲームや実名の選手が登場するサッカーゲームとか、英語を勉強するような実用系のゲームなど、そういうのはまったくできないと思います。
空想科学世界、絵空事、少年少女の夢、そういうものを弊社は創り続けていきたいなと思っていますね。それはオリジナルだろうと版権ものだろうと、そこに垣根はないんです。キャラクターものも、『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル』も『ナルティメット』シリーズもオリジナルゲームのつもりで創ってますから。なので、他の版権ものやらないんですかって言われると、いまは考えていないですね。
――これはまったく雑談なんですが、海外のいわゆる版権ものというか、海外だとようするにアメコミとか。ああいう系のゲームはやったりすることはありえますか?
はい、機会があればありえると思います。映画も観ますし。面白いと思いますし。
――なにか気になるものとか、こういう表現は面白いなというのはありますか。
毎回思いますよ。マーベルですと『アイアンマン』シリーズが一番好きですね。『アイアンマン』の格好良さは私が求める格好良さとはまた別のチャンネルだと思います。
――映画版のトニー・スタークのやつですね。
あれは娯楽作品として好きですね。私自身が思い描く少年少女の夢とは別ですね。
――ほかのインタビューで拝読したのですが、好きな映画のなかに、韓国の映画がありました。韓国の映画はわりと残虐なバイオレンスが多いですが、そういうものはお好きですか。
今もそうですね、好きです(笑) 韓国って恋愛ものと、バイオレンスというかクライムアクションというか、そういうものが多いと思うんですけれども。没入感が非常によくできているタイトルがまれにあります。その多くは復讐ものなんですけど。とくにわれわれアジアの人間、日本人って、見ている原風景が日本と韓国とで似ているんです。
坂道多かったり、家がせまかったり。家のなかを裸足で歩いたり。ハリウッド映画とかって、家のなかで靴はいてるし、テーブルに座るし、ナイフとフォークで食べるじゃないですか。憧れはあっても親しみはないじゃないですか。韓国映画は観ていて、うまそうだなぁと思う瞬間とか、うわぁ汚そうだとかの瞬間があります。字幕以外の視覚情報で入ってくる臨場感や共感する部分が同じアジア人だと、シンクロできるんです。
あとは表現がうまいです。復讐モノなど一方向にトガっています。本当に復讐する側とシンクロしてしまいます。
――こいつは本当に殺さなきゃいけないと。
はい。それくらいの気持ちにさせられます。その役者さんに恨みはないですけど。それぐらい悔しいですね。そこまで一本の映画で感情を持ってかれるような作品って、なかなかお目にかかれないです。
――そういうようなことを、ゲームのなかでやりたくはありませんか?
思いますよ。それを私なりの……やっぱり映画とゲームの娯楽って違うじゃないですか。復讐って、いわゆる禁忌のひとつだと思うんです。やってはいけないことのひとつ。でも人の感情じゃないですか。そこに甘美な魅力って絶対にあると思うんです。『.hack//G.U.』 を創ったときに、主人公の目的を復讐にすえたのは、最初バンダイナムコゲームスさんに猛烈に反対されたんです。結局、だいぶマイルドにしましたけど。
――しかし、ジャンプ漫画とか中でもファンタジーもので復讐というモチーフは結構あると思います。『ジョジョ』もそうですし、富樫先生の話とかにも。
そう思います。
――さきほど、スマートフォンとコンシューマと同じくらいのライン数という話がございました。今後、スマートフォンの方に大きく比重を移すということは?
ないです。今の弊社の考えは、コンシューマーゲームもスマートフォンゲームもどちらもやります。ですが、スマートフォンだけの会社にはなりません。逆に、家庭用ゲームだけでやっていきます、というのも違うと思ってます。いまのお客様のおこづかいが、家庭用ゲームとスマートフォンのソーシャルと両方に遣われているのは事実ですから。だから弊社はいまのところ50:50です。同じ割合で、いまのところやっていきます。でもこれからスマートフォンは減るかもしれません。
――それはどうしてですか?
家庭用のほうで大規模なタイトルが増えてくるというか、仕込んでいるからです。
――では、どちらかというと、比重としては、時期のタイミングの問題があるということですね。動いているものがあるということですね。
あります。10ライン動いていて、さらに未発表で完全に新しいタイトルがプラス5ありますから。
――その辺の話でうかがえることあればぜひお聞きしたいのですけど、あまりございませんよね?
そうですね(笑)
でも弊社で創るタイトルは、どれもそうですが、オリジナルもキャラクターものも、サイバーコネクトツーじゃないと創れない創り方をします。弊社の創った『ナルティメット』シリーズってほかの会社が創った『NARUTO-ナルト-』のゲームとも似てないと思うんです。『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル』もひとくちに格闘ゲームといっても、あそこまで過剰に演出をやる格闘ゲームはないと思います。格闘ゲームとしてのバランスを崩しかねないような調整ですらあります。しかしながら、弊社の創り方はこうで、バトル中のモーションひとつにしても、自分たちでなくてもできる仕事は絶対にしたくないですね。
――なるほど。『ナルティメット』シリーズも『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル』もカメラワークのこだわりが感じられます。とくに漫画のコマからもってきたカメラ視点を採用しているところ。そういった漫画とかアニメにあった表現を利用したいというお気持ちは、原作に対する愛情ということ以外も、クリエイティブな側面からもおありですか?
もちろんあります。映像演出論や映画の撮影技術、アニメの撮影技法だったり、演出表現技法というものは、つねに研究しています。やっぱりアニメが大好きです。
――最近気になっているアニメはありますか?
放送されているやつは基本全部みています。
――最近だと話題になっているのは『ピンポン』あたりでしょうか?
Blu-rayBOX買いました。近日中に届くと思います。
――ああいったかたちの映像、監督は湯浅政明さんで、かなりアーティスティックな方ですが、ああいった方向のものをゲームでやってみたいとお考えですか?
『ピンポン』のあの作家性はゲームには不向きですね。あれは映像作品としてのあり方だと思います。作画ももちろんそうなんですけど、私自身が湯浅監督の『ピンポン』で一番感心したのは、原作の『ピンポン』て18年前の作品を現代としてアレンジされているところです。この18年間で卓球の公式ルールが変わっているところを現代のルールに合わせていたり。今、部活動で卓球をやっている学生さんたちにも観てほしいです。昔の作品なんですけど、現代風のアレンジと、テレビアニメとして1クールで成立させるための原作にない表現、演出、シナリオというものが、多分に入っています。
そこの差異が、すごく湯浅さん自身の作家性を感じるなと思いますね。まったくいなかった登場人物が追加されています。そのキャラクターがいる意味とかが、そのキャラクターを足すことによって変質しています。元々いたレギュラーメンバーの獲得目標だったり、なんでそうなったのかという原作では「想像してください」で終わっていたものを、フィルムに起こしたときに、説得力を薄っぺらなものにしないためにあえて追加されているんです。そこの思考ですね。なんでそういうことをしたかという思考が私のタイプというか好みというか。よくわかるんですね。
もし私が『ピンポン』というもの原作コミック全5巻を映像化させていただくとしたら、同じことを考えると思ったんですね。そこがすごく好きです。
――なるほど。やはりそういった意味では、映像作家的な目線がおありなんですね。『NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストーム2』でステージのマップが切り替わるときに入る演出があります。ナルトたちが屋台越しのカメラで動いているのが見えるシーン。ああいった表現は日本のゲームでしか見たことがない独特なものと感じました。
そうですね。あれはアニメのカッティングですね。
――ではお約束ですが、求める人材をお教えいただけますか。ずっと求人募集はしていらっしゃいますよね。
募集はかけています。1年間ずっと。時期は関係ないです。合格したらいつでも来てください。
――東京スタジオと福岡の二つですよね。求める人物像は?
やはりエンターテインメントが好きな人ですね。
――ゲームにかぎらず?
ゲームにかぎらずです。もちろんゲームが好きな人もいっぱいいます。でも私自身、マンガが一番好きですし。マンガだろうと映画だろうとアニメだろうと好きな人は信用できます。
好きは裏切らない。好きって無償の愛じゃないですか。誰かに頼まれたから好きになったわけではないですし、好きでやることは辛くないじゃないですか。私なんか月に60冊週刊漫画雑誌を読んでいるんです。サンデー、マガジン、ジャンプ、ヤングジャンプ、スピリッツ……と、ずっーと。
アニメは初回はひと通り観て「これはもういいや」って思ったものは数は絞っていくんですが、映画は一年間100本は劇場で観るって決めています。結構無理してますが。試写会にも行きますし、日曜日には3本4本は見ます。漫画雑誌を月60冊、ゲームも何百本、アニメも映画も何十本、大変ですねって言われることもあるんですが、好きでやっていますので大変だとは思ったことはないです。この仕事やってなくても、同じだと思います。『魔神英雄伝ワタル』を見るために学級委員長になる男ですよ(笑)
――先ほどの会社のルールがいろいろあるとのことでしたが。
社内ルールはいろいろありますが、当たり前のことです。今までできてなかっただけで書かれていることは当たり前のことです。
――たしか出社時間以外にも退社しなきゃいけない時間がありました。
徹夜禁止ってやつですね。
――それはやはり効率的にパフォーマンスを発揮するということですね。
そうです。でも繰り返しになりますが、なによりも好きでいてほしいですね。「好きです」っていう人のうち、じつはかなりの割合で「そんなに好きじゃない」んです。どこかで自分でブレーキを踏んでいるのかもしれないですし、専門学校や教育が悪いところもあるかもしれないです。好きっていうだけではクリエイターにはなれないと言われますし。それはたしかにそうなんですが、やはり"全力で間違っています"。何を置いてもまず好きであること。それが一番重要です。勉強なんてあとでいい。2番でも3番でも100番でもいい。まず好きを、すべての原動力がそこです。好きなことのために嫌なこともできますから。
だから本当に"好き"を伸ばしてほ欲しいですね。好きでいる人間をとにかく否定しないでほしいです。それにまわりの人間が手を差し伸べる必要はないので、見守ってほしいなと。サイバーコネクトツーは今までもこれからもすべてがそれを体現しています。頼まれたり、持ち込まれて創った企画は一個もないです。『ナルティメット』シリーズも『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル』も『.hack』シリーズも全部自分たちでこのゲームを創りたい・やりたいっていうものしかありません。たぶん今後もそうだと思いますし、わがままな会社だと思います。
――ほかの版権もののゲームの依頼もおありですか?
頻繁にいただきます。そういった持ち込みを断ると決めているわけではないです。面白ければやります。大体、いただく案件の多くがそうでない話ばかりなんですよ。あと、お話を聞いてみると先方が勘違いされていらっしゃることも多いんです。『ナルティメット』シリーズや『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル』のエンジンでホニャララなIPで創ってくださいといった具合です。そういう「楽したいだけ」の話も多いのです。
これから皆さんには正式にはお伝えできていないタイトルはたくさんありますし、きっと本当に驚いていただける、そして喜んでいただけるタイトルがいくつもひかえています。ぜひ楽しみにしてください。
現代はお客様、一個人の方が情報を発信しやすい時代です。たくさんの意見をいただける世の中ともいえます。われわれは、「60点」と言われたこれまでの経歴を塗りかえるべく、70点、80点、90点、100点の作品を生み出す所存です。これからもがんばっていきますので、ぜひ応援をよろしくおねがいします。
――ありがとうございました。
AUTOMATON vs. 松山洋 サイバーコネクトツーのルーツと信念 (前編)
AUTOMATON vs. 松山洋 サイバーコネクトツーのルーツと信念 (中編)
AUTOMATON vs. 松山洋 サイバーコネクトツーのルーツと信念 (後編)
[聞き手: 今井 晋]
[写真: Mon Gonzalez]
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。