Nintendo Switch版発売記念、言語解読ゲーム『7 Days to End with You』開発者インタビュー。独自性の鍵は「理解の余白」(ネタバレなし)
PLAYISMは本日1月26日、『7 Days to End with You』のNintendo Switch版を発売した。同作の発売を記念して、開発者であるLizardry氏にインタビューを実施。PLAYISMの担当プロデューサーである村林小百合氏が聞き手を担当した。

弊社アクティブゲーミングメディアのパブリッシャーPLAYISMは本日1月26日、『7 Days to End with You』のNintendo Switch版を発売した。『7 Days to End with You』は言語解読アドベンチャーだ。プレイヤーは記憶喪失の主人公として、目の前の赤い髪の人物と交流。しかしこの人物とはまったく言葉が通じない。言葉を理解しながら、この人物と7日間を過ごす。
『7 Days to End with You』は、PC(Steam)/スマホ向けにリリースされ高い評価を獲得。「日本ゲーム大賞2022」のゲームデザイナーズ大賞で2位になるほど評価された。Nintendo Switch版においては、追加要素が搭載。新エンディングも導入される。ちなみに、Steam版もNintendo Switch版を逆輸入してアップデートされた。そんな同作の発売を記念して、開発者であるLizardry氏にインタビューを実施。PLAYISMの担当プロデューサーである村林小百合氏が聞き手を担当した。
ゲームは1週間30分。「ゲームしたい欲」と戦った幼少期
──本日はよろしくお願いします。幼少期は、ゲームは1週間で30分と聞きました。厳しい家だったのでしょうか。
全般的には厳しい親ではなかったのですが、テレビゲームに関しては厳しかったです。小学生の時は週1回30分だけ遊ぶことを許されていました。それ以外の機会ですと、友達の家でやるのだけはOKだったので、よくパーティゲームなどをみんなでやっていました。でもテレビゲームがしたすぎて、兄と一緒に自作のボードゲームを作ったりしていました。“自分が好きなゲームのモチーフのゲーム”を作って、テレビゲームがしたい欲求を紛らわせていました。
私の両親はゲーム以外についてはあまり厳しくなく、いろいろなエンタメに触れさせてもらったと思います。特にボードゲームは容認派でした。当時、ドイツのボードゲームを家族が海外から購入してプレイしたりもしていました。一番やったのは「CATAN」です。今ではすっかり有名どころですよね。ゲームのバランスや、リプレイ性が高いのでやりまくっていました。
ただ、自分はあくまでテレビゲームをしたい人間でした。中学に入るとテレビゲームをしても厳しく言われなくなったので、ハマりまくりました。小学校の時に制限されていた反動か、寝る時間もお風呂の時間も惜しんで一日中ゲームをしてましたね。高校に入るくらいまではオンラインゲームが全盛期で、『マビノギ』をずっとやっていました。
オンラインゲーム以外も勿論やりこみました。家庭用ゲーム機では、ゲームキューブ、NINTENDO 64、Wii、PS2、等で中古のゲームをよくプレイしましたね。当時はお金がなかったので、新作は高くて買えなかったので、中古屋で100円くらいのゲームを買って、面白いのから面白くないのまで、やりまくりました。
──たくさんゲームをされてたんですね。その中でも一番好きなのはどのゲームですか?
『ファイナルファンタジータクティクス』が、ゲームデザインや細かいところの遊びと、奥深さ、ストーリー、メッセージ性を含めて一番好きです。今でさえ、自分はいつかこんなゲームを作れるようになる日が想像できない、と思うくらい完璧だと思います。シミュレーションRPGとして完成されていると思います。サブコンテンツが多くて、熱量が感じられるところもいいですね。当時は夢中でプレイしていただけですが、いま触ってみても本当にそう思います。
本当にいろんなゲームやりましたね。『スマブラ』とか、それこそ最近新作がアナウンスされた『アーマードコア』とか。他にも、名前を言ってもわからないようなマニアックなゲームも大好きでした。
──いわゆるインディーゲームもやられていましたか。
いわゆるインディーゲーム系作品との出会いは小学校のときでした。「1週間30分以内」というルールの中でPCのフリーゲームもやっていました。ボリュームが少なかったりしたので丁度良かったんですよね。『ゆめにっき』『洞窟物語』とか。その時に「RPGツクール」「WOLF RPGエディター」も知りました。中学校ぐらいからでしょうかね。「WOLF RPGエディター」でちょこちょこゲーム制作に挑戦してみたりもしました。結局一度も完成せず、作るのって大変だなと思ったりしていました。
そしてインディーゲーム開発者に。一作目は制作期間3日間、半年で6個完成
──高校生以降はどのようなキャリアを歩みましたか。
高校生くらいから、ゲームちゃんと作ってみたいと思うようになっていました。ただ、技術も知識もないので「僕の考えた最強のゲーム」のアイデアのストックをためる日々でしたね。『7 Days to End with You』のアイデアも、高校と大学で過ごして生まれたアイデアの一つでした。
社会人になってから、1度転職してソーシャルゲームの会社に、プランナーとして入りました。ビジネス的にも成功している会社の中で、もっとも大きいタイトルの責任者をやっていましたね。いろいろ四苦八苦しましたが、「1ダウンロード」の重さを知りました。1ダウンロードは重くて、広告をして数字とにらめっこするのが特に大変でした。1ダウンロードはいくらかかるかの研究を毎日やっていて、1ダウンロードの重みを強く意識していました。
ちなみに、同じ会社にだらねこさん(※)がいて、自分が仕様や体験を決めて、数字の動きは数字をいじるボスであるだらねこさんがすべてやっていました。
※だらねこ……『いのちのつかいかた』を現在開発中の個人開発者。奇しくも、『7 Days to End with You』も『いのちのつかいかた』も、私村林がタイトル担当をしている。
──そこからどのようにインディーゲーム開発者になったんでしょうか。
諸事情でゲーム会社を辞めてから、片手間に趣味でゲームを作っていました。そんな中、1週間で作った自分の2作品目の『もはやガチャだけでいい』が、プレスリリース配信以外なにもしなかったのに広告収入で100円入ったので、額こそ小さいものの、活路を見出しこれはいけると思いました。
そこからゲーム開発に専念できるように身辺を整理し、いろいろと作っていくようになりました。実は、『7 Days to End with You』の前に半年で6個ゲームを作っています。自分の考えたゲームのアイデアストックをどうやってゲームにするのかを練習するために、繰り返しアプリを開発していました。自分はとにかく完成させる事にこだわりました。完璧じゃなくてもいいから、まずは完成を繰り返して、徐々にクオリティをあげていくタイプでした。いつかはゲームで食べていければいいなと思っていたので、最初のゲームは3日間で作ってリリースしました。これは単純にゲームのリリース経験を積むためでした。
宣伝もしてないのでもちろんDLされないし、評価も★1とか2ばかりで散々でした。でも一方で、完成させるたびにノウハウがたまり開発レベルがあがっていったと思います。なので、次は1週間で作る、1か月で作る、3か月で作る、と開発期間も少しずつ長くしながらゲーム制作をしていましたね。広告収入を増やすことを目標として、目標を達成しながら進めていました。
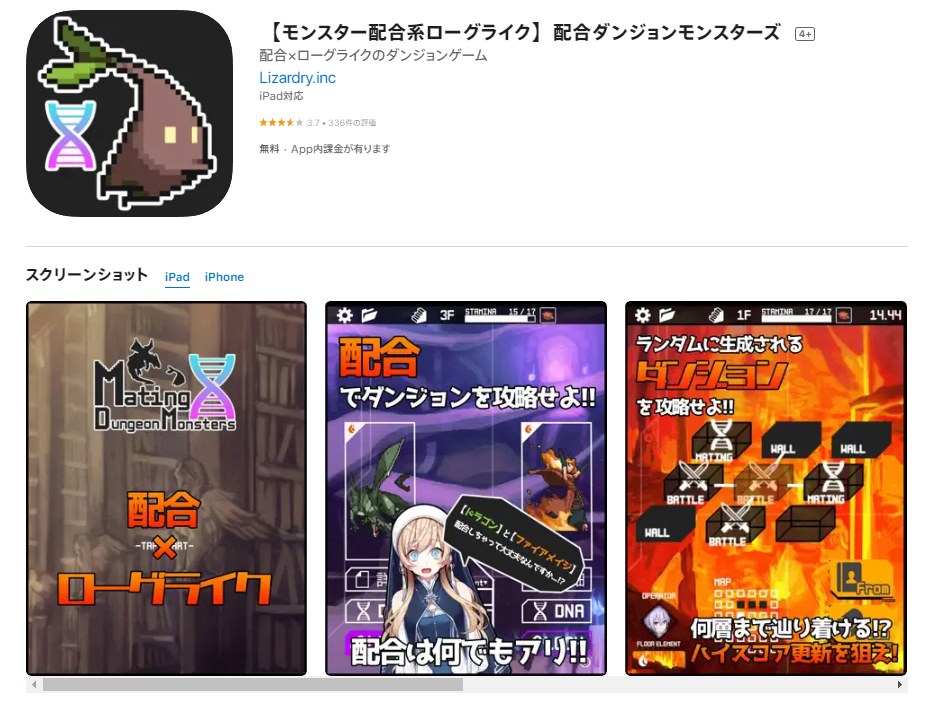
そんな中、1か月で作った『掘るハクスラ』でさらに手応えをつかみました。評価が分かれましたが、ぐっとインストール数が上がったんです。次のゲームでは規模感を上げて、2か月で『配合ダンジョンモンスターズ』を作りました。このゲームまでは広告型のゲームでした。やるからには稼ぎたいし、買い切り型は博打という考えでした。ただ、今までリリースしたゲームを多くのユーザー様に遊んでいただいたおかげで、月にある程度ではありますが、安定してお金が入るようになりました。そのため、博打ではあるけど、挑戦してみたかった買い切り型ゲームとして『7 Days to End with You』を作りました。
きっかけは高校生でのバックパック旅行。15時間労働で3か月で作り上げた『7 Days to End with You』
──『7 Days to End with You』は、完成までどれくらいかかったのでしょうか。
『7 Days to End with You』は着手から完成まで3か月でした。ただし、1日15時間労働でした(笑)もし、会社員をしつつ副業で開発していたなら1年程度はかかったかなと思います。ただ、開発が長期化してくると迷いが生じて、自分の作っているゲームが面白いかどうか悩むようになると思っていました。「本当に面白いのか?当たらなかったら?売れなかったら?」と不安になり、長期化するほど答えがわからなくなります。流行もそうですが、人間の感性は1年で変わると思っていました。そのため、開発期間をぎゅっと詰めてその短期間で頑張って内容を濃くできるように開発しまくりました。
『7 Days to End with You』のアイデアは、高校生の時に生まれました。高校生の時にオートバイで日本一周のバックパック旅行を、分割して長期休みの度にやっていたんです。その時にフェリーの中で出会った海外の人とのコミュニケーションの体験が源泉となっています。

たとえば船旅では、新潟から北海道のフェリーが16時間ぐらいかかったんですよ。その時に海外のお兄さんと仲良くなりました。ただ、密閉された空間なのでコミュニケーションから逃げられない。でも自分は農業高校出身で、英語も苦手意識があり、知っている単語もIとかYouレベルでした。でもそのレベルでも、この人と会話してみたいと思い、何とか意思疎通ができました。フェリーで外国の人と話して、後から気づいたのは「言葉を知ってる」だけが重要なのではなくて、コミュニケーションをとりたい熱量が大事というのが経験としてわかったんです。大人で日本語同士で話しても、会話が通じない人ももちろん出てきます。言語はツールであって、会話は相手へのリスペクトとか、相手のことを知りたいという熱量を持っていると成立するんだと思います。そんな体験ができるゲームがほかでは出なかったので、自分で作ったというところはあります。
『7 Days to End with You』では、相手が自分に熱量を持っていることを伝えることがポイントでした。ゲームの離脱率を考慮して、もうちょっと簡素化してシステマティックに言葉を探して、意味が合ってるかどうかの選択をパズルにすることも考えました。ただ、コミュニケーションの熱量の表現が難しいので、その仕様ではユーザーが離脱してしまうのではと思いました。「この言葉を理解したい」という動機づけをどのようにもってもらえるのかが課題。この人のことをどうやったら理解できるのか、というのをポイントとして作っていきました。
そのため、物語に余白を持たせるためにうまくミスリーディング展開をしたり、理解の余白を産ませる工夫などにも頭をひねらせました。実はゲームに出てくる単語は最初180だったんです。ただいろいろ考えた結果、130に削って理解の余白を出すようにして、プレイ時間を計算しつつ、コンパクトにしようと思って作りました。130の単語であそこまでストーリーを創造できたのは、言葉のパワーだと思います。コミュニケーションにおいては、言葉の苦手意識は実はそれほど重要でなくて、熱量でカバーできるところが重要だと思います。
頭が割れるほど考えた「ルビ入れ」がターニングポイント
──『7 Days to End with You』はかなりオリジナリティの強い作品だと思います。仕様はどのように考えたんでしょうか。参考にしたゲームなどはあったのでしょうか。
知らない言語がでて解読しストーリーを進める、ポイント&クリックでストーリーを進めていくアイデアはもともとありました。詳しい仕様と、ゲームとしての面白さの設計は、3か月で突き詰めて考えました。
影響を受けたゲームは「全部」です。ポイント&クリックの脱出ゲームはもちろんですが、今までプレイしてきたゲームすべてが影響しています。所謂ギャルゲーと言われているような、アドベンチャーゲームもやりこみましたから。ただ、『7 Days to End with You』は、「言語を解読する」というほかにはないゲームシステムが根幹にあったので、基本的な仕様は全部自分で考えました。ただ、「解明した言葉をどう照らし合わせるか」の設計に苦労しました。そのまま置き換えてしまうのも違う。頭が割れるくらいずっと考えて、ひねり出したのが「意味がわかった単語のテキストにルビを入れる」でした。これならゲームとして面白くなると手応えを感じ、買い切り型でリリースしました。

ルビを入れるというのは、面白さのキーだと思っています。プロトタイプの時はルビがなくて、毎日目にするみんなにとって当たり前の「ルビ」にたどりついたのがターニングポイントです。そこまでたどり着くのが大変でした。
──なるほど。ゲームデザイン面の工夫のお話、もっと聞きたいです。ほかに例をいただけますか。
そのほか、特徴的なゲームデザインを考える上でこの作品の場合、物語に余白を持たせるにはどうすればよいか、という事を考えていました。『7 Days to End with You』は、言葉がまったく分からないというインパクトを生み出しています。そのため、あまり注目はされていませんが特徴的なシステムルールがもう一つあります。
それは、すべての文章を3単語以内で区切っているということです。いわゆるアドベンチャーゲームを想像していただきたいのですが……はたして、すべての文章が3単語以内に収まっているものはあるでしょうか。3単語以内で1つの文章を作るシステムだからこそ、余白を広げることが出来るようになりました。この3単語以内というシステムは、本ゲームを作るにあたり言語について勉強した時に考えたものです。
特に、幼児はどのようにして言語を習得するか、未知の言語を習得するときに言語学者はどうするかなど、言語習得のプロセスについて学びました。その点で言うと、一般的なポイント&クリックアドベンチャーにおける、オブジェクトを指して「これはなにか」と尋ねていく方法は、未知の言語を習得するときの手法そのものでしたね。
ただ、このあたりのアイデアは、考えついて1回の制作で完成できたかというとそうではなく、何度もプロトタイプをスクラップアンドビルドしています。新しいゲームを作ろうとしているので、頭の中だけで動かして面白さを確認することがどうしても難しいんですよね。なので、実際に作ってみて、試してみてダメだったら潔く破棄する。作り直す。その繰り返しでした。

何度もいちから作り直してたどり着いた「言語読解のゲーム」
──何度も作り直していたんですね。作り直した要素はほかにどこに何があったのでしょうか。
たとえば、元々は1日ごとに区切るシステムではなく、リアルタイムの時間制限だったり。システム系の文字もすべて架空言語で統一し、現実の文字は一切なかったり。グラフィックも同様で、プロトタイプのアートデザインはもっと寒色系で、暖色系に書き直した後、さらにドットの解像度を上げてすべて描き直したりしています。あのキャラクターも、3~4回は描きなおしてますね。


こんな感じで上げれば数えきれないのですが、無数の可能性の中からすべて再現してみて、実際に手に取って遊び、良いと思った仕様を抽出しています。この作り方は、一人で制作しているからこそ出来るものかもしれません。もしチームで制作していたら。スクラップし過ぎて、メンバーに「このゲームは完成しない」と思われるでしょう。
本ゲームをプレイした後、「言語解読ゲームを作るなら当然こんな感じのシステムになるよね」「すんなり作ったんだろうね」と思うかもしれません。ですが、これらは実はいろいろな可能性を試してみた結果なんです。本ゲームのアイデアの源泉は私が高校生の時の想いでしたから、10年ほど前から存在しています。その間、私の納得できる言語解読ゲームがリリースされたかというと、そうではありませんでした。おそらくですが、「言語解読ゲーム」みたいなアイデアは多くの人が考え付いたと思います。こんなゲームがあったら面白いよね、というのはあったと思います。ですが、リリースはされませんでした。
これは、いかに言語解読というテーマをゲームとして面白さに落とし込むことが難しいかを物語っている筈です。私が本ゲームの制作過程で強く意識し、そして学んだことがあります。それは、アイデアの源泉自体にはあまり価値はなく、それを落とし込む、面白くする、具現化するということにこそ価値があるということでした。
──なるほど。たしかに画期的かどうかと面白いかどうかは全然違いますよね。納得です。リリースについては、どのような気持ちで臨んだのでしょうか。
リリースは、もともと賛否両論でいいからぶつけるという気持ちでやりました。面白くないかもしれないけど新しいゲームだから、と思って。そしたらめちゃめちゃ評価されてとても嬉しかったです。特にプレイしてくれた人の口コミがすごかったです。広告も出してないのに。
このゲームは、ネタバレされると楽しめなくなるので、それを配慮してクチコミを投稿してくれたユーザーの方がほとんどだったと思います。ゲームが流行した時はネタバレ記事や投稿がでやすい印象ですが、本作の場合は真逆で。皆さん、「面白い体験をしたのであなたもしてほしい」としか言わなかった。ユーザーのリテラシーが高く、ネタバレをしない人が多かったのでそれが本当に嬉しかったですね。本作を好きになってくれたユーザーが布教してくれたからこそ、評価されたゲームだと思います。賛否両論ポイントもありますが、批判点についてはテストユーザーからのフィードバックで仕様を思い切って変えたところなので、自分としては納得しています。

──『7 Days to End with You』では、登場人物の性別や年齢、関係性、そして物語はすべてプレイヤー自身の解釈に委ねられます。どのような意図があるのでしょうか。
ゲーム性とマッチしているかどうかを考えたからです。自分が解読した言葉を「違う」「正解ではない」と公式に言われるのはおかしい気がするし、何よりもったいない。だから「正解と言われない方が楽しい」と思ったんです。最近のエンタメの消費の仕方は、結果が先走りしている気がします。映画を倍速で見て、ゲームは実況だけ見て、ネタバレを見ればいいというのは、過程ではなくて結果だけが求められているんじゃないかと思います。でも、エンタメの楽しさは結果ではなくて過程だと思います。単純にゲームをプレイして楽しいとか、敵を倒して気持ちいいとか、このストーリーでこんな感情になったとか、悔しいとか。そういうのが大事だなと。だから正解がなくてもよくて、そこにたどり着くまでの自分の感じたこと、考えたことの「過程」を重視しました。
──Switch版の追加要素についてはどんな仕上がりになっていますか?
PLAYISMさんのおかげで、移植はしっかりできました!追加要素はそんなに大きいものはなく、話がひっくり返ることもないです。ただ、より世界観に浸れるものにして、余韻を楽しむために元々入れたかったものを追加することが出来ました。手に取ってみていただけると嬉しいです。
『7 Days to End with You』は、Nintendo Switch/PC(Steam)/iOS/Android向けに発売中だ。
[聞き手・執筆・編集: Sayuri Murabayashi]
[編集: Ayuo Kawase]
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。



