ゲームの「リメイク」が、時を超える力をもつ理由。名作を風化させないために、私たちができること
リメイク作品には老いと共に臆病になりがちな人間の背中を押してくれる力を持ち、押された先には若い世代をはじめとする新たなプレイヤーが待っている。

過去の名作リメイク。ゲーム業界のトレンドになって久しい言葉だ。インディーゲームをはじめとする小規模な作品と合わせ、開発費用がうなぎ登りにある業界の現状を象徴する概念である。ときには堅実な利益獲得の手段として、ときにはシリーズタイトル復活の踏み台として、今でも重宝されている。同時に「ゲームの保存」という観点でもリメイク作品は役割を果たしている。サービス型の作品や、ハードウェアの機能に依存した作品をはじめ、ゲームの保存が難しいと叫ばれる昨今において、リメイクが果たす役割は大きい。本稿は「ゲームの保存」という観点において、筆者が思うリメイク作品のはたらきについて語るものである。
「ゲームは時を超えない」「ゲームはライブパフォーマンスに似ている」

リメイクの魅力について言及する前に、まず触れなければいけないのは「ゲームは時を超えない」という性質についてだ。そもそもとして筆者は、データを完璧に保存したところでゲームを保存することはできない、と考えている。というのも、ゲームの構成要素には必ず「発売当時を生きているプレイヤー」が含まれており、プレイヤーをゲームと共に保存することはできないからだ。
世に数ある表現のうち、本や絵画、映画、楽曲。これら表現の本質は情報であり、情報は再生媒体が未来に存在する限り、時を超える可能性を持ち続ける。なかでも永遠に再生され、内容の連続性を保ち続けている表現は「古典」と呼ばれる。たとえば、優れた著作は文庫に掲載しようとも、ハードカバーに掲載しようとも、いつ読んでも作品の趣旨となる作者の意図は変わらない。本や絵画には既に作者の意図が備わっており、そこから出力された意図を鑑賞者が受け取り、解釈することで体験が成立するからだ。作品からは常に意図が出力され続けており、それを読み取るだけでよい。
一方でゲームの場合は、人間が遊ばない限り、制作者が作品に込めた意図が出力すらされない。よって、理想的な意図の出力が成立するよう、プレイに使用するハードウェアをはじめ、誰がいつどこで遊ぶのかを想定してデザインされる。発売日周辺におけるターゲット層のライフスタイルを想定して生まれてくる。家庭用ゲームであれば、モニター機器をはじめ、一般家庭が持つハードウェアや家の間取りといった空間構造を意識した設計が成される。若年層向けのゲームであれば、若い身体能力を通じた入力速度を活かすだけでなく、一日の可処分時間を意識した設計が成される。

これは言い換えると、作品が想定するプレイヤーのライフスタイルから自分がズレてしまった場合、作品を十分楽しめないことを意味する。作者にとって、理想的な意図の出力ができなくなるからだ。そして「ライフスタイルのズレ」は必ず起こる。老いによる身体機能の劣化、家庭環境の変化に伴う可処分時間の変化。生活必需品の刷新を通じた、インターフェース入力への慣れ/不慣れ。発売時と現在の世相の違いも含まれる。ゲームは「人間が遊ぶことによって完成される」という都合上、内容の面白さを保ち続けることができない。巷によく言われる「作品がつまらない、のではなく自分がつまらなくなっただけ」という状態は生きていれば遠からず起きてしまうものである。
要するに、ゲームの構成要素には必ず「発売時に生きている人間」が含まれており、人間は発売時のまま時間を超えられないため、ゲームもまた時間を超えることはない。そして、リメイクはこの性質を解決しない。リメイクすること……新しい発売日に生きている人間を想定して内容をチューンナップすることは、構成要素の改変であって、そうして生まれたゲームは、名を借りた別作品である。プレイしたところで、オリジナル版が発売された当時の感覚を味わうことはできず、今の状態を通じた感覚を味わうことになる。
逆に改変を抑えると、どうしてもプレイ中に当時からのズレを通じた苦痛がまとわりついてくる。こうした、ゲームが持つ構成要素が変化する性質は、舞台演劇や音楽のような、ライブパフォーマンスによる表現が持つ性質と似ている。発売時に生きていたあなたにしか味わえない感動がある。よって、リメイクを通じて名作が蘇ることはない。それは別作品なのだから。ではいったい、「ゲームの保存」という観点において、リメイク作品が持つはたらきとは何か。それは世代間コミュニケーションを通じた、ミームの継承によるゲームの保存である。
筆者が思うリメイク作品の意義と、理想的なリメイクの在り方
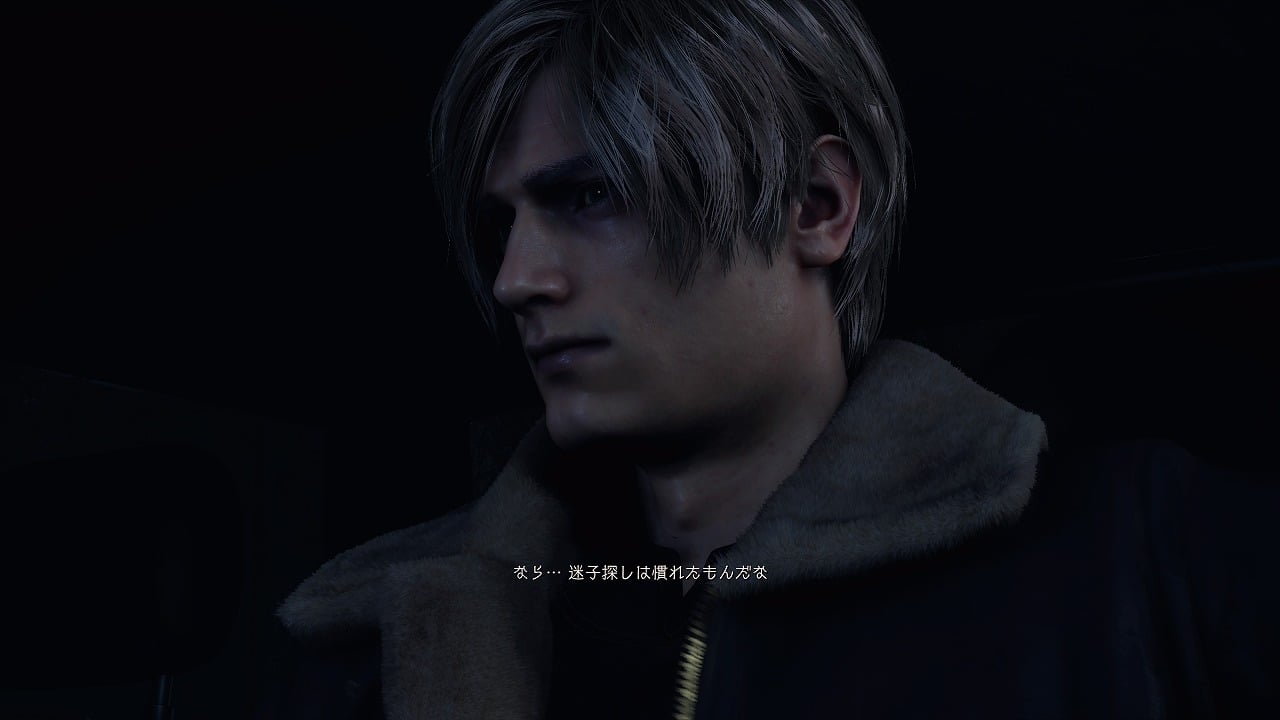
先述したように、リメイク作品そのものは「ゲームを保存」しない。しかし、優れたリメイクは人の心を動かし、感想の伝達という形で、時を超え、ゲームの存在を保存する。リメイク作品を遊ぶと、現在のライフスタイルが当時の要素と反発を起こし、精神的な苦痛がもたらされる。もしくはリメイク版における変更点を、今のライフスタイルを尊重してくれる心地よいものとして感じる。これらの感覚を通して、プレイヤーはオリジナル版をプレイしていた当時の自分と、今の自分を比較することになる。時を経て何ができるようになり、何ができなくなったのか。何を好きになり、何を嫌いになったのか。入力体験を経て否が応でも、直感的に、客観的に理解させられる「作品や自身の不可逆な変化」をプレイヤーは可笑しがる。
同時に、オリジナル版をプレイしていた自分を、紛れもない自分自身の姿であったと肯定する。その延長線上に自分がいるのだと受け止める。客観的にそれは生きていく上で「無駄」な時間であったにもかかわらずだ。夢中になって低確率ドロップアイテムを狙っていた時間。スコアアタックに熱中していた時間。何周も同じストーリーを遊んでいた時間。
ゲームをプレイしている時間は基本的に生存の無駄である。社会を生きて死ぬ上でゲームをプレイする必要はない。しかし、心身ともにあの頃から変化したものの、あいも変わらずゲームプレイという「無駄」な時間をあえて過ごし、生存という規範にとらわれず感情を震わせている。無駄とは余裕であり、余裕とは豊かさである。ゲームを遊んでいる私の人生は豊かである。この事実だけは当時から変わらないことを、リメイク作品は教えてくれるのだ。これは単純な懐古とは少し違う。意識を過去に向け哀愁を覚えるのではなく、未来への希望を与えくれるものだ。あいも変わらず無駄な時間を楽しめているのであれば、もしくは無駄な時間を楽しめるようになったのであれば、きっと未来でも、規範にとらわれずにゲームを楽しめるはず。過去の自分が今の自分の背中を押してくれるような感覚である。
そして、背中を押された先にはSNSのファンコミュニティや、ストアページのレビュー欄がある。未来を想うプレイヤーたちの語らいは、その作品の存在証明となり、新たなプレイヤーの呼び水となる。リメイクが発売され続ける限り、その作品が風化してしまうことはない。ゆえに、理想的なリメイク作品とは先ず「プレイヤーの老い」を肯定してくれる作品であると言える。端的に言えば、発売時点におけるターゲット層のライフスタイルに合わせるのみならず、オリジナル版の再現にこだわることなく、オリジナル版の魅力にアクセスしやすくした作品であるということだ。
これはシンプルに、内容を易化することを意味してはいない。老いたプレイヤーがリメイク版を遊んでも当時の攻略法が通用するというだけでなく、新たに参入してくるプレイヤーと同じ目線に立って作品の感想を語り合えるよう、老いても自信をつけさせてくれるゲームである。優れたリメイク作品は世代間コミュニケーションを育み、やがてゲームは人がもたらす交流に乗って、ミームとなり時を超えていく。

世代間の交流を実現している近年の作品としては、『バイオハザード RE:2』『バイオハザード RE:4 』『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』『ファイナルファンタジーVII リバース』『スーパーマリオRPG』『SILENT HILL 2』といった例が挙げられるだろう。いずれの作品も、オリジナル版の評価点を維持するだけでなく、操作性の改善や難易度の調整、必要ならストーリーの改変など、評価点にアクセスしやすくする配慮を用意することにより、達成感を通じてプレイヤーの老いと過去を肯定し、思わず他者へ攻略や感想、思い出話を語りたくなるくらい、自己肯定感を生み出してくれる。
筆者の経験としては、かつてやり込んだリメイクをプレイすることで新作に思いを馳せたり、オリジナル版未プレイのリメイクを遊ぶことで、目上の人とコミュニケーションが可能になったこともある。ストリーマーがリメイクをプレイしながら、オリジナル版の思い出話をする場面に遭遇したときは、なんだか自分もゲームを遊びたくなってくる。
リメイク作品が続々と登場している昨今。この動きを業界の停滞と捉える人もいるが、決してそうではない。リメイク作品には老いと共に臆病になりがちな人間の背中を押してくれる力を持ち、押された先には若い世代をはじめとする新たなプレイヤーが待っている。彼らとの交流は、ゲームに時を超える力を与えてくれる。作品を遊んだ際は、ぜひ感想を発表することをオススメしたい。ゲームが文化としてより広く、末永く親しまれるために、リメイクが果たす役割は非常に大きい。
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。



