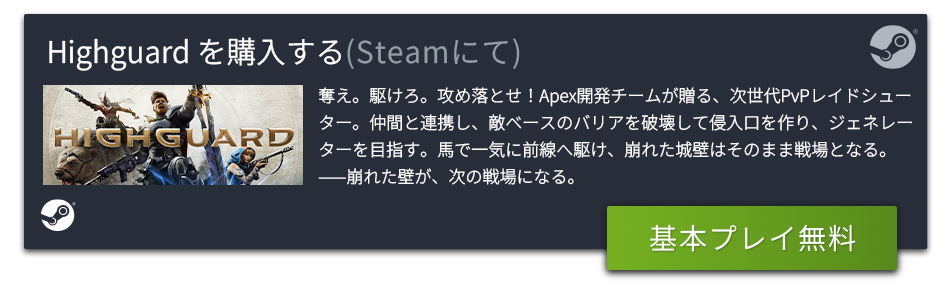Steam・97%好評潜在意識推理ゲーム『マインドダイバー』のルーツが面白い。『Obra Dinn』『Her Story』『Golden Idol』そして「ソラニン」から影響を受け作られた記憶体験
Indoor Sunglasses所属の『マインドダイバー』ディレクタービクター・セルネース・ブレウム氏に向けてメールインタビューを実施する機会に恵まれたので、その内容をお届けしたい。

『マインドダイバー』は9月28日にリリースされた、デンマークのデベロッパー「Indoor Sunglasses」が手がけ、弊社アクティブゲーミングメディアが運営するPLAYISMがパブリッシングを行うタイトル。プレイヤーは他者の記憶の中に入る「マインドダイバー」として、リナという女性の意識の海に飛び込み、欠落した記憶を修復しながら真実に迫っていくミステリーアドベンチャーだ。
Steamのユーザーレビューでは、記事執筆時点で162件のすべてのレビュー中、97%の好評を獲得し、「非常に好評」のステータスを獲得。『The Case of the Golden Idol』、『Her Story』、『Return of the Obra Dinn』などから影響を受けたと話す、断片的な情報を繋ぎ合わせていくシステムなどが好評を呼んでいるようだ。この度はIndoor Sunglasses所属の『マインドダイバー』ディレクタービクター・セルネース・ブレウム氏に向けてメールインタビューを実施する機会に恵まれたので、その内容をお届けしたい。
最初のアイデアからリリースまで4年半かかった
――自己紹介をお願いします。
ビクター・セルネース・ブレウム(以下、ビクター)氏:
こんにちは!私はビクター・セルネース・ブレウム、『マインドダイバー』のディレクターであり、Indoor Sunglassesの共同創設者です。
――『マインドダイバー』は、Steamにて「非常に好評」と大変評価が高いです。この評価はどう受け止められていますか?
ビクター氏:
非常に誇りに思っています。プレイヤーの意見こそが常にもっとも大切だと考えているので、多くのプレイヤーからポジティブな感想や体験談をいただけることは、ゲームで達成できる最高のことだと思います。私たちが作ろうとした体験が、プレイヤーにしっかり伝わり、バグやストレスで台無しにならなかったことに、本当に安堵しています。
――『マインドダイバー』の制作経緯と、開発期間について教えてください。
ビクター氏:
『マインドダイバー』はデンマーク国立映画学校の卒業制作として始まりました。当初のアイデアは、『Outer Wilds』のような探索型のゲームを人間の心の中で作ることでしたが、次第に探索よりもストーリー重視の方向へと変化しました。最初に「学生版」としてリリースした際には、IGFの賞にノミネートされました。
その後、ゲームを完成させるために会社を立ち上げ、ゲーム内のほぼすべてを作り直しました。それから完成までに3年かかりました。資金が何度も尽きてしまい、他社の仕事を請け負って小規模な作業を行いながら開発を続けました。幸運なことに、PLAYISMがゲームのパブリッシュに興味を持ってくれたおかげで、ついにリリースすることができました。振り返ると、『マインドダイバー』の最初のアイデアから発売まで、合計で4年半かかったことになります。
――Indoor Sunglassesはどのようなチームですか?結成のきっかけやメンバー構成を教えてください。
ビクター氏:
私たちはそれぞれ別の学校に通う学生として出会い、個人では作れない大きな学生向けゲームを一緒に作ろうと集まりました。その後、協同の価値観に基づいて会社を設立しました。つまり、戦略的な意思決定だけでなく、関わる全員が平等に報酬を受け取るなど、さまざまなことに全員が関わるという考え方です。
現在、チームは5名で構成されており、『マインドダイバー』の開発経験によって形作られています。私たちは自分の担当タイトルだけでなく、多岐にわたる分野をカバーしています。また、素晴らしいフリーランサーの協力も受けています。音楽作曲の才能ある方、私たちよりも面白いマーケティングコンテンツを作ってくれる方、俳優の方々など、多くの人々が時折手を貸してくれることで、このようなゲームを作ることできました。

――デンマークという土地や気候、社会の空気が『マインドダイバー』の世界観に影響した部分はありますか?
ビクター氏:
そうです!『マインドダイバー』の世界は基本的に現代のデンマークですが、そこにひとつだけSF的な技術を加えています。コペンハーゲンの街並みに自然に溶け込むような、SFと犯罪を組み合わせたプロットを作ろうとしました。未来的な技術はヨーロッパの資金で開発されており、カルト教団の規模も、例えばアメリカを舞台にしたプロットよりは小さめです。
登場人物の関係性や日常の過ごし方には、デンマーク独特の影響が多分に入っていると思いますが、自分では意識していない部分もあります。ただ、自然に感じられる形で表現しました。また、コペンハーゲンに実際にある場所もいくつか登場させています。街の中心にある湖や国会議事堂前の広場、そして遊園地のバッケンなど、物語の舞台をリアルな場所に根ざしたものにするよう心がけました。
――デンマークのインディーゲームシーンは、どのような特徴や雰囲気がありますか?
ビクター氏:
規模としてはやや小さく、すぐにシーンの人たち全員を知っているような感覚になります。ただ、その中でも非常に多様なゲームが生まれており、クオリティの高い作品も多いです。最近では、私たちの友人が『As Long As You’re Here』という認知症をテーマにした美しいゲームをリリースしたり、別の友人はスーパーマーケットライフシム『Discounty』をリリースし、かなりのヒット作となりました。
全体的に職人技のレベルが非常に高いと思います。また、公共の文化助成金があるおかげで、通常では挑戦できないような芸術的なリスクを取れるスタジオがあるのも素晴らしい点です。実際、『マインドダイバー』もその公共資金がなければ存在しなかったでしょう。

推理パズルの名作からインスピレーションを受けた
――本作の「マインドダイビング」という設定の発想はどこから生まれたのでしょうか?
ビクター氏:
私は過去の失恋について多く考え、うまくいかなかった関係で何が間違っていたのかを理解しようとしていました。同時に、『Outer Wilds』や『Return of the Obra Dinn』のような現代の探偵ゲームに夢中になっていました。すると、失敗した恋愛の出来事を思い出としてつなぎ合わせようとする経験が、素晴らしいミステリーゲームになるのではないかと感じたのです。
――ストーリーで特に重視したテーマやメッセージがあれば教えてください。
ビクター氏:
私たちと「過去」との向き合い方こそが、本作の中心テーマです。過去から逃げ続けることと、逆に過去に囚われて動けなくなること、そのちょうどよいバランスをどう見つけるのか。主人公のリナとセバスチャンは、そのジレンマの両極を体現しています。これは私自身ずっと強く意識してきた問題でもあります。セラピーを受けていた時期には、このバランスを見つけることが大きな課題になっていました。
そして、このジレンマは社会全体の政治にまで広がっていると感じます。私たちは過去のどんなものを持ち続けると選び、どんなものを燃やして忘れることを選ぶのか――その問いが常に付きまとっています。

――「意識の海」を泳ぐという体験はとても新鮮でした。ゲームとして落とし込むうえで苦労した点はありますか?
ビクター氏:
「心の中の世界」という抽象的なコンセプトを形にすることが、ここまで難しいとは正直想像していませんでした。強く参考にできる作品もほとんどなかったため、すべてを一から想像して作り上げる必要がありました。そのため、試行錯誤がとても多く、常に明確な方向性があるわけでもなかったんです。
『Psychonauts 2』のドキュメンタリーでも同じように“精神世界”を構築する過程が描かれていて、抽象的な概念をどのように明確にするかで大きな課題にぶつかっていました。それを見て、「経験豊富なDouble Fineでも同じ問題があるんだ」とわかり、とても安心したのを覚えています。
――3Dスキャンを活用したアートスタイルが印象的ですが、このスタイルを採用した理由や狙いを教えてください。
ビクター氏:
私たちは「色あせた記憶を思い出す感覚」を視覚的に表現しようとしていました。そんな中で荒いフォトグラメトリーのスキャンに出会い、これはまさに理想的だとすぐに感じたんです。スキャンは現実世界を元にしていることが見てわかる一方で、それらは不完全で、欠けていて、色褪せている――まさに“記憶”そのもののようでした。

――「エコー」を調査するというシステムの発想は、どこからインスピレーションを得たのですか?
ビクター氏:
『Return of the Obra Dinn』からは、凍結されたシーンや音声トラックといったアイデアを取り入れました。ただ、私たちのシーンはより長くなる傾向があったため、音声を一つの大きな塊として流すと退屈になってしまうと感じたんです。そこで、音声トラックを小さなサウンドバイトに分割し、プレイヤーがそれらを見つけてアンロックしていく仕組みにしました。
また、集めたサウンドバイトを整理・再生するためのツールも必要になり、この部分は何度も作り変えることになりました。実は、初期バージョンのひとつに「花」のようなデザインがあって、私は今でも結構気に入っているんです。でも、ゲームの体験としては少し目立ちすぎたため、最終的にはよりクラシックなデザインに落ち着きました。
――記憶の穴を埋めていく謎解きの難易度が「少し悩めば解ける」程度に絶妙だと感じました。プレイヤーへの誘導や手がかり配置で、特に意識した部分はありますか?
ビクター氏:
私たちはパズルが物語へ自然と注意を引きつけるようにすることに注力しました。つまり、「取ってつけたような謎」や「物語と関係のないギミック」にならないようにしたのです。どのパズルも、プレイヤーがストーリーやキャラクターについて新たな理解を得られるよう設計しています。また、すべてのパズルが論理的で、答えが一つに定まるようにすることにも力を入れました。そのために行ったことのほとんどは、徹底的なプレイテストです!
――ゲーム中に『The Case of the Golden Idol』、『Her Story』、『Return of the Obra Dinn』が飾られていましたが、これらのタイトルは本作にどんな影響を与えましたか?
ビクター氏:
すでに『Return of the Obra Dinn』について触れましたが、本作にとってまさに最大のインスピレーション源です。静止したシーンと推理パズルというコンセプトは、まさにそこから来ています。『Her Story』からは、物語の現実味、実写俳優の使い方、そして新たな情報にたどり着く「突破」の感覚に強く魅了されました。『The Case of the Golden Idol』は開発の後期にリリースされましたが、パズルデザインや世界観づくりが非常に優れていて、多くの刺激を受けました。
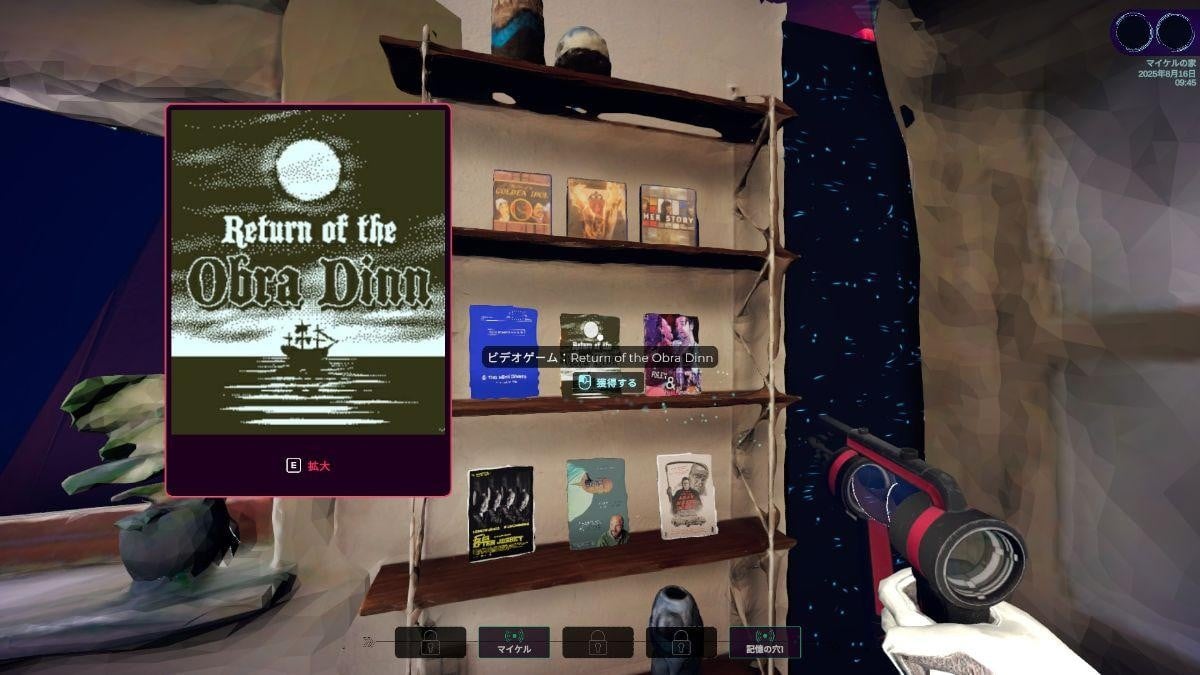
――そのほかにもIndoor Sunglassesのルーツになっている創作物(ゲーム・映画・漫画・小説など)があれば教えてください。
ビクター氏:
たくさんあります。浅野いにおさんの作品――特に「ソラニン」や「おやすみプンプン」からは大きな影響を受けました。彼の胸を締めつけるような物語運びや、実写写真を取り入れた表現には本当に魅了されています。浅野さんが使う「切りつけてくる日常(slice-of-life that slices back)」という表現は、まさに彼の作風を的確に言い表していると思います。
映画「エターナル・サンシャイン」は、物語におけるもっとも直接的なインスピレーション源でした。同じような自然体の恋愛描写を持つゲームを作りたいと強く思っていましたし、もちろん「記憶」というテーマも本作と共通しています。
最後に挙げたいのが、小説「アレクサンドリア四重奏」です。愛と政治を描いた非常に重層的な物語で、一つの物語が読み進めるうちに少しずつ多面的に見えてくる構造が本当に見事です。『マインドダイバー』がその語りの質に並ぶとは思いませんが、いつかそこに届きたいという気持ちで制作しています。
――新作タイトルなど今後はどのような作品を作ろうと考えていますか。
ビクター氏:
私たちはすでに新しいプロジェクトに着手していますが、まだ非常に初期段階のため、具体的なことをお話しするのは難しい状況です。ただ、多くの人と同じように、私自身も世界の環境・政治・経済の状況に強い懸念を抱いています。次に作るゲームは、そういったテーマ――特に「労働・資本・自然」のせめぎ合いについて扱うつもりです。
ゲームとしては『マインドダイバー』よりもシステムドリブンになる可能性が高いですが、それでも人間らしさを中心に据え、ミステリー要素によってプレイヤーの好奇心を刺激する作品になるでしょう。そして、きっとまた超現実的(シュール)なものになると思います!
――最後に読者に向けて一言お願いします。
ビクター氏:
『マインドダイバー』の中に、あなた自身の人生や人間関係のかけらを見つけてもらえたら嬉しいです。プレイ前よりも何かを持ち帰ってもらえるような、そんな作品であればと願っています。そして、これからも好奇心を持ち続けてください。読んでいただき、そしてプレイしていただき、本当にありがとうございました!
『マインドダイバー』は、PC(Steam)向けに発売中だ。
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。