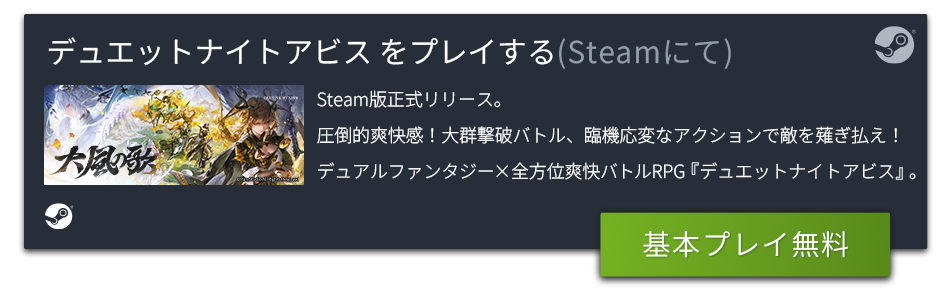『ソニックレーシング クロスワールド』はセガの「秘伝のタレ」がゲームデザインに注ぎ込まれたゲームだった。『セガラリー』から『頭文字DAC』まで、受け継がれる血脈
『ソニックレーシング クロスワールド』の開発者に、アーケードゲームから本作に受け継がれた歴史についてうかがった。

セガは9月25日、『ソニックレーシング クロスワールド』を発売した。対応プラットフォームは、PC(Steam/Epic Gamesストア)およびPS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch。プラットフォーム間のクロスプレイにも対応する。またNintendo Switch 2ダウンロード版・アップグレードパスが今年冬販売開始予定となっている。
本作は、「ソニック」のキャラクターたちによるレースゲームシリーズの最新作だ。過去作を主に手がけてきたSumo Digitalではなく、セガのソニックチームと、アーケードゲーム『頭文字D』シリーズや音楽ゲームを手がけたアーケードチームが手がけるという。
弊誌はこのたび、本作のクリエイティブディレクターを務める小早川賢氏と、アーケードゲーム『頭文字D』シリーズのプロデューサーであった新井健二氏にインタビューを実施。一見するとカジュアルなパーティーゲームのような本作が、『頭文字D』というコアなアーケードレースゲームからどんな影響を受けて変化を遂げたのか。セガの歴史とともに紐解いていく。
コロナ禍をきっかけに『ソニックレーシング』の内製化へ
――自己紹介の方よろしくお願いいたします。
小早川賢(以下、小早川)氏:
セガの第2事業部で『ソニックレーシング クロスワールド』のクリエイティブディレクターをしている小早川と申します。第2事業部は『ソニック』やアーケードゲームを制作している部署でして、私はアーケードゲームの部門も担当しています。10年以上、「コハD」として音ゲーを作ってきまして、新井さんと一緒に制作に携わったこともあります。
新井健二(以下、新井)氏:
新井と申します。私は2002年から2025年3月末まで『頭文字D』シリーズのプロデューサーを担当していました。第2事業部で小早川が中心となって制作していた音ゲー開発のお手伝いもしていましたね。今はコンテンツ・プロデュース室におりまして、海外のデベロッパーさんと共同で、タイトルの立ち上げなどを模索しています。本日はよろしくお願いいたします。
――新井さんは『ソニックレーシング クロスワールド』についてはどのように関与されてるのでしょう。
新井氏:
レースゲームということで、『頭文字D THE ARCADE(以下、頭文字DAC)』のチームが『ソニックレーシング クロスワールド』に携わることになり、立ち上げのときに関わっていました。あとはプロデュースワークの端っこをちょっとお手伝いしたりもしていました。
――新井さんのドライブゲーム制作のキャリアについて、もう少しご紹介いただけますか。
新井氏:
元々は1991年にグラフィックデザイナーとしてセガに入社しまして、子どもの頃から車やバイクが大好きだったので、入社してからずっと上司にレースゲームを作りたいとアピールし続けていたんですね。
それが叶って、1994年にリリースされたアーケードゲーム『セガラリーチャンピオンシップ』(以下、セガラリー)で、コースデザインやUIを担当し、初めてレースゲームに関わらせていただきました。その後も、『セガツーリングカーチャンピオンシップ』や『セガラリー2』などで、デザイナーやアシスタントプロデューサーとして、レースゲーム制作にずっと関わってました。
転機が訪れたのが1999年、アメリカのレースNASCARを題材にした『NASCAR ARCADE』というレースゲームで、初めてプロデューサーを担当しました。その後2002年に『頭文字D ARCADE STAGE』をプロデューサーとして立ち上げ、それからはほぼずっと『頭文字D』シリーズを担当してきました。最近までほとんどレースゲーム専門屋みたいな状況でしたね。
――これまでの『ソニック』のレースゲームは Sumo Digitalさんが開発することが多かったと認識しているのですが、なぜ今回は『頭文字DAC』チームが合流することになったのでしょうか?
小早川氏:
経緯としては、2020年頃のコロナ禍の時期に、全社を挙げてアーケードゲームだけでなく、コンソールゲームにもリソースを傾けましょうという方針が打ち出されました。その際、当時セガ・インタラクティブという別の会社であった我々アーケードチームと、セガゲームスというコンソールゲームの会社が合併して、ソニックチームとして同じ事業部に所属することになりました。これが一つのきっかけです。
また、これまで外部の Sumo Digital さんが手掛けていたレースゲームのラインを内製化することになりました。たとえば今回のマルチプラットフォームで一緒に遊べるクロスプレイのような、高度なゲーム制作をするためにはネットワークのノウハウも必要で、そういった事情もあって、4~5年前に『頭文字DAC』チームが指名されて、ソニックチームと一緒に本企画を立ち上げた、という経緯となります。

『頭文字D THE ARCADE』のようにコーナーの正解ラインは1つではない
――『頭文字D』チームは、どのようなゲームを作ってきたのでしょう。
新井氏:
『頭文字D ARCADE STAGE』が登場するまでのレースゲームは、たとえば20位からスタートしてA地点からB地点まで走りながら他の車を抜いて1位を目指す、といったゲームが主流でした。他の車はあくまで障害物みたいなゲームだったんですね。それが『頭文字D ARCADE STAGE』では、初めて1対1のバトルになりました。
バトルにフォーカスしたことで、コンピューター対戦だけでなく、プレイヤー同士が1対1で遊んで、勝った、負けた、嬉しい、悔しい、という感情を繰り返し楽しんでいただくゲームになったんですね。バトルを楽しんでもらうことが目的なんです。この目的を達成する手段として、バトルをしやすい運転性能や走行性能にこだわりました。当時、他のレースゲームの中には、真っすぐ走るだけで精一杯で、プレイヤー同士で競うなんてとんでもない、というものもたくさんあったんですね。
我々としてはまず簡単に、しかし簡単すぎずに、自分の運転スキルが上達するのを感じられる難易度の運転性能や走行性能を調整しました。プレイヤーがバトルに集中して楽しめるようなゲームということを念頭においてずっと開発を続けてきましたね。
――当時のレースゲームが順位を上げていくスタイルだったのに対し、『頭文字D ARCADE STAGE』は対戦を重視したゲームだったんですね。その後、対戦することが当たり前になっていく中で、『頭文字D ARCADE STAGE』チームは、時代の変化に合わせてどのような特色を出していったのでしょうか?
新井氏:
アーケードゲーム『頭文字D』シリーズが登場した2002年頃は、車を買うことや運転することがまだまだ憧れだった時代でした。なので、我々が作っていた運転性能も、本物の車にかなり寄せていったんです。しかし時代を経ていくと、車は運転を楽しむよりも、移動手段の1つであったり、家族や友人と過ごすための道具として扱われるようになってきましたよね。
そこで、車らしさよりも友達と遊ぶことに焦点を移して、車の運転性能をどんどんシンプルにしていきました。ただし、シンプルで簡単すぎるとカジュアルっぽいゲームのようになってしまったり、上手くなる楽しさがなくなってしまいお客様が離れてしまう。このちょうどいい塩梅を狙って収束した結果、最新作『頭文字DAC』に繋がっている感じですね。
小早川氏:
『頭文字DAC』の初期は、『セガラリー』に似た遊びやすい挙動からスタートしましたよね。しかし、シリーズで言うと3、4、5あたりは本物の車に寄せたことで、かなり難易度が高くなった記憶があります。
新井氏:
そうです。アーケードゲーム『頭文字D』シリーズはこれまでに10作品作っていますが、小早川が言ったように、3、4、5と難しくなっていきました。5が難しさの頂点にあったんじゃないかと思います。
小早川氏:
5が一番難しかったですね。ただしアーケードゲームとしては、やはり初めて触ってもすぐに遊べることが非常に重要です。難しさを突き詰めていくのでは、みんなを楽しませることはできませんよね。シリーズとしては9作目あたりとなる『頭文字DARCADE STAGE Zero』あたりからスタッフ構成も変わっていき、車よりもレースゲームが好きというスタッフも増えていきました。もちろん、新井さん含めて車好きなスタッフもいる混在したチームになっているので、車らしさと遊びやすさを両立した挙動になっていったと思います。
そして、今回の『ソニックレーシング クロスワールド』に至るところで、この『頭文字DAC』チームの走りやすさというDNAがそこに結び付いたのではないかと思います。本作は『頭文字DAC』同様に、遊びやすい挙動を持ちながらも、複雑な要素を細かく積み重ねることで、同じ走行ラインでもいろんなテクニックを駆使できるように設計されています。こういった走やすさ、走りの奥深さは『頭文字DAC』から継承されたノウハウなんじゃないかなと思います。

――「いろんなテクニック」について少し具体的に教えていただいてもいいでしょうか
小早川氏:
たとえば競合製品では、最速を目指すためにインコースを詰めれば良かったりします。一方で本作が『頭文字DAC』のDNAを受け継いでいるなと思うのは、アウトコースから入ってインにまくるといった、コーナーでの抜き方などがかなり『頭文字D』ライクなんですよね。さまざまな要素が挙動計算に含まれているので、単純に最短距離を狙えば早いわけではなく、車の挙動を意識しながら、インから差すのか、それともアウトからまくるのかを、プレイヤーが考えて実践できるように設計されています。
また、『頭文字DAC』では「碓氷峠」が分かりやすいんですが、実際のコーナーよりも幅を広く作ったりしていて、原作漫画のようなコーナーでの抜きつ抜かれつの攻防を演出できるような設計にしていたりします。
こうした走行ラインの導き方や、抜き方の構成や駆け引き、コース設計における配慮は、他のレースゲームにはない、アーケードゲーム『頭文字D』シリーズから受け継いだ独自のノウハウだと思います。本作においても敵車を 抜く瞬間は一番気持ちいいところじゃないかと思います。
新井氏:
ただ速い人がバトルに勝つわけではない、という奥深さですよね。「強い人が勝つ」と言いますか。コーナーには一般的に正解のラインがあるんですけど、『ソニックレーシング クロスワールド』には正解が1つではなく複数のラインがあるんです。そういった遊びの幅が広がっているのが、やっぱり『頭文字DAC』らしさが入ってるところじゃないかと。
小早川氏:
タイムアタックでも速いタイムを出すには、非常にいろんな考えが必要な奥深さがあります。これが競合作品と比べて大きく違う点であり、『頭文字DAC』から継承された私たちの強みだと考えています。

ベースになったのは『ソニック』でも『頭文字D』でもない、セガの秘伝のタレが詰まったゲーム
――本作はドリフトの挙動も他のレースゲームとは少し違ってますよね。外からまくることができるという点も含め、他に何か特徴があれば教えていただけますか?
小早川氏:
ドリフトに関しても色々ありまして、アーケードゲーム『頭文字D』シリーズは『セガラリー』からずっと一人のプログラマーの方が走行挙動をコントロールしてきました。今回、その方の弟子が『ソニックレーシング クロスワールド』の挙動プログラムを担当しています。また、その方が今回の走行挙動を作るにあたって、アーケードゲーム『頭文字D』シリーズからではなく、『セガラリー』から設計のベースを持ってきてるんですよ。これ新井さんも知らなかったんじゃないですか?
新井氏:
へえ、なるほどね。
小早川氏:
『セガラリー』をベースにしつつ、その方が参考にしたのが実は『アウトラン』なんです。ドリフトしながら挙動をコントロールするあの気持ち良さは、『アウトラン』を参考にしながら作ったと言っていました。
新井氏:
なるほど、彼はレースゲーム大好きだもんね(笑)
小早川氏:
そうですよね(笑)『アウトラン』自体はAM2研(第2研究開発部)の制作ラインなので、本来は我々のDNAではないんですが、お弟子さんはAM2研から分家した組織にいたこともあり、そういった経緯からDNAが継承されたのかもしれません。なお、分家した組織では『SEGA-RaceTV』というレースゲームなんかも作られていました。
『セガラリー』の挙動をベースに、『アウトラン』を参考にしつつ、Sumo Digitalさんが作ってきた操作感と『頭文字D』のDNAを統合して、今回の挙動を作り上げた。なので、『セガラリー』的であり、『アウトラン』的でもあり、ドリフトの気持ちよさというものをかなり意識して作ってきたのが本作です。ちょっと複雑ですが、そういった背景が実はありました。
新井氏:
今のめちゃめちゃいい話ですね。
小早川氏:
細かくて分かりづらいと思いますけど(笑)
――秘伝のタレみたいなゲームですね。
新井氏:
セガの中の秘伝のタレですよね。アーケードゲーム『頭文字D』だけでなく、『セガラリー』や『アウトラン』といったレジェンド級のゲームの良さがぎゅっと煮詰まってるゲームだと思います。
――秘伝のタレのほかに、これはアーケードゲーム『頭文字D』チームが作ったものだと感じられる要素があれば教えてください。
新井氏:
ゲームセンターでは、100円玉を1枚入れて面白くなければすぐに辞めてしまうのでとっつきやすさが大事です。『ソニックレーシング クロスワールド』も我々が遊んでみてそのとっつきやすさを感じました。そして最初はとっつきやすいのに、バトルをすると奥深さがあり、勝っても負けても納得感がある。運ではなく勝ったときに嬉しい、負けた時に悔しいと感じるところは、『頭文字DAC』から受け継がれた伝統的なものが生きていると思いました。
小早川氏:
車体のカスタマイズ性についてもアーケードゲーム『頭文字D』のDNAを強く引き継いでいるつもりです。本作のカスタマイズ設計を担当したスタッフは、長年『頭文字DAC』など車のゲームに携わっており、車のパーツ設計を担当していました。日本でも彼しか知らないパーツの形状があるくらい、実際に車をいじることが好きな人間なんですよ。
新井氏:
いや本当にね、歩くWikipediaみたいな社員がいるんですよ(笑)ただ知識として知ってるわけでなく、実際に手を動かして実体がともなってるので説得力もあります。車体のカスタマイズのアイデアが出てくるときも机上の空論ではないんですよね。

小早川氏:
そういったメンバーがいるので、『ソニックレーシング クロスワールド』でも車の前後を合体させるシステムを導入しました。『頭文字DAC』をご存じの方なら分かると思いますが、シルビアと180SX(ワンエイティ)の前後を組み合わせてシルエイティを作るようなシステムですね。この前後合体できるシステムも『頭文字DAC』のオマージュが入ってとも言えます。
あと『頭文字DAC』は、アーケードレースゲームの中でもステッカーを貼って痛車を作れるという面白い特徴があります。このステッカーを貼れる機能も本作では導入してるのでアーケードゲーム『頭文字D』シリーズのDNAを感じるところだと思います。ほかに、コース設計のカーブの形状もアーケードゲーム『頭文字D』シリーズをかなり意識して作っていますね。
――本作のカーブは特殊とのことですが、どういうカーブなんですか?
小早川氏:
本当に峠みたいなコースがあるんですよ(笑)
新井氏:
実は、ああいったカーブを作るのはすごく難しいんです。たとえば外に出てその辺にあるカーブも単純に効率的に作られているわけではなく、事故を起こしにくく曲がりやすい、という設計思想がきちんとあるんです。『頭文字DAC』は実際の峠道を参考にして作っているので、今回の『ソニックレーシング クロスワールド』にも現実の設計思想が取り入れられていると思いますね。
小早川氏:
新井さんから補足があったように、気持ちよく曲がれるコースデザインをするのは非常に難しいですが、これまでの経験から実現できたのではないかと思います。

――レースゲームでは、カーブはコースの「形を整えるため」に作られやすい認識です。しかし『ソニックレーシング クロスワールド』では、コーナリング自体にメッセージ性が込められた設計だと。
小早川氏:
その通りです。ここはインを差して抜いてほしい、といったコーナーをかなり意識して設計しています。そういう視点でコースを見ていただけると、また違った面白さを発見できると思います。
――ありがとうございます。ここまで何度も出てきた遊びやすさや気持ちよさ、つまり「手触り感」は、ゲーム業界でよく聞く言葉です。何が手触り感を生み出しているとお考えですか。
新井氏:
「手触り感」は「感」という言葉で表されているように、数値化や言語化が難しいものだと思うんですよね。あえて言語化すると「思った通りに動かせる、ような気がする感覚」でしょうか。実際には練習しないとそんなに思った通りに動かせないのですが、自分の手の中に車があるかのように感じられる。その感覚が手触り感として残ってると思いますね。
小早川氏:
ゲームにおいて楽しいつまらないと感じるのは、成功と失敗を体感する瞬間です。良いゲームとは、もっとこうすれば上手くいく、というプレイ感覚を得られることが最も重要です。しかし、レースゲームのカーブはいろんな曲がり方ができてしまうため、何が一番良かったのか、成功したのかを感じづらいんですよ。
『頭文字DAC』からつながる本作は、一回コーナーを曲がるだけでも、もっとこうすれば上手く曲がれたかなという気持ちにさせる、そんな余地をしっかり残すように設計されています。これは秘伝のタレの一つであり、面白いと感じる挙動になっているのではないかと思います。新井さん、上手くコーナー曲がれている感覚を作るの意外と難しいですよね。
新井氏:
言葉で言うのは簡単なんですけど難しいです。昔は、それができなかったレースゲームが多かったんです。なので、レースゲームは難しいとかつまらないと思われがちで、レースゲームもだいぶ淘汰されてきました。今回の『ソニックレーシング クロスワールド』では、そういった部分を払拭できてるのではないかと思いますね。
小早川氏:
そこは意識して開発しています。

音ゲーのようなイントロやサビがあるコース設計
――ありがとうございます。小早川さんにお聞きしたいのですが、元々『チュウニズム』など音ゲーを作られていたということで、音ゲー作りとレースゲーム作りに共通する部分はありますか。
小早川氏:
『ソニックレーシング クロスワールド』をアーケードゲーム『頭文字D』チームと一緒に制作することになって、音楽ゲームチームがよく使っているエディターというものの導入を行いました。これまでの『頭文字DAC』や、競合製品等もそうだと聞いていますが、レースゲーム制作においてはグラフィックデザイナーがコースを引くのが主流だったんですよね。しかし、本作ではエディターを制作・導入することでプランナー=ゲームデザイナー自身がコースを引ける設計になっています。これは品質の高い音楽ゲームを作るためには必須の制作手法で、そのノウハウを取り入れたわけです。
セガのアーケードチームのゲームデザイナーは、ゲーム自体がめちゃくちゃ上手くて、そのジャンルのゲームを熟知しているのですが、そういったスタッフがコースエディターを使って、ベストなラインを微調整しながらコースを作ることができるようになるんです。『頭文字DAC』が日本一上手いメンバーや、音楽ゲームが日本一上手いメンバー、競合作品が日本で数番目に上手いメンバーもいるので、彼らの深い理解がそのままゲームに反映することができましたと思います。
また、コースエディターを使うことで、ゲームデザイナーがレースゲームのリズムを作れるんですよね。音楽ゲームでは最も重視しているのが、1プレイにおける感情の曲線です。イントロ、Aメロ、Bメロ、サビ、アウトロという盛り上がって終わる構成がしっかりしてると面白くなるんですね。
この設計思想を取り入れることによって、1レースが非常に気持ちいいものになっているんです。この気持ち良さは、感情曲線のコントロールを精密におこなうことで生まれるものであり、音ゲー制作のノウハウをかなり踏襲していると思います。
――レースゲームを曲に例えられるのは面白いですね。それぞれのコースでサビを探すのも面白そうです。
小早川氏:
探せばすぐに感じると思います。これイントロだな、Aメロだなって感じで、最後に盛り上がるのはサビだなとしっかりと感じられるように作ってあります。また、本作の楽曲を担当しているスタッフも音ゲーを作ってきたスタッフなので、BGMもそのコース設計に合わせて作曲しています。プレイヤーが感情移入しやすいコースに設計できているのは、音ゲー制作で培ってきたノウハウだと思います。
―― レースゲームにも感情曲線があったんですね。
新井氏:
そうなんですよ。実際のF1サーキットも抜きどころのコーナーであったり、最高速が出る直線といった起承転結のような盛り上がるポイントが必ずあるんですよ。それと同じことを無意識にやってきたんだな、と思いながら聞いていました。
音ゲーに限らずかもしれないですけど、お客様のことを考えてどこで盛り上げるか、どこで波を作るかといった考え方はレースゲームも似てますよね。あとは、音ゲーチームはお客様の心を最初にガっと掴む設計がすごく上手いと思いましたね。

パーティーゲームのように楽しめてアーケードのような奥深い競技性のあるゲーム
――これまでの『ソニック』のレースゲームの多くはSumo Digitalさんが手がけていました。その過去作で優れていた要素として、『ソニックレーシング クロスワールド』に引き継ぐべきと感じたものがあれば教えてください。
小早川氏:
『ソニック』シリーズのレースゲームの最大の魅力は走行の気持ち良さだったと考えています。これは偶然だったとは思いますが、我々が得意とする気持ち良い走行と共通する部分が多くあったので、そういったところはSumo Digitalさんをリスペクトして、彼らの感覚も残しながら我々の良さを乗せるようなチューニングを意識して作りました。
それからコースのアートワークですね。コースのアートワークは彼らが抜群に優れていたので、我々も参考にしつつ、実際に過去作からアレンジして持ってきたコースも多いです。彼らのアートワークの秀逸さに感心しつつ、我々も学びながら制作させていただきました。
そして車のデザインも素晴らしく良かったです。Sumo Digitalさんは歴史のある非常に優秀なスタジオなので、そういったところを我々も学びながら作ったことで、今回の作品のクオリティにたどり着けたのだと思います。
『ソニックレーシング クロスワールド』では幸いにも過去作に比べて予算と期間を少し手厚めにいただきました。これによってSumo Digitalさんがきっと作りたかったであろう部分にまで、我々が手を入れて制作することができたと思っています。
――これまでの『ソニック』のレースゲームは、パーティーゲームという文脈で展開されていたと思います。今回は、セガの秘伝のタレのようなテクニカルな要素がたくさん入ってますが、どのようなプレイヤー層をターゲットに開発しましたか。
小早川氏:
大きく2軸のターゲット層を持っていることは間違いないです。ソニックのIPはグローバルに広がっており、特に映画の登場以降は、世界中にキャラクターファンを抱えています。アクションゲームとしてのソニックは難易度が高いものもあるため、そうしたファンが気軽に楽しめて、すぐに夢中になれるゲームということを第一に考えてます。パーティーゲームと感じるような逆転しやすい要素はこの層に向けて作られています。
もう一つのターゲットが、競技性を求めるお客様です。本作はクロスプレイのオンライン対戦に対応しており、本気で競い合うことで長く遊べる、というのがもう一つのコンセプトです。ガジェットシステムはオンラインでもやり込めるような仕様になってますし、アーケードゲームでは定番のランクアップシステムもあるので、コアユーザーが長く深く楽しめる設計を目指したつもりです。
―――ありがとうございました。最後に『ソニックレーシング クロスワールド』の「推しポイント」を教えていただけますか?
小早川氏:
『ソニックレーシング クロスワールド』は、アーケードのチームが作ったこともあり、やはりアーケードゲームのような作品になってます。日本のアーケードゲームは、オンライン対戦を通じてコアなプレイヤーも満足できるということを目指した、世界的に見ても不思議な市場です。我々がずっと作ってきたアーケードゲームのDNAを受け継ぐ本作を世界に発信できることが我々の挑戦であり、どのように受け入れられるかを非常に楽しみにしています。
ネットワークテストや体験版をプレイした方は楽しんでいただけたと思いますが、この楽しいを世界中の人たちが言ってくれることが嬉しいですし、そうなるといいなと思いながらインタビューを締めたいと思います。ありがとうございました。
――ありがとうございました。

『ソニックレーシング クロスワールド』は、Nintendo Switch/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One PC(Steam/Epic Gamesストア)向けに9月25日発売。またNintendo Switch 2ダウンロード版・アップグレードパスが今年冬販売開始予定となっている。
[聞き手・執筆・編集:Haruki Maeda]
[聞き手・編集:Ayuo Kawase]
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。