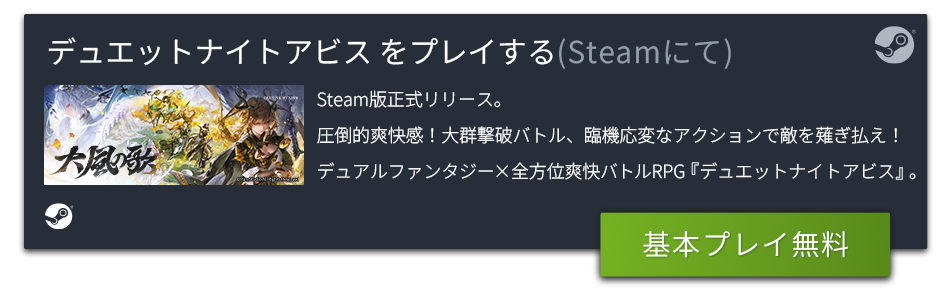『ソニックレーシング クロスワールド』は、アイテムありワイワイガヤガヤだが“実力主義ガチレースゲーム”である。友達で遊んで楽しいがあくまで「パーティーゲーム風」である理由を開発者に訊いた
『ソニックレーシング クロスワールド』の開発者に、本作のゲームシステムを深掘りして訊いた。

セガは9月25日、『ソニックレーシングクロスワールド』を発売した。対応プラットフォームは、PC(Steam/Epic Gamesストア)およびPS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch。プラットフォーム間のクロスプレイにも対応する。またNintendo Switch 2ダウンロード版・アップグレードパスが今年冬販売開始予定となっている。
本作は、『ソニック』のキャラクターたちによるレースゲームシリーズの最新作だ。過去作を主に手がけてきたSumo Digitalではなく、セガのソニックチームと、アーケードゲーム『頭文字D』シリーズや音楽ゲームを手がけたアーケードチームが手がけるという。
弊誌はこのたび、本作のクリエイティブディレクターを務める小早川賢氏と、アーケードゲーム『頭文字D』シリーズのプロデューサーであった新井健二氏にインタビューを実施。本作で実装されたトラベルリングやガジェットなど、さまざまなシステムはどのような意図で実装されたのか。システムについて深く掘り下げていく。
アイテムがあっても上手い人が勝つ、「パーティーゲーム風」のアーケードゲーム
――自己紹介の方よろしくお願いいたします。
小早川賢(以下、小早川)氏:
セガの第2事業部で『ソニックレーシング クロスワールド』のクリエイティブディレクターをしている小早川と申します。第2事業部は『ソニック』やアーケードゲームを制作している部署でして、私はアーケードゲームの部門も担当しています。10年以上、「コハD」として音ゲーを作ってきまして、新井さんと一緒に制作に携わったこともあります。
新井健二(以下、新井)氏:
新井と申します。私は2002年から2025年3月末までアーケードゲーム『頭文字D』シリーズのプロデューサーを担当していました。レースゲームということで、『頭文字D THE ARCADE(以下、頭文字DAC)』のチームが『ソニックレーシング クロスワールド』に携わることになり、立ち上げのときに関わっていました。
――『頭文字D』はアーケードゲームということもあり少しコアな印象があります。一方で『ソニックレーシング クロスワールド』は、より何でもありなパーティーゲームらしい要素が強いですよね。この二つの性質を、すんなりと融合させることはできたのでしょうか?
小早川氏:
やはりアイテムの存在が『頭文字DAC』とは大きく異なります。『頭文字DAC』を含む古くからのレースゲームの多くには、先頭車が後続車を引っ張る「ラバーバンディング」という機能があります。しかし、『ソニックレーシング クロスワールド』にはこの機能がありません。代わりに、引っ張ってくれる役割をアイテムで補うという、異なる設計思想で作られているんです。
このアイテムによる順位の変動というものが、パーティーゲームの構成要素となっているのですが、このノウハウは当初、我々になかったので制作には非常に苦労した点でもありました。『頭文字DAC』では、この「ラバーバンディング」によって抜きつ抜かれつの演出がしやすい構成になってるんですよ。
新井氏:
『頭文字DAC』は差が開きっぱなしにならないように調整しているわけですね。
小早川氏:
『ソニックレーシング クロスワールド』は挙動の気持ち良さや遊びやすさに加えて、アイテムというもう少し大胆な逆転要素が加わることで、「パーティーゲーム風」になっていると思います。ただ、実際に遊んでみると、パーティーゲームのような見た目とは裏腹に、戦略や駆け引きがかなり本格的に調整されているのも遊んで頂けるとわかると思います。
――「パーティーゲーム風」という表現は面白いですね。プレイしてみると確かにそう思えます。
小早川氏:
ベースはアイテムがなくても操作して楽しめるレースゲームという土台があって、そこに「ラバーバンディング」の代わりとなるアイテムの要素を入れていきました。そのあたりが「パーティーゲーム風」と感じられる点だと思います。
一方で、我々は競技性の高いゲームに仕上げたかったので、アイテムを使えば一方的に勝てることはなく、アイテムを使われた時に必ず対策もできるように設計しています。この対策も含めてしっかり考えることで、パーティーゲームのように楽しさは残しつつ、全部「運」で勝つのではなく、最終的に戦略を練った「強い人」や「上手い人」が勝つようなバランスにできたと思ってます。

トラベルリングにより1位であることが不利にならない
――プレイしてみてトラベルリングが最大の特徴だと感じました。丸ごと変化するコースが本当に予想できなくて驚きました。あらためて、なぜこのトラベルリングを実装するに至ったのか、そのコンセプトと理由を教えていただけますか。
小早川氏:
トラベルリングは、企画段階でいくつかのアイデアを検討する中で、「驚き」というキーワードをプレイヤーに提供するために選ばれたシステムです。映画「ソニック」シリーズをご覧になった方は分かると思いますが、次はどんなシーンが来るんだろうというワクワク感を常に感じられる作品だったと思います。
本作は、映画「ソニック」で魅力を感じたお客様もゲームを遊びたくなるような、いわゆるライトユーザーもターゲットにしています。そうした方々が一度レースを走るだけでも、飛び込んだ瞬間に景色も音楽も変わって楽しく驚ける、その感覚を与えることを目指して制作を行いました。これがトラベルリングを導入した大きな理由の一つです。
――「驚き」がキーワードとのことで、2周目のクロスワールドが自動的にランダムに選ばれるかたちでも驚きはありそうに思えます。しかし、実装としては1位のプレイヤーがランダムなクロスワールドを2択から選べるようになっています。なぜ、このような仕組みになっているのでしょうか。
小早川氏:
このゲームジャンル、特にアイテム制のレースゲームでは、1位になることが不利になるケースが多いんですよね。これは追従するプレイヤーがアイテムを使って攻撃できるシステムがあるために起きる現象です。それによって1位になりたくないという状況が生まれがちで、我々はその点をゲームデザインとして解消したいと考えていました。
また、今回実装したガジェットシステムにより、プレイヤーは得意なコースや苦手なコースに合わせてカスタマイズできるようになっています。こういったシステムを前提として、1位のプレイヤーが自分に有利なコースを選択できるというプラスの要素を加えることで、ゲーム序盤で1位を走っても不利ではないと感じさせることを目指しました。
また、コースを選べること自体が楽しいというのもあります。1周目を1位で通過してコースを選べたら、ちょっと得した気になるじゃないですか。このゲームは3周走って12人の中で1人しか1位になれませんが、1周目でも1位の優越感を得られるように感じて頂けることも目指しました。
――私が1周目で1位になれたときは、走ることに必死でコースを選ぶ余裕はありませんでした。でも、実力がともなえば行き先のコースを瞬時に把握して、有利なコースを選べるようになると。
小早川氏:
そうです。ガジェットに合わせた得意なコースを選ぶことで有利に走れます。それから、2周目のトラベルリングにはランダムでフィーバーゲートも登場するんですよ。かなりランダム性が高いのですが、相手の実力を見ながら、あえてフィーバーゲートを選ぶという戦略も可能です。
たとえば、アイテムボックスがたくさん出現するフィーバーが発生すると、後続車が持ってる強力なアイテムをリセットできます。このジャンルでは、後続車が強力なアイテムを持って追い上げてくる戦術も一つの定番ですが、それを崩せるんですね。どのフィーバーが出るかは分からないですが、そこにかけて突っ込むという戦略が取れる等、さまざまなところで1位に選択権があることに意味をもたせました。

――なるほど、このあたりの仕組みを理解していると、1位であることがかなり有利になりそうですね。
小早川氏:
初めての人はシンプルに 1周目1位でコースを選べて楽しい、理解していれば有利なコースや戦略を選べる、という2層構造で設計したつもりですね。
――このジャンルでは1位のプレイヤーが不利になりやすいものの、アイテムにより抜きつ抜かれつというランダム性も面白さだと思います。1位が独走しすぎない、追いつきやすすぎない、この難しいバランスをどのようなアプローチで調整しましたか?
小早川氏:
我々アーケードゲームの開発チームには、そのジャンルのゲームが日本一上手いと言っても過言ではないメンバーを集めて開発を行います。今回の作品でも、そういったメンバーがガチで対戦を繰り返して検証し、これならいけると納得できるバランスになるまで徹底的に追い込んで調整しました。
これは、おそらく他の会社ではやってないことではないかと思います。とはいえ、ゲームとしては逆転できる方がやはり面白くなるので、ほんのわずかな匙加減ですが、逆転しやすいような設計は意識して作っています。
――基本的には上手い人が勝つ、でも逆転要素もあるくらいのバランスですかね。
小早川氏:
その通りです。我々は「走力」と呼んでいるのですが、走力が高いプレイヤーが勝ちやすいように設計しつつも、走力が同じくらいだとどちらが勝つかわからない、くらいのバランスを目指して調整しました。
Switch版でも同時に3コース読み込みつつ、シームレスなコース変化とクロスプレイを実現
――トラベルリングは、ロード時間もなくシームレスにコースが変化するので実装が大変だったのではないでしょうか。技術的にどういう風に実装したのか教えていただけますか。
小早川氏:
技術的な話として、トラベルリングの仕様を実現する難しさは、見た目の通り1つのコースを選んだときに、データとしては3つのコースを読み込まなければならない点にあります。通常のレースゲームの3倍の容量を読み込みながらレースをスタートするため、ロード時間やハードウェアへの負荷など、非常に難しい検証しながら開発を進めていきました。具体的な内訳は申し上げられませんが、初期段階からかなりの時間をかけたつもりです。やはり3コースを読み込むことによる処理不可が一番のネックで大変でしたね。
本作で使用しているUnreal Engine5は、高性能な反面、ハードウェアに高い負荷をかけるゲームエンジンでもあります。3つのコースを読み込む負荷に加え、Unreal Engine5自体の負荷が同時にかかることも、開発においては苦労した点でしたね。『頭文字DAC』でもUnreal Engineを長年使ってて苦労してきましたが、そのあたりのノウハウが生きたのではないかと思います。
新井氏:
そうですね。汎用的で使いやすいUnreal Engineですが、良し悪しがありますね。
小早川氏:
ゲームエンジンとして様々な表現ができる反面、レースゲームには使わないような機能もたくさん入っており、使い方によってはハードウェア等に負荷をかけることもありますね。

――本作はクロスプレイにも対応しているので、Nintendo Switchでも3コースを読み込みつつ、ロード時間なくコースが変化することに驚きました。Switch版ならではの特別な工夫はあるんですか。
小早川氏:
Switch 版に関しましては非常に多くの苦労をしています。見た目は一緒でも、ほぼ違うゲームが動いてると言っていいくらい作りが異なるんですね。それによって皆さんにストレスのかからない読み込み時間や処理速度を実現したつもりです。
私自身もSwitch版でよく遊んでいますが、上位機種と比べても遜色のない、同じ遊び心地になるように作っています。やはり世界中にSwitch版を待っているお客様がいるIPですので、そこはもう妥協せずにやり切ろうと思って開発しました。
――技術的なお話は難しいと思いますが、Switch版を成し遂げられたのは、異なる作りになるほどに、さまざまな部分を徹底的に最適化したと。
小早川氏:
その通りです。ここで我々がアピールするポイントがあるとすれば、Switch版をプレイしても、ハードウェア性能の差をほとんど感じないように作ったことです。これは30フレームでも楽しめる設計にしたことが大きいです。30フレームで楽しめることを前提としつつも、60フレームではより滑らかに動く設計にすることで、30フレームでも満足できるようなゲームにできたと思います。60フレームを前提に作ってしまうと、30フレームでは快適に感じれないんですよ。
実は、最新作『頭文字D THE ARCADE』の少し前に開発した『SEGA World Drivers Championship』というレースゲームがありまして、これはさまざまな事情があって30フレームで作ったんですよね。本作のスタッフにもこのタイトルに関わったスタッフがおり、当時30フレームでレースゲームを楽しくすることにすごく苦労したことが活かされ、30フレームでも楽しめるレースゲームにできたのだと思います。
――異なるフレームレートでクロスプレイができ、それがしっかりと同期して成立するレースゲームはほとんどないですよね。
小早川氏:
30フレームと60フレームのプレイヤーがいても、不平等を感じさせないようにする点はクリアできたのではないかと思います。開発スタッフはすごく苦労したのですが、なかなか見た目では伝わらない点なので、スタッフに代わりちょっとアピールさせていただきます。Switch含めてクロスプレイできるゲーム自体、世の中にあまりないとは思いますが、ない理由がよく分かりましたね(笑)
2周目は驚かせつつ簡単に、3周目は盛り上がるコース設計
――2周目に選ばれるクロスワールド専用コースは個人的な感覚として、まずギミックが派手で、落下するようなコースも多く、通常コースよりも難しい印象を受けました。これは意図的に難しく作られているのですか。
小早川氏:
実は、クロスワールド専用コース自体は初見でも対応できるように、できるだけ簡単に作っています。通常のコースは、1周目と3周目を走ることで、このカーブは上手くいった、ここは失敗したと認識して上手く走れるようになっていきます。しかし、2周目のクロスワールドは1周しか走らないため、簡単にしてあるとはいえ、難しく感じたのではないかと思います。
また、2周目のコースでは入った瞬間に、いきなり滝に落ちたり、空を飛んだりといった、プレイヤーが驚くようなギミックを必ず入れることを意識しています。多くの人にとって初めて走るコースになるので、カーブのようなテクニカルゾーンは少なくし、テクニックがなくても見た瞬間に行先を判断する、対応力を問われるような設計としています。

――たしかに直線の多いコース設計になってましたね。ネットワークテストのタイムトライアルでは、クロスワールド専用コースが練習できなかったこともあり、難しく感じてしまったのかもしれません。
小早川氏:
製品版では、タイムトライアルでもクロスワールド専用コースを3周走るコースが登場しますので、そちらで練習していただければと思います。ネットワークテストでは練習する場を用意しなかったので、いきなり飛び込んでも問題ない難易度のコースをなるべく配置していました。
――3周目になるとダッシュパネルが増えたり、新しいショートカットが開通していたり、レースが展開が早くなる印象です。こちらも意図的な設計でしょうか。
小早川氏:
やはりファイナルラップは勝負を決する重要な局面ですので、最後に盛り上がって終わるように設計しています。それから、最高速が上がるリングの配置数も増えるなど、後続のプレイヤーが追いつきやすい設計をかなり意識しました。制作途中、2周目がすごく盛り上がっちゃうこともあって、3周目に戻ってきたときに楽しくなかったんですよ(笑)
音楽ゲームでも同じですが、やっぱり最後は盛り上がってなんぼなんですよね。3周目も必ず盛り上がれるように、ギミックが増えたり、新しいコースができたり、アイテム配置も増えたりといった、最後が盛り上がる工夫を入れていきました。
――ちなみに3周目の変化はコースによって毎回同じですか。
小早川氏:
3周目の変化パターンもいくつか用意しています。たとえばダッシュパネルやアイテムの位置が変わるなど、細かい工夫をたくさん施しています。何回遊んでも驚きがあるように、何回遊んでも飽きないような設計を目指しました。オンライン対戦で繰り返し遊ぶゲームなので、戦略が固定化されてしまうのを避けるため、このような設計にしています。
覚えゲーではなくガジェットと基本的なテクニックのみで競える
――ここからレース全般の質問です。キャラクターとマシンのカスタマイズよりも、ガジェットのカスタマイズの方が走りに大きく影響するように感じました。設計意図を教えてください。
小早川氏:
このジャンルのゲームでは、比較的性能のいいキャラクターやマシンに人気が集中する傾向にあります。オンライン対戦において、みんなが同じキャラクターとマシンで染まってしまうと面白くないじゃないですか。
我々はそれを避けたかったので、見た目には影響しないガジェットシステムで走りに変化を与えられるように設計しました。これにより、性能は意識しつつも、みんなが好きな見た目のキャラクターやマシンでレースを楽しむこともできるようにしました。マシンカスタマイズで色々なことができることも、同じ方針で作っています。
――ガジェットの組み合わせが膨大なので、デバックが大変だったのではないですか。
小早川氏:
お察しの通りデバッグは大変でしたね。ネットワークテストでも1つ問題のあるガジェットが見つかってしまいまして、残念ながら発売時にはオンラインプレイでは使えないものが1つだけ存在することになりました。逆に言うと、それほどにさまざまな可能性を秘めたシステムでもあるわけです。
我々は、アーケードゲームなどでもオンライン運営してきた経験もあるため、必要に応じてバランス調整や修正といったことを、今後やっていくつもりです。一時的に使えないガジェットは問題を解消して再び使えるようにしたり、あるいは新しいガジェットを追加して相対的にバランスを整える、といったことも含めて運営をしていく予定ですね。

――アイテムを使えばオフロードをショートカットができる箇所はありますが、ルートを覚えたうえでテクニックを駆使するようなショートカットは少ないように感じました。これも意図的なものでしょうか。
小早川氏:
競技性を担保するためには、基本的な力量の範疇を超えた知識やテクニックで勝負が決まってしまうのは不平等に感じると我々は考えています。
音楽ゲームでも同じで、音楽ゲームは覚えゲーと思われがちですが実際は違います。基本的な自力があれば、ほとんどの曲はクリアできるように作られているんですよね。特定の曲や場面でしか使えない、覚えないといけないような要素を入れてしまうと、途端に面白さや競技性を失ってしまって、ここだけ覚えれば勝てるという感覚になってしまいます。
我々はそういった要素をできるだけ排除し、基本的なドリフト技術や、アイテムを使う技術を駆使することでどのコースでも対処できるような設計にはしています。
――オンライン対戦ではスピードモードはどこに相当するのでしょう。ランクが上がればスピードモードも上がるのでしょうか。
小早川氏:
オンライン対戦は、「ソニックスピード」のみとなっております。スピードが速すぎると、我々が提供したい駆け引きの実現が難しくなると判断したため、ソニックスピードでの競技を提供しております。
また、製品版では、グランプリをクリアすると「スーパーソニックスピード」というモードが登場します。このモードは初期からダイナミックカメラの設定にもなっており、かなりスピード感を感じる設定になっています。もしさらなるスピード感を得たい場合は、このモードに挑戦してみてください。ソニックゲームらしい、ご満足いただけるプレイ体験を提供できるのではないかと思います。
――ちなみに、『頭文字DAC』では一人称視点で遊ぶプレイヤーが多い印象ですが、一人称視点の実装予定はありますか。難しいとは思いますが。
小早川氏:
このゲームではエアトリックという回転できるシステムがあるので、一人称視点だとすぐに酔ってしまうんですよね。通常の車ではありえない上下移動をするゲームですから。
新井氏:
そうなんですよ。ちょっとでも不自然な動きすると、あっという間に酔っちゃうんですよね。
小早川氏:
ですので、皆さんを酔わせないために、一人称視点の実装予定はありません。もし実装したら遊んだ人の98%酔わせる自信があります(笑)

チーム戦における光のラインはデバッグから生まれたラバーバンディング表現
――ここからはゲームモードの質問です。ネットワークテストでの期間限定4人チーム戦のフェスタがすごく楽しかったです。そのフェスタにおいて、チームメンバー間が光でつながるエフェクトが革新的で素晴らしいと思いました。前後や上下左右にいるメンバーの位置が一目で分かるうえに、野良マッチングでも絆を感じられる。この表現が生まれた経緯や、実装の工夫について教えてください。
小早川氏:
レースゲームでは自分の車に集中してしまうので、なかなか他の車を意識することが難しいです。チーム戦は前作『チームソニックレーシング』からあった要素ですが、本作でも異なるシステムでチーム戦を実現しようと実験していたのですが、なかなかチームとして遊ぶプレイ感が良くならなかったんですね。
そんな時、プログラマーがデバッグ用にポリゴンでラインを引いてくれたんですよね。それが非常に良くて、これいいじゃんと(笑)会話しながら実装を確定し、そこからデザイナーが見栄えを整えて実装しました。
実はあのラインは、先述した「ラバーバンディング」(先導車が後続車を引っ張る機能)の機能もあるんですよ。一人が独走するとチームのみんなが引っ張られる仕様になっていまして、従来の「ラバーバンディング」は見えなくて伝わりにくかったところを、プログラマーがラバーだからゴムのようなものを付けて見やすくしたという経緯もあったりしました。開発のトライアンドエラーの中で生まれたアイデアですね。

――あのラインは見た目だけじゃなくて本当に引っ張られてるんですね。先を走れば逆に引っ張っている。
小早川氏:
実際に引っ張られてますし、ゴムと同じで遠くに離れるほど強く引っ張られるんですよ。ですので、強い人と組むとチーム全体が引っ張られて速くなる、というのもチーム感を出してる1つの要素になっています。
――グランプリモードでは、レース中のキャラクターの掛け合いが楽しかったです。掛け合いは全キャラの組み合わせが用意されるんですか。
小早川氏:
正確に言うと、すべてのキャラクターのすべての組み合わせを用意しようとしたら、さすがにやりすぎだと言われたので多少調整はかけています。ですが、このキャラクターとこのキャラクターが出会ったら絶対会話するよね、という組み合わせはすべて用意しました。
加えて、特定コースの作品に登場するキャラクターが走っている場合、セリフが変わったりするんですよ。たとえば、『ソニック フロンティア』のコースで、その作品のヒロイン「セージ」が登場するとセリフが変わったりするので、こういうセリフを探す楽しみもあると思います。
――コースによってもセリフが変化するんですね。キャラゲーにおいてボイスの掛け合いは重要な要素だと思います。
小早川氏:
意外なキャラクターを好きになれるような仕組みにはできたかなと思いますので、是非あまり知らなかったキャラクターも使ってみて、好きになってほしいですね。

――ちなみにコラボキャラクターには掛け合いはありますか。ネットワークテストで参戦していたジョーカーにはセリフがなかったかと思います。
小早川氏:
残念ながら、コラボキャラクターやDLCキャラクターには掛け合いのボイスは実装していません。作品によっては国によって声優さんが変わるといった事情や、本作の膨大なかけあい量で、追加実装するキャラクター数分、対応するのが現実的にかなり難しいというのもありまして、より多くのキャラクターを登場させるために泣く泣く、対応しないという方針にさせていただきました。
その代わり、コラボ元の作品のSE(効果音)を鳴らすなど、世界観を感じてもらえるようにはしたつもりですので、そこを楽しんでいただければと思います。ボイスについてはさまざまなご意見をいただいていますが、我々としては苦渋の決断をしているというところです。
――タイムトライアルについて、ネットワークテスト中はSランクが難しくて取れませんでした。ワールドランキングを見ると、ドリフトの切り返しでチャージするガジェットで埋め尽くされていました。これ以外のガジェットでもSランクが取れるような設計になっていますか。
小早川氏:
全然なってます(笑)全てのマシンで取れるような設計はしています。ただネットワークテストでは、我々の想定しない使い方をしているマシンもあったのですごく驚きが多かったです。
――最後に締めとして『ソニックレーシング クロスワールド』の「推しポイント」を教えてください。
新井氏:
『ソニックレーシング クロスワールド』は非常に遊びやすいゲームになっていると思います。そして、世界中で大人気のソニックというキャラクターが登場するゲームです。これを機にレースゲームの人口が増えてくれたら、レースゲームを作ってきた私としてはとても嬉しいです。
また、これから様々なコラボレーションも予定されているので、ぜひ皆さん楽しみにしてゲームを購入していただけたらと思います。
――ありがとうございました。

『ソニックレーシング クロスワールド』は、Nintendo Switch/PS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One /PC(Steam/Epic Gamesストア)向けに9月25日発売。またNintendo Switch 2ダウンロード版・アップグレードパスが今年冬販売開始予定となっている。
[執筆・編集:Haruki Maeda]
[聞き手・編集:Ayuo Kawase]
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。