『鬼武者 Way of the Sword』までの“20年間”は、開発陣さえじっと待ち続けた。必要だったのは、現代に斬りこむ「タイミング」
『鬼武者 Way of the Sword』の二瓶賢ディレクターと門脇章人氏プロデューサーに対してメディア合同インタビューを実施。20年ぶりの新作が実現した理由などを訊いた。

『鬼武者』シリーズ20年ぶりとなる新作として話題の『鬼武者 Way of the Sword』。このたび東京ゲームショウ2025にて、本作品のディレクターを務める二瓶賢氏、並びにプロデューサーを務める門脇章人氏に対して、複数メディアによる合同インタビューが執り行われた。本稿ではその模様をお送りしよう。
『鬼武者 Way of the Sword』は『鬼武者』シリーズ最新作。対応プラットフォームはPC(Steam)/PS5/Xbox Series X|S。発売日は2026年を予定している。本作にてプレイヤーは時の剣豪「宮本武蔵」として、瘴気によって不可思議な姿と化した江戸時代初期の「京都」を舞台に、はびこる幻魔を斬り伏せながら、己が戦う理由を探し求めていく。
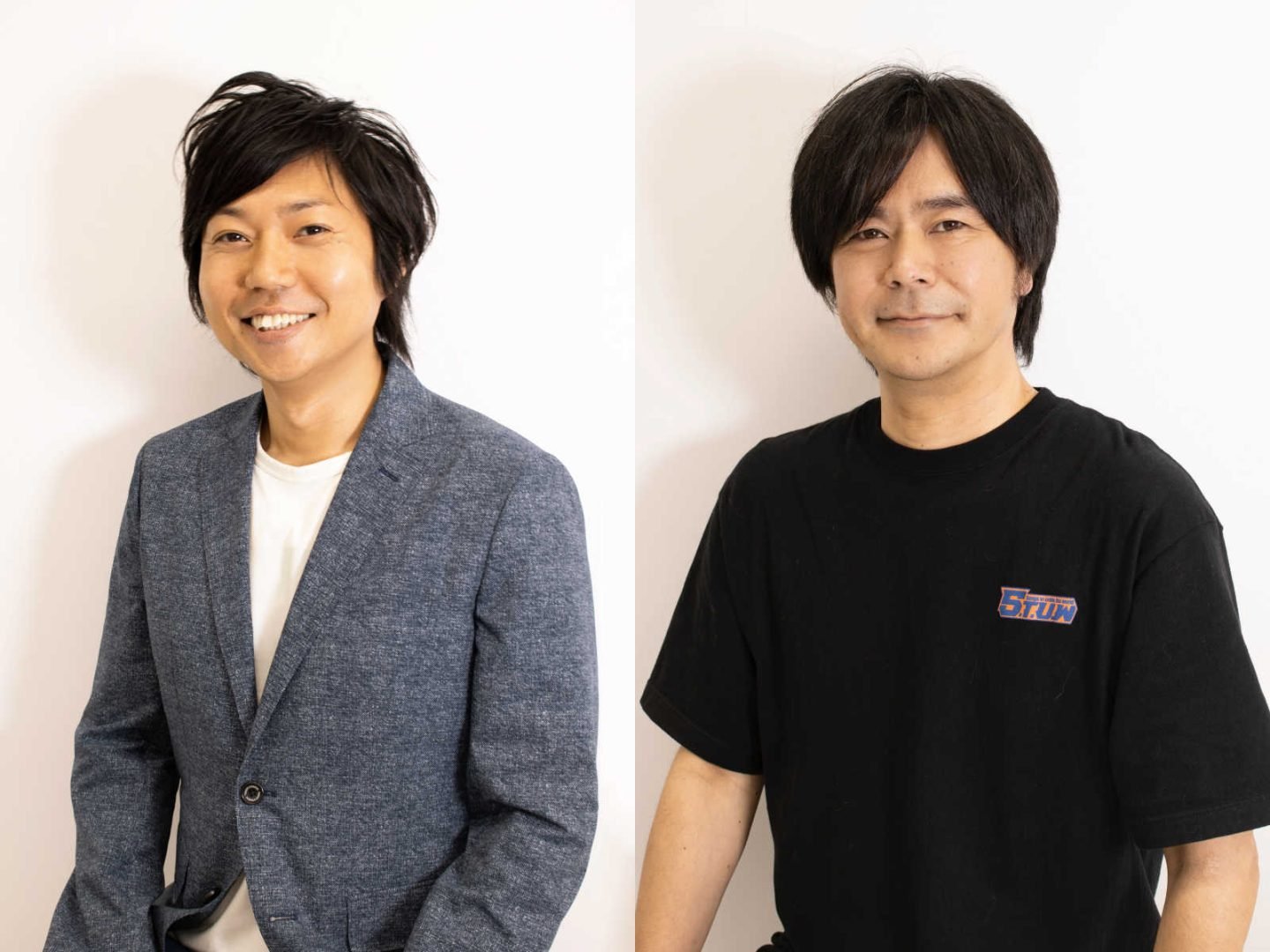
――本作には「一閃」をはじめ、習得に練習が必要なアクションが多く存在します。一方でシリーズ前作からかなり時間も経過したので『鬼武者』を知らない人もプレイすることになると思いますが、どのような工夫を盛り込みましたか。
二瓶氏:
おっしゃる通り、本作は『鬼武者』に触れたことがない人もターゲットにしています。そこで、本作には難易度設定を設けています。物語を味わいたい人向けの「活劇」と、アクションゲームに慣れた人向けの「剣劇」です。この2つの違いに関しては。敵の強さが違う、というだけではなく、「一閃」の出しやすさも異なっています。ただ、過去作と比較すると「一閃」自体の出しやすさは難易度関係なく楽になっていると思います。もちろん、繰り出すにあたって練習は必要不可欠です。
――充実したチュートリアルが用意されているのでしょうか。
二瓶氏:
はい。武蔵が新しいアクションを覚えるたびに、それを試せる場所に出くわす、といった工夫をしています。
――主人公・「宮本武蔵」の成長システムについてお聞かせください。ゲーム的なレベルアップやスキル習得はどのように行うのでしょうか。
二瓶氏:
成長要素は複数あります。探索を通じてアイテムを入手することにより、ステータスの上限があがったり、「魂吸収」により集めた「赤魂」を消費して、スキルツリーを伸ばしたりしていく方式になっています。装備品による強化要素もあります。

――宮本武蔵が扱う武器のバリエーションについてはいかがでしょう。
二瓶氏:
本作で武蔵が扱う武器は「日本刀」のみです。そのうえで、必殺技「鬼の武具」という形で刀以外のアクションを使うことができます。こちらは主にフィールドの探索を通じて獲得することが可能です。
――複数の「鬼の籠手」が登場しますが、これらは本作においてどういう位置づけですか?
二瓶氏:
「鬼の籠手」は、宮本武蔵や佐々木巌流など、キャラクターの人生を変えるキーアイテムとして位置づけられています。数は多くありませんが、物語の主軸に関わる非常に重要な存在です。
――ボス戦についてはデモ版では剣同士の打ち合いがメインでしたが、製品版では遠距離戦や巨大な敵との戦いなどもあるようで、どういった体験バリエーションが用意されていますか?
二瓶氏:
まさにおっしゃる通り、本作に用意されているのは剣同士の打ち合いだけではありません。遠距離攻撃をしてくるボスであったり、巨大な武器を振り回すような敵も登場します。ただし、急にシューティングゲームになったり、パズルゲームになったりといったことはせず、あくまで剣戟アクションの範疇で作っています。

――『鬼武者』といえばやりこみ、周回プレイだと思っています。オープニングからエンディングまでゲームを1周するにあたって、どれくらいのプレイ時間を想定していますか?
二瓶氏:
メインのプレイ時間はおよそ20時間程度を想定しています。これにサイドミッション(クエスト形式)も用意しており、それをやり込めばさらに時間は伸びます。このサイドミッションがこれまでとは異なる遊びの広がりを見せてくれると思います。
――寄り道、というと、「鬼の佳人」や「出雲阿国」といった仲間との交流もあるのでしょうか。
二瓶氏:
あります。プレイヤーが交流したい仲間を選んで、コミュニケーションをとることができます。絆を育むことで、ゲームプレイにさまざまなメリットがもたらされる、というシステムも用意されています。
――本作は京都が舞台、かつ宮本武蔵らしい「何でもアリ」戦法を活かせるフィールドギミックが各所に用意されていると伺っています。本作にはどういったロケーションとギミックが登場するのでしょう。
二瓶氏:
まずは舞台に関してですが、デモ版に登場した「清水寺」をはじめ、いくつか京都の名所が登場します。もちろんダークファンタジーらしいフィールドも用意しています。
そして、フィールドギミックについては「その場所に自然とあるようなものを活かす」といったデザインになっています。たとえば、屋内であれば床に敷いた畳をヒックリ返して盾にする、というプレイができます。ただ、役割としてはマンネリを防ぐスパイスであり、活用しなければゲームクリアできないということはありません。メインはあくまで剣戟です。

――本作のストーリーについてお聞きします。『鬼武者』シリーズはもとより、戦国時代とダークファンタジーの要素を融合した作品になっていますが、本作ではどのような融合を果たしているのでしょう。
二瓶氏:
本作はゲームとして面白い内容に仕上がるよう、ファンタジーや江戸時代の文化背景を融合させた物語体験を作り上げています。当然、時代考証に関して、専門家の方に意見を伺っておりますが、内容として優先されているのは「ゲームとして面白いか」という部分です。
――合わせて、主人公に「宮本武蔵」を起用した理由を教えて下さい。
門脇氏:
実を言うと、開発当初は宮本武蔵を主人公にする予定ではありませんでした。主人公は「名も無い武将」という設定だったんです。しかし、グローバル展開を狙うにあたって、わかりやすいアピールポイントが欲しかった。そこで、二瓶と相談したところ、「宮本武蔵」という偉人の名を借りようという決断に至りました。
――海外において宮本武蔵は実際に人気があるのでしょうか。
門脇氏:
かなり人気の高い人物であると認識しています。著名なフィクションにも多数登場していますし、彼の著書とされる「五輪書」が海外向けに翻訳されて読まれていますからね。
――本作に起用されている三船敏郎氏のフェイスモデルは、どの年代をイメージしたものになっていますか?
二瓶氏:
20歳代前半に彼が出演した映像作品を研究して、宮本武蔵というキャラクターに落とし込んでいます。ただ、表情を作る際に「特定の作品における三船敏郎」を意識して作っているわけではありません。あくまで宮本武蔵という人物と、三船敏郎氏という人物が自然に重なり合うように制作しました。
――2006年発売の『新 鬼武者 DAWN OF DREAMS』以来、20年ぶりの新作となりますね。以前、他のインタビューにて「今が最適なタイミング」とおっしゃっていましたが、このタイミングで再始動に踏み切った大きな決め手は何だったのでしょうか?
門脇氏:
「最適なタイミングになった」という方が正しいかもしれません。まず、かねてより社内の要望がありながら、プロジェクトのために開発メンバーを集めることができませんでした。弊社はさまざまなビッグタイトルを抱えており、同時に、昨今のゲーム開発には非常に数多くのスタッフが必要になってきます。
そうした中で、2020年頃にようやく新作を作れる体制が整いました。これに加え、技術的にRE ENGINEが成熟してきたというタイミングも重なり、この時期に再始動が決定しました。更に言うと、剣戟をメインの遊びに据えたアクションゲームの人気、というのも私達にとって追い風ではないかと思っています。
――過去作と比較すると、現在どのくらいの規模で開発を行っているのでしょう。
門脇氏:
ゲームを作っているメンバーだけで、現在180人くらいです。カットシーン担当のスタッフなど、他にもたくさんのスタッフが本作に関わっています。過去作と比べるとかなり大規模な体制になっていると思います。

――シリーズファンに向けて、本作ならではのアピールポイントを教えて下さい。
二瓶氏:
過去作品から醍醐味である「バッサリ感」の表現が非常にパワーアップしております。切ったあとの肉片が自由ベクトルで落ちていくなど、この技術的な表現は今だからできることだと思います。ストーリーの描写やカットシーン、細かな手の動きなども、ハードウェアの進化のおかげでトップクラスの表現力でできるようになっていますね。
――アクションが苦手な方や未経験者へメッセージをお願いします。
二瓶氏:
今回東京ゲームショウ2025で実際に触れていただいた方からは「見て感じるよりも、触ってみたらすごく楽しい」という声を多くいただいています。気持ちよくバッサリ斬れるという点に全力を尽くして作っていますので、一人でも多くの方に触れていただきたいと思っています。
――ありがとうございました。
『鬼武者 Way of the Sword』はPC(Steam)/PS5/Xbox Series X|S向けに、2026年発売予定だ。
[聞き手・執筆・編集:Takayuki Sawahata]
[編集:Hideaki Fujiwara]
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。




