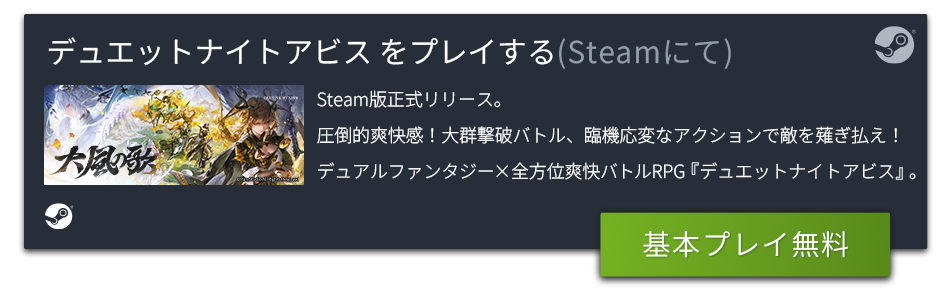「G TUNEが変化していることをゲーマーに伝えたい」PCメーカー・マウスコンピューターが、TGSへ“大規模出展”に舵切った理由を担当者に聞いてみた
マウスコンピューターがなぜ「東京ゲームショウ2025」の出展に大きく力を入れているのか、担当者に詳しく伺った。

マウスコンピューターは9月25日、「東京ゲームショウ2025」へ出展した。同社は、例年多くの企業に試遊用のPCを貸し出すなど、どちらかといえば裏方としてイベントを支えてきたBTOパソコンメーカーだ。そんな同社が、本イベントでは大規模なブースを出展。ブースではマウスコンピューターのPCで各社のゲームを体験できるほか、ブース内のステージでさまざまなイベントを開催した。
マウスコンピューターは、BTOにてPCを販売するメーカーだ。ゲーミングPCブランド「G TUNE」「NEXTGEAR」など、さまざまなブランドから各用途に向けた製品が展開されている。通信販売を軸に、個人・法人向けにPCの販売をおこなっているほか、イベントの際には企業へ自社ブランドのPCの貸出もおこなっている(関連記事)。
このたび、弊誌はマウスコンピューターにてセールスプロモーションを担当する桑園勉氏にインタビューを敢行した。これまでは自社ブランドのPCの貸し出しに力を入れてきた同社が、なぜ「東京ゲームショウ2025」の出展にここまで力を入れているのかについて詳しく伺った。
マウスコンピューターのゲーミング展開PRの一手として
――自己紹介と、どういったお仕事をされているのか教えてください。
桑園勉(以下、桑園)氏:
マウスコンピューターの第二営業本部販売促進室でセールスプロモーションを担当している桑園勉と申します。特にゲームのパブリッシャー様と連携したり、こういったイベント出展の際に各パブリッシャー様とのコミュニケーションをさせていただいたり、eスポーツチーム様とのコミュニケーションなどをおもに担当しております。
――マウスコンピューターはどちらかというと、「東京ゲームショウ」(以下、TGS)では機材貸出メインで、今まで裏方としての立ち回りが多い印象でした。今回は大きな規模のブースで出展されています。1日に4本ものイベントをされていますし。結構な方針転換に見えますが、意図を教えて下さい。
桑園氏:
たしかにここまで大規模に出展するのは2019年以来です。「どうしたんだ」という風にお話をいただくことも多いです。ただ、実は昨今のマウスコンピューターのゲーミング展開を思い返していただくと、昨年のNEXTGEARの立ち上げから今年のG TUNEのリブランディングに至るまで、実はマウスコンピューターがゲーミングにしっかり力を入れているということが文脈としてあるんですね。
――ああ、なるほど。リブランドしたことを周知させたいんですね。
桑園氏:
ええ。その上で、我々がゲーミングに対して注力しているということは、弊社Webサイトで発信はさせて頂いていますが、それだけですとどうしても伝わり切らないと思っています。そこでこのTGSという年に一度のゲームの祭典でブース出展をさせていただくことで、今までマウスコンピューターを知らなかった方にも、今までのマウスコンピューターを知っていた方にも、新しい我々の取り組みをお届けしたいという思いがあって、このブースの規模での出展になりました。

――なんとなく、雰囲気で出展されているわけではなく、目的がちゃんとあるんですね。面白い。
ちなみに今回の出展では、試遊機もありますがPCへのアピールにもスペースを使われています。試遊機をいっぱい置く選択肢もあったのでは。
桑園氏:
マウスコンピューターはあくまでもハードウェアの会社ですので、試遊機の量を多くすれば、たしかにそれだけたくさんのお客様に機体を触っていただくことが可能です。ただ、その場合は会場に足を運べない方には情報をお届けできません。そこで今回は、そういった方にも我々の製品PRをお届けしたいという思いから、ステージを用意し、すべてのステージコンテンツを配信してお届けすることにいたしました。そのため、ステージが必要だったので試遊機は20台が限界でした笑
――ブランド方針が変わったということを伝えるため、これまでどんな取り組みをされましたか。
桑園氏:
たとえば、今年1月G TUNEをリブランドさせていただいたときに「ブランドが変わりました」と言うだけではなく、G TUNEデスクトップPCのフラグシップのモデルチェンジいたしました。
これには何が変わったかを明確に知らしめたいという意図がありました。より変わったということを発信するのに、文字や言葉だけではなくてビジュアルでどう変わったかを示す必要があると思っています。それが発表会だったり、イベントの出展だったりが良い手法だと考えていますので、こういった取り組みを前面に押し出しています。
――リブランドすることで、周囲やユーザーからの反応どうでしょうか。あるいは自分たちのこういうところが変わったぞ、といった実感はありますか。
桑園氏:
ユーザーの皆様からの反応としては、これまでのG TUNEファンの方からご意見お伺いする機会があって、新しい製品展開もいいね!とご好評頂いています。変わった事をポジティブに受け入れて頂けていることに安心しています。
トレンドってどんどん変わっていくもので、やっぱりリブランディングする前のPCケースはリリース当時のトレンドを踏襲していて、今となっては古いイメージが拭えないものでした。
それをフラグシップもそうですし、7月から新しく展開しているマイクロミニタワーのケースもそうなんですが、今のトレンドを取り入れて今の世代のお客様に刺さるものを展開するというかたちで、ブランディングも切り替えていく必要があると思っています。
――トレンドを見据えて、プロダクトの方向性も変わったと。
桑園氏:
はい。ここは少し語弊もありますが、方向性が変わったと言うより、新しいアレンジを加えたという方が適切かと思います。
フラグシップもミニタワーも、新しいモデルと以前のモデルを見比べていただくと、やっぱり古さは感じてしまうと思います。それは良い悪いではなくて、当時のトレンドを踏襲しているからそうなるのは仕方がないことですね。なので、お客様のトレンドが変わったなと感じたタイミングで、我々もトレンドを取り入れる努力をし続けていかなくてはいけないと思っています。

――今回のリブランドの発表は、ちゃんと今の時代のトレンドを見ているという意思表明でもあるわけですね。ちなみに、僕はクラシックなマウスコンピューター製品も好きなんですが、そちらの方向性は今後どうなるんでしょうか。
桑園氏:
トレンドを取り入れていくとお話ししましたが、それでもクラシックなものを捨てているとは思っていません。というのも、G TUNEはコアゲーマー向けの製品である。これは変わっていないんですね。コアゲーマー向けの製品展開を行う事と今のトレンドを取り入れることは、相反しないことと考えています。
派手すぎず、それでいて変わったことを意識しつつシックなテイストを残すということは、今のフラグシップモデル群に採用されているフルタワーケース「240P」で実現出来ていると思っています。実は、この製品では製品設計側のメッセージとして、RGBに頼らない間接照明のLEDライティングにするという設計思想が踏襲されているんです。
マウスコンピューターの強みはなんなのか?
――最近のマウスコンピューターは、どういったところに力を入れているんでしょうか。
桑園氏:
特にどの部分と限定すれば、「新製品展開」でしょうか。ここ最近はG TUNEもNEXTGEARも大量に新製品を投下させていただいているんですが、これらの製品は今のトレンドに対してしっかりフォーカスする形でデスクトップもノートPCもどんどん変わっていますね。NEXTGEARになりますけど新しいコンセプトの製品も準備して(スイッチャブル)、どんどん新しい挑戦をしています。
――こうして変化を続けているマウスコンピューターには、BTOメーカーやパソコンメーカーでたくさんのライバルがいらっしゃると思いますが、自分たちの個性や特徴、強みは何だと思いますか。
桑園氏:
私が実際にG TUNEのプロダクトに携わるようになって気づいたのは、ターゲットにしているユーザーに対する解像度の高さですね。特にG TUNEのデスクトップがわかりやすいのですが、G TUNEはコアゲーマーを対象にしているブランドです。そこでコアゲーマーが求めているものの解像度の高さに関しては、強みのひとつですね。
――コアゲーマーへの解像度の高さとは、具体的にはどういったものですか。
桑園氏:
今のゲーマーは、ゲームだけをするわけではないじゃないですか。ゲームをしながら通話をしたり配信をしたり、いろいろなマルチタスクが当たり前の状況になっています。そんな現状だと、メモリが標準搭載16GBでは正直厳しいと思っています。であるならメモリ32GB搭載は当たり前だろうと。あとは無線のゲームパッドなどのゲーミングデバイスを使う場合にBluetoothが標準で搭載されているとUSB接続の送受信機(子機)が不要で便利です。よくどっか行っちゃいますしね笑
ほかにはインターネットの宅内引き込み場所とゲーム機を置く場所が離れていると、有線LANの引き回しは大変です。ですが無線LANならそういったストレスから開放されます。
ちなみに私もG TUNEデスクトップを使用していて、今のくだりはすべて実体験です笑
このあたりが、「解像度の高さ」と表現した自分たちのターゲットにしているコアゲーマーに対する製品設計部分です。
――ゲーマーの桑園さんらしい視点です。ありがとうございました。

この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。