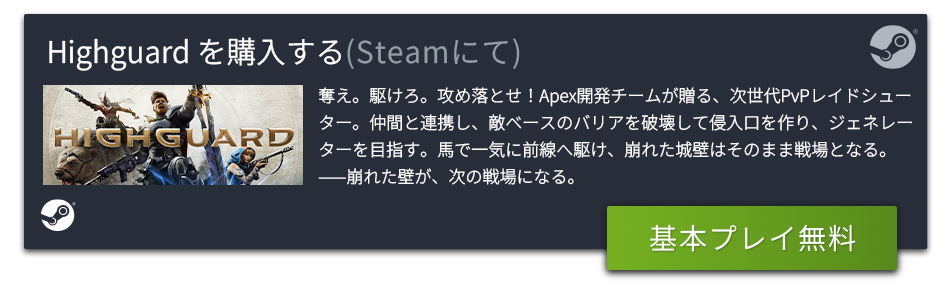「手塚治虫」の「対戦トレーディングカードゲーム」はなぜ生まれたのか? 手塚眞氏×イバイ・アメストイ氏インタビュー 前編
なぜ「手塚治虫作品」の対戦トレーディングカードゲームは生まれたのか。『アトム:時空の果て』誕生の秘密とその背景を、手塚眞氏とイバイ・アメストイ氏が語る。

『火の鳥 鳳凰編 我王の冒険』や『ASTRO BOY・鉄腕アトム -アトムハートの秘密-』など、現在までさまざまなハードを対象にゲーム化されてきた漫画家「手塚治虫」の作品たち。アクティブゲーミングメディアは新たな手塚ゲームプロジェクト『アトム:時空の果て(Astroboy: Edge of Time)』を正式発表した。
既報の通り、『アトム:時空の果て』は手塚治虫のキャラクターたちが登場する対戦トレーディングカードゲームだ。時空の果てにただよう未来都市「スプロール」を舞台に、プレイヤーは多元宇宙から送られてきた手塚治虫キャラクターをカードとして使役し、彼らの運命の行く末を追うことになる。本作ではサイバーパンクを基調とした完全オリジナルなストーリーにも力を入れるほか、カードの配置場所が「エンフォーサー(前方)」と「ガーディアン(後方)」に別れているなど独自のゲームルールも存在している。
手塚治虫作品の生誕から90周年、なぜいまあらためて手塚治虫ゲームを開発しようと考えたのか、またなぜカードゲームへと至ったのか。今回は株式会社アクティブゲーミングメディアの代表取締役であるイバイ・アメストイ氏と、手塚プロダクションの取締役である手塚眞氏にお話をうかがった。
――なぜ「手塚治虫」のゲームを?
イバイ・アメストイ氏:
当社のなかに、トレーディングカードゲームをやりたいというプロデューサーがいて、彼がけっこう面白い企画を持っていたんですね。ただその企画を進めるにあたって、シナリオとキャラクター、そしてどんなテーマで開発を進めるかという最大の問題がありました。当初は会社のなかで協議して、いろいろなIPホルダーと連絡を取って交渉していたんですが、幅広いキャラクターが存在し面白いシナリオを作れるほどの大規模なIPがないと行き詰っていたんです。その時、私には手塚プロダクションに近い“友人”がいることを思いだして、眞さんに声をかけたんですね。1000枚から2000枚のカードを作れるほどのキャラクターが存在するIPは、日本国内だと手塚治虫先生の作品しかないと。今思い返してみれば、当然の流れだったと思ってますね。
――手塚眞さんはその企画を聞いたとき、どう思われましたか?
手塚 眞氏:
最初は単純に手塚キャラクターを使ったゲームかなと思ってたんです。でも実際にお会いして内容をお聞きしたら、ちょっとこれまでのゲームとは違うようでした。それと僕が一番惹かれたのは、ゲーム内のキャラクターは原作の絵を使わずにほかの方々が描くという部分で、それなら面白くなるんじゃないかなと思ったんですね。
これまでも手塚の作品を使ったゲームはいろんなプラットフォームで出てたんですけども、キャラクターの絵におぶさっているだけみたいな企画が多かったんですよ。だからなんかゲームっていうと、実はあまり期待しないっていう感じにもなっていて。ただ今回は、絵を変えてストーリーもオリジナルでいきますと聞いたときに、「あ、やる気だな」と思った。すごく期待したんですね。
――イバイさんはスペイン出身ですが、手塚作品は何歳から読まれていたんですか?
イバイ氏:
親父が大好きで家にたくさんの単行本があったんですね。10代のころに読んでいて、20代前半はブランクがあったんですが、30代に入ってからもう1回読み直したんですよ。なにを読んでも面白かったですね。
――ちなみに一番好きな作品は?
イバイ氏:
わたしは「アラバスター」ですね。「アラバスター」はストーリーは本当に暗いですし、本人はあまり好きじゃなかったというお話は聞いてるんですけど、キャラクターデザインが本当に素晴らしいしかっこいい。やっぱり眞さんは選べないですか?
手塚氏:
どれとは言えないですね。本当に選べないです。どれも好きですよね。ただ、もし個人的にこの作品をもう一回読もうとかって思うと、暗いのが多いですね。暗いというか大人向けの、「奇子」とか「人間昆虫記」とかそういうものですね。
イバイ氏:
あと「きりひと讃歌」ですね。「きりひと讃歌」はもう、キャラクターは本当に素晴らしいですね。
――手塚作品はたくさん存在しますが、ビデオゲーム化も頻繁に行われてきましたね。
手塚氏:
そうですね。手塚プロダクション自体で作っているわけじゃないんですけど、そういう話がきたときは、なるべく積極的に聞くようにしていました。
――ファミコンでは、「火の鳥」を題材にした『火の鳥 鳳凰編 我王の冒険』などもリリースされていました。同作の物語は本編からは大きく変わっていました。
手塚氏:
そもそも手塚治虫の考えたストーリーって、ゲームに向いてるストーリーではないんですよ。ものすごく心情的であったり、人間関係などが複雑だったりすることが多いんです。そのままゲームになるというもんじゃないので、やっぱりゲームっていう世界に1度置き換えたほうがいいと思うんです。
あと手塚のビデオゲームって、ひとつひとつの世界観だけでも作れるとは思うんですけど、今回の企画はいくつかのストーリーやキャラクターをあわせてやるというものです。それによって新しい世界観を作ると同時に、手塚治虫の世界を広げようという企画で、そもそもゲームっていう以前にそういう考え方が面白いなと思ったんです。
イバイ氏:
過去の作品に関して、眞さんは監修とかされたんですか?
手塚氏:
会社としては監修をするんですけど、私は参加しませんでしたね。基本的には窓口となる担当者がいますから、やはりその時点で監修が済んでしまうような場合も多かった。ただ今回のは内容が特殊なケースだし、やっぱり絵を変えるということに関しては、私が近くにいたほうがいいだろうなと思いました。
――手塚眞さんは、今回のプロジェクトに深く参加されるということでしょうか?
手塚氏:
どこまでを深いというのか、わかりませんけども。
イバイ氏:
深くというよりは、ひとつひとつ重みがあるというんですかね。眞さん本人でしか指摘していただけないところをチェックしていただいています。50年前、60年前に大事に制作されたキャラクターを描き直しているわけですから、そのキャラクターの本質を一番わかっている眞さんからは、非常に貴重なアドバイスをいただいています。
手塚氏:
今回のプロジェクトでは、キャラクターのイメージが原作から大きく変わっているので、そんなに細かく指摘するつもりはないんですよ。原作のなかで一番大事なポイント、「実はここはこうじゃないか」とか、曖昧な部分に関しては「原作だとこうですね」とか、そういうような話はします。ただ、あんまり押し付けがましく言うつもりはないんです。
前にイマジという香港の会社が、全編CGIの「アトム」の映画を作りました。あの時はキャラクターをなるべく原作に近くしたいっていう話があったんで、担当の技術者と細かい話をしてました。この部分の大きさを何パーセントどうしようとか、ここはちょっと長すぎるとかね。ほんと具体的な指示で、設計図の上で「ここをもっとこうしたほうがいい」とか実際に画を書いたり、そういったやりとりを続けて制作してたんですよ。
そういう場合もあるんですけど、今回は逆にある程度おまかせしてやったほうが面白いと思ってるんで、あんまり口出しすることはないですよ。ただ、たとえば最近見せてもらったこの「ロビタ」。「ロビタ」って、「火の鳥」のなかでは脇役だけど、すごく味わいのある印象的な存在です。それがこんな感じになるっていうのは面白いなと思ったんですけど、これを見たときに目がピカーンと光っていて。いかにも強そうなんですけど、実は「ロビタ」って目のないキャラクターで、目がないことで逆に表情が見えるっていうね。目があるのもいいんだけど、たとえば目のない瞬間もあっていいんじゃないかっていう話をしたりとか。あと手も、本当は漫画の「ロビタ」って、手がハサミみたいな形をしてるんですよ。でもこれは指が5本あるので、そこをもう少しハサミみたいにできると、より漫画のイメージに近くできますよねとか。
――ほかにもキャラクターのイメージで気をつけている部分は。
イバイ氏:
外国人でも日本人でも好むような、中間的なキャラクターデザインにはしようと思いました。手塚先生自身もそういう考えでデザインを考案したのかもと思ってますね。もともと私は“ザ・日本のコンテンツが好きな人”というわけではなかったんですけど、手塚先生のキャラクターデザインは昔から大好きでした。
――今回のプロジェクトでは、クールなサイバーパンク調で手塚治虫作品のキャラクターたちが再構築される予定となっています。
手塚氏:
手塚のキャラクターはそういう世界観と相性が良いんでしょうけど、表現の仕方はだいぶ変わってくると思っていますね。やっぱり手塚治虫の漫画の基調っていうのは、シンプルってことでもあるし、もともとディズニーの絵柄の影響ってのもあったんで、かわいらしいですよね。それをがらっと変えて、クールなかっこいい感じの絵柄にしようというプロジェクトですから。大きく変えたほうが面白いと思いますね。
イバイ氏:
ここは実はとても難しいところでして。手塚プロダクションの玄関には、「アトム」のフィギュアがたくさんあるんですよね。「アトム」は基本的にかわいいじゃないですか。すごくかわいいキャラクターで、ほんのちょっと身体を細長くして大人っぽい「アトム」にしたら、もう不自然に感じてしまう。
でも今回はそのまま「アトム」を出すわけにはいかないし、それを変えなければいけない。でもどう変えるのか。いかついものを作ったら、それはもちろんかっこいいものが作れると思うんですけど、それは「アトム」でなくなるし。漫画家の浦沢直樹先生は「PLUTO」でどうやったのか。しっかりと変わっているんだけど、誰が見てもこれは「アトム」なんだなとわかるようなキャラクター作りをしないといけない。
もちろんこれは「アトム」に限らず、ほかのキャラクターでもある壁なんですけどね。ただ、「アトム」はそのなかでもっとも難しいかなと思うんですね。「火の鳥」だってそうですよね。やっぱりでかいドラゴンみたいなものを作るのは簡単ですけど、「火の鳥」は優しい顔をしていますし、それを残さないといけないと思いますから。ちょっと難しい、独特なキャラクターが多いですね。
――ビジュアル的なリブートという印象も受けます。
イバイ氏:
キャラクター1人1人を新しい世界観とシナリオに合わせて変えていくんですね。
――手塚治虫先生や手塚眞さんは、いままでビデオゲームに対して興味を示されたことはあるんでしょうか?
手塚氏:
正直に言うとですね、父親も私もわりとメカ音痴なところがあってですね。あまり、その、特にゲーム関係のものには手を出さなかったんですよ。私自身はコンピュータグラフィックスとか、そういう映像に関わる部分はやっていましたけど。正直言って、ゲームは全然興味なかったです。だから私のゲームのキャリアって、『インベーダー』で終わってる感じなんです。
――『インベーダー』はプレイされてたんですね。
手塚氏:
一番最初のね。喫茶店に行くと、どこにでも置いてあってね。そのぐらいですよね。あとなんだっけな、打ち返すやつがあるじゃない。ピンポンみたいな。
イバイ氏:
『PONG』ですか?
手塚氏:
っていうやつなんですかね。
イバイ氏:
『PONG』はもう、一番初期の。
手塚氏:
最初のやつですよね。そのぐらいですよ。
イバイ氏:
めずらしいですよね。ゲームを開発するにあたって、一番大事なのはシナリオとキャラクター、そしてゲームプレイそのもの。手塚作品のIPがあれば、シナリオとキャラクターは必ずカバーできているじゃないですか。あとは面白いゲームプレイさえあれば、無限の可能性がある世界観だと思います。
手塚氏:
実はこれを言うと恥ずかしいんですけど、一度任天堂と一緒にゲームを作りかけてたんですよ。ニンテンドー64が出たときに、手塚プロと任天堂で組んでゲームをやろうとしていて、私がディレクションをやってたんですけど、結局完成しなかったですね。マシンのスペックが高すぎて、追いつかなかったっていう。
あの時は任天堂と一緒に開発していたゲームプロジェクトはいくつかあったんですけど、どれも完成しなかったですね。糸井重里さんの『マザー』とか、同時期にやってたんですけどね。
――どういう理由で開発はストップしたんでしょうか?
手塚氏:
64のスペックがよくわからないという状態の時で。任天堂も実はちゃんと把握できないっていうぐらいにね。
イバイ氏:
あの頃は業界内の各社による研究はあったと思うんですけど、今のようにゲーム開発のAからZまでが共有されている時代ではなかったと思いますね。
手塚氏:
そうなんです。だからゲームを開発しながら、マシンもこういう使い方あるんだみたいなね。そういう時期だったんで、やたら時間がかかっちゃって。で、たぶんね、3年か4年開発やってたんですよ。それでもまったく出来上がらなくて、途中でギブアップしたっていうのが、正直なところです。
イバイ氏:
3年とか経ってくると、開発もダレてしまいますからね。
手塚氏:
そうですね。
後編に続きます。
[聞き手 Shuji Ishimoto]
[写真撮影 Mon Gonzalez]
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。