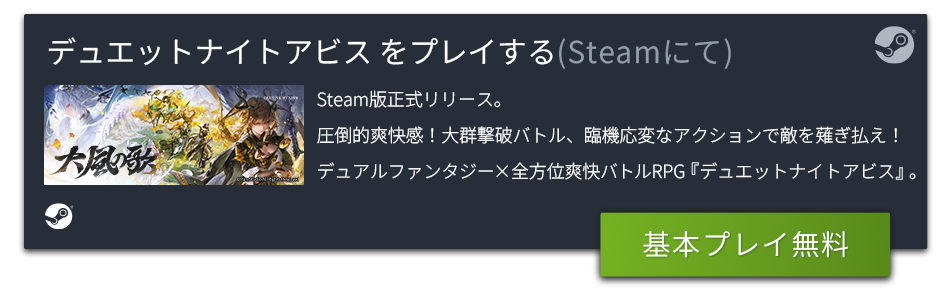Q.「ゲームを作らないパブリッシャーがなぜ忙しいんですか」A.「できる以上のことをする必要があるから」。PLAYISMが今忙しい理由、そして業界未経験者も含め求める人材とは
弊社アクティブゲーミングメディアのパブリッシング部門PLAYISMが、人材を募集中だ。その分野は多岐にわたり、プロデューサーをはじめとしてさまざまなポジションを求めているという。そのポジションや理由を訊いた。

弊社アクティブゲーミングメディア(以下、AGM)のパブリッシング部門PLAYISMが、人材を募集中だ。その分野は多岐にわたり、プロデューサーをはじめとしてさまざまなポジションを求めているという。
AUTOMATONはPLAYISMと同じ部署にあり、デスクは隣。隣を目にするとPLAYISMにはたくさん人がおり、みんなそれなりに忙しそうである。しかしなぜゲームを作らないパブリッシャーに人が必要で、なぜ忙しそうなのか。求人インタビューに答えてもらうに際して、そうした疑問にも答えていただいた。なお、以下が今回の募集要項である。興味がある方は、下記リンクを参照してほしい。
・ポジション:
プロデューサー
アシスタントプロデューサー
マーケティング担当
動画編集
翻訳
ローカライズマネージャー
プログラマー
──自己紹介をお願いします。
水谷:
水谷です。AGMのBtoC事業本部長兼PLAYISMの事業責任者をしています。

──求人をしたいというところから今回のインタビューにつながりましたが、なぜそもそも求人を?
水谷:
PLAYISMを本格的に組織化をしていきたいと思ってます。なんとなく今まで幼虫が一生懸命頑張ってきた感じでしたが、さなぎになって成虫になりたいと思っています。
──なるほど。
水谷:
これまでは組織化ってきっと大事なんだろうなあと思いながらも個人戦をずっとやってきていましたが、このやり方のまま巨大になることって難しいと感じ始め、今の現状を幼虫と表現しました。規模感からして今まではそれで特に問題はなかったのですが、ただ、事業が大きくなってきて、やることが多岐にわたるので、組織化をしっかりやるタイミングなんだなと思っています。
──では、成虫化するにあたって必要なポジションのスタッフはどこになりますか。
水谷:
理想の組織としては、いろんなポジションが必要です。まずは、プロデューサーやアシスタントプロデューサーがいる。それといままでは宣伝部がなかった。プロデューサーが個々で宣伝を頑張っています。今後はマーケティング専門の担当者は当然必要です。それとローカライズマネージャーも新たにいりますね。部内に翻訳者もいるのですが、マネージャーが欲しいです。カスタマーサポートも頑張っているスタッフがいますが、属人化をやめたいんです。QA/デバッグもみんなで頑張っているが、デバッグチームを作りたい。動画作る人ももっといればいいし、プログラマーも優秀な人がいればいいですよね。
──人をたくさん入れられる経済的な体力があると。
水谷:
あります。売上規模が大きくなってきたので、どんどん人を入れていきたいです。ひとりひとりが今は忙しくて。
そもそもなぜパブリッシャーに人手が必要なのか
──少し初歩的な疑問かもしれませんが、なぜパブリッシャーが忙しいのでしょうか。デベロッパーが忙しいのはわかります。でもなぜパブリッシャーが忙しいのか疑問で。作ると売るでいうと、作る方が圧倒的に大変というイメージがあるので。
水谷:
パブリッシャーが忙しいとか、人が必要なのかとか、外から見ると不思議に思いますよね。インディー専門のパブリッシャーはゲームを作ってもないし企画もしてない。開発よりはるかに楽だと思います。が、実際は結構大変なんです。ちょっとざっと述べてみます。パブリッシャーのすることは以下みたいな感じです。
・販売プロデュース
・ローカライズ
・移植
・QAデバッグ
・ファーストパーティー交渉
・リリース作業
・トレイラーなどの作成
・宣伝・PR
・イベント出展
・パッケージ販売業務
・カスタマーサポート
・セール対応
・ほか数字の分析などいろんな雑務
──タスクとして見ると結構多岐にわたりますが、そこまでですか?
水谷:
ただするだけならできるんですが、ちゃんとしようとすると、大変なんです。今はパブリッシャーは、ちゃんとしないと意味がない。それが昔との違いだと思います。昔はパブリッシャーがいないとゲームを発売できなかったから、パブリッシャーに頼りましたよね。しかし今は個人でリリースできますよね。だから、パブリッシャーの意義が問われる。高品質なローカライズやボイス収録導入、付加価値をもたらす幅をだす必要がでてきた。
宣伝も同じです。昔はプレスリリースの書き方や送り先もわからなかった。だから、パブリッシャーがそういうことができるので、意味があった。しかし今は個人でも国内だけでなく海外のメディアも含めて、個人で送れるようになった。“ただ送ってる・やってる”程度なら、個人でやった方がいいですよね。だからパブリッシャーならではの宣伝がいる。
なので、ひとつひとつの取り組みの幅が広くなってきた。「できる」だけでなく「ちゃんとできる」が必要な時代なんです。より深くやる必要がある。

直近で移植・販売・宣伝を実施したNintendo Switch版『8番出口』
──「できる」と「ちゃんとできる」は文面こそ似てますが、かなり違うと。
水谷:
そうですね。それと、昔はインディーゲームはパブリッシャーが何もせず勝手に完成していたんです。でも今はインディーパブリッシャーもゲームの開発や品質に対するフィードバックが求められると感じています。ゲームとしてこれが必要であるとか、余分であるとか。フィードバックをして、作ることにも介在していく。そういうところでも、デベロッパーに対してバリューを提供しなければいけなくなっている。年々やることは増えています。
──フィードバックというのは、なんのためのフィードバックなんでしょうか。そのゲームらしさを磨くためなのか、売るためなのか。
水谷:
究極的には売れるためだと思いますが、完成度を上げることが必要です。「作りたいものを作って売れる」だけならそれが一番いいですが、なかなかそう簡単にいかない。「作りたいものを作りつつ、世の中の求めるものとのすり合わせをする」。魅力を残しつつ、不要な部分は削ぎ落とす。あるいは追加すべきものを足す、そういうことを相談しています。そういう役割を担わないと、今はパブリッシャーの価値がないと思っています。
……実はPLAYISMのプロデューサー……というか僕は、上の作業を一通りひとりでできた時代もありました。
──どうして昔はできて、今はできなくなったんでしょうか。
水谷:
前述したように、かつては「できる」こと自体に価値があったからです。ただこなせればよかった。ゲームをリリースしただけで喜ばれました。ただ、徐々に「ちゃんとできる」ことが必要になってきた。そしてやるべきことが多くなった、という感じです。昔は1万本を目指していたけど、今は10万本を目指しています。で、売れれば売れるほどカスタマーサポートがくる。日本語に、英語に中国語。しかもカスタマーサポートは多言語で対応しなきゃですよね。そんな感じで、やることは多くなっているし、求められるものが多くなった。
同じゲームをパブリッシングするにしても、昔に比べてローカライズコストは倍になってたり、カスタマーサポートコストも倍になってたり。宣伝も量が必要です。
──たしかにひとつのゲームでも、パブリッシングの負担は上がっていることにはなりますね。
水谷:
はい、それとインディーゲームが増えて競争が苛烈なのもありますよね。インディーゲーム自体が増えたので、ライバルパブリッシャーと同じことをやってても勝ち抜けない。Steamの人気の新作に出てこない。ちゃんと研究して工夫しないと売れなくなってきている。うまくいかないと「デベロッパーのためになれていないな」と感じますね。
競争が苛烈で個人でいろいろできるとなれば、必然的に求められることも多くなる。なので、パブリッシャーと組む価値をデベロッパーに提供するためには、パブリッシャーとしての専門性を高める必要がある。そのためには優秀な人材が必要になるというわけです。
──パブリッシャーもまたデベロッパーに価値を測られており、それに応える必要がある。いろいろ頑張らないといけなくて、そうなると忙しくなるわけですね。

ゲーム販売だけでなく、おビンタおグリップの販売も行った『薔薇と椿』
ほしいのは「指摘する人」ではなく「伴走できる人」
──では、今一番足りていない、欲しいと思う人材を教えてください。
水谷:
ゲームへフィードバックをする人ですかね。これはすごくセンスとスキルが必要なんです。ただフィードバックをするだけでなく、開発者のことを真摯に考えて寄り添わないといけないので。当たり前ですが、状況に合わない雑な提案をしたり、現実的ではないことを言ったりとか、そういうことをしてはいけない。だから、フィードバックをやりたがる人は多そうですが、実はすさまじく難しい。
──単なる批評家になってはいけない?
水谷:
ええ。いろんな足し引きの案内が必要になります。たとえばよくあるパターンとしては、最初一緒に仕事を始めた時はゲームに尖った部分があるんです。ビジュアルだったりお話だったりシステムだったり。ただ、ゲームを作るうちに、その尖りが見えなくなってくることがあります。たとえば、ゲーム開発者は釣りイベントを増やしがちで。でも多くのゲームにおいては、それが必要でなかったりします。余分なものを増やすことになるんです。
サブコンテンツを入れるか。入れるなら何か。そういうのを考えていく上で求められるのは、ゲームの編集力かなと思います。いいところを輝かせるためには、本当に必要なものを足していく、あるいは不要なものを削っていくアプローチがいる。そしてそういう提案をデベロッパーに聞いてもらうために、信頼を勝ち取る必要がある。コミュニケーション能力もいります。
──ただ真っ当なことを言うだけでもダメ、と。
水谷:
まっすぐ正面からいっても、理解してもらえないこともありますよね。デベロッパーもプライドをもって開発しているし、仕事のパートナーにはそのやり方を理解してほしい。だから、ただ直球で伝えるだけではダメ。相手にちゃんと理解してもらえるように言葉を選ぶ。難しいですけどね。
一方で、現状のPLAYISMでもそういうことにチャレンジしていて、デベロッパーとの調整がうまくハマった時は、結果や数字につながっているとも感じています。成功体験もできつつあります。
──それをやるのがPLAYISMのプロデューサーであると。
水谷:
そうですね。プロデューサーは今はリリースや宣伝もローカライズチェックもやっているので忙しい側面もあります。だからこそ、宣伝部が欲しいんです。今のメンバーはそれぞれ、宣伝ノウハウはいろいろある。ただ、それをうまく共有しきれていない。たとえばひとりはTikTok広告に詳しいんですが、僕は知らない。なので、そこの知識差がノウハウの共有で埋められないと、仲間がすでに知っていることを別途一から勉強することになる。それはもったいないですよね。
PLAYISMにはノウハウの器があまりできていない。宣伝もローカライズも、人によってやり方が違うとかあるんですが、組織でノウハウ溜めて、そういうのを減らしたい。チームとしてのノウハウにもっと厚みをもたせたいですね。
──いまのPLAYISM……というか水谷さんのモットーみたいなものを言葉であらわすとするならなんでしょう。
水谷:
「For the game」です。すべてはゲームのため。あるいはゲームの完成度のため。もちろんデベロッパーは重要ですが、デベロッパーが嫌がってるからやめようというのはしたくない。もちろんデベロッパーが一番そのゲームに近いところにいて創造主で、ゲームを理解できている存在ではあります。しかし世の中のユーザーの波長と合うとは限らない。成功のための有用な意見があっても、気を遣って引っ込めてしまって、ゲームが良くならないケースもあります。時には、ゲームの完成度のために、デベロッパーと戦わないといけない瞬間がある。そこで戦えるかどうか。
よくある例としては、もう開発に疲れたから出したいというデベロッパーがいたりして、そのまますぐに出すことが本当にいいのか。もうちょっと作り込んだら化けると進言したり、あるいはデバッグや調整を一緒にしたり。そういうことをしていくんです。

ゲームの完成形を開発者と模索した『Refind Self: 性格診断ゲーム』
成長の理由と成長の先
──さきほどから規模拡大であるとか、事業成長的なお話をされていますが、PLAYISMって結局どれくらいの事業規模なんでしょうか。
水谷:
金額公表は難しいのですが、直近5年で売上は3倍になっており、基本的にはずっと右肩上がりで伸びている感じです。ただ、売上は大きいですが、その多くはデベロッパーに還元しています。その他今開発しているタイトルの開発支援にまわしていたり。売上を積み上げて、その利益を使ってデベロッパーを支援して。そのサイクルです。
──成長のきっかけを教えてください。
水谷:
いくつか区分を分けると、Nintendo Switch参入や市場獲得、パッケージ参入などがあげられます。小売店の人からよく聞くのですが、なぜかよくわかりませんが、PLAYISMのパッケージはインディーゲームの中ではよく売れるらしいんです。明確な理由は自分たちでもちょっとわかっていないのですが。そのほか大きなきっかけとしては『Bright Memory』や『ごく普通の鹿のゲーム DEEEER Simulator』『アイドルマネージャー』などの発売を経てぐっと規模が大きくなった印象です。
それと、Indie Live ExpoやPLAYISM Game Showといった生放送番組が始まってから、認知度が大きく変わりました。これらの番組が始まった時期と、規模拡大の時期はかぶっているので、関連しているのかなと。ブランドの安心感が出たのかなと考えています。
──ちなみに、事業成長と人の拡充ペースは比例していますか。
水谷:
正比例するものではないですね。大局的には売上も連動して大きくはなっていますが。ひとつは、出すタイトルがここまで当たるとは思っていなかったので……。もうひとつは当然、組織を拡大すれば売れるというわけではまったくない。そうであれば、一番大きい会社が一番ヒット作を出せるはずですからね。ただ、人が増えることで丁寧にゲームを出していけるので打率は上がるのでは、という認識です。一般論としてはあまりに少人数のパブリッシャーよりは多人数のパブリッシャーの方が任せやすいと思うので、それもあって人は増やさないといけないと思っています。
インディーデベロッパーの規模も大きくなりましたよね。昔は個人が普通でしたが、今は数十人のチームもある。だからコストも大きくなって、回収する必要があるお金も多くなっていく。そうなれば、パブリッシャーとしても打率を上げて、そうしたことをサポートしないといけないですよね。
──成長のお話をされていますが、成長の先には何があるんですか。
水谷:
僕は今の状況をいいなと思っています。というのも、昔はタイトル獲得や支援に1000万円使うかどうかを会社に相談した時は、それはそれは長い大会議をした上で本当にやるのかやらないのか皆で必死で考えて合意をとる必要があった。でも今はかなりの額をもっと早く動かせるようになってきた。単純に使えるお金が増えてきた。そうなると、売れなさそうでも尖ったゲームを支援できるようになった。
そもそもとして僕自身がこの仕事をやる中で、自分の好きなタイプのゲームが世の中からなくなるかもしれないという危機感を勝手に抱いていました。当時は売切型のゲームそのものさえもなくなりそうな勢いでしたしね。売れそうな理由なんて何もなくても、面白いゲームを作る人に、ゲームを作り続けてほしい。自分が遊びたい尖ったゲームを世の中に普及させていきたい。そうすると世の中もそういうゲームに価値を見出すことになる。そういうサイクルを作り続けたいんです。そのために、成長したことで得たお金を次世代のクリエイターに投資して、そういうサイクルの世界を維持したいんです。

前作に続き、シリーズで開発援助も行った『Momodora: 月影のエンドロール』
それと、いまはインディーゲームは成長していていっぱい出てるしお金も集まっている印象ですが、いつかこのバブルは弾けると思います。そのときには、今よりもインディーゲームに出資する人は少なくなると思う。そういうときにもちゃんとお金を出せるようにしていたいですね。
──会社のお金を使って、自分の推しゲーに投資できるのはちょっとロマンあります。
水谷:
(笑)その分責任がともないますけどね。売れなかったり、完成度低いまま世に出すとなると最悪ですよね。こいつが作品を台無しにしたと言われますから。でも自分がいいと思ったゲームを見つけてきて、投資して、サポートして、それが世に出ていろいろ反応があるのは本当に楽しいです。ユーザーからダイレクトにフィードバックをもらえるのが面白いですね。唯一無二の仕事だと思います。
ほしい人材と待遇
──ありがとうございます。では求人なので、お給料の話もしていただけると。
水谷:
中小企業としては普通だと思います。めっちゃ低賃金ではないと思いますが、大企業でもないのでめちゃくちゃ高いわけでもない。ただ結果を出したり、成果を出したことに対しては、待遇に反映されやすい会社だとは思います。
──ゲーム業界経験の有無についてはいかがでしょうか。
水谷:
ゲーム業界経験者なら大歓迎ですが、未経験でもOKです。経験者歓迎な理由は、流れがわかるからです。実は今のチームは未経験者が多いんですが、パブリッシングの流れがわかっているとありがたいです。
インディーゲームを売った、作った経験があるとなお嬉しいです。昔はインディーゲームを売ったことがある人というのはなかなかいなかったのですが、今はそんな経験のある人も出てきたというのもあります。ただ、規模感が重要なので、大きな会社出身の人は面食らうかもしれない。リスクやリターンの規模感が違うのでそれに適応できるかが重要で。大きな会社とはやり方が違うし、泥臭いことが重要なので、それに耐えうるかですね。
──未経験者の場合、どういうマインドが求められますか?
水谷:
新しい業界ですから、こうすればいいとかどんどん変わっていきますし、常日頃新しいことを試し続ける必要があるので、ベタかもですが好奇心ですかね。自分で考え、仮説を立てて、それを実現させること。いろいろ考えながら切り拓いていきたい、今くすぶってる人にきてほしい。
──具体的には、どういうスキルがあるといいですかね。
水谷:
ものすごく具体的には、英語ができると任せられることが多くはなりますよね。
──ほかには。
水谷:
メンタリティ寄りの話ですが、歓迎してるのは「頑張ったことがある人」ですね。どんなことにでも、いいんです。頑張らないといけない仕事なので。
ほかには、やっぱりインディーゲームが好きな人ですかね。好きじゃないと楽しくもないでしょうし、インディーゲームに関わる仕事に対して幸せだと感じられるなら、相性はいいんじゃないかなと。
それと、僕はこの仕事の一番いいところって、やったことがものすごくダイレクトに返ってくることだと思います。自分が仕掛けたことの反応も数字も全部見れる場所にいるって案外早々ないんじゃないなと。そういうのを楽しいと思えるならば、かなり楽しい仕事だと思います。

──なるほど。だいぶイメージが湧いてきました。社内ながら応援しています。ありがとうございました。
以下、改めて求人項目を掲載する。興味がある方は、下記リンクを参照してほしい。
・ポジション:
プロデューサー
アシスタントプロデューサー
マーケティング担当
動画編集
翻訳
ローカライズマネージャー
プログラマー
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。