書評『マインクラフト 革命的ゲームの真実』
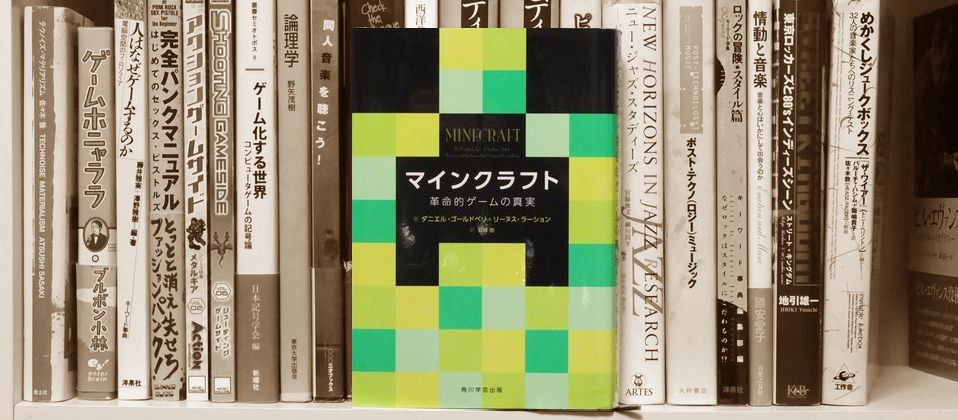
Gamer's Bookshelfは、ゲームに関係する書籍を紹介する定期連載。隔週掲載予定。第1回となる今回とりあげるのは、その存在をご存知の方も多いであろう『マインクラフト 革命的ゲームの真実』である。
本書は『Minecraft』の誕生からその爆発的な成功までを、NotchことMarkus Perssonの人生とともにつづったルポルタージュである。このように書くと、いかにもありがちな成功者から学ぶIT系の自己啓発本を想像されるかもしれない。だが安心してほしい。本書はそういった類のビジネス書ではなく、ゲーマーにも充分楽しめる内容になっている。

もちろんMarkus Perssonが育った家庭環境と手にした成功の巨大さを考えると、これはまさしく歴史に残る成功譚だ。めぐまれない家庭環境、地道な努力、数々の出会いと偶然からつかんだチャンス、そして成功者の苦悩。内向的なナードのMarkus PerssonをNotchという現代のヒーローに仕立てあげるには、豊富なエピソードがそろっている。だが本書の著者らは、一人の天才にすべてをゆだねることなく、『Minecraft』の成功までの道のりを多面的に描いてゆく。
意外なキーマン、Carl Manneh
実用書を期待して本書を手にした人ならば、世紀の大ヒット作の理由のひとつくらいは書いてあるだろうと思うかもしれない。しかしながら本書には安直な「ヒットの秘訣」といったことは一切書かれていない。主眼はあくまでも一人の男が偶然にも大ヒットゲームを生み出した過程とその背景にあるのだ。
なかでも興味深い偶然は、Notchが会社をおこすくだりだ。
すでに『Minecraft』のヒットによって個人開発者として成功していたNotchは、あのValveからのヘッドハンティングをはねのけて、かつての同僚Jakobと新会社設立を模索していた。しかしNotchもJakobも会社経営とは無縁のプログラマーである。そこで召喚されたのが現在『Minecraft』を販売しているMojangの社長であるCarl Mannehだ。
Carl MannehはNotchが当時勤めていた会社の社長で、ビデオゲーム業界とはまったく関係のない人物だった。靴紐の販売、レコーディング・スタジオ、写真アプリの開発といった小さな会社を経営してきたこの実業家は、仕事の合間を縫ってゲームを作る若者に非常に寛容であった。
日本と同様、スウェーデンにも副業を禁止する社内規程はめずらしくないそうだ。仕事の合間にゲームを作るNotchのような開発者にとっては、それらの規定は足かせとなる。事実、前の会社では副業禁止規定のために、彼はトラブルに巻き込まれている。
それに対してCarl Mannehは、Notchのゲーム開発に興味さえしめしたそうだ。寛大なこの上司は、ことあるごとにNotchをはげまし、会社の仕事とゲーム開発を両立できるように調整さえしてくれたそうだ。結果、Notchから大きな信頼を得たCarl Mannehは、『Minecraft』ともゲーム開発とも関係ないにもかかわらず、Mojangの社長に抜擢されたのである。
IT都市ストックホルム

さらに本書は『Minecraft』の誕生と成長の物語を、北欧のゲーム業界という背景のもとで生き生きと描きだす。創業まもないMojangは、ストックホルムの南側の島Södermalm(セーデルマルム)にオフィスをかまえた。Södermalmには『Battlefield』シリーズのDICE、『Just Cause』のAvalanche Studios、『Hearts of Iron』といったストラテジーゲームの名門Paradox Interactiveなど錚々たる大手デベロッパーがひしめいている。
ゲーム産業にかぎらず、SkypeやSpotifyといった企業がスウェーデンに起源を持つ。スウェーデンは世界でも1、2を争うブロードバンド普及率を誇り、国の大型投資によって2000年代を通してIT大国に成長した。他方、内部告発サイトWikiLeaksのサーバーがSödermalmに設置されていたり、クラッキングによる映像表現を行うデモシーンが古くから存在していたりするように、スウェーデンはハッカーの国でもある。大手企業のシステム開発者が裏稼業でクラッキングに手を染める、といったファンタジーが現実味がおびるのもストックホルムの面白さだ。
IT系の大企業が集中するとと共にパーソナルコンピューティングの古い歴史をもつストックホルム。そこではAAAタイトルが生みだされるオフィスのそばで、日夜様々なインディーゲームも生みだされるというわけだ。本書が描くそれらの雰囲気は、単に『Minecraft』の生まれ育った故郷という意味だけではなく、北欧のゲームシーンに興味があるゲーマーにとっては興味深い内容になっている。
インディーとメジャーの共生関係
そんなストックホルムの雰囲気を描写しながら、本書はさらに北欧のゲームシーンの特殊性に踏みこんでいく。それは端的にいうとアンダーグラウンドとオーバーグラウンドの連続性であり、インディーとメジャーの共存である。
そもそも先述したスウェーデンのゲーム産業の多くは、デモシーンに由来する。1970~80年代の初期コンピュータ文化に芽生えたデモとよばれる表現、そこではマシンの性能を駆使してCGと音楽をリアルタイムに表示することにしのぎをけずってきた。北欧のプログラマーやアーティストたちはグループを結成し、デモパーティーとよばれる場所で作品を発表してきた。それらのグループのいくつかがゲーム開発者となり、パーティーのいくつかが北欧のゲーム系イベントの源流となっている。
実際に『The Darkness』や『Brothers: A Tale of Two Sons』等で高い評価を獲得しているStarbreeze Studios、『ALAN WAKE』と『MAX PAYNE』で有名なフィンランドのRemedy Entertainment、さらにはあのDICEもデモグループに起源を持つそうだ。
つまりスウェーデンのゲーム産業にはデモシーンを中心としたハッカー文化が脈々と受け継がれているのだ。アンダーグラウンドの地下水脈が、メガパブリッシャーの資金によってオーバーグラウンドに顔を見せる。この共生関係こそが北欧のゲーム業界を一段と魅力的なものに思わせる部分だ。
このような伝統のなか、現在のインディーシーンにつながるイベントとして本書は2008年に開催されたNo More Swedenに焦点をあわせる。スウェーデン版のIGFとでもいうべき本イベントは初開催ということもあり当時はたった15名の参加者しか集まらなかったそうだ。前世紀のデモパーティーに比べるとその規模はまだまだ小さい。
そこにはKnyttシリーズで有名なNifflasことNicklas Nygrenや、『Hotline Miami』で一躍商業デビューをかざったJonatan "Cactus" Söderströmなど、現在からみれば豪華な面子がそろっている。彼らは商業的には無名にひとしかったが、インターネットのフリーゲームの世界では高い人気を誇り、寄付やシェアウェアによって生計をたてていた。
今ではスウェーデンのインディーシーンの恒例行事にまで成長したNo More Sweden。集まった若者たちはインターネットという新たな流通網をえることで、自由に創作を続けていく環境をととのいつつあった。かつてのデモシーンがメジャーなデベロッパーに成長するまでの登竜門であったならば、あらたなインディーシーンはアンダーグラウンドでありつづける自由をあたえたといえる。
しかし、ここでも本書は両者の対立よりも共生を強調する。
“大手ゲーム企業とインディ系ゲーム開発者の戦いは、巨人兵ゴリアテと羊飼いダビデの戦いだったのだろうか?リングの赤コーナーには利己的で資本主義的な大企業がいて、青コーナーには理想を追い求めるインディ系開発者がいる。そう表現したい気がするが、残念ながらそれは間違いだ。インディ系開発者たちは、ビジネスとしては取り組めそうにない実験をおこなうクリエイティブな存在として、つねにゲーム業界の大手企業と共存してきた。とはいえ、趣味でコードを書くだけではなく。ゲーム開発者として食べていこうとすれば、大企業の巨額プロジェクトに参加する以外、ほとんど選択肢はなかった。しかし、ここにも転機が訪れる。新しいデジタル技術によってゲームの流通方法が変わると、フリーランスのゲーム開発者にも収入を得るチャンスがやってきたのだ。”(本書78pp.)
つまり、いつの時代にも自己表現としてゲームを開発する人々は存在したのだ。創りたいゲームを実現するため、大手企業の受託開発をするものもいれば、貧乏生活を覚悟してインターネットで販売するものもいる。やり方が違っても、全体の構造そのものはそれほどかわらない。結局のところ、ゲーム業界とはそれら全体を指すわけだからだ。そして、『Minecraft』が成功した下地にも、そのような北欧ゲーム業界の長い伝統がよこたわっている。
『Minecraft』の保守性と岐路に立たされるMojang
そのようなスウェーデンのゲーム業界にあっても『Minecraft』の急成長は前代未聞の出来事だった。幸か不幸かそれはゲーム産業という枠組みを超えた一大現象として語られている(この日本版の本の帯には「たった一人でゲーム業界を変えた男」という大げさなキャッチコピーが踊っている)。オープンアルファによるファンディング、頻繁なアップデート、ユーザー参加型コンテンツといったその「ヒットの秘訣」については、既にメディアでいくらでも指摘されているので、ここではいちいちとりあげない。
帯には大変申し訳ないが、本書が強調しているのはどちらかといえばビジネスにおけるNotchの保守性であると思われる。つまり、アルファ版の販売や頻繁なアップデートはビジネス上のイノベーションというよりも『Minecraft』がシェアウェアの伝統にのっとっていることをしめしているのだ。さらに同時期に脚光を浴びたF2Pというビジネスモデルと比較すれば、『Minecraft』がおこなってきた開発と販売の手法はむしろ保守的であったとすらいえる。
しかしながら『Minecraft』をというモンスタータイトルを擁するMojangに対する世間の見方は、Notchの考えとはことなっている。投資家David Pakmanいわく「「マインクラフトの真の価値は、ゲームにあるわけではない」し、「その真の価値とは、マインクラフトの周囲に集まる熱心なプレイヤーたちの巨大なコミュニティにこそある」。つまり、Mojangは伝統的なゲーム開発者というよりも、Facebookのような革新的な(あるいはかつて革新的とされた)SNS企業に近いというわけだ。
その見方が正しいかどうかはともかく、すくなくともNotchの会社の設立意図にそわないのはあきらかだ。Mojangの社是は「世界でいちばん影響力のあるインディ系ゲーム開発会社を目指す」ことであって、コミュニティ運営でもグッズ販売でも投資家からの資金集めでもないのだ。それどころかNotchとJakobにとってMojangとして最初に開発する予定だったのは『Minecraft』ではなくJakobのあたためていたカードゲーム『Scrolls』であった。
その一方でMojangはレゴとのライセンス契約を含め多くのグッズ販売も開始している。さらには人気の動画配信者のLydia Wintersを広報役として雇い、コミュニティ運営を強化している。著者はこれらの方針を『Angry Bird』のヒットで知られるフィンランドのRovioと比較する。単発ヒット作をグッズ販売や映画化によって延命させるRovioのその手法を、NotchやJakobは腐しているが著者たちはその両者を客観的に描いている。
“しかし、見方を変えれば、モヤング社が創立者の望んだ方向とは別の方向へ向かっていることの証拠が、このレゴブロックだともいえる。(・・・)彼の目から見たロヴィオ社は、良いゲームをつくろうとしている企業ではなく、貪欲に利益だけを追求している企業なのだ。だから、ロヴィオ社のようになるのはまっぴら御免だと思っている。とはいえ、事情をよく知らない人がこの時点でモヤング社を眺めてみれば、ロヴィオ社との違いなどはっきりとはわからないだろう。(・・・)会社に大金が流れ込むにつれ、明らかにマインクラフトの進路は変わってきた。ゲームは次第に、マルクスがコントロールできる範囲を離れていった。”(本書212-213pp.)
とはいえこれらはすべてたんなる過渡期の問題かもしれない。『Scrolls』は本書の出版後の現在も正式版がリリースされていない。『Minecraft』と同様のヒットを飛ばすことは難しいかもしれないが、作品としての高評価が与えられたならばMojangは優秀なインディー開発者としての名誉を預かるだろう。もちろん、さしたるヒット作にめぐまれずMojangが『Minecraft』一本で勝負していくこともありうるだろう。その場合、活躍の場を失ったNotchはMojangから離れるかもしれない。いずれにせよ「インディーデベロッパー」としてのMojangは、そのアイデンティティをめぐって岐路に立たされているのだろう。
本書はそれを幸とも不幸とも見なさない形で幕を閉じている。華々しい成功を書き綴るのでもなく、インディーとしての理想をかかげるのではなく、一人の人間としてのMarkus Perssonに焦点をあわせた本書は客観的であり、かつ物語としてもドラマティックだ。なかにはゲームの魅力を心理学者チクセントミハイの概念で説明したり、急に金持ちになることの苦悩を学術的に分析したりするなど、不必要と思われる章もある。だが、全体から見れば非常にバランスが取れた読みがいのあるルポルタージュに仕上がっているといえるだろう。
この記事にはアフィリエイトリンクが含まれる場合があります。



